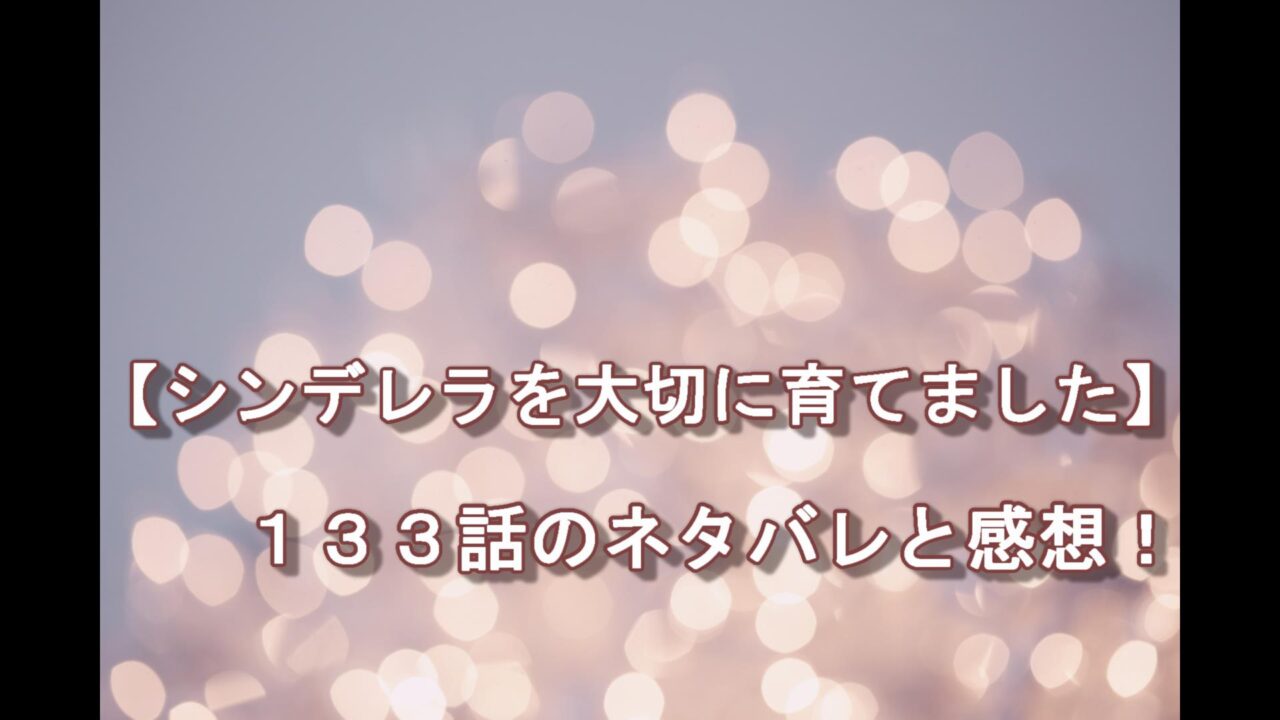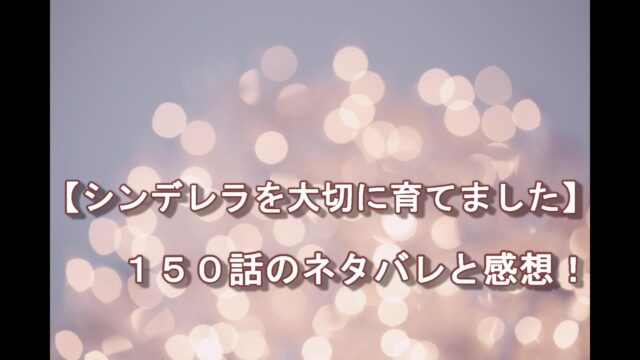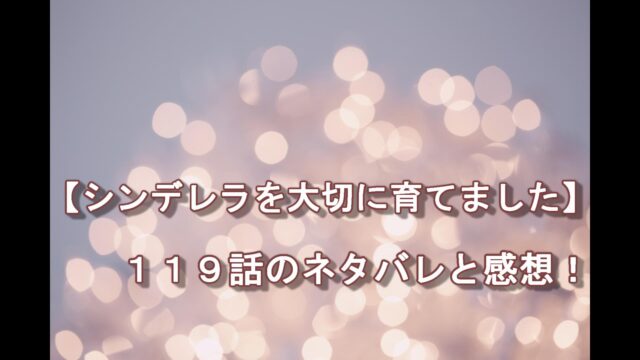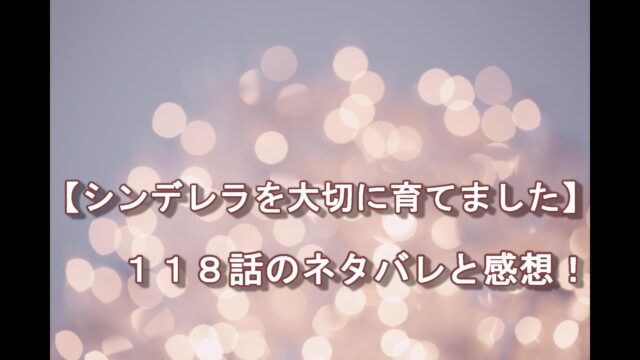こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は133話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

133話 ネタバレ
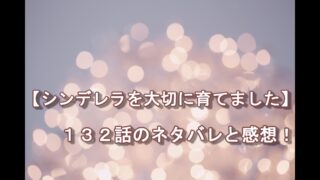
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 絶望を呼ぶ再会
「アシュリー、何してるの?」
書斎の前でアシュリーを見つけたリリーが尋ねる。
アシュリーは本を持ってどこに行くか悩んでいた。
今日彼女がしなければならないことは半分程度しかできなかったが、それでも昨日読んでいた本の次の内容が気になって耐えられなかったためだ。
彼女はリリーを見て声を低くして言った。
「本を読みたいんだけど、アイリスに内緒で読もうと思って」
どういうことか分かったリリーの顔に笑みが浮かぶ。
彼女は仕事をせずに遊ぶとき、アイリスがどんなに小言を言うか知っている。
むしろ、自分のやるべきことは自分でやれという放任主義の母親より、アイリスの方が小言が多いほどだ。
彼女は書くべき便箋を持ち上げて言った。
「温室に行きなさい。そこはアイリスもあまり入らないから」
温室はリリーの聖域に等しい。
アイリスもよほどのことがあれは温室には触れなかった。
アシュリーは彼女の非行に目をつむってくれるリリーに感謝の意を表し、温室に向かう。
「リリー、アシュリ一を見た?」
数分後、書斎に押し入ったアイリスがリリーに尋ねる。
マーシャに手紙を書いていたリリーは、頭を上げずに無関心そうに答えた。
「いいえ」
「あの子、どこに行ったのかしら?今日までにハンカチの刺繍することにしたのに!」
「勝手にしてるわよ」
「自分でやるという言葉に信じて一週間目よ」
こう見ると、アイリスが母親のようだ。
リリーはニヤリと笑って首を横に振る。
アイリスは書斎を見て回り、書斎のドアの取っ手を握りながら言った。
「温室にいるのかな?」
その瞬間、リリーは頭をさっと上げた。
アイリスが温室に行ってはいけない。
彼女はアシュリーを隠すために素早く話した。
「そこにいないわ。私が今、そこから出てきたのだから」
「そうなの?」
じゃあ、どこに行ったの?
アイリスはリリーの言葉を疑わずに眉をひそめる。
そしてドアを開けながら言った。
「じゃあ、後苑にいるのかな?」
最近、庭を手入れし直すために花を植えた。
苗より種の方が安いので、苗半分、種半分で。
アイリスはアシュリーが花の種から芽を出すのを不思議に思っていたことを思い出す。
夢中でお花見してるんじゃないの?
アイリスがそう思って外に出ると、リリーはため息をついた。
早く使って温室に行ってアシュリーを隠してあげないと。
リリーはマーシャヘの手紙を書き終える。
そして便箋をとって今度はパトリシアに手紙を書き始めた。
すると、今度はルーインが書斎のドアをノックし、こっそりと顔を出して聞いた。
「お嬢さん、中にアシュリーお嬢さんもいらっしゃいますか?」
今日に限ってアシュリーを訪れる人が多いね?
リリーはペンを持ったままルーインをまっすぐに見つめながら尋ねた。
「いいえ、どうしたんですか?」
リリーの質問にルーインはしばらく口をつぐんだ。
彼がアシュリーを探す理由は、ダニエルが朝家を出る時、子供たちを注意深く観察するよう指示したためだ。
「特にアシュリーを見守ってほしい」と。
しかし、リリーはその事実を知らない様子で、ルーインの経験上、相手が知らないことは主人の許諾なしに話してはならない事案だ。
「さっきアイリスさんが探していたので、私も探しているのです」
「温室にはいないでしょう。私がさっきそこから出てきたので」
「分かりました」
この階を探してみないと。
ルーインはリリーの言葉にうなずいて身を引いた。
リリーが彼の背中に手紙を書き終えたら自分も探してみると言っているのが聞こえた。
リリーがアシュリーを見つけるのを待ちきれない。
ルーインはそのままこの階に上がり、窓の外から邸宅の外を見回した。
幸いなことに、屋敷の外に人は誰もいなかった。
少なくともアシュリーお嬢さんが家の中にいるということだね。
ルーインはそう思ってため息をつく。
アシュリーは温室に座って本を読んでいた。
まだ読み終わってないグラハムの民話だ。
彼女の一番好きな話は妖精のティータイム。
月が明るく昇った翌日、草むらに白い石が丸く円を描いたように置かれた現象が現れる。
グラハムはそれが妖精が一晩中ティータイムを楽しんだ現場だと話していた。
白い石の上に妖精たちが座って、真ん中に妖精の食べ物を置いて一晩中楽しい時間を過ごすという。
妖精の食べ物は何だろうか。
アシュリーの頭の中に丸くて可愛いシューと、柔らかくてほろ苦いティラミスが浮び上がる。
妖精たちはそのような甘いものだけを食べて生きているのかもしれない。
「ティラミスが食べたいな」
アシュリーはそうつぶやきながら長い椅子に仰向けになった。
スカートの裾が膝の上まで上がってきたが、彼女は気にしなかった。
そのまま大きな本に鼻を突っ込んで本を読む彼女の後ろの窓ガラスに男が近づいてきた。
フレッドは丸屋根の邸宅に近づく。
確かにそうだが、執事が彼を中に入れるはずがないことはよく分かっている。
彼は注意深く外に突き出た温室に向かった。
温室は庭園に通じる門があるものだ。
フレッドはこの家が温室をほとんど使わないことも知っている。
温室を通じて家の中に入ればいい。
そう思って石を拾い上げた彼は、そっと開いた窓を見つけた。
あそこに入れるかな?
フレッドは窓に近づき、女性が窓のすぐ前の椅子に横たわっているのを見つけた。
金髪のきらめく髪が太陽の光を浴びて輝いている。
本の下でアシュリーの顔を見たフレッドの動きが止まった。
「誰だ?」
彼はアシュリーの美貌に目を離すことができなかった。
その瞬間、アシュリーもフレッドを発見する。
フレッドはびっくりして悲嗚を上げようとしたところを素早く叫んだ。
「私だ、お父さんだ」
アシュリーはじっと男を見た。
顔を包帯で巻いた男は、手で自分の胸を一生懸命叩いていた。
もしアシュリーが悲鳴をあげて誰かが走ってきたら困る。
アシュリーは悲鳴を上げようと口を開けて止まった。
お父さんだって?
彼女は目を大きく開けて包帯で顔を巻いた男を見る。
そして慎重に窓に近づき、もう少し隙間を開けた。
「お、お父さん?」
アシュリーはこの状況を信じることができなかった。
この男が父親ではないという考えのためではない。
彼女は少し前までは死んだと思っていた父親が生きて帰ってくる夢を見たから。
死んだと知られた彼女の父親が実は生きていて、とても多くのお金を稼いで帰ってくるのだ。
そしてアシュリーを抱きしめて会いたかったと言ってくれる夢を見た。
しかし、もはやそうではなかった。
彼女は母親の関心と愛を得ていて、父親の代わりと言うのはおかしいが、ダニエル・ウィルフォード男爵もいる。
アシュリーはこれ以上父親が生きて帰ってくるという考え自体をしなくなった。
ところが、自分を父親だと主張する男が現れたのだ。
最悪の展開ですね。
フレッド?がアシュリーと遭遇してしまいました。
アシュリーは父親を見て何を思うのでしょうか?
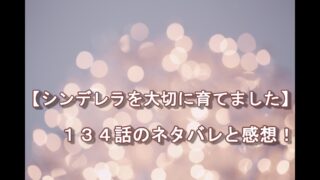





https://recommended.tsubasa-cham.com/matome/