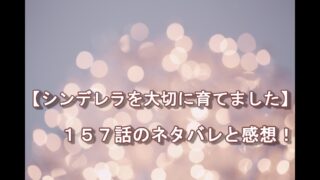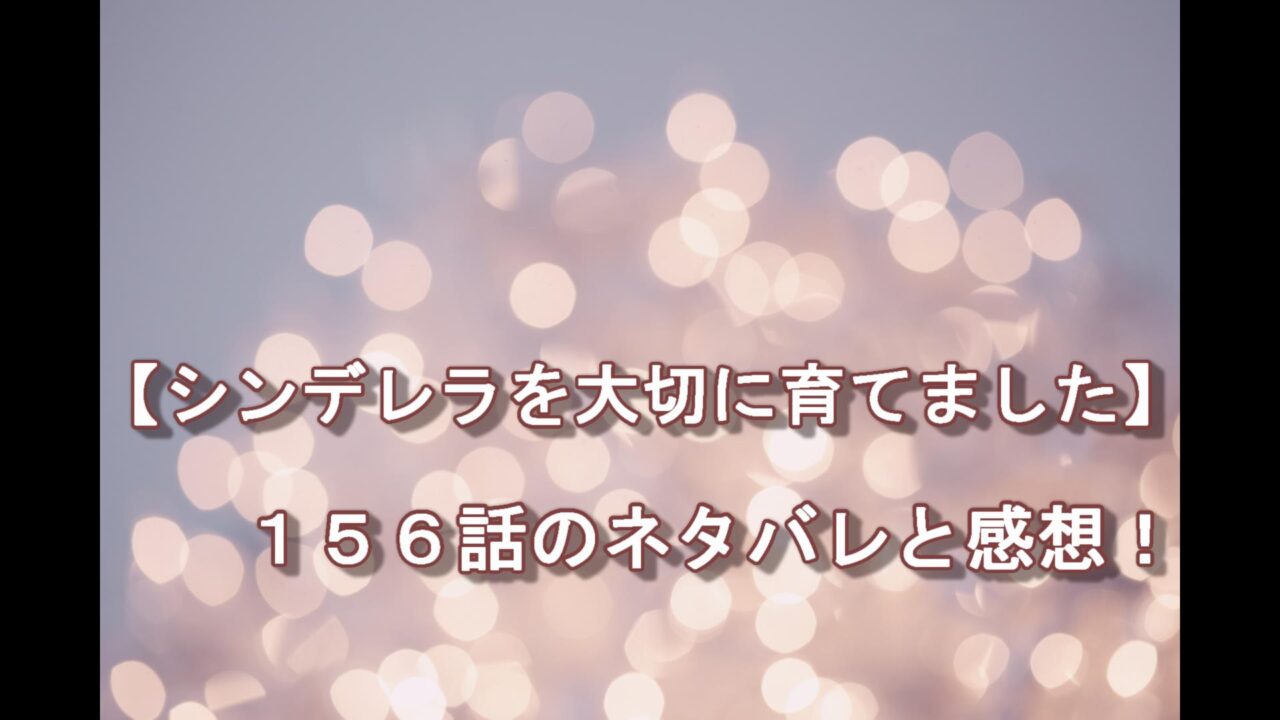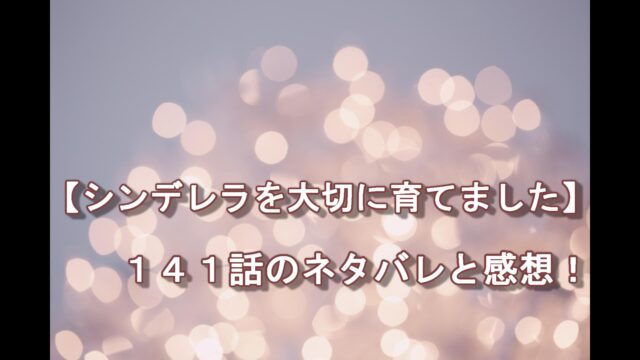こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は156話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

156話 ネタバレ
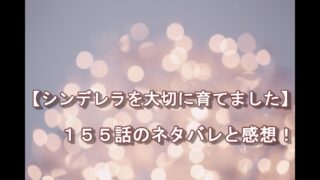
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 母と息子の会話
王妃候補の最初の試験当日。
使者たちはどの時よりも慌ただしく駆けつけてきた。
みな試験の結果がどうだったのか、3人の候補者が行ったティーパーティーがどうだったのか気になったからだ。
ゴシップ新聞では、どうやって知り得たのか、3人の候補者が準備したティーパーティーのテーマと出された料理について取り上げており、人々はバーンズ家のティーパーティーで出された柔らかいケーキが何だったのか気になっていた。
「ふわふわの食感だったとか?」
「柔らかくて口に入れた瞬間に溶けてしまったんだって」
「今回も妖精の商店で販売されるのでしょう?」
みんな、バーンズ夫人が作った今回のケーキも妖精の商店で販売されると信じて疑わなかった。
そうであるなら、今回も妖精の商店で予約をしなければならない。
おかげで妖精の商店は、今後6ヶ月間の予約がぎっしり埋まるという記録を打ち立てた。
「美味しいね。そう思わない?」
一方、城の片隅では王妃と王子が食事をしている。
今回の食事は急遽、王子の要請で行われたもので、ヘダーは息子が何の理由で呼んだのか察していないふりをしていた。
「ええ、美味しいですね」
本当に?
ヘダーはリアンの皿をちらりと見る。
王子の皿にはまだ食べ物がしっかりと残っていた。
何も手をつけず、フォークを持ったり置いたり、カップを取ったり置いたりを繰り返していたのだから当然だ。
味見さえしていないのに、どうやって美味しいというのだろう?
誰か他の人なら王妃を前に緊張してそうなるだろうと考えたが、リアンが母の前でそうするはずがなかった。
結局、ヘダーはため息をつき、リアンが話したい話題に持っていくため、新しい話題を切り出すことに。
「昨日、バーンズ家のティーパーティーで珍しいケーキを食べたの」
「バーンズ家」という言葉に、リアンの顎がピクリと動いた。
そうなるだろうと思っていた。
ヘダーは笑いをこらえつつ、知らないふりをして言葉を続ける。
「素晴らしいわね。次にバーンズ夫人が送ってくれるときには、そのとき分けてあげるわ」
「ええ、お母さま」
リアンはとうとう我慢できずに口を開いた。
ヘダーは彼がなぜ話しかけてきたのか分からないふりをし、表情にそれを表した。
「その、バーンズ家のティーパーティーのことです」
何を言えばいいんだろう?
リアンは何を言うべきか分からず、母の顔色をうかがう。
彼は困惑していた。
もし問題が起きたのなら、それは全て彼の過ちだ。
リアンは一度口を閉ざしたが、すぐに言葉を続けた。
「バーンズ家のティーパーティーで問題があったのなら、それは私の過ちです。ですので、バーンズ家の試験の点数を少しだけ上げてください。」
え?
ヘダーは予想外の頼みに呆然としながら息子を見つめる。
彼女が想像したのは、バーンズ家のティーパーティーで何があったのかを尋ねてくることだった。
点数を上げてほしいと頼むとは思ってもみなかった。
「ミスですって?それはどういう意味?」
王妃の問いに、リアンは目をぎゅっと閉じる。
彼の両親もダニエルが彼を弁護して貴族社会で自業自得の経験をさせることが必要だと考えているのは知っていた。
しかし、その貴族がバーンズ家であるとは思っていなかった。
彼が何をしたか分からないようだった。
リアンは、自分がバーンズ家でティーパーティーが開かれる日に仕事をした話を慎重に始めた。
そして、塩を持ってくるという重要な指示を壮大に失敗してしまったことも。
「全く、とんでもない話だ」
ヘダーは息子の信じられない失敗に笑いを漏らす。
王妃の笑い声に外で待機していたロアン侯爵夫人が何事かと覗き込んだ。
「塩を砂糖と間違えたですって?」
王妃の笑い声がさらに大きくなった。
リアンは母の笑いにどうしていいか分からず座っていた。
信じられない失敗ではある。
しかし、母がこれほど楽しむとは思っていなかった。
「それで、どうなったの?」
「バーンズ夫人が来て収拾しました。台無しになった果物は全て捨てられ、残ったものは服飾用に回されました。タルトを作ったんですよ。そして卵でケーキも作ったんです」
「すぐに収拾したって?」
リアンの答えにヘダーは、自分が大笑いしたことも忘れ、大きく目を見開いた。
ティーパーティー中に事件が起きたのに、それを誰にも気づかれないように収拾しただけでなく、見事なデザートを新たに作り出すなんて。
彼女はふと、ロアン侯爵夫人が自身の後任としてバーンズ夫人を推薦したいと言いかけたことを思い出す。
センスと手際の良さに優れた夫人だと言っていたか。
「お母様、バーンズ夫人が収拾していなかったら、私のミスでアイリスとバーンズ夫人に大きな損害を与えてしまったでしょう。彼女が私のせいで迷惑を被らなかったら良いのですが」
少し考え込むヘダーに、リアンが真摯な声で話しかけた。
ミルドレッドを思い浮かべていた王妃は、息子の懇願するような視線を目にして彼をじっと見た。
彼女は王子を産んでから今まで、一度も誰かに「助けてほしい」と頼まれたことがなかった。
もちろん、リアンの周りにいる人々は、ケイシー卿やウィルフォード男爵のように競争心の強い人々ばかりなので、王妃にまで助けを求める必要がなかったのかもしれない。
しかし、彼女にとって、息子が自分にこのようなお願いをするのは初めてで新鮮だった。
「あのお嬢さんがそんなに好きなの?」
王妃の質問に、リアンの身体が硬直した。
彼は一瞬戸惑いながら王妃の視線を避け、再び彼女をまっすぐ見つめながら答える。
「はい」
「私の記憶では、彼女が君を一度拒絶したはずだけど?」
「それは・・・誤解でした。今は彼女も私のことを気に入っています」
「それならジュゼッペ、どうして試験を中止してほしいと言わないの?」
試験の最中に王子が候補者の中の一人と恋に落ちて試験を中止するというのは、珍しいことではないが、あり得る話だ。
母の言葉にリアンは一瞬戸惑いながら答えた。
「アイリス、いやバーンズ嬢が試験を続けると決めたそうです」
「自信があるということなのね?」
ヘダーはそう言って微笑んだ。
王妃になる人間にはその程度の自信が必要だ。
そして王妃になる人物だ、そのくらいの意気込みは必要だろう。
彼女がアイリスに心を寄せるように促そうとしたところで、リアンが再び口を開いた。
「それよりも、勝たなければ自分の立場が危うくなると言っていました」
「立場?」
何を言っているのか理解できず、大きく目を見開いた王妃は続きを待つ。
息子が何を言っているのか理解した。
アイリス・バーンズ。
美しくも裕福でもなく、優れた家柄でもない令嬢。
もし王子が今、試験をやめて彼女と結婚するとすれば、アイリス・バーンズは運が良い王妃になるだろう。
しかし、試験に勝利するならば、資格を持ち、実力を証明した王妃となる。
「ふむ・・・」
ヘダーは椅子に背を預け、胸の前で腕を組んだ。
少しずつ彼女もアイリスを気に入るようになった。
どんな地位に就くためにも、ただ運に頼るのではなく、その資格を示そうとする姿勢が気に入ったのだ。
王妃は目を細めながら言った。
「どうやら今の君にとって最も必要な人かもしれないわね」
「どうやらではなく確信しています。彼女は僕に多くのことを教えてくれたんです」
「具体的に言えば?」
「責任感です」
リアンの表情には、誇らしさと自信が溢れていた。
なるほど。
ヘダーは最近、息子が少し変わったという報告を思い出す。
以前は嫌がっていた授業や訓練にも熱心に取り組み始めたと聞いていた。
王の代理として処理していた業務も、以前はいい加減に片付けたり逃げたりしていたが、最近では専門家を呼んで意見を聞くようになったとも聞いている。
突然、息子が成長したのは喜ばしいことだが、それはアイリス・バーンズ嬢の良い影響だったのだ。
「そう、試験はそのまま進めることにしましょう」
「母上、アイリスのティーパーティーはどうでした?」
話を終えようとする母の言葉に、リアンは慌てて尋ねり。
このまま話が終わってはいけない。
アイリスがそのせいで損をすることがあってはならないのだ。
彼女に挽回させてあげなければならない。
息子の質問にヘダーは微笑んだ。
彼女はパンを裂きながら言った。
「心配いらないわ。バーンズ家のティーパーティーの点数が一番高かったから」
リアンの目が大きく見開かれる。
しかし彼はすぐに笑顔を見せ、ようやく自分の皿に盛られた料理を食べ始めた。
「美味しいですね」
母と息子の会話。
王妃もアイリスのことを気に入っているみたいです。
今のところアイリスが第1候補のようですね!