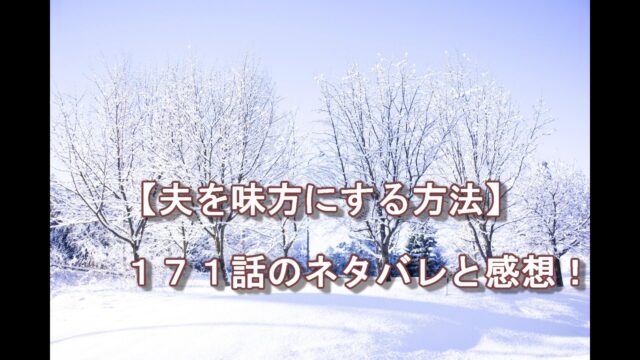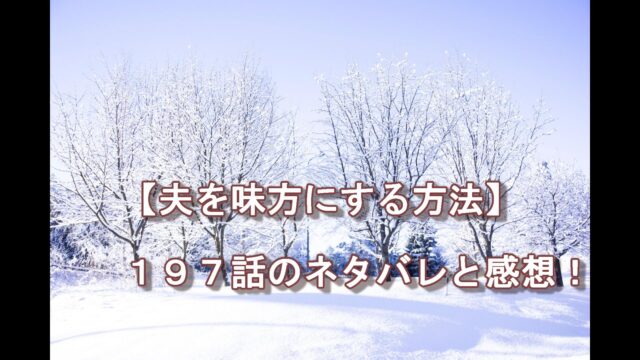こんにちは、ピッコです。
「夫を味方にする方法」を紹介させていただきます。
今回は198話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

死ぬ前に読んでいた本の中の悪女ルードべキアに憑依してしまう。
前世では養子となった家族から虐待を受けていたけど、ルードべキアも同じような境遇だった…。
しかも父によって政略結婚させられた北部最高の冷血な騎士イースケは原作で自分を殺すことになる夫だった!
小説の内容をすでに知っているルードべキアは、生き延びるために夫を愛する演技をするが…
ルードベキア:ルードベキア・デ・ボルヒア。本作の主人公。愛称はルビ。
イースケ:イースケ・バン・オメルタ。ルビの結婚相手。愛称はイース。
エレニア:エレニア・バン・オメルア。イースケの妹。愛称はエレン。
フレイヤ:フレイヤ・バン・ピュリアーナ。イースケの幼馴染。
ボルヒア:教皇。ルビの父親。
チェシアレ:チェシアレ・デ・ボルヒア。長男
エンツォ:エンツォ・デ・ボルヒア。次男。
ローニャ:ルビの専属メイド

198話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ちび王子様の夏⑦
とにかく、ダニルは泣き止んだ。
泣き止んだのはいいけれど、今度はお腹が空いたと訴え始めた。
私もお腹が空いていた。
財布をひっくり返していたユリが、自分の小遣いがなくなっていると文句を言ってる。
財布をひっくり返しても何の助けにもならなかったが、悔しい気持ちだった。
どこかに食べ物はないか?
周囲を見回しても、大きな岩とごつごつした地面ばかりだった。
「ユリ、こんな大きな岩を見たことある?」
「いや。でも、ここはもしかして巣じゃないかな?ものすごく大きな鳥が住んでいるのかも。」
「そんなに大きな鳥が本当にいるのかな?ひな鳥も見当たらないし。」
「親鳥がひなを隠しているのかもしれないじゃない。」
私たちは立ち上がって、巨大な巣をあちこち見渡し始めた。
そうすると、一方にだけ植物のつると枝がぎっしり詰まっているのが目に入り、それを手でどけてみる。
湿って崩れかけた枝が飛び散りながら、隙間が現れた。
そのとき、私の隣でじっと震えていたダニルが突然叫んだ。
「わあ、本当だ!見てこれ!」
「何?ひな鳥でもいるの?」
「いや、卵だよ!」
本当に卵があったのだ!
慌てて駆け寄り、目の前にあるその卵を見て、私は思わず息を飲んだ。
庭で遊んでいて鳥の巣を見つけることは何度かあったけれど、こんなに大きな卵は初めて見た。
その大きさはほぼ私たちと同じくらい。
しかも、その色も少しおかしかった。
なんともいえない紫色が微妙に混ざった奇妙な色だった。
「これ、何の卵なの?何の卵だと思う?」
木の枝を拾ってきたユリが、その奇妙な卵の表面をつつき始める。
卵があると主張したのは自分だったのに。
「やめて、それで割れたらどうするつもり?」
「食べればいいんじゃない?」
「卵をそのまま食べるの?」
「知らない。でも、冒険の本ではみんなそうしてるじゃん。」
確かに本に出てくる冒険家たちはそうしていた気がした。
でも、どんなにお腹が空いていても、生きたままのひな鳥が入っている奇妙な卵を食べる気にはなれなかった。
「やめておきなよ・・・。」
そこまで言ったところで私は口を閉じた。
ダニルがなぜそんな顔をするのか気になりつつ、何も言い返せなかった。
息が詰まるような感覚があったからだ。
代わりに手を伸ばして、卵をつつき続けていたユリの腕をつかんだ。
ユリが私をじっと見つめる。
私は何も言わずにユリの後ろを隠れるようにして見ていた。
そのうち、私たち全員がそれを目撃した。
それはまさに巨大な鳥だった。
ユリが言っていた通り、とてつもなく大きな鳥だった。
問題は、どこか奇妙だということだ。
くちばしが非常に長くて細いのはさておき、全体の見た目は立派なカナリアのようだったが、足が四本もある。
しかも、そのうち二本はどう見ても鳥の足ではなかった。
さらに、あれは尻尾ではないのか?
まるで誰かが変なカナリアに猫の尻尾を切ってくっつけたようで、その体だけが異様に大きくなったように見えた。
そして、その奇妙な鳥はなぜかとても怒っているように見えた。
「わあ、でっかい鳥だ!」
ユリが驚いた声を上げたと同時に、その大きな鳥が私たちに向かって突進してきた!
私たちは悲鳴を上げながら、無我夢中で逃げ出した。
横に飛び込んだ。
ざわざわした髪の上を冷たい風が吹き抜けた。
「ギャアアアアー!」
大きな鳥が怒りに満ちた声を上げる。
かすれたようなその声は少し滑稽にも聞こえたが、恐ろしくてまったく笑えなかった。
しばらく上空を旋回していた大きな鳥が、恐ろしい鋭い爪を広げながら再び降下してきた。
そのまま私の頭を掴み取ろうとでもしているかのようだった。
「うわああああああ!」
私たちはほとんど一つの塊になって転げ落ちるように巣の外に飛び出した。
もっと遠くまで逃げたかったが、それも叶わなかった。
しかし、その瞬間、上空から「ポンッ」と不気味な音が聞こえてきた。
それと同時に、大きな鳥が再び叫び声を上げる。
「ギャアアア!」
「わあ、もっと大きい鳥だ!」
ユリが感嘆の声を上げたが、今回は特に驚くような感じではなかった。
突然現れて、短くて太った足を持つさらに大きな鳥は、立派なカナリアに似ているようでいて全く違った。
以前、本で見たような毒蛇と豹を混ぜたような雰囲気を持っているように見えた。
と
にかく、でっぷりとしたその巨大な鳥は空中で旋回し、巣の近くを回ってから一方向へと降りていく。
その大きな鳥は少し疲れているようだった。
羽をばたつかせ、しばらく誰の目にも止まらないような仕草で周囲をうかがっていた。
さらに大きな鳥がその前に降り立ち、じっと見つめていた。
その直後、大きな鳥はついに正気を取り戻したようだった。
「ギャアア!」
「プルルル、プルン・・・」
「ギャアア、パッ!」
「プルルル!」
何をしているのだろう?
彼らが何者かはわからないが、今の様子を見る限り、大きな鳥がさらに大きな鳥に向かって何かを訴えているようだ。
不思議なことに、直接襲い掛かる様子はない。
「ねえ、あいつら何をしてるんだろう?」
「わからない。同じ仲間ではないみたいだけど・・・。」
奇妙な怪物のような鳥たちが言い争う隙を見て、私たちはそっと後退し始めた。
さっきは気づかなかったが、よく見ると一方向に森へ通じる道が開けていた。
「ギャアアア!」
大きな鳥が相手に向かって激しく鳴き声を上げるのを合図に、私たちは後ろを振り返ることなく全力でその道を駆け出した。
途中、私たちは茂みの中の小さな水たまりに飛び込んだ。
「そこだ!」
ほぼ自分たちの背丈ほどの水たまりを抜け、次にどちらの方向へ進むべきかを考えながら進むと、大きな木の根元に洞窟の入り口が見えた。
私たちはすぐさまその木の洞窟に入り、一息ついた。
胸がまだ激しくドキドキしていた。
暗い洞窟の中で私たちはみんなうずくまって息を整えていたが、誰も口を開かなかった。
正直、話す気力もない。
恐怖で疲れ切っていて、お腹も空いていた。
そして母に会いたくなった。
「アリョシャ・・・。」
ゴロゴロ、バン!
ダニルが私に何か言おうとした瞬間、外で突然雷鳴がとどろいた。
あまりの驚きに私たちは全員しばらく固まってしまった。
まさか、こんなところで雷雨に遭うなんて!
どんな冒険の道が険しいとしても、これは本当にひどすぎる。
私の隣で丸くなっていたダニルが、再び小声で話しかけてきた。
「アリョシャ、雨が降ってきた。」
「雷雨だからすぐ止むよ。」
「本当にそうかな?もし止まなかったらどうするの?」
どうしようもない。王子様だって雨には勝てないんだから。
私?疲れていたからか、特に苛立つこともなかった。
その代わりに、ユリがやたらと説教を始めて少し苛立っていた。
するとダニルが、鼻をすすりながら頭を掻いて、何やら怪我をしたようだとつぶやいた。
「怪我したって?どうやって?」
「わからない。でも血が出てる。」
暗くて詳しくはわからなかったが、ダニルの頭からは確かに血が滲んでいるようだった。
遊んでいてどこかを少し擦りむくなんてことはよくあることだし、気にしすぎる必要はなかった。
私たちはみんな、それくらいで泣く年齢ではない。
ただし、見た感じではダニルが一番ひどい状態だった。
ユリが待ち構えていたかのように、意地悪そうに言った。
「おい、正直に白状しなよ。私たちよりたくさん食べたからそれがバチ当たったんでしょ?」
「バチじゃないよ?それに、私が言ったわけじゃなくてアリョシャが言ったんだ!」
「何だって?!」
ユリが私に飛びかかろうとした瞬間、私は背中からひっくり返って地面に尻もちをついた。
何か起きたのかと大げさに騒いでいたダニルが、本当に血が出ていると言いながらさらに大声で叫び始めた。
「どこも痛くないのに、一体どこから?」
「ここだ、ここ。触ってみて!」
「お前の思い込みだろ・・・あれ?本当に血が出てる。」
右耳のあたりに手を当ててこすってみると、少しヒリヒリした。
指先をよく見てみると、やはり血がついている。
どうやら逃げる途中でどこかに引っ掛けたらしい。
ただ、どうして私よりもユリとダニルがこんなに大騒ぎしているのか理解できなかった。
ユリは鳥の羽をつけて飛ぼうとするように、「私がいなければ、誰があなたをライバルとして相手してくれるの?」などと訳のわからないことを言いながら騒ぎ立て、ダニルはダニルで静かにすすり泣いていた。
何か言おうとしたが、彼らには何も聞こえていないようだった。
暗くて湿った洞窟の中でこんな状態でいるなんて、本当に最悪だ。