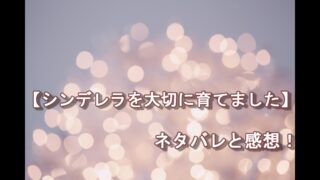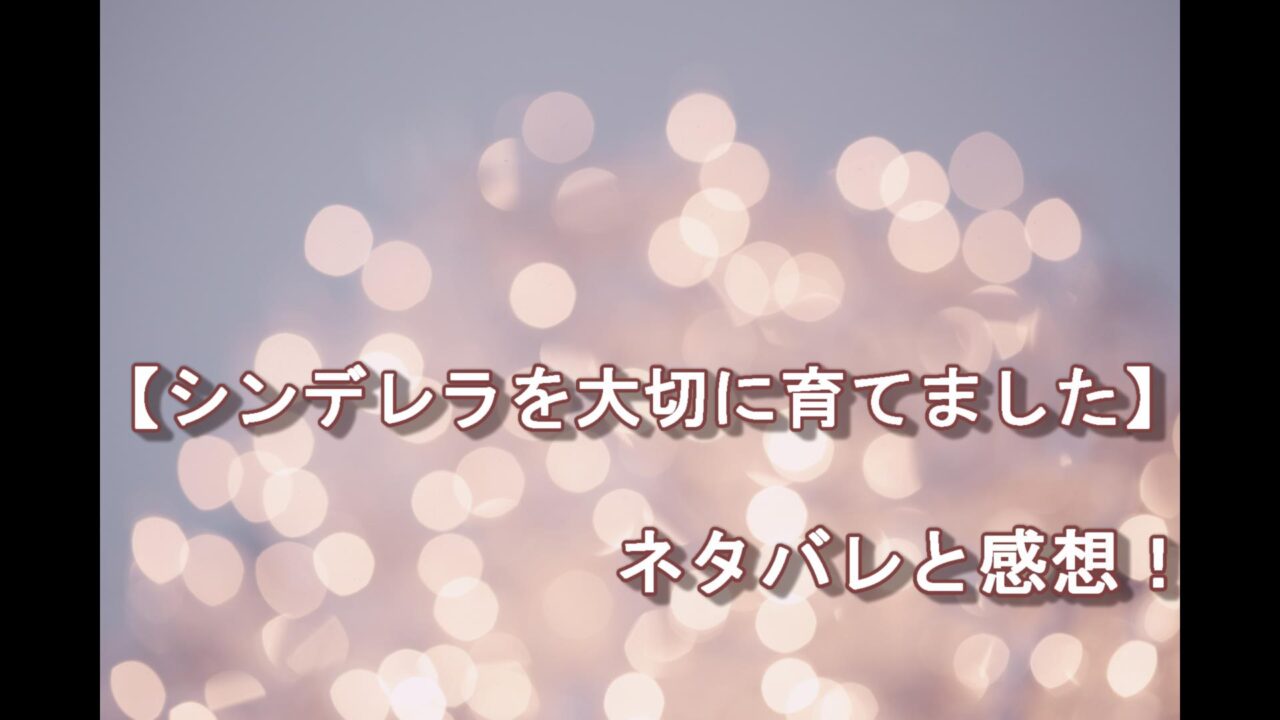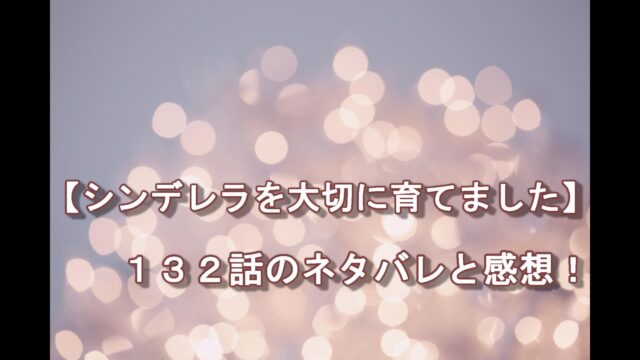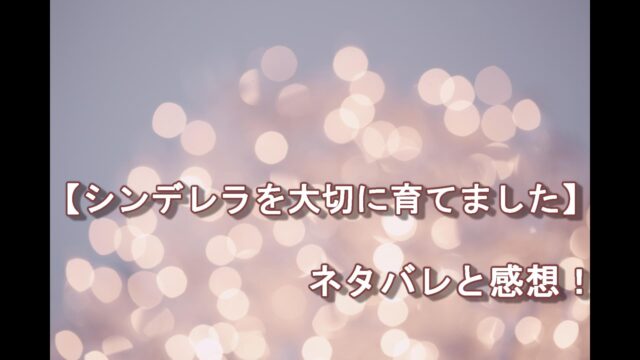こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は165話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

165話 ネタバレ
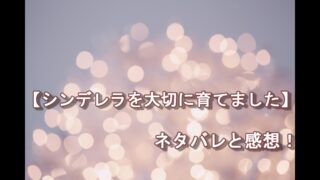
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 結婚観②
その時、ジェネビーブが面白がるような口調で言った。
「お二人はとても仲が良いのですね。」
応接室にいた全員が、私とダニエルを見つめた。
手紙のやり取りについて話すのは、客人を前にして適切ではない。
私はすぐに姿勢を正して謝罪した。
「申し訳ありません。ウィルフォード男爵に、王子様がどれくらい滞在されるか伺っておりました。」
嘘だが、そう言うのが自然だろう。
リアンはすぐに答えた。
「今晩まで大丈夫です。」
「それでは、殿下。夕食をご一緒する栄誉をいただけませんか?」
リアンの表情が明るくなった。
一方で、ジェネビーブの顔は少し曇っている。
私はリアンが返事をする前に、ダグラスにも声をかけた。
「ケイシー卿も、もしお時間があれば侯爵夫人と一緒に夕食を召し上がってはいかがですか?」
その瞬間、ジェネビーブの表情が和らいだ。
そういうことか。
私は彼女の顔が硬かった理由が理解できた。
自分だけが招待されて息子が招かれないのではないか、と心配していたことに気づいた。
「ありがとうございます。」
ダグラスは私の言葉が終わるや否や、すぐに返事をした。
そして少し焦った表情でジェネビーブを見つめて尋ねた。
「お時間は大丈夫ですか?」
ジェネビーブは少し呆然とした表情だった。
彼女はかすかに笑みを浮かべ、私に向かって言った。
「ご招待ありがとうございます。それに、バンス家の驚くべき料理の腕前が気になっていたところです。」
ケイシー侯爵夫人が私の料理の評判を知っていることに驚いた。
私は居間にいる召使いに夕食の準備を頼むため、席を立ちながら言った。
「まだ夕食の時間まで余裕がありますので、出かけてこられても構いませんよ。私たちも墓地に行かねばなりませんので。」
「大丈夫です。」
今回もダグラスが先に返答した。
私はケイシー侯爵夫人に微笑みかけながら応接室を出た。
その後ろからダニエルもついてきた。
「侯爵夫人が来られるとは思いませんでした。」
「リリーが気になって来たのでしょう。」
私の返答に、ダニエルの視線はリリーへと向けられた。
彼女はアシュリーと一緒に立っていた。
アイリスもアシュリーの近くで、こちらをじっと見つめている。
「侯爵夫人はリリーについて何か言いましたか?」
「まあ、あれほど露骨なことはないでしょう。」
ケイシー侯爵夫人の言葉は、リリーがダグラスと必ず結婚しなければならないかのように聞こえた。
彼女がダグラスの母親である以上、仕方がないことだろう。
「リリーを説得するつもりですか?」
ダニエルの質問に、私は首を横に振った。
正直に言えば、私もリリーがダグラスと結婚してくれたらいいとは思う。
あれほどリリーを想い、彼女のために努力しているのだから。
しかし、リリーが嫌ならそれでいい。
ダグラスが良い人で、条件が揃っているからといって、その努力が必ず報われなければならないわけではない。
「私の娘は、誰かの努力の報酬や代償ではありません。」
私はダニエルの頬に軽くキスをしてそう言い、台所へと向かった。
客は6人、我が家の人数を合わせると5人。
合計11人分の食事を用意しなければならないので、台所の料理人に頼む必要があった。
「お肉が足りません。」
フィリップまで来るとなると9人分になる。
料理人が困った顔で言った。
牛肉の在庫が不足しているのだ。
一人か二人が食べられる程度しか残っていない。
豚肉は幸いにも家族が食べても余るほどあるが、それでも9人分には足りないそうだ。
鶏肉は使用人たちが食べる分だけしか残っていなかった。
「サラダを出すのは・・・。」
「侯爵夫人と王子様は気に入らないでしょうね。」
野菜を好んで食べる人ならともかく、貴族はあまり野菜を好まないので、こんな時にサラダを出すのは気が引ける。
少し考え込んだ後、料理人がメニューを提案した。
「肉を全部挽いてミートローフを作るのはどうでしょう?」
それも微妙だ。
中にパン粉や野菜を混ぜてかさ増ししている感じがして、他に何か付け合わせがないと、侯爵夫人や王子をもてなすには物足りない気がする。
「豚肉はたくさんあるの?」
私の質問に料理人は首を振りながら答えた。
「細かく切れば7人分くらいにはなるでしょう。でも、それが限界です。」
「もっと細かく切ればいいじゃない。」
料理人の顔には「何を言っているんだ?」という表情が浮かんだ。
しかし、いい考えが浮かんだ私はワイン貯蔵庫へ向かいながら言った。
「一口サイズに切って、塩と胡椒を振ってください。それを揚げるのよ。」
家の地下にあるワイン貯蔵庫で、ワインビネガーを探し出したことを思い出す。
料理人が高級だと褒めてくれたものだ。
それを使って甘酢ソースを作ればどうだろう。
色は少しくすんでしまうかもしれないが、私の記憶にある甘酢ソースは醤油や澱粉を加えて濃厚かつツヤがあるものも多かった。
私の説明を聞いた料理人は黙々と、たくさんの豚肉を一口大に切り始めた。
アイリスのティーパーティー以来、彼は非常に協力的に動いてくれている。
料理を任せて、私は棺を静かに運ぶ準備のため、2階の自室へ向かった。
棺を運んで戻ってくると、料理人は豚肉を牛乳に漬け、一度揚げて私を待っていた。
「ケイシー卿。」
「こんにちは、侯爵夫人。」
フレッドの棺を運んで戻る途中でフィリップに出会ったため、招待客は3人から4人に増えていた。
9人分の食事を準備しておいて正解だった。
私は客人を食堂に案内し、席に着くと、料理人が甘酢豚を運んできた。
「これは甘酢豚です。」
「それは何ですか?」
「肉を揚げたものです。上にかかっているソースはワインビネガーで作ったものです。」
私の説明に、ケイシー侯爵夫人の目が大きく見開かれた。
彼女はこれを食べても良いのか迷っているように周囲を見回したが、リアンが迷わず肉を口に運ぶのを見て驚いた顔をした。
「美味しいですね。」
「甘酸っぱくていい。」
リアンとダグラスの称賛に、ジェネビーブも勇気を出して一切れ食べた。
そして、タイミングよく料理人がサラダも持ってきて言った。
「牛肉のサラダでございます。」
その瞬間、ジェネビーブから感嘆の声が聞こえた。
「あら、美味しいわ!」
サクサクに揚がった肉と甘酸っぱいソースの組み合わせに、彼女も満足そうだった。
味が悪いはずはない。
私はダニエルを見てにっこり笑った。
ダニエルも私を見て笑っていた。
「バーンス家の子どもたちを招待したいのですが。」
食事を終え、簡単なデザートまで食べると、ジェネビーブが上着を整えながら私に尋ねた。
本日のデザートは桃のバラのタルト。
アイリスのティーパーティーで料理人に教えたものだが、最近彼はこれをさまざまな方法で作っていた。
桃を薄くスライスして花びらのように並べたり、パイ生地を手のひら大にして一人分の花のタルトを作ったり。
私は料理人がパイの上に刻んだチェリーを2、3粒置いているのを見て、軽く感心した。
確かにひとつアイデアを出せば、彼のような専門家たちは素晴らしい応用力を発揮するものだ。
少し前に作り方を教えたカステラも同じことだ。
厨房の使用人たちは、すでにカステラを分厚く焼き、その間にジャムやクリーム、切った果物を詰めて売り始めた。
「光栄です。」
私は笑顔で答えた。
そして何も考えていないように見えるリリー、アシュリーとは対照的に緊張しているアイリスを見回した。
緊張するべき人が間違っているのではないか?
緊張しているのはダグラスも同じだった。
彼は何とも言えない表情で母親に何かを言おうとしたが、その前にフィリップが彼の肩を軽く叩いて気をそらす様子が見えた。
「それでは、すぐに招待状をお送りします。」
ケイシー侯爵夫人はそう言うと、子供たちを一人一人見つめてから席を立った。