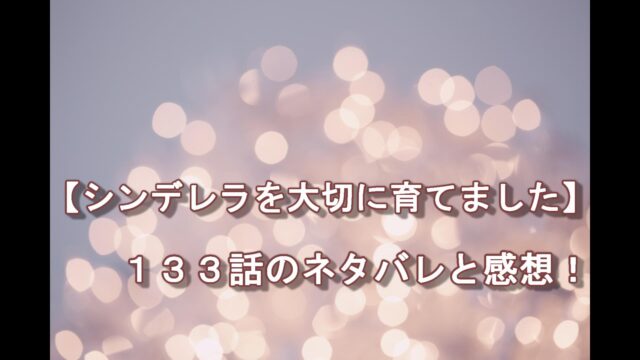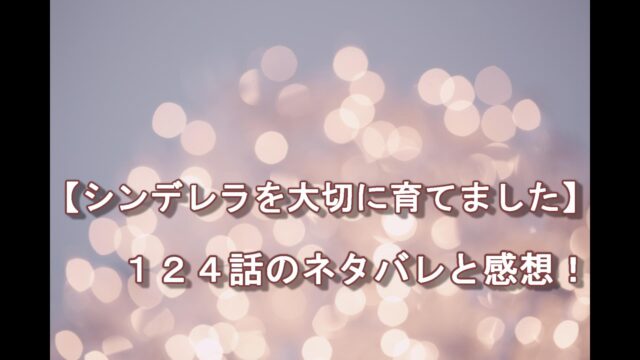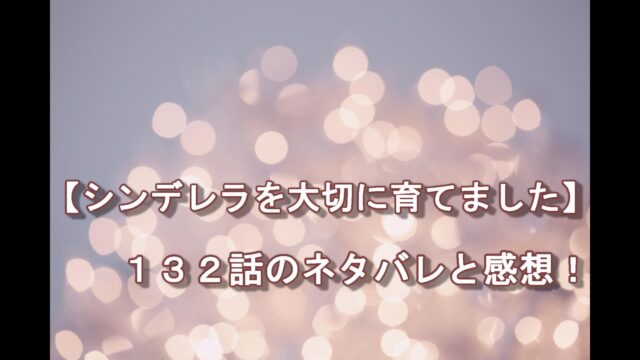こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

186話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 3人の候補者⑤
「ちょっと待ってください!」
叫んでみたものの無駄だった。
本当に一人で服を着るのが試験のようだった。
「あり得ない…。」
アイリスは下着姿のまま茫然と立ち尽くし、ドレスの入った衣装ケースを見つめた。
このドレスを一人でどうやって着るのか。
普段着ならともかく、公式な場で着るようなドレスは複雑で、一人で着るには時間がかかる。
過去に侍女がいない場合には、寮の仲間同士で助け合いながら服を着たこともあった。
しかし、今回は助けを求めようと扉を開けて廊下を見渡してみても、侍女たちはいなかった。
明らかに「助けるな」という指示が出ていたようだ。
彼女は誰かが近づいてくるのを見て期待を膨らませたが、それが男性だと気づくと急いで部屋の中に入り、扉を閉めた。
「まさか、呼びに来たのではないでしょうね?」
アイリスはそう呟きながらも心を決めた。
誰かが彼女を呼びに来て、その人の助けを借りるという計画は危険だ。
その人が男性である可能性もあるし、予期せぬタイミングで呼びに来るかもしれない。
国王や王族と一緒に参加する食事会で失態を晒すわけにはいかない。
「できるわけがない。」
アイリスは侍女が置いていったドレスを手に取った。
仮縫いをしている時に何度も試着しているので、着方は覚えている。
手が必要なのはその複雑さのためだ。
彼女は下着とペチコートを身につけ、ドレスを床に広げて置いた。
そして慎重に体を入れた。
彼女はスカートの裾を手に取り、下からドレスを引き上げた。
「面倒くさいわね。」
袖に腕を通すと、アイリスは大きくため息をつき、戸惑い気味に動きを止めた。
幸いにも夏用の軽い生地だったが、もし冬用の重い生地だったら大変なことになっていただろう。
彼女はスカートを持ち上げた後、同じようにクリノリンを床に広げ、その中に入った。
そしてスカートの内側にクリノリンを収めるように持ち上げた。
侍女がいれば、クリノリンを最初に着用し、侍女が髪型を乱さないように上からドレスを着せてくれただろう。
しかし、一人で着る場合はそうはいかない。
侍女がいない生活に慣れているおかげで、アイリスは一人でドレスを着る方法を熟知していた。
彼女はクリノリンがスカートの内側でしっかり収まるように何度も整え、その上にスカートを下ろした。
そして、クリノリンが見えていないかを全身鏡の前で前後から確認した。
問題は背中のリボンを結ぶことだった。
アイリスは腕を伸ばして背中にあるリボンを掴み、上手く調整して結ぶ必要があった。
彼女はそのままそろそろとドアの方に向かって歩き出した。
「すみません。」
幸いにも、通りかかった人がいた。
アイリスはその女性の服装を見て、その人が侍女ではないことに気づいたが、それでも仕方がなかった。
男性でなくて本当に良かった。
男性であれば頼むわけにはいかなかっただろう。
通りかかった女性はアイリスの呼びかけに振り向き、扉を少しだけ開けてアイリスの方を見た。
「こんにちは。私はアイリス・バンスと申します。」
初めて見る顔だったが、城内にいること、そして侍女ではないことから、その女性が貴族であると察した。
アイリスはその判断に基づき、礼儀正しく自己紹介をする。
予想外に自己紹介を受けた女性は戸惑い、思わずこう答えた。
「ランバート伯爵夫人です。」
「ランバート伯爵夫人、少しお願いしてもよろしいでしょうか?」
ランバート伯爵夫人は驚いた表情を浮かべた。
彼女はこの場に一時的に滞在しているだけで、王妃候補たちの家族が王妃候補を監視しないように見張るために来ているだけだ。
この試験は、王妃候補たちが一人では難しい仕事をどうやって周囲の人に助けを求めるかを評価する目的で行われているもの。
当然、見知らぬ人々から助けを得ることが試験の一部だった。
他人に助けを求める条件が課されていた。
アイリスが侍女を呼ぶようお願いする場合でも、彼女はできる限り遅く呼びに行くだろうと予測していた。
それは決してアイリスに対する悪意からではない。
むしろ、クレイグ侯爵夫人から「他の候補者を極力助けないでほしい」と依頼されていたからである。
「何ですか?」
侯爵夫人が戸惑いながらアイリスに近づくと、アイリスは彼女が部屋に入れるようドアを開けて中へ案内した。
そして鏡の前に進み、リボンの一端を侯爵夫人に差し出した。
「これを持ってください。」
「持てと?持つだけでいいんですか?」
「はい。持ってくださるだけで結構です。」
目の前でリボンを持つようお願いされるのを嫌がる様子は見えたが、拒否することもできない。
アイリスが彼女の名前を知っている状況で、この試験が終わり、相手が「ランバート侯爵夫人」という人物からの依頼を断るのは難しいだろう。
困惑していた侯爵夫人は、仕方なくアイリスが差し出したリボンを手に取った。
そしてアイリスは熟練の手つきでそのリボンを引き寄せ、ドレスを締め始めた。
助けがなければ一人でドレスを着るしかなかったとしても、リボンを握ってくれる程度の手助けなら問題ないだろう、とアイリスは考えていた。
そして、不器用なアシュリーのおかげで、一人でリボンを結ぶことにも慣れていた。
もちろん誰かがリボンを持ってくれた方がよいが、家ではアシュリーがほとんど役に立たなかったため、リボンを押さえてくれるだけでもありがたい存在だった。
「できました。ご協力ありがとうございました。」
わずかな時間でリボンがしっかり結ばれたことを確認すると、アイリスは体を回して礼を述べた。
ランバート侯爵夫人に対して感謝の気持ちを伝える彼女の姿に、侯爵夫人は困惑して目をぱちくりさせた。
信じられない。
このお嬢様が一人でドレスを着たというのか?
頭の中でアイリス・バンスというお嬢様に関する情報が浮かび上がった。
バンス家は経済的に厳しいと聞いていた。
娘が三人いるとか。
三人の娘がいれば、少なくとも侍女が一人か二人はいるはずだ。
一人でドレスを着るのが得意だというのは、つまり侍女の助けを借りずにドレスを着たということなのだろうか。
何ともランバート侯爵夫人はアイリスに対して感嘆を覚えた。
侍女を雇うことも難しいほどの状況で生活しているはずのお嬢様が、運よく王妃候補の試験を受けられる立場にいるとは。
このようなお嬢様を助けることさえしない自分の態度を思い返すと、侯爵夫人の心には半分罪悪感、半分感銘を受けた気持ちが交錯し、そっと彼女を見つめるのだった。
「振り返ってください。リボンをもう一度結んで差し上げますわ。」
「いいのですか?」
「リボン程度なら大丈夫ですわ。」
侯爵夫人は戸惑いながらもアイリスの後ろに回り、彼女のリボンを解いてもう一度美しく結び直してあげた。
そしてリボンが解けないように自分の髪留めを使ってしっかり固定することまでしてくれた。
「お手先がとても器用ですね。ありがとうございます、ランバート侯爵夫人。」
美しく整えられたリボンを見て、アイリスはぱっと笑顔になり、感謝の言葉を述べた。
それだけでランバート侯爵夫人の中でアイリスに対する印象が大きく変わった。
困難を乗り越え、王妃候補となった素晴らしい資質を持つ若い女性。
ランバート侯爵夫人は心の底から、アイリスが王妃になってほしいと考え始めた。