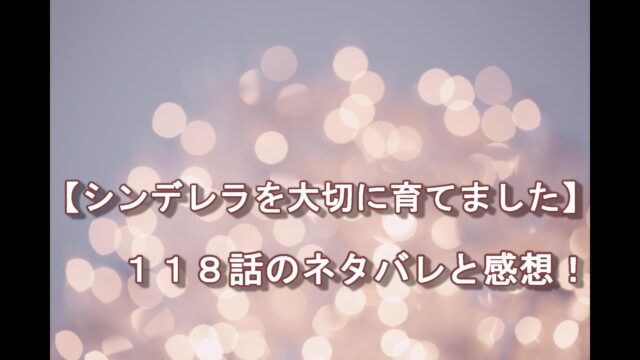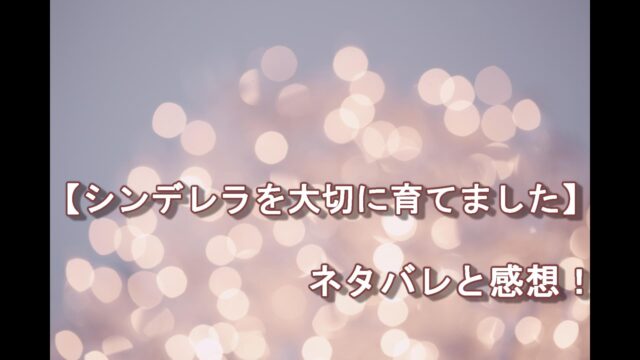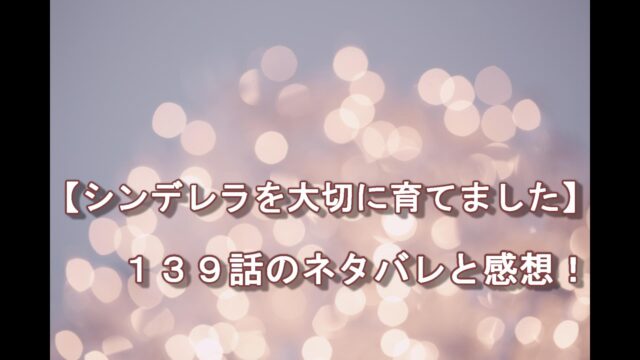こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

192話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 試験の結果③
「それで、どうして?」
アイリスが尋ねた。
ダニエルが大丈夫だと言っても、彼女はまだ心配そうだ。
私は彼女に近づき、肩を抱きながら言った。
「前に城で行われた試験の結果がまだ出ていないんだ。だから、君が経験したことの中に、誰かの役に立つようなことがないかと思って聞いてみたんだ。」
「誰かの助けを受けたことがむしろ感謝されるべきではないですか?」
彼女はそう反論する。
しかし、私はアイリスがまだ心配しているように見えた。
私は彼女が安心するように、少し気まずそうに言った。
「ウィルフォード卿が適切に状況を見て話をしてくださるわ。」
驚いたことに、アイリスはその言葉だけで安心したような表情を浮かべた。
ダニエルのことを少し怖がっているようだが、彼の仕事ぶりには信頼を寄せているのだろうか?
周りの者たちはそう思っているようだが、なぜ彼を恐れるのかは分からなかった。
私はアイリスと一緒にケイシー警部補を案内するため、応接室に向かいながら軽く尋ねた。
「ところで、あなた、ウィルフォード卿が怖いの?」
「え、怖くなんかないですよ……。」
怖くないと言うのなら、何だって言うのだ?
私が困惑した表情を浮かべると、アイリスは口をつぐみ、唇をかみしめた。
そして、まるで後ろにダニエルがいるかどうか確認するかのように振り返った。
ダニエルは少し前に出て行った。
アイリスがランバート夫人から助けを得たという話を聞くと、すぐにまた城に行かなければならないと言って立ち去ったのだ。
アイリスのためにこれほど尽力してくれる人を怖がるなんて、ありえない。
アイリスがダニエルを怖がる理由をどうにかして理解しなければならないと思った。
「旦那様、妖精ですよね。」
「それで?」
「妖精が何を考えているのか分からないんです。」
なんだって?
私は笑いながら聞き返した。
「妖精だと知らなかった時も、彼が何を考えているのか分からなかったでしょ?」
確かにダニエルが妖精でもそうでなくても、彼の考えを読むのは難しい。
それが彼の魅力の一部ではあるけれど、時々それがイライラすることもある。
「そうだけど、人間だと思っていた頃は、旦那様が取る最悪の行動が少なくとも想像できたの。でも妖精となると、それが全く分からないの。」
「アイリス、誰かが君に悪口を言ったり、大声を上げたりしたら、絶対に黙っていないで。立ち向かって、その言葉を後悔させてやりなさい。」
アイリスの目が丸くなった後、すぐに柔らかくほころびた。
彼女は私に微笑みながら言った。
「はい、心配しないでください。」
そう、その通りだ。
私は肩を叩きながら応接室に向かった。
リリーと一緒に座りながら何か楽しい話をしていたフィリップは、私が入るとすぐに立ち上がり挨拶をした。
「良い午後ですね、バンス夫人。」
「どうも、ケイシー卿。リリーを集会に連れて行かれるんですね?お心遣い、ありがとうございます。」
「いいえ、才能ある画家を紹介できることは私の大きな喜びです。リリーにとってもきっと役立つでしょう。」
それに異論はない。
リリーはもっと多くの人々と出会い、より多くの経験を積むべきだ。
しかし、私は相手の言葉に反応せず、心配そうな表情で答えた。
「リリーのことをこうして気にかけてくださり、本当に感謝しています。ただ、以前お手紙でも申し上げたように、リリーの安全を最優先に考えていただけると嬉しいです。」
少し前、リリーを連れて行く許可を求めるフィリップからの手紙に対し、私はそのように答えていた。
リリーを連れて行ってくれること自体はありがたいが、彼女の安全を最優先に考えてほしいと。
フィリップを信用していないわけではない。
ただ、少し前にアシュリーの件があったので、どうしても心配になってしまう。
気持ちとしては私も一緒に行きたいが、それはリリーが絶対に望まないことだろう。
「私は大丈夫ですから。」
リリーは不満そうな表情をしていたが、フィリップは違う。
彼は真剣な表情で手を胸に当て、言葉を紡いだ。
「リリーの安全を最優先に考えることをお約束します。」
「ケイシー卿がそこまでしてくださるなら、少し安心しました。本当にありがとうございます。」
「いいえ。大切な家の娘さんをエスコートするわけですから、これくらいは当然です。私は家主としてもリリーをしっかり守りますので、ご心配なく。」
その集まりはカフェで行われるのではなかっただろうか?
貴族たちはお茶を楽しみ、貴族でない知識層はコーヒーを嗜む。
だから芸術家たちの集いもカフェで行われると聞いていた。
私が困惑した表情を浮かべると、フィリップが穏やかな表情に変わった。
「リリーを連れていく集まりの場所を変更しましたが、それをお伝えしていませんでした。申し訳ありません。いずれにせよ、市内のカフェよりもこちらの方が良いと思います。そちらの奥様も安心されるでしょう。」
「それはどこなの?」
私はフィリップに視線を向けて急いで尋ねた。
「ブイ氏のギャラリーです。」
ん?
ちょっと待って、ブイといえば私がカイラの絵を売る際にフィリップと競り合ったあの人物だよね?
一度会ったこともある。
フィリップがギャラリーに招待してくれた時もその場にいた。
ラントルフ・ブイ。
どんな顔をしていただろう?
顔は思い出せないけど、制服を着ていたことだけは覚えている。
そして、フィリップより背が低かったことも。
「ブイ氏と親交があるようですね。」
私の言葉にフィリップの顔が少し明るくなった。
彼がラントルフを一目置いていることは知っていた。
しかし、今回招待されるということは、親しくなったようだ。
いや、そうではない。
むしろ親しくなったのではなく、ラントルフがフィリップに、いかに自分が親しい画家が多いかを誇示するために招待した可能性もある。
前回、ラントルフが自分のギャラリーに招いた際のように。
私は自分の言葉に反応できずにいるフィリップを見て、目を細めた。
すると彼は一呼吸置いて、声を落として言った。
「恥ずかしいことですが、私がリリーを連れて行き出席することが、彼女にも大いに役立つでしょう。」
確かに。
彼の言葉が意味するところは理解できた。
ラントルフが自分の知り合いの画家を誇るように、フィリップはリリーを誇りたいということだ。
私は内心で少し困惑しながらも、微笑みを浮かべてフィリップに言った。
「それなら安心しました。リリーが素晴らしい経験を積めることを願っています。」
「ありがとうございます。リリーもきっと多くを学ぶことでしょう。」
リリーは私に目配せをし、私も彼女に微笑み返した。
彼女の瞳には期待と興奮が輝いていた。