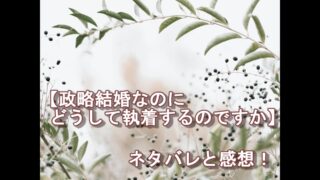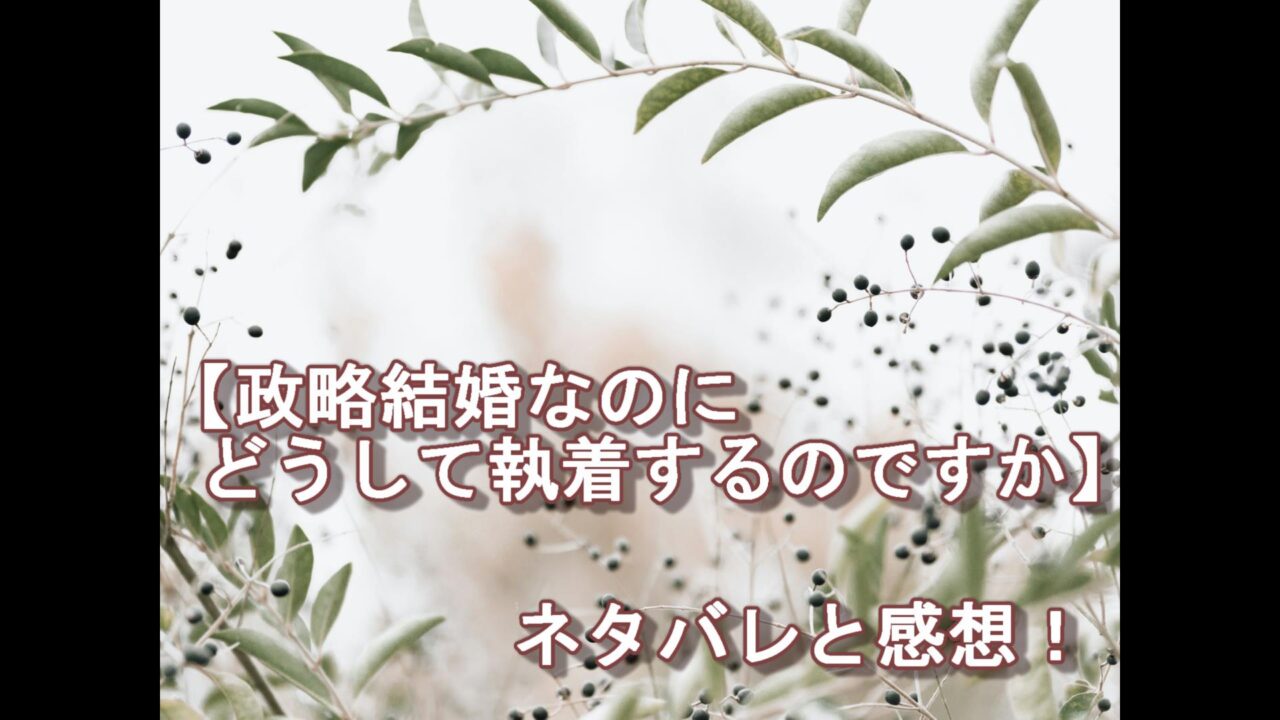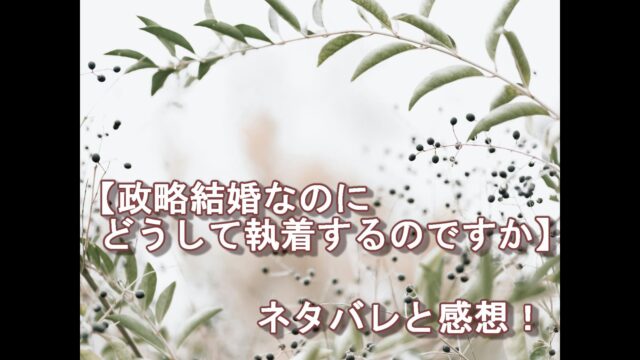こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

97話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 死を迎えた時期③
温かく沸かした水を飲みながら、フレイが尋ねた。
「侯爵夫人は、王位継承の問題がこの会議場の中で対話によって解決される可能性がどのくらいあると思いますか?」
「それは私も伺いたいテーマですね。殿下はどうお考えですか?」
「0割。」
少しの迷いもなくすぐに返ってきた答えに、ナディアは非常に驚いた。
「それでも不自由で、お忙しい方々が一堂に会する理由は何でしょうか?」
「無理に事前布告なんてしたら、体裁が悪くなるじゃない?『私たちはやるべきことはやった』って、名分を積み上げている最中なんだ。」
ナディアは先ほどよりさらに驚いた。
どうやら見えないところで遊んでばかりいたわけではなさそうだ。
彼女は思わず拍手を送らずにはいられなかった。
「素晴らしいですね。おっしゃる通りです。」
「外戚部のおかげさ。」
さらには剣の扱いまで知っているとは。
思わず感動の涙を流しそうになった。
だがナディアが感動しているのとは対照的に、
フレイの表情はどこか曇って見えた。
本来なら褒められると喜ぶタイプじゃなかったっけ?
ナディアは不思議に思いながら尋ねた。
「表情が暗いですね。何か気になることでもありますか?」
「また戦争が起きそうで嫌なんだ。魔族の侵略を防いでから、どれだけ経ったと思う?……人が死ぬのは嫌だ。東部の被害が完全に回復する前にこんなことが起こるなんて、それがただ悲しいだけなんだ。」
「………」
そう語るフレイは、本当に寂しそうに見えた。
しばらく地面を見つめていた彼は、苦笑いを浮かべながら口を開いた。
「僕があまりにも弱くて、失望した?リアムなら今ごろ、ひたすら勝利のことだけを考えているだろうね。」
彼の弟は、強く、賢く、決断力もあった。
冷酷な面はあるが、いずれにせよ自分の配下はしっかりと守る。
それだけで仕える価値のある主君ではないか?
だから、バラジット公爵が自分の弟に味方しているのは、ある意味とても当然のことだった。
しょんぼりした様子のフレイが肩をすとんと落としかけたそのとき――
「私はそれが殿下の長所だと思います。」
「えっ?」
「ある意味、それが殿下が王位を継ぐべき理由かもしれません。」
「そ、そうかな?」
「それに、罪悪感を持つ必要はありません。いずれは起こるはずのことでしたから。それが先王の突然の死によって、少し早まっただけのことです。」
「……」
フレイはしばらく何も言えなかった。
少し経って、彼は口元にかすかな笑みを浮かべながら言った。
「そんなふうに評価してくれて本当にありがとう。侯爵夫人と話していると心が楽になる。ウィンターフェル侯爵は良い妻を持っていて羨ましいよ。」
「恐れ入ります。」
彼が落ち込んだままだと厄介になる可能性もあったが、まったく心にない言葉というわけでもなかった。
うちの父親が、だからバラジット公爵のような人物が王になると考えてごらん。
『それは本当にぞっとする話だよ……。』
ナディアは思わず身震いしそうになった。
その後に続いた会話は、今の政局とは関係のない話ばかりだった。
飼っている犬が子犬を5匹も産んだとか、外泊している婿殿の小言が日を追うごとにひどくなっているとか、西部の料理が食べ慣れると意外と口に合うとか。
まるで複雑な現実から目をそらし、しばしの休息を取ろうとしているかのようだった。
数時間後、会談場のテントの中から誰かが重い足取りで歩いて出てきた。
荒々しい怒鳴り声が何度か響いた後のことだった。
フレイがつぶやくように言った。
「終わったのか?」
「結果はあまり良くなかったようですね。」
「うん、どうやらそうだ。」
その後に続いて領主たちがぞろぞろと出てくるのを見て、本当に会談が終わったのだとわかった。
会談場から出てくる彼らに共通する点が一つあるとすれば、それは皆、表情が険しいということ。
「侯爵夫人、それでは私は外叔父様のところへ行ってきます。」
「はい、また後ほど。たぶんそんなに時間はかからないと思います。」
「私もそう思います。」
グレンが現れたのは、大半の出席者たちが席を立った後のことだった。
ナディアは立ち上がって、近づいてくる彼を迎えた。
「どうだった?」
「もちろん、却下された。」
「それは私も予想していました。問題はその後です。遺言状を調査してほしいという私たちの要求に反対する人なんていないはずですよ。」
「何だって?くだらない言い訳を並べて言い逃れするとは。まったく話にならない条件を提示して、遺言状を……!」
激しく叫ぼうとした彼は、落ち着こうと深く息を吐いた。
いったいあっち側が何を言ったのか、グレンがここまで激しく怒っている理由が気になった。
ナディアが訝しげに尋ねた。
「いったいどんな条件だったんです? 領地を返還しろとか言ったんですか?」
「いや、そういうわけじゃなくて……」
「じゃあ?」
「公爵令嬢の身元を明かせ、というのが最初の条件だった。」
「……」
あまりにも不意を突かれて戸惑い、彼女は言葉を失ってしまった。
むしろ声を荒げたのは、他の家臣たちだった。
「一体どんな理由で一つの家門の夫人の身元を明かせという要求をするんですか?」
「元々バラジット家の人間だから、配慮されて当然だと?」
「そうだと言っていたよ。」
「結婚してどれくらい経ったと思ってるのに、今さらそんなことを……。」
「奥様は我々ウィンターフェル家の一員です。」
皆が興奮して騒いでいる中、ファビアンが慎重に口を開いた。
「それが、法的に言えば子どもがいてこそ正式な夫婦と認められる――あっ……す、すみません、侯爵様。」
主君の鋭い視線に慌てて口を閉じたものの、すでに言ってしまった後だった。
ジスカールが再び口を開いた。
「確かにあの娘が空気を読めないのは事実ですが、侮ってはいけません。バラジット家が本当に正式に反発してくれば、名分の面では我々が押される可能性もあるのです。」
「それを分かっていて出した条件だろう。あいつらの土地ではユオン長の調査を拒否する口実がないから、巧妙に過ちをこちら側に向けさせようとしているんだ。」
「ずる賢い連中だ。」
「ハヤカンが無事に過ごせるかどうかも怪しいな……」
家臣たちが口をそろえて政局について論じていたとき、
辛うじて衝撃を乗り越えたナディアが口を開いた。
「私は行きたくありません。」
「当然だ!そんなことは考えたこともない!」
当たり前のことをなぜわざわざ言うのかというような口調だった。
グレンは声を高めて彼女の肩をつかんだ。
そのおかげで彼女は半ば強制的に彼と目を合わせなければならなかった。
彼はナディアの目を見つめながら言った。
「君はもうウィンターフェル侯爵家の人間なんだ。俺が守るべき存在だ。俺の庇護の下にある人間なんだよ。あいつらが君を手放したからって、素直に返す理由なんてないだろ。」
「でも、私のために他の領主たちが反乱が起こるかもしれません……」
「どうせユオン長を調査する気がないから、ああいう条件を出したのさ。それでもし反発する者が出てきたら……」
「……」
「私が直接、剣を抜いて倒すから心配しないで。あなたがバラジットに戻るようなことは絶対に起きない。何も心配しないで。」
「……」
ナディアは丸くなった目で顔を上げた。
彼の話す顔はこれまでにないほど真剣だった。
何か返事をしなければならないような気がしたが、返す言葉が思い浮かばなかった。
彼女はただ唇を閉じるしかなかった。
黄砂の地に吹く冷たい風のせいか、唇がすっかり乾いてしまったようだった。
誰かが鋤でかき回したかのように、手のひらがざらざらしていた。
いや、ざらついているのは手のひらだけだろうか?
鋭い感触に、静かに拳を握る彼女の喉がゴクリと鳴った。
「グル……」
ナディアが何か言おうと口を開いたその瞬間、隣から「ヒュイッ」と風切り音のような音が聞こえてきた。
騒がしい音に、二人の首が同時に振り返った。そこには驚いた顔で口をわずかに開けて立っている侍女たちがいた。
「……」
「……」
「……」
妙な沈黙が流れた。
凍りついた荒れ地の上を風が吹き抜けていく音だけが響いていた。
パチン。
沈黙が破られたのは、誰かが手を叩いた時だった。
パチ、パチパチ。
パチパチパチ。
誰かが始めた拍手の音は、たちまち他の家臣たちにまで広がっていった。
皆、手を合わせて拍手している。
他の家門から来た人々がこの光景を見たなら、きっと奇妙に思ったことだろう。
「えっと、その……なんだ。まあ、そういうことですね……」
「見ていて気持ちがいいです。でも、周りに人がいることを少し考慮していただけると……」
「静かにしろ。」
「はい。」
だらしなく響く声に拍手の音が止んだ。
誰かが手を叩いた。それがさらに気まずさを増した。
「ゴホン、フム。」
ナディアはわざとらしく咳払いをしながら身体をそらした。
顔に血が集まるのを隠すためだったのか、気まずさのせいだったのかはわからないが、首も耳まで赤く染まっていた。
「そ、外に長く立っていたので少し寒いですね。このまま馬車に戻ります。」
「そうですね、分かりました。」
そう言って彼女は馬車の中へすっと入ってしまった。
馬車の扉が完全に閉まったのを確認したグレンは、顎を横に動かした。
家臣たちが立っている方向だった。
怒気と苛立ちが完全に混ざり合った視線だ。
最初に手拍子を始めたアドリアンが困惑して尋ねた。
「な、なぜそんなふうにご覧になるのですか、領主様?」
「分からないから聞くのか?」
「い、いえ……あっ、あの!今大事なのはそれじゃありませんか? 今後どうされるのか。交渉は決裂したのですから。」
「どうでもいい。対話で解決しなかったなら、武力で解決するしかないだろう。」
「それは幸いですね。武力で解決するのは私たちの特技じゃないですか。」
「その通りだ。」
グレンの視線が席に座っている他の侍女たちへと向かった。
荒野で夜を明かすわけにもいかない老人だったので、ひとり忙しそうに旅の支度をしていた。
その中にはバラジット公爵家の紋章が刻まれた馬車もあった。
彼はその中に乗っている老人を思い出した。
会談中は寡黙でほとんど言葉を発しなかった、狐のような老人を。
『これでもう本当に戦争だな。』