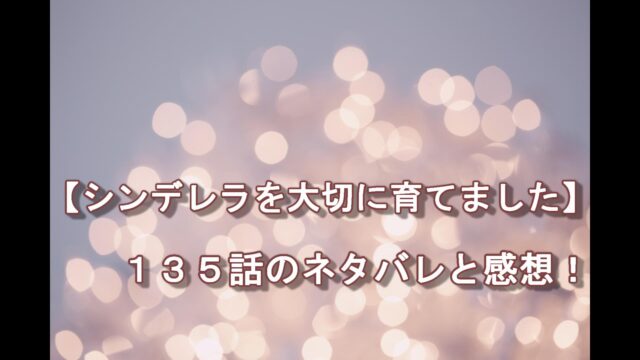こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

197話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 新しい事業③
カーシ夫人が去ってからあまり時間が経たないうちに、性格の良いダニエルが戻ってきた。
彼は相変わらず爽やかな表情で、一人で満足そうに微笑みながら私の方へと近づいてきた。
「解決しました。」
「解決ですか?」
何が解決したというのだろうか?
少し混乱していた私だったが、彼が言ったのがアイリスの件であることに気づいた。
「解決したの?どうやって?」
私はすぐ立ち上がり、ダニエルの顔に微笑みを浮かべた。
彼は私の隣にやってきて、隣に座るようにソファを軽く叩いた。
そして口を開いた。
「ランバートの夫人がアイリスを助けたと認めました。夫人は城で働いていますから、アイリスが人を呼び寄せたのは確かです。」
私は微笑みながら身体を寄せ、ダニエルの肩に寄りかかる。
彼の存在は新しい息吹のように感じられた。
城を自由に出入りできる権限も、上流貴族ならではの特権である。
ダニエルは公爵家の出身だが、王の親戚であるためその立場は特別だった。
彼はそうではないと否定したが、私はアイリスが王太子妃候補になったことに、彼の力が無関係ではないだろう。
今後、王太子妃候補に何か問題が起こったら、推薦人が城に出向いて仲裁したり弁護したりする必要があるからだ。
城に自由に出入りする権利がない下級貴族の推薦が通るとは考えにくい。
「まだアイリスの採点結果は出ていませんが、最も迅速で、出廷の趣旨に沿った行動をとったので、期待していいと思います。」
それは間違いないと確信した。
私が彼の言葉を受け入れると、ダニエルは一旦口を閉じてこう尋ねた。
「ところで、誰が訪問したんですか?」
「どうして分かるんですか?そんなことも知る力があるんですか?」
もしかして妖精の能力には、そんなことを知る力もあるのだろうかと私は考えた。
私が驚いた顔をすると、彼はニヤリと笑いながら言った。
「帰り道で、私たちの馬車が通り過ぎるのを見ましたよ。リリーンはケイシー卿の馬車に乗って出かけ、戻ってくる途中でアイリスとお喋りしているのを見たんです。」
ダニエルが城に行ったり来たりしたと聞いて、アイリスが気になって彼に質問したようだ。
なるほど。私は彼の冷静な推理に目を見張りつつ、彼が「自分の」馬車ではなく「私たちの」馬車と言い直す機会を逃さなかったことに気づいた。
「カーシー夫人が来ましたよ。この暑い中、わざわざ歩いてきてあなたの馬車を降りて行かれました。」
私の言葉にダニエルの目が大きく見開かれた。
彼は私の手を取り、手の甲にキスをしながら言った。
「私のものはあなたのものです。」
そんな言葉に私が心を乱すと思ったなら、彼は甘い期待を抱きすぎだと考えた。
私は彼の頬に手を当て、唇を重ねる。
ダニエルの息遣いが乱れていくのを感じた。
彼は私の腰を掴み、私の唇をさらに深く奪おうとした。
「ミルドレッド。」
ため息のように私の名前を呼ぶダニエルの声が、どこかくすぐったく感じられた。
最初はゆっくりと始まったキスが、徐々に熱を帯びていく。
彼は唇を離すと、まるで満足できないかのように、私を再び捕まえてキスを続けた。
「ちょ、ちょっと待って。」
息が苦しくなって、私は彼の胸に手を置いて止めた。
すると次の瞬間、ダニエルの動きがピタリと止まった。
「ちょっとだけ待って。」
息が足りない。
このままでは倒れてしまいそう。
私は息を整えながら、彼の胸に頭を預けた。
彼とキスをするのは本当に良いけれど、ここがどこで何時なのか、全く忘れてしまった。
今は何時?
日がどこまで昇っているのか気になって、私は窓を見た。
その時、ダニエルが低い声で謝った。
「すみません。」
「何が?」
「少し理性を失ってしまいました。少し離れた方が良さそうですね。」
理性を失った?私が?
私はその言葉に驚き、彼の顔を見つめたが、彼の真剣な表情からそれが本音であることを悟った。
ダニエルは私をソファの隣にそっと座らせると、立ち上がって反対側へと移動した。
「それが理性を失うことなの?」
ダニエルの顔が赤くなった。
理性を失ったというのは、恥ずかしいということ?
私は彼の顔を見つめた後、少し微笑んだ。
「でも、私が押し返したから、急に止まったんじゃないの?」
私の質問にダニエルは少し困惑した表情を浮かべた。
彼は不思議そうに尋ねた。
「ミルドレッド、君が少しでも不快なら、止めなければならないでしょう?」
正論すぎて返す言葉が見つからなかった。
それはそうだよね。
私は視線を逸らし、話題を変えるために口を開いた。
「カーシー夫人がなぜ来たのか、知ってる?」
「わかりません。」
「私を妖精の代母だと思ったみたい。」
ダニエルの眉が上がった。
彼はため息をつき、私に再度謝った。
「申し訳ありません。」
「いいえ、怒っているわけじゃないです。ただ面白かっただけです。」
本当にただの冗談だった。昔のことを思い出して、軽く笑いながら言っただけなのだ。
エリザベスも私を妖精の代母だと思い込んでいた。
どうしてそのように思ったのかも理解できる。
この場所にはカメラも電話もない。
何かが起こったら、時間差を置いて人々の噂として広まる以外にないということだ。
そうなると、必ず歪曲が生じる。
その歪曲が極端なら、「妖精の代母」という誤った噂も訂正が必要になるだろう。
しかし、今回のカーシー夫人の訪問で、それが確信に変わった。
人々は妖精の代母の助けを必要としている。
ダニエルの言葉は正しかった。
エリザベスが妖精の代母に頼ろうとした理由も、カーシー夫人が訪ねてきた理由も、全て私がいる社会のシステムが解決してくれないことが問題なのだ。
私はため息をつき、再び言葉を口にした。
「ただ、あなたがなぜ妖精の代母の存在に疑問を持たなかったのか、それが不思議です。」
「なくならないといけないと話したわけではありません。ただ、必要がなくなるべきだと話しただけです。」
その言葉がまさにそれだった。
私の顔に浮かんだ表情を見て、ダニエルは薄く笑みを浮かべた。
彼はテーブルの上に手を置いてから再び口を開いた。
「それで、カーシー夫人は妖精の代母にどんな願いを叶えてほしいと言ったのですか?」
「必ずしも妖精の代母でなくても叶えられるような願い事でした。」
ダニエルの顔に戸惑ったような表情が浮かんだ。
私はそれに合わせてテーブルの上に手を置きながら尋ねた。
「クリノリンって知っていますか?」
「クリノリン?女性たちがスカートを履くとき、そのふくらみを保つために着る下着、というか道具のようなものですよね。」
「よく知っているね?それをどうして知っているの?」
驚いた表情を浮かべる私に、ダニエルがすかさず言葉を返した。
「作っている人を知っているんです。」
「そうなんだ?」
「知らなかったけど?もしかして、ダニエルも答えられるかもしれないわね。」
私は急いでカーシー夫人が持ってきた製品について説明した。
それは新しいクリノリンで、腰回りの一部だけを膨らませることができる道具だということだった。
そして声を低くして続けた。
「私が住んでいた場所にもそんなものがあったのよ。」
「人気があったんですか?」
「おそらくそうだと思います。ほぼ百年前に流行していたデザインですけど、当時の記録がまだ残っていますし、人気はあったでしょうね。」
ダニエルの目が大きく見開かれた。
彼は私に問いかけた。
「百年前に流行したデザインだって?」
私はそれを聞いて、彼が住んでいた場所の文化や技術がどれほど発展していたかについて無知であることを悟った。
そうか、以前彼に「馬車ではなく、車に乗りたい」と話したことがあったが、それが何のことか彼は分からなかったのだろう。
「うーん、私が住んでいた場所は、ここよりもいくらか進んでいましたよ。もちろん、ある部分はここより進んでいないこともありましたけど。」
「馬車より速い車というのも、その進化の結果なのですか?」
車って何で動いていたんだっけ?蒸気?
私は正直に答えた。
「科学技術は私が住んでいた場所の方が少し発展していました。馬のように生きている生命体の助けを借りずに、人間が作った機械で速く移動できるんです。遠くにいる人ともリアルタイムで会話できる技術もありますよ。」
その瞬間、私は長い間携帯電話を使っていなかったことに気が付いた。
ミルドレッドになって数週間、携帯電話の振動が無意識のうちに失われていたのだ。
ダニエルは真剣な表情を浮かべていた。
彼は腕を胸の前で組みながら私をじっと見つめ、静かに言った。
「不便を感じていたことでしょう。」
「驚くような話をひとつ教えてあげましょうか?」
「大丈夫ですよ。どんな話をされても、すでに十分驚いていますから。」
「私が住んでいた場所では、女性がズボンを履くことも普通でしたよ。いわゆる『パンツ』と呼ばれるものです。」
私の予想通り、ダニエルの眉がピクリと動く。
この国では男性すらズボンを履く習慣がないのだ。
「下着ではなく、表に着るものだということですか?」
「そうです。それにスカートも、これくらい短いものを履いています。実際、今この場所のように、裾が地面につくほど長いスカートを履く人はほとんどいません。」
「長いスカートは不便ですからね。」
私が軽く笑いながらお茶を一口すすったのと同時に、ダニエルのため息が聞こえてきた。
彼は一瞬考え込むように口を開く。
「どうやら、私はあなたに何か恥ずかしいことをしてしまったようですね。」
それが何を意味するのか分からないまま、私が少し戸惑った表情を浮かべると、ダニエルはやや困惑した様子で奥歯を噛み締めながら言葉を続けた。
「私がしっかり仕事をしなかったせいで、ガードがあなたをここに連れてきたのですか?」
私は一瞬、口を閉じた。
「そうだね、罪悪感を感じている。特に最初の頃はすべてが怖かった。薄い靴底の靴や不快な下着、長すぎて歩きにくい服、そして息苦しい社会的ルール。それに加えて、いつの間にか三人も子供がいたんだ。私が本来よりも少し多く食べていたからだろうか?年を取ったから体重が増えたと弁解した記憶がある。もともと自分の年齢なんて覚えてないけど。」
「正直に言うよ、ミルドレッド。もし私があなたと同じ立場だったら、あなたのようにうまくやれる自信はない。」
そうか。
私はダニエルの喉が詰まるような告白に、彼の経験を思い浮かべた。
彼の言葉通り、私はただここに放り込まれたにすぎない。
私の頭の中は自分の記憶とミルドレッドの記憶が混ざり合い、目の前には大人の手が必要な三人の子供たちが見えてきた。
私の状況を振り返りながら、そのまま座り続けることもできたかもしれないが、何かが私を立ち上がらせた。
それが家庭の力ではなかっただろうか。
「あなたでも同じだったと思いますよ。」
彼はそれ以上のことをうまくやれるのではないかと思っていた。
しかし、私の言葉に、彼は冗談だと思ったように笑いながらも、私の表情を見て、それが本気だと感じたのか、少し驚いた様子で尋ねた。
「それは本気で言っているのですか?」
「はい。あなたなら私よりももっと上手くやれるのではないでしょうか?」
「とんでもないことを、ミルドレッド。いいえ。誰がどうであれ、あなた以上に上手くやれる人はいないでしょう。」
そうだろうか。
私もそんな風に思うことがある。
もちろん、誰であれ私以上に上手くやれるなんて思っているわけではなく、私が平均以上には上手くやれていると思っているだけだけれど。
それでも誰かがそう思ってくれること、そしてそれを理解してくれることは嬉しいものだ。
私は何も言わず、茶碗を持ち上げてわずかに微笑んだ。