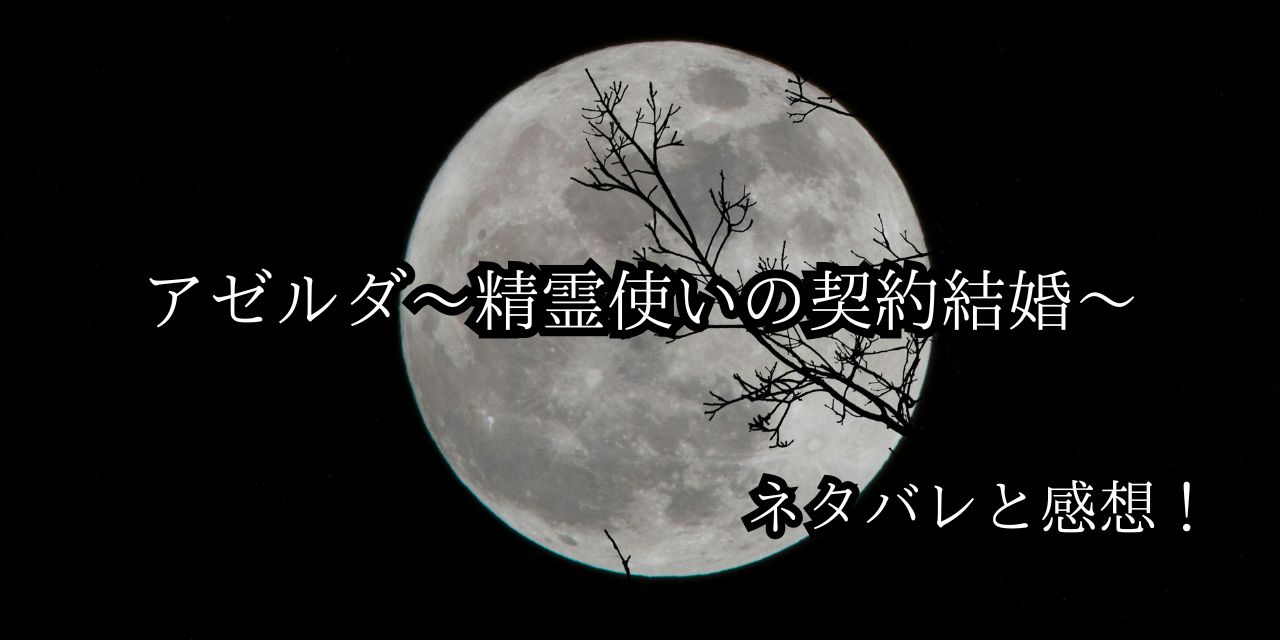こんにちは、ピッコです。
「アゼルダ~精霊使いの契約結婚~」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

35話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 友達③
アゼルダは、憤りや絶望を浮かべない顔で口を結んだ。
「あなたが間違っているとは思わない。でも、あなたと関係があるかもしれないという話は理解したわ。権力争いってことね?」
コチータ公主はあまりにも驚いたのか、口をあんぐりと開けた。
「アゼルダ、あなた…そんな話を聞いても私が狂ってるって思わないの?」
「信じてるわ。あなたは良い人だし、もし本当に狂ってるなら、救済院に行って人を助けたりはしないでしょ。」
「……そんな話を信じるなら、私の方がもっとおかしいんじゃない?」
「何言ってるの。あなたがしたことじゃないのに。私がなんであなたを憎むと思うの?」
「アゼルダ!」
コチータ姫は叫び声を上げるように声を張り上げ、席からばっと立ち上がった。
あまりにも突然だったため、立ち上がった拍子に大きな椅子が倒れそうになった。
姫の顔が今にも泣きそうだったので、アゼルダは椅子を避けて立ち上がり、彼女を抱きしめた。
「大丈夫、大丈夫。」
「こんな……ううっ、話せる場所が……あなたしかいなくて、うっ……今まで誰にも言わずにやってきたけど、あなたが都を離れたら……もう一度会えるか分からないし……私が誰かと会うのを嫌がるでしょう?きっと……私の誤解じゃないって、分かってほしくて……。」
「うん、分かったよ、コチータ。落ち着いて。泣かないで。全部信じてるから。」
「こんなことを話したら、皆きっと狂ったと思うでしょうと思ってた。話せる相手もいなかったし……でも、あなたは……アランジュ様の娘だから。」
「うんうん。誰にも言わない。」
「私の立場では絶対に誤解できないほどの事例が積み重なっていたの。だから……これは私の被害妄想じゃない。だから……あなたも……あなたもダメになったらいけないから……うっ、私が、私があなたともう一度会えなくなるなんて……うっ。」
「大丈夫。私は元気にやっていけるよ、コチータ。」
感情をあまり表に出さない少女が自分を心配してくれる感覚は不慣れだった。
この話を、たった三度目に会った自分に打ち明けるほど、彼女も孤独で辛かったのだろう。
この話をできる人もいなかったのだろう。
徐々に人々は彼女から離れていき、母親は首都の施設に押し込められ、父親は病と闘いながら子どもたちを気にかける余裕もなく、状況はより悪化するばかりだったに違いない。
「大丈夫、平気だってば。」
自分の事情をすべて理解してくれる人に出会えたという安心から、これまでの寂しさが突然この感情は抑えきれないものだったようだ。
コチータ姫は涙を止められず、アゼルダは彼女の震える背をそっと撫でた。
「……ごめんね。見えない終わりを見てしまったみたい。」
「少し落ち着いた?」
「最近ちょっと……私、うまくやれてるのかな。ただ……最初から何もかも無くすために、好きになったんじゃないかって、そんなことばかり考えてたら……落ち着かなくなっちゃって。話せる人もいなくて、急にすごくこみ上げてきちゃった。えへへ。」
涙を浮かべながら、淡い色の目で少し笑った彼女を見て、アゼルダは言葉を失った。
この建物に住む人間の誰一人としてそんなことを考えたりしない。
王宮の外れまで出かけて、救済院でボランティア活動をしているこの優しい姫が、そんなことを考えていたなんて。
あまりにも一途で非論理的なところが、むしろ彼女のことをより理解させた。
自分もそこにいたから。
他人の視点から見て、自分の価値が外的な出来事で再評価されるその状況に置かれてみると、まるでカエル地獄のように、ずっと下へ、またさらに下の水路へと落ちていくしかなかった。
「そんなこと考えないで。君は……何かを間違っているわけじゃない。君はいい人で、ちゃんとした人だよ。人が君を避けるからといって、君が間違っているわけじゃないし、人が君を信じないからといって、君が嘘つきだというわけでもないんだ。」
公女は自分の席に戻ると、テーブルに伏せて涙をぬぐい、鼻をしっかりとかんだ。
そして少し気持ちが晴れたような顔で笑った。
「もう、これ以上慰めなくていいわ。」
「慰めじゃないよ、コチータ。」
言いたいことが喉元までこみ上げてきたアジェルダが口を開いたその瞬間、扉のほうから何かが動く音が聞こえた。
「お入りなさい。」
重い扉がゆっくりと開かれた。
アジェルダはそっと言葉を飲み込みながら、ドアの前に立つ侍従を見つめた。
食事を運ぶ侍従とは服装が違っていた。
「何事ですか?」
「お姫様、陛下がお呼びです。」
「父上が?お席にいらっしゃったのでは?」
「いえ、シェイド・カルロス公爵様が都にいらっしゃると聞いて、姫様に王様と共に席をご一緒したいとおっしゃいました。今は体調も少し良くなったとのことで、無理をしてでも席に着かれたようです。」
姫の後ろから彼女の護衛騎士が近づき、姫の椅子を引いた。
「行きましょう。」
「ええ、でも……公爵夫人は?」
「ご一緒いただきたいと望まれました。」
アジェルダは思いもよらずこの会話を聞いていて、呆然としながら自分を隠した。
「私がですか?」
「はい。」
しかし、自分が王に直接会う必要があるのだろうか?
彼女は王子を殺すという覚悟で生きている人間だった。
自分の両親を殺した王子の心臓に刃を突き立てるという覚悟で。
その王子の父親に会って、何を言えばよいのか分からなかった。
アジェルダがぼんやりしているのを察したのか、席を立った公女が彼女の手を引いた。
「一緒に行きましょう。」
「でも……」
「わざわざ来るようにおっしゃったのだから、仕方ありません。これまでアジェルダ……ゴホン、公爵夫人が宴に参加されなかったのでお招きする機会がなかったのですが、陛下は……惜しまれていたのです。」
重要な要点が抜けているやや曖昧な言い方ではあったが、アジェルダはその言葉の空白をすぐに埋めることができた。
『陛下はあなたのご両親を大切にされていた』
惜しいことだ。
守ってくれればよかったのに。
怒るべきか、感謝すべきか。
行くべきか、行かないべきか。
気持ちを整理できなかった心に、ふとシェイドの顔が浮かんだ。
彼がそこにいるのなら、なんだか大丈夫な気がした。
どうせ公爵夫人の役割をしに来たのだから、最後まできちんと務めて戻ろう。
アジェルダはかすかに決心して席を立った。
アジェルダは姫のあとをついていきながら、自分の服装がきちんとしていないのを気にしたが、今さら着替える時間はなかった。
「急いで呼ばれた入場だから、服装は気になさらなくて大丈夫ですよ、公爵夫人。ふふ、あなたは本当に可愛らしい性格ですね。」
「恐れ入ります、姫様。」
こっそり姫にも聞いてみたが、冗談を言っているのか、本当に大丈夫なのか分からず、アジェルダは少し緊張したまま礼服の裾を持ち上げた。
王の寝室はこの城の最も中心に位置していた。
アジェルダは歩けば歩くほど、だんだんと華やかになる北部の装飾を目にしながら、歴代の王たちの肖像画を一つ一つ眺めていった。
初代王の絵の背景には、起源を知ることのできない床に横たわる巨大な頭のようなものが描かれていた。
それがドラゴンの頭であるというのが学者たちの定説だった。
その絵から離れるほどに、絵は徐々に明確になっていった。
王の寝室にたどり着いたアジェルダは、さっき食堂の扉が無駄に大きいと感じたことがまったく意味のない考えだったことに気づいた。
ここには本当に巨大な扉があった。
言葉が出ないほどで、しかも3階にある扉なのに、こんなにも大きいとは。
アジェルダは自分の背丈の二倍半ほどもある、華やかな宝石の装飾が施された扉を見つめているうちに、扉が開く瞬間を見逃してしまった。
「ようこそ、公爵夫人。」
彼女を迎えたのは、コチータ姫より少し明るい金髪を持つトコペン王子だった。
いつも腰に剣を下げているその腰元に、手が自然と動くのを慎重に抑えながら、丁寧に頭を下げ、王室の礼儀に則って挨拶をした。
「いらっしゃい、妹よ。」
「……お兄様、父上はご無事ですか?」
「今日は比較的顔色がいいようだから、会話を交わすには問題ないだろう。ただ、またどうなるかはわからない。顔を見たらすぐ戻った方がいいだろう。」
コチータ姫は裾をつまんで王子の横を通り、奥へと駆け込んだ。
「あなたの舞を断ってからずっと会いたかったのに、ここで会えるとは。」
あの王子は本当に病気なのだろうか。
アジェルダは内心でそう思いながら、王子のエスコートに微笑む顔を避け、姫のあとについて彼の横を通り過ぎた。
中に入ると濃い薬草の匂いが鼻をついた。
シェイドは目を閉じている王の手をぎゅっと握っていたが、公女とアジェルダが部屋に入ってくるとすぐに頭を下げて挨拶した。
「お父様!」
コチータ公女がベッドの上に駆け寄ると、王はゆっくりと目を開けた。
病色が濃く、瞳の白目部分が濁っていたが、娘を見つめるその眼差しは温かかった。
「お父様!」
「はは、我が可愛いお姫様。」
思ったよりも若々しい声だった。
ずっと病気で寝たきりだと聞いていたため、無意識に国王の年齢がかなり高いと思い込んでいたが、よく考えてみれば年齢はそれほどでもなかった。
せいぜい五十代前半である。
公女が身を起こすと、アジェルダがベッドのそばに歩み寄った。
公爵がアジェルダを紹介した。
「こちらは私の妻、アジェルダ・カルロスです。」
「ほう、お前が……。もう夫人もいるのか。…お前も大きくなったな、シェイド。昔は私の足元をうろうろしていたものだ。」
「殿下のご加護のおかげです。」
「はっ、何が私のおかげだというのか。私はここに閉じ込められて……毎日命を繋ぐだけの日々だ。お前のおかげだよ、お前のおかげでな。婚姻を……家庭を守るのは簡単なことじゃない。若いお前にとっては大きな重荷だったろうに、それを背負わせてしまったようで、すまなく思っている。」
「殿下が一日も早くご回復されるのを待っていると、毎日が短く感じられます。」
アジェルダは王のやせ細った手を両手でしっかりと握りしめ、シェイドの表情からぬくもりを感じ取った。
他の者が見ればいつもの無表情と変わらないと思うかもしれないほどわずかな変化だったが、彼女は王が心から再会を喜び、敬っているのが分かった。
「殿下、以前お目にかかったときよりもお顔色が少し良くなられたように思います。」
「男たちは皆……。たとえ嘘でも言ってくれたのに、お前はそれすら言ってくれなかった……コホコホ。」
体調が悪化しているのか、笑い声はとてもかすかだった。
「それでも、こうして皆が集まっているのを見るといいものだな。これからも……こんな姿をよく見られたらいいのだが。体がよくなくてな。我が姫と王子が……まだとても幼いのに、私がこれ以上弱ってしまったら心配だ。」
トコペン王子がベッドのそばにさらに近づいた。
「そんなに幼くはありませんよ、お父様。コチータももう結婚してもおかしくない年齢ですし。」
「……そうだな、そうだ。しかし、シェイド。我が姫と王子を頼んだぞ。」
シェイドは真剣に頭を下げ、王子は少し気分を害したのか、表情をこわばらせた。
「頼む人が他にいないからってシェイドに頼むのですか?シェイドは私と同い年なのに。覚えておられますか、お父様?」
「我らは……カルロス家に忠誠を誓っているのだ、息子よ。だが……北部の魔物の数が減るべきなのに、むしろ増えているというのはおかしなことだ。私の時代にはそんなことはなかったのに……」
シェイドは頭を下げた。
「その数が増減するのは、人間の意志でどうなるものでもありません。いずれにせよ、安定するものと信じております。」
「私が心配しているのは、守護者の意識だ。」
王はゆっくりと笑い、何度か咳をしたあと、続けて言った。
「早く北部が安定してこそ、我が王子がドラゴンに会って正式に守護者として認められるだろう。私の若い頃は今のように魔物が多くなかったから、騎士を引き連れて……もちろんその中にカルロス公爵もいたが、とにかく彼らと共にドラゴンに会いに行ったのだ。その時の恐ろしかった記憶がある。今でもはっきり覚えている。あの巨大で美しい生き物が眠りから目覚めて、私を守り、我が国を守ってくれると人間の声で話してくれたあの瞬間を……。」
ドラゴンの意識があるからこそ、アジェルダは興味を持っていたのだった。
あのとき、王子とドラゴンを一緒に楽しむのが一番楽しかったから。
もしドラゴンを実際に見たらどうだろう?
アジェルダは年老いた王の声を聞きながら、心の中で巨大で美しいドラゴンの姿を想像した。
なぜか、自分が崇高な使命を持っているように感じた。
回想にふけりながら声を発した王は、シェイドの手を再び撫でた。
「我が息子が……ドラゴンの守護者として加護を正式に受け継いでくれれば……そうすれば私は安心して……楽に休むことができそうだ。頼んだぞ、シェイド。」
「……お任せください。」
ゴホッ、ゴホッ。肺に穴が開いたかのように深い咳き込む音が何度か続いた。
王は喉の奥から小さな息を漏らしながら、しばらく息を整えた。
「最近……少し体の調子が悪くてな。」
「お父様、カルロス公爵が北部から良い薬を持ってきました。それをお持ちしましょうか?」
王女が王のかすれた声に胸を痛めて、勢いよく言葉を吐き出すと、王は片方の口元を上げて笑った。
「ふふ、そなたが?薬を持ってきたと?もう何でもできるようになったというのか?」
「何をおっしゃるのですか。」
シェイドの声は少しかすれていた。
彼の顔には心配の色が濃く浮かんでいた。
王は王女と話を交わしていたが、シェイドの手を離さず、長い間握っていた。
自分の息子の重い病の心配で独白を避け、皆に背負わせたかったのかのように。
長くはない会話の終わりに、安心したのか、王は目をしばらく閉じたまま、再び開けた。
今回、王の視線がとらえたのはアゼルダだった。
アゼルダは自分を長く見つめる王の視線に最初は戸惑ったが、その視線を避けずにまっすぐ見返した。
王子に似たようで、姫に似たようでもある目だった。
なぜか何かを懐かしんでいるように見えた。
王はシェイドを見ながら優しく笑った。
「君は良い奥さんを持ったな。そっくりだ。」
「はい。」
「精神が長く乱れていたようだ。また……混乱してくる。まだ私は彼女が死んだということが、彼が死んだということが……信じられない。彼らは本当に若かったのに。まだ……若い年齢なのに、生きていたら。アランジュ・メディス、その治療師がいれば……この病もきれいに治療してくれたかもしれない。彼女は本当に才能があって……もしかしたら天賦の才かもしれない、そんな女性だった。」
アゼルダは自分のことを「本当にそっくりだ」と——王の言葉の意味に気づいた彼女は、目を伏せた。
驚きもあり、王に言葉をかけるのが気まずくて怖くもあり、黙っている彼女の代わりに、シェイドが落ち着いて答えた。
「悲しいことです。私の妻にとっても。」
「そなたはアランジュを覚えておらぬだろう? まだ幼いころだったからな。」
「ぼんやりとした面影だけ覚えていますが、父が何度か褒めていた記憶はあります。」
あの方が私にそんなことを言ったことはない。前世でも、今世でも。
アジェルダは驚いて、シェイドの冷静な横顔を見つめた。
「こ、ゴホッ、これは……まったく……嬉しいことだな。そうか、そなたの……そなたの父も……本当に良い人だった。周りの人がどんどんいなくなるのを見ると、私もそういう年になったのかと思ってしまう。最近は何もかもがあまりにも早く過ぎていくようで……寂しくなることが多い。良い人ほど、先に連れていかれてしまうのだな。」
まるで死にそうな気分だった。
これもすべて年寄りの妄言だと思って忘れてしまうのだろうな。”
「どうしてそんなことをおっしゃるのですか。まだお世話しなければならない国民がたくさんいます。どうかお体を起こしてください。」
「頭ははっきりしているんだ。でもやりたいことが多すぎて……言いたいことも多くて……でも時折、心がすごく揺らいで、そのまま死んでしまいたい瞬間が少しずつ増えてきたんだ。たぶんこんなふうに死んでいくんだろうな。これが私が……ドラゴンの加護を失ったという……私の子たちがその加護を受け継いだという証拠と考えるべきだろうか? 王位を継ぐということ……王家を継ぐということだ。」
「陛下……」
「太平盛世までは望まないが……」
それが最後の言葉だった。
王はその後の言葉を飲み込み、口を閉ざして目を閉じた。