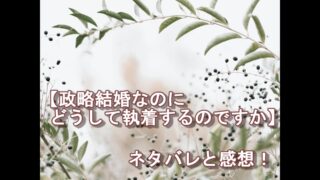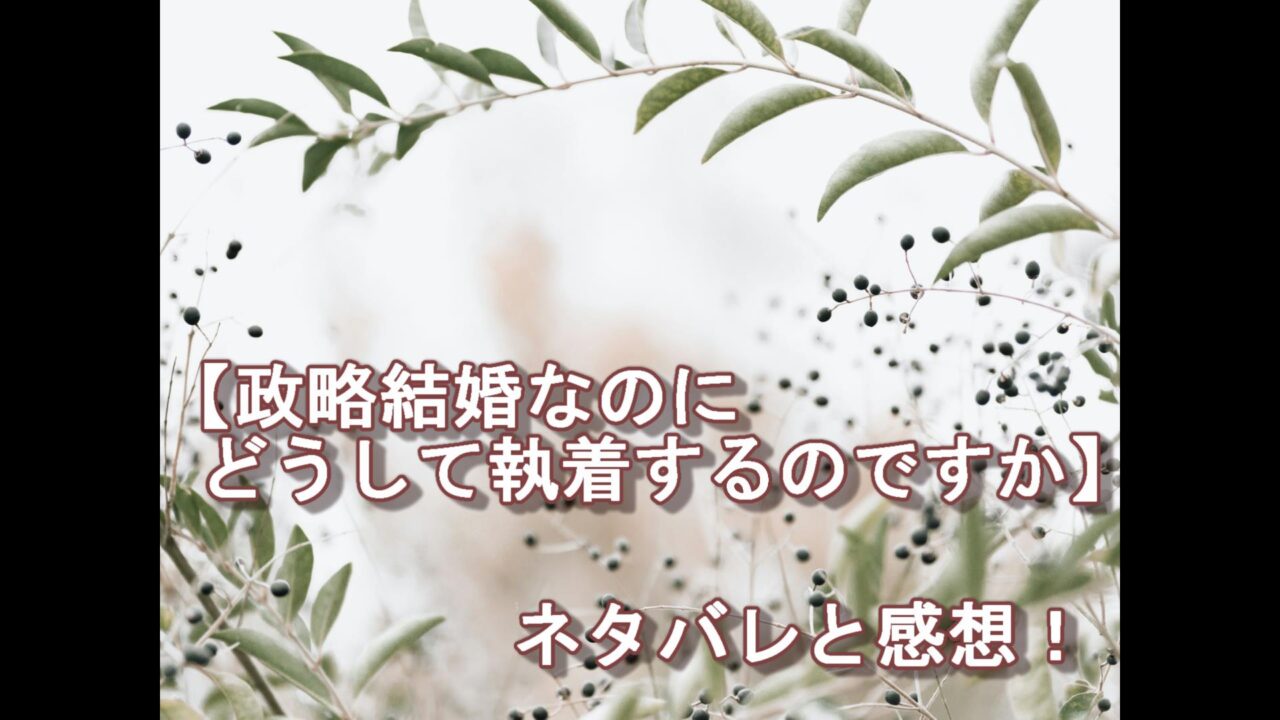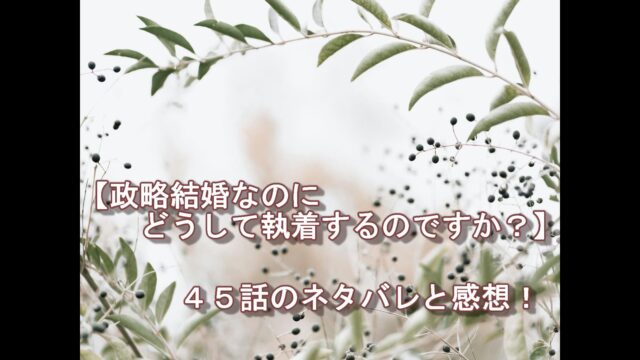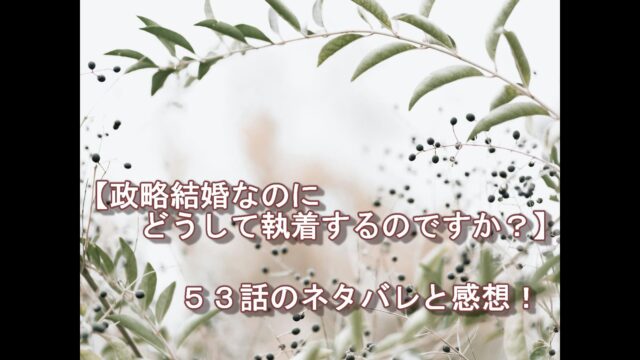こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

104話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 罪悪
持っていたものを落としそうになるほど驚くという感情がどういうものか、グレンは初めて知った。
正直、知りたいとは思わなかったけど。
カラン!
持っていた杯が床に落ちて粉々に砕けた。
父が意識不明の状態だという知らせを聞いた時でさえ、手の力が抜けたりはしなかったのに。
一瞬、目の前が真っ暗になるような感覚だった。
グレンはかろうじて声を出しながら、後ずさった。
「ナディアがポロで捕まった……?」
「ジスカール卿を助けに行く途中で一時的にポロに立ち寄ったようです。そこに敵が潜伏していたようです。」
「それで今、彼女の生死がわからないということか?」
「南部軍がポロの者たちを処刑したという知らせはありません。……ですが、降伏交渉を行うという知らせはありません。現時点ではテニア城に幽閉されているのではないかと思われます。」
「……」
彼は思わず拳を握りしめていた。
『落ち着け、ナディアが処刑された可能性は低い。』
彼女は名のある騎士ではなく、ただの貴族婦人だ。
つまり、ナディアを処刑したとしても、戦局に影響を与えることはほとんどないということだった。
むしろ、無力な貴婦人に対する態度が問題視される可能性がある。
誰も状況を知らずに非難ばかりを受けることになるだろう。
『こういう場合はそろそろポロとの交渉についての提案が来るはずなのに……』
敵将の妻を捕らえたとなれば、そのチャンスを逃すはずがない。
何の知らせもなくテニア城に戻ったというのは理解し難い。
『まさかナディアがウィンターフェル侯爵夫人であることに気づいていないのか?それとも彼女がバラジット公爵の令嬢だからか?』
グレンは慎重な様子で眉間をしかめながら尋ねた。
「テニアの城主は誰だった?」
「もともとはロハス卿でしたが、少し前にバラジット公爵の家臣であるタクミ卿が、城主代理を務めていると聞いています。しかも、彼が統率していた兵たちを指揮していた張本人だとか。」
「それなら、ナディアの素性に気づかないわけがないな。」
彼はナディアの顔を知っている数少ない人物の一人だった。
いや、むしろ幸運だったのかもしれない。
何にせよナディアは公爵の娘ではないか?
公爵の家臣が彼女を軽んじたり、勝手に処刑することなどできるはずがない。
つまり、彼が彼女を救出しに行く前でも、ナディアが無事でいる可能性は高いということだった。
考えを終えたグレンが言った。
「とにかくテニア城に使者を送れ。ポロとの交渉の意志があると伝えるんだ。」
ナディアは間もなく自分が尋問を受けるだろうと考えていた。
なぜジスカール卿を救うための部隊に同行していたのか、父を裏切ったのは本当なのか、などなど……。
あちら側で下心を抱いていた者が数えきれないほど多かったからだ。
だが数日経っても、彼女の体に指一本触れた者はいなかった。
身の回りの世話をしてくれる侍女たちを除けばの話だ。
だからといって、気が楽になるわけではなかった。
むしろ、かえって不安になっていった。
外の状況がどうなっているのか、もうグレンが自分の拘束を知っていてもおかしくないはずなのに、彼がどう反応したのか誰一人教えてくれなかったからだ。
結局、我慢できなくなったナディアが先に口を開いた。
「この城の城主に会わせて。いや、会わせてほしいの。」
彼女は記憶をたどり、この城の主人がカリオン・ロハスという名の騎士であることを思い出した。
あいまいながらも面識のある人物だった。
「城主様ですか?うーん、今はお忙しいかと……」
「お茶一杯飲む時間もないってことはないでしょう。一度、お話ししたいんです。」
「とりあえず分かりました。お伝えしてみます。」
実際、その時点でもナディアは、城主が自分の願いを聞き入れてくれるかどうか確信が持てなかった。
ウィンターフェル侯爵夫人でありバラジット公爵領の人間を捕虜にして顔一つしかめなかったとは。
これはただ単に、無駄な問題を起こすのが嫌だという意思と変わらない。
だから彼が本当に自分の居場所を突き止めてきたとき、ナディアは相当に驚かざるを得なかった。
そして、城主の正体が自分が知っていた人物ではなかったことにも、もう一度驚かされた。
「……タクミ卿?」
同時にかつて疑わしく思っていた疑問点の答えが見えてきたようだった。
テニアの城主は別の人物だったのか。
「ロハス卿でしたら、少し前に戦死なさいました。その息子があまりにも幼いため、私が任期を終えるまでの間だけ臨時で城主代理を務めることになりました。」
「そうだったんですね。」
そういえば、そんな話を聞いた覚えがある気もした。
すると彼がナディアの向かい側に座り、侍女たちはお茶を出したあと、静かに下がった。
ナディアは率直に尋ねた。
「どうして今まで私を訪ねてきてくださらなかったんですか?城主代行がタクミ卿だなんて、ますます気になりますね。私たちの知らない間柄ってわけでもないですし。」
「……いろいろとあって忙しかったのです。わざと避けたわけではありません。」
ナディアの目が疑わしそうに細まったが、彼女はそれ以上は追及しないことにした。
本当に気になるのは別にあったからだ。
「まあ……いいでしょう。それはそれで。」
「では今度はこちらから質問させていただきます。私を、正確に言えばテニアの城主に会わせてほしいと願った理由は何ですか?あらかじめ言っておきますが、解放してほしいというお願いは受け入れません。いくら公爵令嬢の願いでも、それはお応えできません。」
「無理なお願いをするつもりはありません。交渉自体が成り立たないでしょうから。ただ、ひとつ気になることがあるんです。」
「気になること?」
「はい、もし私を捕まえる時に公爵家の厨房長も一緒に連れてきたんですか?本城にいる彼を連れてくるのはかなり大変だったでしょうに。」
「……?」
質問の意味が理解できないという表情だった。
しばらくその意味を考えていた彼が答えた。
「そんなことあるはずがありませんよ?どうしてそんな質問をなさるのか、私としても気になります。」
「では、あなたは覚えているんですか?」
「え?」
「私の死と、あなたとの婚約破棄のことです。」
「……」
彼の表情が一瞬で氷のように凍りついた。
肯定の返答に等しい反応だった。
「覚えているんですね。」
「な、なぜ……」
「バラジット公爵家の使用人たちは、一度たりとも私の好みや意向を尋ねたことがありません。食事に出される料理だけでなく、服や装身具も同様です。「家具まで……すべてが父とカレンに合わせられていました。私が北部へ向かう前まで、誰ひとりとして私の意見を尋ねた人はいませんでした。」
「……」
「前世でも同じでした。あなたを除けば、私の意思を尋ねた人はいなかったんです。なのに公爵家の厨房長を連れてきたということは、あなたが前世を覚えているという以外に説明がつきませんよ? それに、首都で私にそんなことを言ったじゃないですか。」
「……」
彼の表情は困惑で青ざめていた。
ナディアが溜息をついて言葉を続けた。
「いつからだったんですか?」
「……それほど経っていません。首都にいるときは本当に思い出せなかったんです。思い出しながらも一部は忘れていたわけではありません。」
「わかりました。それは信じます。では、私を捕虜として連れてきておいて、ただ見守っているだけの理由は?それはどういうことなのでしょう?」
「……」
タクミはしばらくの間、彼女の視線を見つめることができなかった。
やがて彼は立ち上がった。
「……!」
ナディアはその突然の動きに思わず体を緊張させ、反応してしまった。
ガクン!
しかし、強張っていたのが嘘のように、その後の行動は床に膝をつくことだった。
「あなたに謝りたくて、そうしました。でも、どうしても勇気が出せなくて……全部、私が悪いんです。」
「……はぁ。」
罪人のようにうつむいている彼の姿に、ナディアは溜め息をこらえきれなかった。
「謝るということは、つまりあなたに非があるということですね。じゃあ、カレインが言ったことは全部、本当だったんですか?」
「あの女がなんと言ったんですか?」
「私と離縁するために、事故に見せかけて私を殺したって。すべてあなたと共謀したって言ってました。」
「………」
彼は何も言えない様子で再び視線を下に落とした。
その反応を見て、ナディアは答えを聞かなくてもわかる気がした。
ナディアは静かに続けた。
「実はカレインが言う前から、父は準備を進めていたんです。あなたが私と離縁しようとしているのかもしれないと。」
その時、タクミが驚いたように顔を上げた。
彼女は驚いた顔を見つめながら肩をすくめた。
「まさか死ぬなんて思わなかったけどね。」
「えっ、どうして……。」
「体調が悪いという理由で私の訪問を受け入れてくれなかったじゃないですか。一度や二度の話じゃありません。一瞬で態度が変わったのに、何か起きているって気づかないはずがないでしょう?」
「………」
彼は言葉もないように口を閉ざした。
返事はしばらくしてからようやく絞り出された。
「なぜそうしたのか……聞かないのですか?」
「聞かなくても分かる気がします。お父様が私を捨ててカレインと婚約すれば爵位を与えると約束したのでしょう?あなたは欲に目がくらんでその手を迷わず取った。あなたの目的は出世……違いますか?」
「……そうです。すべて私の欲のせいです。」
ナディアがそろそろ平手でも飛ばすべきか悩んでいたそのとき、思いがけない出来事が起きた。
「な、泣いてるんですか?どうして泣くんですか?」
自分の目の前でひざまずいたタクミの目から涙がぽろぽろとこぼれていたのだ。
ナディアの口がわずかに開いた。
「すべて私の過ちです。欲に目がくらんで愚かな選択を……。」
「いや、それより……まず涙を止めてから話して。」
「私が過ちを犯したのは事実です。でもあなたが亡くなってから、私は心から自分の過ちを悔い改めようと思いました。時間を戻してでも、誤りを正せるように……。」
「なに?」
ナディアの目が見開かれた。
しかしそれもつかの間、彼女の顔に微かな光がよぎった。
時間を戻すという出来事が理由もなく起きたわけではない。
誰かの介入があったと考えれば当然のことだ。
ナディア自身は少なくともそれに関与していなかった。
だから残された答えはタクミただ一人。
「時間を巻き戻すだなんて、もしそんな方法がなかったらどうするつもりだったんですか?
まるで童話に出てくるような荒唐無稽な話を……」
「私がこの世界に存在しているということ自体が、超自然的な力がある証拠ではないでしょうか。」
非現実的な話ではあったが、実際にそれを経験している身としては否定もできなかった。
ナディアは小さくため息をつきながら眉をひそめた。
「ということは、私に前世の記憶を与えたのもあなたということですね。でも、時間を巻き戻したのはあなたなのに、どうして先に記憶を取り戻したのは私なんですか?」
「……あなたに選択権を与えたかったのです。私がしつこく証明するつもりでした。もし望むなら、私との婚約を拒否して新しい人生を生きてほしくて……。」
その言葉にはかなりの信ぴょう性があった。
ナディアが時間を遡ってきたことを初めて気づいたのは、婚約の知らせを初めて聞いた日だったのだから。
だからといって、彼の言葉に矛盾がないというわけではなかった。
「では、今こうして私を捕まえに来た理由はなんですか?私に新しい人生を生きてほしいと言っておきながら。言ってることが矛盾してるじゃないですか。」
「それは……。」
黒い瞳が揺れながら震えていた。
心の中の言葉を口にすべきかどうか悩んでいるようだった。
そしてついに、彼は涙ぐんだ目でナディアを見上げながら告白した。
「あなたに……許されたいです。そしてもう一度、戻りたいんです。」
「……戻るって、どこへですか?まさか私のもとへ戻るって意味じゃないですよね?」
「あなたが好きです。思い返せば最初に会った時から惹かれていた気がします。」
「……。」
ナディアは本当に、完全に言葉を失ってしまった。
戻ろうって?
まさか、二人の関係が悪くなかったあの頃に?
裏切りの前の関係に戻ろうっていうのか?
その瞬間、彼女が元婚約者の頬を打たなかったのは、自分が捕虜であり、命の権利が彼の手にあることをかろうじて意識していたからだった。
彼女はしばらく沈黙しなければならなかった。
怒りを静める時間が必要だったのだ。
「今あなたが言っていること、どれもこれも筋が通っていません。私に選択権を与えたかったなら、私が自分で生きていけるように放っておくべきだったんです。前世で一度もなかった愛の告白を、なぜ今さらするんですか?」
「だから、それは……」
「ああ、本当に時間を巻き戻したら欲が出たんですか?」
「……」
「以前は過去に戻れさえすれば、もう望むことなんてないと思ってたのに、いざ叶ったら気持ちが変わったんですか?私が生きて動いているから、もっと欲張りになったんですか?」
「……」
すると彼は、言葉が詰まったように口を閉ざした。
だが、沈黙は時に多くの言葉を語るものだ。
ナディアは自分でも気づかないうちに苦笑いを浮かべた。
『目の前に見えると欲が出た、か……。そう、それが人間ってものだ。』
目の前に切実に望んでいたものがあると、欲しくなってしまうのが人間の本性。
かつて彼が主君に差し出された「対価」の前で間違った選択をしたように。
『ある意味、一貫しているのはいいことだ。』
そしてそれは「タクミ」という人間が、時間を越えてきた後も変わっていなかった証拠でもあった。
ナディアはしばらく言葉を止め、呼吸を整えた。
しかし、かすかに震えるようなその息遣いは、決して平静とは言い難かった。
気持ちを抑えようと深呼吸をしている彼女の前で、タクミがもう一度許しを請うた。
「私が……未熟でした。」
「出ていって。私の前から消えて。」
「………」
すると彼の目が、衝撃を受けたように大きく見開かれた。
まるで傷ついたとでも言いたげな表情を浮かべる彼に、ナディアは再び皮肉な笑みを浮かべて言った。
「出て行って。」
「……」
何かを言おうと唇を動かすようだったが、タクミは口を閉じたまま席から立ち上がった。
そして涙を拭いながらこう言った。
「では、ごゆっくりお休みください。ご希望のことがあれば、いつでも使用人たちを呼んでお申し付けください。」
ナディアは遠ざかる彼を見送らなかった。
間もなく「バタン」と扉が閉まる音がしてから、ようやく彼女は悪態をつくことができた。
「狂ってるわね。」
ナディアは彼を憎んだ。
そして憎いほどに……彼が怖かった。
神の生殺与奪権を握っている相手が怖くないはずがない。
『しばらくは私に対する罪悪感から危害を加えないだろう。でもそれがいつまで続くかは分からない。』
自分が悪いと分かっていても、謝罪が繰り返し拒絶されれば腹が立つのが人間の心理というものだ。
これ以上彼を拒み続けるなら、今のような対応が続くとは限らなかった。
ナディアはスプーンを動かしながら決心した。
『彼に罪悪感が残っているうちに、どうにかしてここから脱出しなければ。』