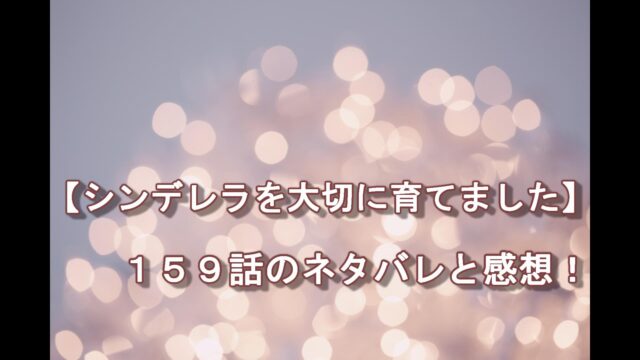こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

203話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 皇太子妃の資質
「ようこそ。」
城から来た馬車に乗ってアイリスが到着した。
アイリスは馬車から降りるやいなや、王妃が自分を迎えに出てきたのを見て驚いて立ち止まった。
「ご招待いただきありがとうございます、殿下。」
アイリスは慌てて腰をかがめて挨拶した。
しかしヘダーはにっこり笑って彼女の手を握った。
「いいのよ。今日は散歩もしなかったから、体がうずうずして検査結果も出てきたことだし、ちょうど良かったわ。」
とはいえ、王妃が自ら出迎えに出るのは普通ではない。
アイリスは気まずい表情を見せないように気を使った。
その時、王妃の後ろで一歩下がって立っていたロアン侯爵夫人が近づいてきた。
「それは殿下に差し上げる贈り物ですか?」
「はい。カステラです。生クリームを塗らなくても、果物のコンポートを塗らなくても大丈夫です。」
またカステラを食べたがっていた王妃にとってアイリスがカーシに頼んで作ってもらったのは、彼女の言葉を忘れずに覚えていたからだった。
できるだけ多くの人が食べられるよう、数枚焼いて一番よく焼けた部分だけを切り取ってきた。
おかげでカーシはその日、腕が取れそうなほど痛くなったかもしれないが、王妃様に喜んでもらえたという満足で十分だった。
アイリスが手にしたバスケットを受け取るロアン侯爵夫人を見て、他の貴婦人たちの視線が一斉に集まり、すぐに散っていった。
彼女たちもカステラが人気であることを知っていた。
妖精の泉で売っているが、大量生産が難しいため予約した人にしか売られておらず、まだ食べたことがない人の方が多いデザートである。
その希少性に加え、すでに食べた少数の人々とミルドレッドに贈られた幸運な数人の口から口へと噂が広がり、城で働く人たちも一度は食べてみたいと思っていたところだった。
「前に食べたあのケーキね。」
王妃が満足そうな表情で言いながら、ケーキの皿を取ると、ロアン侯爵夫人はアイリスが持ってきたバスケットを彼女に渡した。
「どうぞ。私のお気に入りのお茶も用意しましたから。」
そう言って王妃がケーキを取ろうとするのに対し、アイリスは丁寧な態度で皿を差し出した。
ヘダーは再びアイリスの所作が上品であることを確認し、満足そうに微笑んだ。
他の候補者に比べて目立つほど美しい容姿でもなく、裕福そうな衣装を着ているわけでもなかった。
しかしアイリスにはどこか人目を引くところがあった。
多くの人の中に紛れていても自然と感嘆が出るほど整った所作や、優雅な態度のようなものがあった。
動きが控えめでありながら堂々としており、自信に満ちて見えた。
また、若い人たちは顔立ちや噂、感覚に惹かれるかもしれないが、年配の人たちにとってはアイリスのこのような態度が人気だった。
外見はいつか年を取れば失われるものだし、服装はお金があれば解決できる。
しかし姿勢や態度、言葉遣いなどはかなりの時間をかけて矯正する必要がある。
王妃はその点でアイリス、そしてそのようなアイリスを育てたミルドレッドが気に入った。
「陛下。」
ヘザーとアイリスがあらかじめ用意された席に座ると、ロアン侯爵夫人が自らカステラを切り分けて持ってきた。
ヘザーは何もなかったようにカステラを見て眉をひそめたが、何も言わなかった。
彼女が以前に食べたときは、生クリームと鮮やかな色の果物が数個のっていた。
しかしこの日は生クリームを持ってくる間に溶けるのを心配して、メイドはあらかじめ準備していなかったのだ。
アイリスが「果物のコンポートや生クリームがなくても大丈夫です」と伝えたが、ロアン侯爵夫人がそれを気にしていたのは明らかだった。
仕方ない。
ヘダーは微笑みながらグラスを持ち上げた。
ロアン侯爵夫人も年を重ねていた。
誰でも年を取れば少しずつ忘れっぽくなるものだ。
いや、違うかもしれない。
ロアン侯爵夫人はすぐに自分の失敗に気づいて顔を赤らめた。
その時、アイリスが素早く口を開いた。
「うちの母も家でお茶菓子を楽しむ時は、こんなふうに何も添えずに食べるのを好んでいます。それがカステラの食感を一番よく味わえる方法だとおっしゃっていました。」
「そうなのね。」
「一度このように召し上がってみて、どちらがお好みか……どの食べ方が一番口に合うのか探していく方法も良いと思います。うちの妹はこれをチョコレートにつけて食べるのが好きなんですよ。」
ヘザーはアイリスの言葉にニッコリと微笑んだ。
どの妹のことを言っているのだろう?
彼女の脳裏に「ケイシー卿を密かに想っているリリー」と、社交界で美人と噂されているアシュリーのことがよぎった。
「これをチョコレートに付けて食べたら甘すぎてくどくなるかも?」
ヘザーの返しに、アイリスの顔に笑みが浮かんだ。
彼女は肩をすくめながら言った。
「だから私とリリーは味覚が鈍いんですよ。」
チョコレートを付けて食べるという妹はアシュリーだったようだ。
なるほど。
ヘザーも思わず声を出して笑ってしまった。
面白い家族ね。
王妃が声をあげて笑うと、ロアン侯爵夫人はもちろん侍女たちも驚いてアイリスを見つめた。
彼女がこれほど大きく笑うことは滅多にない。
その事実を知らないアイリスはヘザーと一緒に笑っていた。
「あなたは姉妹たちと仲が良いのね。」
「母がいつも言っていました。姉妹ほど親しい友はいないと。」
「そうね。」
ヘザーの目が細くなった。
彼女には姉妹がいない、兄弟だけだ。
しかしロアン侯爵夫人を見るたびに、姉妹がいてうらやましいと思っていた。
「そういえば、ロアン侯爵夫人にも姉妹がいるわね。」
「グレゴリー伯爵夫人ですよね、殿下。」
ロアン侯爵夫人が素早く口を挟んだ。
「グレゴリー伯爵夫人」という言葉に、アイリスの表情が一瞬曇ったが、すぐにいつもの表情に戻った。
もちろんヘザーはその変化を見逃さなかった。
彼女はなぜアイリスの表情が曇ったのかを理解できず不思議に思いながら、イサベルに尋ねた。
「伯爵夫人は元気にしているのか?」
「はい、殿下。おかげさまで元気に過ごしております。」
そのときようやくヘザーの脳裏に、グレゴリー伯爵夫人がどうして本家に戻って過ごしているのかが思い浮かんだ。
彼女の息子がロアン侯爵夫人の音楽会である令嬢を打ったと聞いたのだ。
そしてそれがまさに目の前に座っている、アイリスの妹、リリー・バンス嬢だった。
しまった。
話題の選択を誤ったと思ったヘザーの表情がわずかにこわばった。
しかしその時、ロアン侯爵夫人がアイリスを一度見つめてから言った。
「そういえば少し前にバンス嬢とパトリシャが一緒に慈善活動をしてきたという話を聞きました。」
パトリシャって誰だったかしら。
ヘザーは少し考えたあと、すぐにグレゴリー伯爵家の令嬢パトリシャのことを思い出した。
グレゴリー伯爵が自分の妹を勘当したのに、そのグレゴリー令嬢と慈善活動を一緒にしているって?
ヘザーの顔に一瞬驚いた表情が浮かんだ。
これは一体どういうこと?勘当された男の妹と親しくしているの?
驚いたヘザーとは対照的に、アイリスの顔には微笑みが浮かんだ。
彼女はロアン侯爵夫人に向かって礼儀正しく言った。
「私たちの集まりを支援してくださって本当に感謝しています、侯爵夫人。」
「支援?」
ヘザーの問いかけに、イザベルの顔にほのかな笑みが浮かんだ。
彼女は誇らしげに言った。
「パトリシアとマーシャがバンス孤児院と慈善活動をしているというので、少し支援させていただきました。」
「マーシャ?」
「私の昔からの友人の娘なんです。もともとは妹が世話をしていたのですが……」
グレゴリー伯爵夫人が何か不都合な出来事によって本家に戻り、ロアン侯爵夫人がその世話をしているということだった。
ヘザーの頭の中に、彼女が最近できた孫とその孫に関することで城を出たいと話していたことが浮かんだ。
なるほど。
ヘザーはいつの間にか会話の話題がアイリスが令嬢たちと共にしていた慈善活動の話に移っていたことに気づき、にっこり笑った。
ロアン侯爵夫人の長所だ。
細かい部分は忘れてしまっても、彼女は不快な話題を自然に別の話題に変える優れた能力を持っていた。
「慈善活動をしたと?」
ヘザーはにっこり笑いながら尋ねた。
それもそのはず、王妃候補試験では慈善活動が必須項目とされており、候補たちは誰もがそれぞれ慈善活動に取り組んでいたからだった。
どんな慈善活動をしているのかという王妃の質問に、アイリスは慎重に答えた。
「少し前に、親しい方々と一緒に孤児院へ行ってきました。」
「いいことをしたのね。」
慈善活動をするのも王妃の義務のひとつである。
ヘザーが満足げな表情でお菓子をつまむ一方で、アイリスの表情は曇っていった。
やはり城が望んでいたのは、その程度だったようだ。
貴族たちと一緒に孤児院や病院を訪れ、必要な物資を届けること。
それが悪いというわけではない。
アイリスはその行為も十分に立派だと思っていた。
だが、孤児院や病院は衛生状態が良くないため、そんな場所に頻繁に通えば病気をもらうこともある。
さらに、孤児院がある場所は治安もそれほど良くない場所がほとんどだ。
貴族の令嬢のように良い服を着たお嬢様たちだけで出歩くには、安全とは言えない。
そんな危険を顧みずに行う活動だ。
当然、勇気が必要であり、素晴らしい行いだ。
しかしアイリスは、もう少し長期的なことをしたかった。
彼女は勇気を出して言った。
「孤児院に必要な物を届ける以外に、他にも何かできることはありますか?」
「他のこと?」
「いろんな慈善活動をしてみたいです。もちろん、孤児院に通うだけでも十分立派だと思いますが、もし他にもできることがあるなら、それもやってみたいです。」
王妃とロアン侯爵夫人の視線が交錯した。
二人はアイリスの言葉が何を意味するのか考え始めた。
慈善活動は単なる体験ではない。
それは奉仕活動だ、そして貴族という立場の人が果たすべき義務に近づいていた。
「“ほかのことをしたい”って、どういう意味なの?」
王妃の質問に、アイリスは一瞬口を閉じた。
彼女は王妃とロワン侯爵夫人を見つめた後、ゆっくりと口を開いた。
「孤児院や病院に必要な物資を届けるのは、素晴らしいことだと思います。でも、それは一時的なことですよね。」
アイリスは、その日一度良いことをしたと考えて満足するのは終わりだが、孤児院はそうではないと考えた。
そこにいる子どもたちは生き続けなければならず、アイリスとその友人たちが届けた物資は、どれだけ多くても一週間も持てばいい方だ。
アイリスはもっと長期的で、責任感を要する仕事がしたかったのだ。
「うちは、去年まで少し、本当に少しだけですが、貧しかったんです。」
そこまで話したアイリスの顔が赤くなった。
十九歳のお嬢様が他人の前で「自分の家は苦しかった」と話すのは、とても大きな勇気が必要だ。
その相手が、将来の姑になるかもしれない王妃であれば、なおさらだ。
しかしアイリスは、自分がどんな慈善活動をしたいのかを王妃と侯爵夫人に理解してもらうには、自分が経験した状況を話す必要があると考えた。
「もちろん、今はとても良くなりましたけど……」
急いでそう付け加えたアイリスは、自分でも驚くほど大きく息をついた。
同時に赤くなっていた頬も元の色に戻った。
「そのとき感じたのは、不安でした。遠い未来のことではなく、ごく近い1年後に何が起きるかすら予想できなかったんです。」
人の視野が狭くなることは、恐ろしいことだ。
合理的な判断ができなくなる。
いつもパンを食べるより、本を一冊読むことの方が長期的には良いという判断さえ、飢えて死にそうな状況では下せない。
アイリスは他の人たちがこんな経験をしないことを願った。
孤児院で人の愛情を求めながらも、突き放されて育つ子どもたちを見ると、なおさらそう思った。
彼女は顎を上げて王妃を見つめた。
そしてゆっくりと言った。
「もっと長期的に人々を助けたいんです。」
ヘダーとイサベルの視線が再び交差した。
アイリスの話がどういう意味なのか理解していた。
だが確認のためにイサベルが尋ねた。
「どのくらい長期的って意味?」
「分かりません。最低でも10年です。孤児院のすべての子どもたちが立派な大人に成長できるように助けるなら、10年でも足りないと思います。もしかしたら一生やらなければならないかもしれません。」
ヘザーの目が細められた。
彼女は慎重に尋ねた。
「バンス嬢、慈善家になりたいのかい?」
アイリスの目が細まった。
慈善家?考えたこともなかった。
でも、必要ならば慈善家になってもかまわないと思った。
「必要なら、慈善家になるのも悪くないと思います。」
アイリスの答えにヘザーはふうとため息をつき、ソファに背を預けた。
彼女は一度アイリスを見つめ、それから聞いた。
「王太子妃ではなく、慈善家になりたいのかい?」
王妃の質問に、アイリスの目が大きく見開かれた。
ロアン侯爵夫人は、アイリスがどう答えるのか興味津々な様子で見守り始めた。
王妃ではなく慈善家になりたい?
アイリスの表情は静かに落ち着いた。彼女は淡々とした表情で言った。
「両方やりたいんです。」
ヘダーの顔にかすかな微笑みが浮かんだ。
彼女はティーカップを持ち上げて言った。
「欲張りなオ嬢さんね。」
アイリスはもちろんロアン侯爵夫人も黙った。
しかし、アイリスは口を閉じなかった。
彼女は静かに話した。
「私はリアンを、いえ、殿下を愛しています。殿下でなくても彼を好きです。同時に、王妃になりたい気持ちも、人々を助けたい気持ちもあります。」
アイリスはゆっくりと息を吐いた。
そして王妃に向かって続けた。
「はい、殿下。私はとても欲張りなんです。」
そしてそれは間違っていなかったという母の言葉を思い出した。
アイリスは自信があった。
自分は間違っていなかった。
人は生きていく中で欲が多くなることもある。
ミルドレッドは、誰かに被害を与えるのでなければそれはとても良いことだと言っていた。
「そうね。」
お茶を飲み終えた王妃がカップを置いて口を開いた。
彼女はアイリスを見ながら微笑んだ。
「気に入ったわ。この国の王妃になるなら、その程度の欲は持っていないとね。」