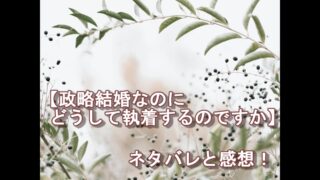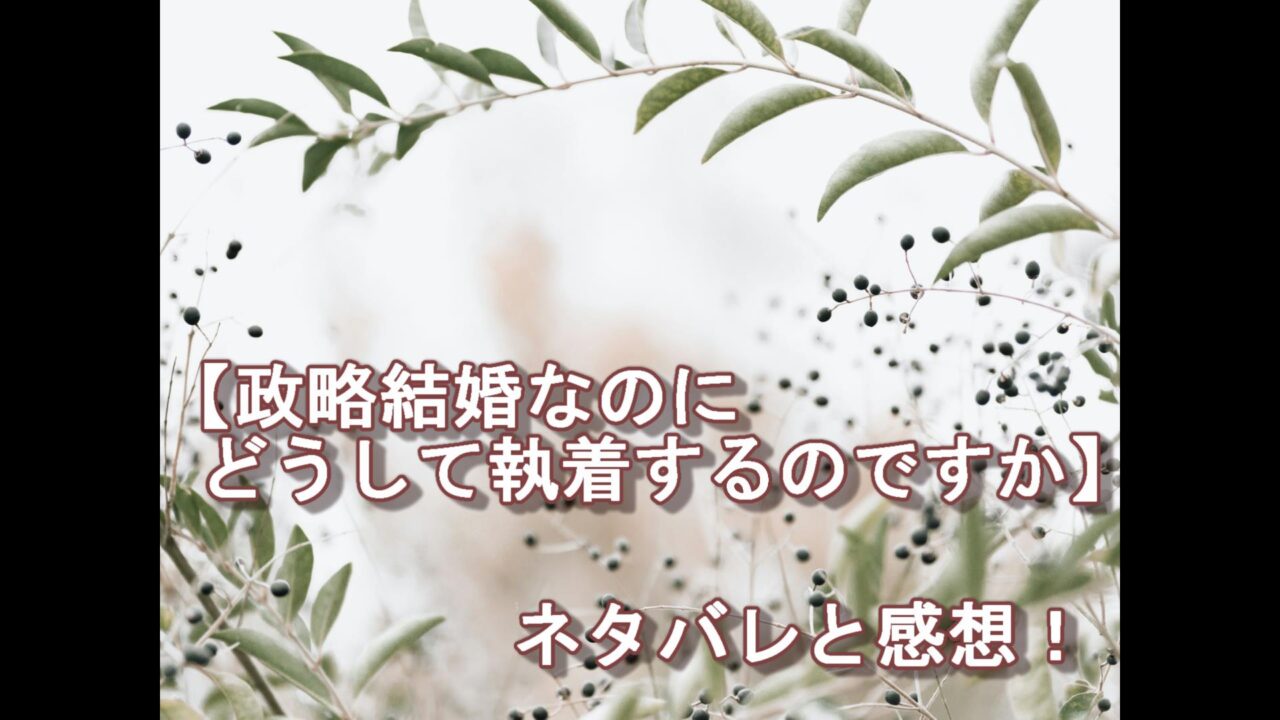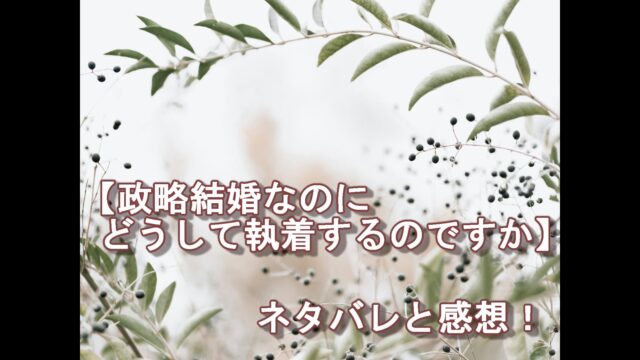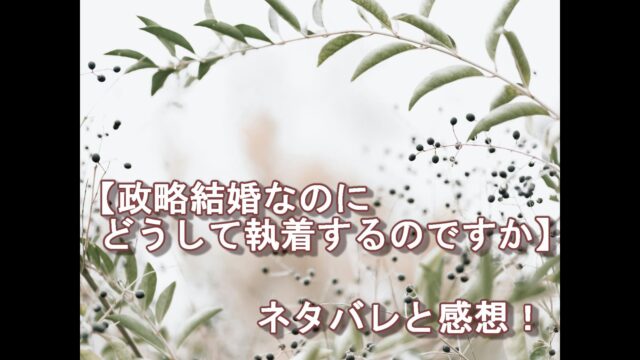こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

109話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 清算すべき縁②
陣営に戻る道。
グレンは最後の瞬間までナディアの心を変えようと必死だった。
「実際にやってみてどうだった?怖くなかった?今すぐでもやめたいなら、いつでもいいよ。」
「グレン、それってまさか説得のつもりじゃないですよね?」
「……」
まあ、あまり効果的ではなかったという話だ。
心を開こうとする意志が少しも見えない彼女の返答に、グレンはまたしてもため息をつくしかなかった。
「前から感じてたけど、本当に……一途さはすごいな。」
「褒め言葉として受け取ります。次はもう少し近づいてくるみたいですね。」
さらにもう一息吐いて、もっと大きな危険を監視することになるかもしれないと話す彼女に、グレンの表情はさらに暗くなった。
「私が知っているタクミ卿は慎重な人だ。私たちが陽動作戦で逃走していることに気づいていてもおかしくないし、様子を見て動かない可能性もある。今日も彼らは一歩も動かなかった。」
「今日は遠くから姿を見せたじゃないですか。だから次は、もう少しそれらしい餌を投げてみるってわけです。たとえば……」
何かを言おうとしたナディアが言葉を濁した。
グレンはその疑問を堪えきれないように問いかけた。
「たとえば?」
「うーん……なんでもないです。」
「言いかけるともっと気になるじゃないか。」
ナディアは答えずに、ただ笑った。
『あの人は時間を巻き戻してでも私に執着しているから。』としか答えられないノロッとした言い方だった。
「気が乗らないならやめましょう。ダメそうなら諦めるしかないですよ、まあ。」
「奴がせめて理性の糸を手放さないことを祈るしかないな。」
敵が自分の予想より理性的で冷静であることを願うなんて、初めてのことだった。
自ら危険を冒すと言い張る妻を見つめながら、グレンはまたひとつため息をついた。
「ウィンターフェル侯爵の旗が……また現れました。」
「………」
これで既に四度目だった。
しかも、時間が経つにつれて少しずつ、じわじわと近づいてきていた。
まるで手を伸ばせば届きそうなほどの距離。
川向こうを見つめるタクミの目つきは暗く沈んでいた。
四度の脱出すべてにナディアが関わっていた。
これはもう、ただ見過ごすことのできない餌だと判断された。
そして彼女のそばには、いつもウィンターフェル侯爵がいた。
その姿を見つめるタクミの表情は、まるで紙をくしゃくしゃに丸めたように歪んでいた。
『……情けない奴め。』
どれだけ不足しているからといって、そんなつまらないことで自分の妻を囮にするというのか?
もし自分だったら絶対にそんなことはしなかっただろう。
たとえナディア自身が囮になると主張したとしても、彼女を一番安全な場所にしっかり隠しておいたはずだ。
そしてナディアの宝物箱には、彼女の好きなものでいっぱい詰めておくのだ。
ナディアは複雑で難しいことには関心を持たないのだから。
だからこそ、ますます理解できなかった。
ナディアがなぜあんな男を選んだのか、その理由のことだ。
部下が歯を食いしばりながら川向こうを見つめている上官に慎重に話しかけた。
「どうなさいますか?今回で四回目です。」
「ここまで来ていて、何の反応も見せないわけにはいかない。次に現れた時にはすぐに追跡できるよう、万全の準備をしておけ。」
「はい?」
最後のざわめきは、別の誰かから発せられた声だった。
彼は喉を鳴らして反対の意志を示した。
「ここまで逃げてきて、あんな策略に乗ってしまっていいんですか?ダメです、タクミ卿。我々を引きずり込もうとしている罠です。」
「その通りです。我々が川を渡ろうとする時に、川の水で押し流す計画ではないかと心配になりますが、いかがでしょうか?」
「乾季で川の水量は多くない。そんな心配はいらない。」
剣のように鋭いその返答に、反対する者たちの表情はさらに険しくなった。
「では、川を渡った後に何か別のものを用意していたのでしょう。責任重大です。渡ってはいけません。」
「……」
分かっている、頭では理解していた。
しかし、罠だと分かっていても引っかからざるを得ない“魅力”というものが存在するのが世の常だ。
ナディアと再び一度、二人きりで話したかった。
彼女に聞きたいことが山ほど積もっていた。
なぜ自分ではダメなのか。
かつて彼女を裏切ったことが、その理由なのか。
面と向かって、一生悔やみながら生きるから、一度だけチャンスをくれないかと。
彼女に新しい世界を見せてあげたのは自分なのに、彼女があの男を選んだ理由が何なのかと。
問いただして、その答えを得たかった。
「もう一度お考えください、タクミ卿。無理を通すのは最善ではありません!」
「エイデン卿でさえ、軍を無理に動かす必要はないとおっしゃったではありませんか?川を渡らないのなら、これ以上応じる必要はありません。」
他の者たちの非難が集まってきたが、すでに別のことに心を奪われていた彼の耳には、それが届かなかった。
誰かが視野を遮っているかのように、右しか見えない目標しか見えなかった。
左を見回したタクミがゆっくり口を開いた。
「皆が見落としている点が一つあるようです。」
はあ、タクミの口からいら立ち混じりのため息が漏れた。
ナディアが目の前にいる。
まるで手を伸ばせば届くような距離だ。
これで気が狂いそうな状況なのに、くだらない問題で論争になっているから、いら立たないわけがない。
彼は苦々しそうな口調で言葉を継いだ。
「指揮官は私だ。」
「はぁ、暑い。」
晴れ渡った雲一つない空からは、ぎらぎらとした太陽の陽射しが照りつけていた。
土手に立ったまま、何もせずに時間だけが過ぎていく行為が、もう五度目だった。
いくら本人が提案した計画とはいえ、ため息が漏れないわけにはいかなかった。
「暑い……」
ナディアが上着の襟をぱたぱたと動かして暑さを和らげようとすると、それでも手を離さなかったグレンが提案した。
「そろそろ我々の計画通りに動くつもりがないと見なければならないのでは?」
「おかしいですね。そんなはずは……」
川の向こう側を見つめるナディアの目つきが鋭くなった。
時間を巻き戻す方法を探してもがき、ついには成功するほどに執着する男だ。
目の前でうろうろしていれば、追いかけて来ないわけがないと思っていた。
だがこの頃になると、自分の判断が間違っていたのではないかという疑念も湧いてきたのは事実だった。
ナディアが揺らいでいると感じたのか、グレンは再び穏やかな声で説得を試みた。
「仮にタクミ本人が、明らかに罠だと分かっている場所へ歩いていこうとしても、周囲がそれをただ見ているだろうか?当然、止めるだろう。」
「うーん……」
「だから、動きがないのも当然なんだ。残念ではあるが、誘引策を試してみるには十分だろう。」
「そうですか。」
いくら強く執着していても、見え見えの罠に引っかかるほど理性を失っていたわけではないのか?
自分の判断が間違っていたという考えに、ナディアの表情が曇りかけたその瞬間だった。
「え?」
疑わしげなファビアンの声が耳元で囁かれるように聞こえてきた。
「奥様。あそこ、近づいてきてるようです。」
「うん?」
「え?え?本当に追いかけてきています!」
一群の兵力が川を渡ろうとしていたのだ。
その姿を発見したナディアが短く感想を述べた。
「まあ、本当ね。あらかじめ準備していたのかしら。夢中で押し寄せてきているわ。」
「のんきに感想を言ってる場合か!」
グレンの手が、ナディアの乗った馬の手綱をつかみ、馬の頭をぐるりと回した。
そして同時に駆け出し始めた。
ウワアアアアア!
森の中へと走り出すナディアの背後から、追撃隊の叫び声がけたたましく響き渡る。
それにようやく警戒態勢が動き出した。
確かに成功したという実感が湧く。
同時に彼女の瞳がわずかに曇った。
言葉にできない感情がこみ上げてきた様子だった。
『まさかとは思ったけど、本当に自分の足で歩いてくるなんて……。』
数歩前が崖だということを知らないはずがないのに……。
一瞬ほかの思考に囚われた彼女が首を振って気を取り直した。
『今は集中するとき。余計な考えはあとで。』
草原の上を走るナディアが唇をしっかりと結んだ。
「撃つな!火矢を放ってはならん!」
最初、弓騎兵たちはそれが射程距離が狭いために矢を惜しむという意味だと思った。
追撃する敵に火矢を使うなとは、まさかの命令だったからだ。
彼らが命令の真の意味を悟ったのは、しばらく経ってからのことだった。
当然、すぐに反応することはできなかった。
「矢を放ってはいけないだなんて、それはどういうことですか!」
「上から下った命令だ!絶対に矢を放つな!」
「そんなはずありません!命令が誤って伝わったのでは?」
「くそっ!詳しいことは私も知らん!とにかく命令に従え!」
タクミが直接下した命令だという言葉に、兵士たちは不満を抱きつつも従わざるを得なかった。
命令違反はすなわち死を意味する。
しかし、彼がそう考えて下した命令ならば、きっと理由があるはずだと、彼らは渋々納得したのだった。
一部、不満を口にする者もいたが、あえて命令に逆らうほどの度胸はなかった。
「森に入れば障害物が多くなるはずだけど、今じゃなければ……」
「何がどうなってるのか分からないけど、とにかく従え。何か考えがあるんだろう。」
こうしてバラジット軍の追撃隊は森の中へと進入した。
・
・
・
「本当に矢を使わないんですね。」
ファビアンの驚嘆した声が、ざわついた馬蹄の音を貫いて聞こえた。
まさかまさかと思っていたが、本当にこんなことまでナディアが予想していたなんて、すべてが予想通りに進んでいるようだった。
ファビアンは感心しながら尋ねた。
「奥様は一体どうやってここまで予想なさったのですか?」
「それは……まあ、そういう方法があるんです。詳しくは聞かないでください。」
『あっちの指揮官は私の前世の婚約者なのに、私にやたらと執着している―なんて口が裂けても言えない話だ。』
いつものことながら、ウィンターフェル家の連中はそれ以上質問を投げかけなかった。
「奥方様にはすべてお考えがあったのでしょう。」—そう言って、手綱を軽く引くだけだった。
良心の呵責を振り払うように、ナディアはグレンに視線を向けた。
「グレン、ここからはあなたの判断に従います。ここからはもっと深く入り込んだ方がいいでしょう?」
「もちろん。」
敵が罠にかかったにもかかわらず、グレンの表情は揺らがなかった。
なぜ矢で攻撃しないのか、その理由を察していたからだ。
『カラアイ遠征以来、しばらく混乱があったのはすべて知っているけれど……』
ほんの少しの因縁で、そんなにも切なさを感じるものだろうか?
自分の知らない二人だけの事情があるかもしれないという思いに、彼の胸の奥で嫉妬の炎がぱちぱちと燃え上がった。
もちろん、ナディアに面と向かって問いただす勇気はなかったが。
だから、しつこく湧き上がる嫉妬を深く心の奥にぎゅっと押し込めるしかなかった。
いつの間にか太陽は地平線の下へと沈んでいた。
森の中の太陽は、なおさら早く沈むものだ。
夜が完全に暗くなるまでには、さほど時間がかからなかった。
やがて追跡していた南部軍は認めざるを得なかった。
「逃しました。」
「……」
タクミは返事をする代わりに、さらに唇を固く噛みしめた。
今にも手に届きそうだった目の前の何かが、するりとすり抜けていったのだった。
栗色の髪は、いつの間にか跡形もなく消えていた。
まるで希望や苦悩そのもののように、彼女は距離をじりじりと保ちながら森の中へと逃げていった。
そして、一瞬のうちに姿を消した。まるで「お前には絶対に私を手に入れることはできない」と告げるかのように。
「やられたな。」
脱力感なのか怒りなのか分からない感情が全身を包み込んだ。
しかし不思議と、不快ではなかった。
目の前からナディアの姿が消えると、ようやく理性が戻ってきた。
ようやくわかった気がした。
自分がここに引きずり込まれた理由が何なのか。
感情に圧倒された彼は、乾いた笑いを漏らした。
「タ、タクミ卿……?」
理由もわからず、その笑い声に他の者たちは不安げな目を交わし始める。
その中の数人が勇気を出して口を開いた。
「どうなさいますか?名残惜しい気持ちはありますが、これ以上追うのは無理です。」
「それに兵士たちもかなり疲れています。この辺りで一度休憩を取るのがよろしいかと。」
「そうですね。夜が明けたらまた追跡を……」
「好きにしろ。」
彼はその一言だけを残して、静かに幕の中へと歩いていった。
残された者たちは互いに困惑した視線を交わしながら、すぐに野営の準備を始めた。
ナディアを捕まえるために後ろを振り返りもせずに追跡してきたため、宿営装備など持ち出しているはずもなかった。
幸いだったのは、ここが森の中だったという点だ。
木々や植物を使えば、一晩過ごす寝床程度はなんとか確保できる。
兵士たちは身を横たえる場所と、簡単な食事の準備を始めた。
さまざまな火攻めの準備物を手にして忙しそうに駆け回る人々の中で……ナディアだけがぽつんと立ち尽くしていた。
何もすることがなかったからだ。
そんな彼女にグレンが近づいて言った。
「もうすぐ戦闘が始まる。君は安全な場所に避難していてくれ。」
「わかりました。」
ナディアも今回ばかりは、自分が危険を冒すとまでは言い張らなかった。
囮としての役割を担っていた時とは異なり、今ここに自分が残ることで得られるものは何もなかったからだ。
「グレン。」
「ん?」
席を離れる直前、ナディアは振り返ってグレンを呼び止めた。
自分の名前を呼ばれるや否や、彼は反射的に後ろを振り向く。
彼女はにっこりと笑ってこう言った。
「怪我しないで。傷一つない姿で、また会いましょう。」
「もちろん。」
短く挨拶を交わした後、ナディアはすぐに広場を離れた。
急いで馬に乗る彼女の周囲には、数人の護衛兵たちが付き従っていた。
彼女はどれほど馬を走らせ、無我夢中で駆けていたのだろうか?
敵軍の姿が完全に見えなくなった頃、ナディアはファビアンを呼び尋ねた。
「ファビアン卿、安全でありながら戦況も見渡せる場所はありますか?」
「それが……少し遠回りにはなりますが、あの丘の上なら可能かもしれません。」
返答するファビアンの指先は、右頬のくぼみを覆っていた。
「そちらへ行きたいんです。遠くから見守るだけでも、いいですよね?」
「うーん……」
ファビアンの口からため息が漏れた。
領主様がマダムを連れて行くようにと指示した場所は別にあったが、マダムの願いを真っ向から無視するのは気が引けたからだ。
『それにしても、うちのマダムは領主様のことがとてもお好きなようだし……』
愛する男が戦場に出ているとわかっていながら、状況もわからない場所でただじっとしているわけにはいかなかった。
「では、こちらの道へ方向を変えましょう。私が道案内します。」
結局、彼はナディアの望むとおりに、森の全景が見える高台に登らざるを得なかった。
「……あぁ……」
そしてナディアがその場所に到着した時、上から見下ろした森はすでに炎に包まれていた。
真っ赤に燃え上がる炎のために、夜明けのように明るかった。
空を見上げると、煙がもくもくと立ちのぼっていた。
遠くから人々の悲鳴、そして怒号がかすかに聞こえてくる。
彼女は縄を握ったまま、その光景をじっと見つめていた。
まるであの炎の中心にいる男の姿が思い浮かんだからだ。
『……死んだのかしら?』
彼の最期を自分の目で見たのか、それとも反対の結果だったのかは知る由もなかった。
彼女が言いようのない感情に呑まれ、ぼんやりと下を見つめていたそのときだった。
「作戦は成功しました。ですが、領主様の安否についてはあまりご心配なさらないでください。」
「あの方が直接森の中へ入ることはありません。」
「……やはり、そうですよね?」
ナディアは無理に口元を持ち上げて微笑んだ。
しかしその目は、少しも笑っていなかった。
焼き尽くされたものたちを全て飲み込んだ火炎が静まるまで、彼女はその場から一歩も動くことができなかった。
そんな中、いつの間にか東の空が青く明け始めていた。