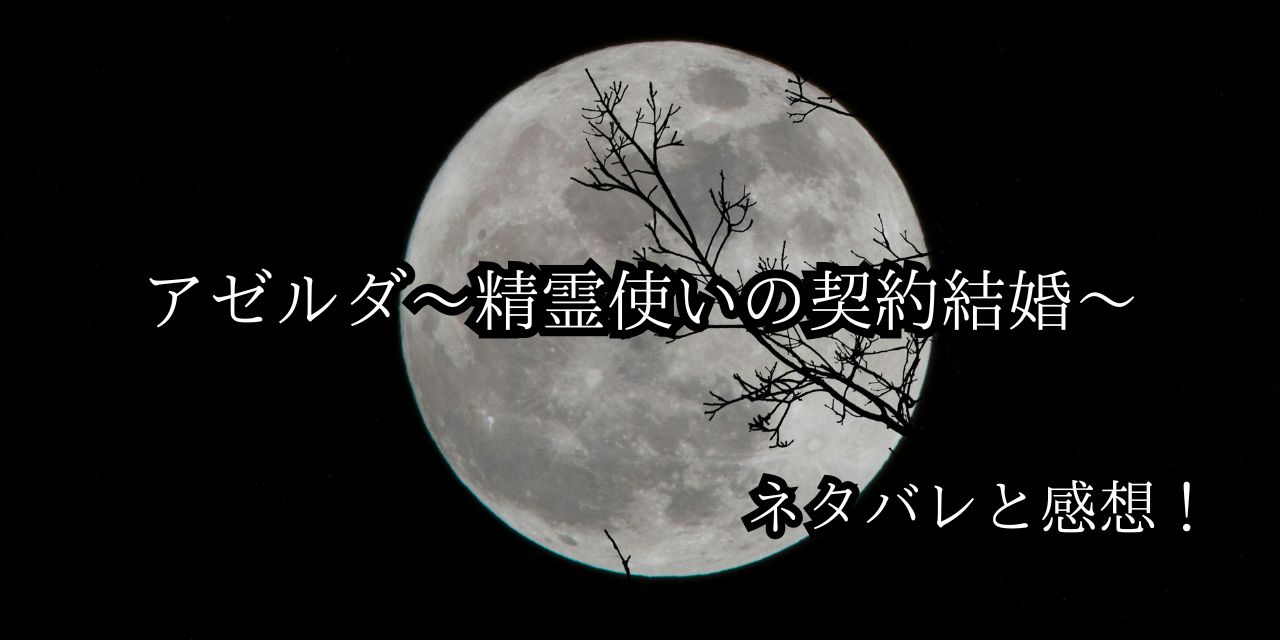こんにちは、ピッコです。
「アゼルダ~精霊使いの契約結婚~」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

41話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 魔女狩り
アジェルダは日々の仕事がひと通り片付いたあと、再びひっそりと公爵邸をあとにした。
契約する時に本城からの外出については自由にしていいと言われていたが、公爵に何も言わずにそっと出て行くことが少し気にかかった。
しかし顔を見て嘘をつける自信がなかった。
今回の首都訪問では、心身が疲れて人が少ない静かな場所を見てまわる、という手紙をジェフに残したことが前回とは違った点だ。
彼女は何度もテレポートゲートを使い、服を着替えながら移動し、人目のない森にたどり着いてようやくラウルに頼み、瞳と髪の色を黒く変えた。
森の小さな池に映る自分の姿を覗き込んでみた。
確かに、髪の色と瞳の色が変わるだけで印象がすっかり変わっていた。
ここにフード付きマスクを被り、大きなマントを羽織って体型をわかりにくくすれば、誰にも自分だと気づかれないだろう。
なぜか気持ちが焦っていた。
ジュディロからの命令を受けてから、そう時間が経たないうちに首都から支援兵たちが出発したはずだ。
この頃の北部では、魔物たちの接近を防ぐために城壁の外に塀を作ったり、地中にトンネルを掘ったりしていたが、それを手伝う人員たちのことだ。
アジェルダが井戸に映る自分の顔を見て気を引き締めて席を立つと、うさぎ肉をかじっていたラウルが彼女の気配を察して慌てて走ってきた。
【もう行くの?】
「そうよ。今回はジュディの夫を救わなきゃ。食べ終わったら行きましょう、ラウル。」
ラウルのふさふさした黒いしっぽが、ふわふわと揺れた。
【うわ〜、もうこんな不味いウサギ肉ともお別れか。これが幸せってこと?】
「何言ってるのよ。呆れるわ。」
ラウルは気分が高まったときのように、ぴょんぴょんと宙に浮いて走るふりをしながら、彼女の隣を歩いていた。
[美味しい~ 本当に我慢できない~ 誰でも味わえばこうなるって~]
ラウルが興奮しているのを見て、彼女も悪い気はしなかった。
彼女はまたいくつもの道を迂回し、また迂回して数日の時間をゆったり過ごして北部に戻った。
一方、北部では、聖騎士に関するよくない噂がざわめいていた。
皆が休憩中に話していたが、やがて皆が声を揃えて聖騎士を非難し始めた。
王子が聖騎士についての悪い噂を信じていたという話まで出て、その証拠としてはさらに、公爵様があの魔女の手のひらで踊らされているという話まで広がった。
運が悪いことに、聖騎士であるアゼルダが戻ってきたことがまさに彼女に関する話題と重なったため、人々の頭の中にそれが強く印象づけられてしまった。
剣を両腰に携えた聖騎士が平常通りにテレポートゲートから歩いて出てくると、人々は彼女をすぐに引き寄せた。
広場を通り過ぎた人々がその不穏な雰囲気に巻き込まれ始めると、あっという間に大きな人だかりができた。
アジェルダは、不審な行動をしている人々の顔が見覚えのあるものではないと気づき、そっと黒い手袋から手を引いた。
普通の住民たちだったが、彼らが群れを成している以上、前に進むことはできなかった。
人々の顔からは今までにない敵意が感じられた。
彼女を見る視線は、ただの好奇ではなく、まるで仇を見るような視線だった。
これほど多くの人々に見られるのは、前世での死を思い出させた。
首を切られる瞬間、人々が「魔女を殺せ!」と叫びながら、体に唾を吐いていた場面がよみがえった。
手先が冷たくなるような気がした。
「これ、いったい何が……?」
〔まったく……どう考えてもいいことじゃないね。〕
「これほどまでに雰囲気が悪かったことはなかったのに。おい、人間。大丈夫か? 顔が真っ青だぞ。]
「大丈夫です。少し気分が悪いだけで……」
魔女!
最初は幻聴かと思った。
人々がたまに彼女をそのように呼んだことはあったが、ここまで露骨に人を罵倒することはなかった。
だが、それは幻聴ではなかった。
「魔女!どうしてまたここに戻ってこようなんて思ったのか?」
「神託じゃなかったら、今ごろ死んでたわよ!」
「消えろ、この魔女め!」
「公爵様のそばから離れろ!」
「死なないんだって? 痛くもないんだろ!」
一人が叫び始めると、あちこちから後を追うように罵声が広場を揺るがすほどに大きく響き渡った。
頭が混乱した。
「そうだ、その魔女は痛みが何かもわからないんだ!」
ヒュッ!
何かが飛んできたのを反射的に感じた。
彼女の腕に当たって砕けたのは卵だった。
痛みはそれほどなかったが、湿った感触は人の気分をとても不快にさせた。
頭がクラクラするようだった。
なぜ、なぜこんなことばかり起きるの?私が何を間違ったっていうの?
ぴちゃぴちゃと落ちてくる汁を茫然と見つめている彼女が、何の反抗もせず、どんな言い返しもせずにいることで、群衆はますます勇気を持った。
「死ね、この魔女!」
「北部へ消えろ!」
悪意のこもった叫びとともに、トマトや卵、小石のようなものが次々と飛んできた。
彼女がじっと立ち尽くしていたことが気に食わなかったのか、人々の怒りが高まり、飛んでくる石の大きさも次第に大きくなっていった。
当たったら痛そうだとか、避けなければならないという考えすら浮かばなかった。
ポクッ!
頭のてっぺんに、ぐしゃっと潰れたトマトがはじけた。
感情がとても混乱していた。
ウェンマンでは、彼女の呪文がなければ人間界の物質に干渉しないようにしているラウルが、その場でふっと立ち上がり、石を一つくわえてはき出した。
彼はイライラしているのか、彼女の隣で尻尾をピンと立てて歯ぎしりをした。
彼がとっさに反応しなければ、その巨大な石は彼女の頭を直撃していただろう。
耳障りな声で気分の悪い呪文を吐き出しながら、彼は不満そうにうなった。
[なぜ黙っているんだ?]
「……ラウル。」
[防護膜を作るしっかりとした方法から、人間数名を燻製肉にして吊るす方法まで、いろんな対処法がある。言ってくれ。]
「ラウル、どうして……どうしてこんなことばかり……こんなふうに……」
顔は青白く、唇は青ざめていて、焦点の定まらないまま立っている彼女の姿は、誰が見ても正常ではなかった。
彼女は両腕を上げて無意識にただ防御しているだけで、まともな意識を持って話すことも、何かを判断することもできる状態ではなかった。
「(ちっ、人間。今回もまたこうなるわけ? こんなことして何が変わるっていうの? 前世と何が違うっていうの? 私があんたをあの女神の前で助けようとした理由がわかってるの? 時間を巻き戻すのが簡単に見える? 笑わせないで)」
ラウルの荒れた気配にはもう慣れたと思っていたが、彼が本音を込めて唸りながら怒りを露わにした時の圧はまったく違っていた。
アジェルダは、彼の鋭い視線に見つめられてようやく我に返った。
「ごめんなさい、また私が……」
「(謝るくらいなら、現実から逃げるな。逃げたいなら自分の足で逃げなさいっての、くそっ)」
ラウルが放った叫び声は、空気を震わせるほど鋭かった。
その声が目に見えないラウルのものだとわからなくても、人々は本能的に身をすくめるほどだった。
アジェルダはようやく周囲を見渡した。
ラウルが身を震わせて立ち上がり、自分のために飛んできた石たちを防いでくれていることに、ようやく気づいた。
そうだ、彼の言う通りだった。
逃げるなら二本の足で堂々と逃げるべきだ。
自分が何か大きな過ちを犯したわけではないし、彼らからこんな仕打ちを受けるほどのことはしていない。
いや、良いことだってたくさんした!
事情がどうであれ、命を懸けて救った騎士や傭兵はどれほどいる?
もちろん、彼らに迷惑をかけたこともあったが、助けになった日も多かった。
「魔女が何だって?」そんな声も今は意味を持たなかった。
ただ防御の姿勢で身を丸めていた彼女は、ゆっくりと腰を伸ばし、前を見た。
すると人々は何かを投げつけようと上げていた腕を止めた。
その場にいた群衆たちにはためらいの感情があった。
目の前の女性がただの弱者ではないという思いが、罪悪感なく当然のように攻撃してよいという感情をためらわせた。
まるで何かをするかのように道具を投げつけてきたが、彼らは内心、彼女が反撃しないと思っていた。
この巫女が神託の中に描かれていた悪であるかもしれないという考えも浮かんだが、彼女が策略の犠牲者のように見えたためだ。
しかし、彼女がじっと鋭い視線で群衆の一人一人を見つめ始めると、人々はぞっとし始めた。
「……な、なんだよ、あの目は」
「ま、まさか俺たちに何かしてくるんじゃ……?」
「魔女だ!やっぱり魔女だったんだ!」
しかし、ざわつく声たちを、彼女はただ見つめ返しながら黙っていた。
そして、しばらくの沈黙の後、アジェルダは口を開いた。
「私は何も悪いことはしていません。なぜ私がこんな目に遭わなければならないんですか?」
「悪くないだと?」
「お前があの魔女だろうが!」
「そうだ!」
非理性的な怒りを理性的に説得しようとしたところで意味はあるだろうか?
再び「ウオーッ」という声と共に、周囲の屋台の物が飛んできた。
アジェルダは、自分が騎士ではないということをその瞬間幸いだと思った。
騎士であれば、群衆に対して剣を抜くことはできない。
言い争いをすることも問題になる。
そうだ、我慢するだけでは何も変わらないなら、正当防衛というものを見せてやろう。
アジェルダは民間人を相手に剣を抜くつもりはなかったが、鞘ごとベルトから抜き取った。
だがまったく攻撃する気のないその行動すら、群衆には大きな脅威として映った。
群衆の中には、タジから来た傭兵たちも混じっていた。
彼女が剣の鞘に手を伸ばしたのを敏感に察知した彼らは叫び声をあげた。
彼らもまた、武器を探して背中や腰に手を伸ばした。
一触即発の状況だった。
「これは一体どういうことだ!」
そのときカロティンが巡察隊を率いて現れ、人々が描いた円の外側で叫び声を上げた。
馬に乗って領地を巡察していたカロティンは、遠くから群衆が集まっているのを見て、急いで駆けつけてきたのだ。
看板まで掲げて集まっているのを見て、喧嘩か何かかと思ったが、これは想像以上の、最悪の状況だった。
カロティンは、巫女に関するよくない噂や、突然舞い降りた神託についてはある程度知っていた。
しかし、その巫女がこんなにも早く北部に戻ってくるとは、まったく予想もしていなかった。
これは面倒なことになった、と思った。
円を描いて集まっていた群衆は、自分たちは正義の側にいて、あの巫女が死ぬことで罰を受けると信じていたため、カロティンを見ても気まずくなることもなく、むしろ歓迎の表情を浮かべたが、彼は険しい顔つきでその様子を見つめた。
武器を構えようとそっと手を上げた者たちは、手を下ろして間隔をあけた。
カロティンと4人の騎士は馬から降り、人々が開けた通路を通って広場に入ってきた。
「整領士。」
返事はなかった。
卵とトマトが飛び交う壁のような人だかりを前に、彼女は剣を持って彼らを見据えた。
言葉を交わす気はなかった。
それほどまでに疲れていた。
カロティンは、彼女の手にある剣鞘をちらっと見てから、自分の後ろにいた巡察隊の一人に合図を送った。
その者がアジェルダに馬を引いてきた。
彼女はその馬の手綱を素直に受け取ったが、すぐに馬に乗ることはなかった。
自分の服からぽろぽろと落ちる卵の白身や、地面に散乱した潰れた果物や野菜を見下ろし、雑多な人々を静かに見つめたあと、群衆を見渡した。
「ここは私が収めましょう。」
アジェルダは手綱を握りしめ、ぎゅっと目を閉じた。
たとえカロティンが来なかったとしても、そう簡単に何かされることはなかっただろうが、民間人に被害が及ぶ前に事態が収拾されたのは、良かったと言える。
泥で汚れたマントの裾を肩から引きずり下ろして地面に叩きつけると、カロティンは馬に軽やかに乗り上がった。
群衆は一様に、カロティンが何をしようとしているのか見守るような表情で彼を見つめていた。
どうやら、彼の行動は彼らの予想の範疇ではないようだ。
カロティンは手にした大きな司令棒を空中でぐるりと振り回し、人々の耳目を引きつけた。
「ひとり残らず、ここにいる者は全員その場を動かずに留まってください!」
人々は、いつも自分たちの味方をしてくれていた第1騎士団の剣が、まさか自分たちに向かってそのような言葉を投げるとは思わず、戸惑った表情を浮かべた。
「……私たち、一体何を間違ったというんですか?」
「カロティン様!私たちはただ、あの魔女を捕まえようと……」
「その女が一言も話せないのを見てくださいよ!やましいことがあるに違いありません!」
カロティンは堂々と怒鳴る人々に向かって立ちはだかった。
騎士団の4人が、彼の指示を待って立っていた。
「彼らを全員一時拘束しろ。判断は隊長が下す。」
「はい!」
第1剣からの命令だった。
騎士団の親戚もその中に混じっていたが、その命令に不服を唱える者はいなかった。
彼らが合図を送ると、騎士団の予備要員までもが出動し、理詰めで多くの群衆を連行した。
北部全体がひっくり返るような大事件だった。
アジェルダがカルロス公爵邸の入り口に到着したとき、ちょうど執務室にいたシェイドの耳にもこの事件の知らせが入った。
彼はその知らせを聞くや否や、勢いよく席を立った。
彼女がどこへ行ったのかを尋ねたところ、その知らせを持ってきた使者は、あの女騎士がこの領地へ戻ってきていると告げた。
アスコとシェイドの視線が交わった。あれほどのことがあっても北部を離れないミジの頑固さ。
一人の目には疑いが、一人の目には困惑が浮かんでいた。
青い馬具をつけた二頭の馬が馬小屋の間を歩いてくると、使者が冷や汗をかきながら手綱を差し出した。
カロティンは馬から軽やかに飛び降り、馬から降りた女騎士の背中に向かって問いかけた。
「どこへ行くつもりだ、女騎士?」
「傭兵の宿所へ向かいます。」
「だが、団長殿が長くお待ちだったぞ。」
「構いません。後ほど伺います。」
カロティンは何かを言おうとしたが、彼女の耳にまだぶら下がっている、ぶらぶらと揺れる卵の殻のようなピアスを見て、それ以上何を言えばよいのか分からなくなり、口をつぐんだ。
「医療班を傭兵団の建物の方へ送ってください。」
「いえ。怪我はしていません。」
「そうか、わかった。後で話そう。」
アジェルダが体を向けると、カロティンは彼女の背中に向かって、ひとり目で感謝の意を伝えた。
彼女がいなかったら、前の戦闘でシェイドがどうなっていたかと思うと、まだ胸が痛んだ。
こんな待遇を受けるのは彼女ではないのに。
どうしてそんな信任がこんなときに下されたのか。
少なくとも彼はその信任と彼女は無関係だと信じていた。
報告のため急いで執務室に駆け込んだが、執務室の中にはアスコだけが残っていた。
「隊長は?」
「ええと……その……公爵様のところへさっき……」
アスコはカロティンが飛び込んできた扉を指差した。
「こんなに急ぎの報告があるのに、一体どこへ行ったんだ!」
アスコが舌打ちした。
「どこ行ってたのよ……。空気読まないにもほどがあるわよ、カロティン卿。」
部屋に着くまでのあいだ、運が良かったのか悪かったのか、あの女性以外とは誰ともすれ違わなかった。
その女性はカロティンの姿を見るなり「傭兵様!」と叫び、手にしていた刺繍を投げ出して、急いで風呂の準備とタオルを用意すると言い残して姿を消した。