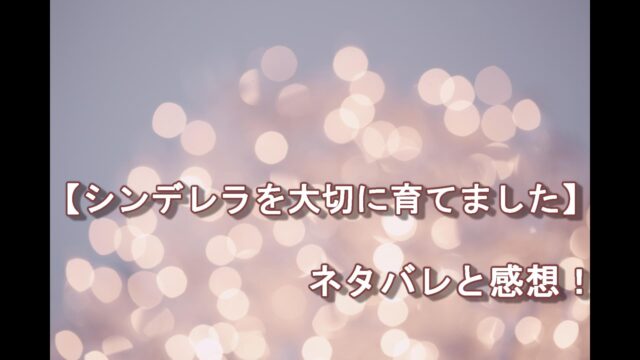こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

208話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 娘の成長②
二日後、私は子どもたちを連れて契約した建物へ向かった。
そこは以前、木材置き場として使われていた場所で、建物の裏手には深い森が広がっていた。
アイリスは質問を繰り返し、リリーとアシュリーは物珍しそうに周囲を見回していた。
「ここなんですか?」
少し驚いたような顔で建物を眺めながら、アイリスが尋ねた。
そう、ここだ。
犬たちを初めて連れてきたとき、彼女は渋い顔をしていたが、今回はわりと満足そうに言った。
「いいですね。すごく広い気がします。」
「食堂や休憩室も作らないといけないことを考えたら、このくらいの広さは必要かもしれないわね。」
もし厨房を作るなら、食堂と休憩室を分けた方がいいだろうが、今はそこまで作る余裕はない。
しばらくは、ここで働く人たちは弁当を持参するしかなさそうだ。
市内から距離があるため、食事をとる手段は弁当を持ってくる以外なさそうだった。
私は、規模が大きくなれば厨房を作って料理人を雇うことも考えていた。
「すごく広いですね。」
そのとき、見学を終えたリリーとアシュリーが戻ってきて言った。
広すぎて、しばらくは一部のスペースしか使えないかもしれない。
「人員はもうそろいましたか?」
「うん、半分くらい。」
できれば経験者がいいが、私のやり方で作るビヌーを作った経験者がいるはずもない。
もちろん何も知らない人より、既存のビヌー作りの経験がある人のほうが助けになるだろうが、残念ながらほとんどの人は仕事を断ってきた。
断られた理由も理解できる。
今はビヌーの木が枯れてしまっているが、数年経てばまた芽吹き、そうなれば元のビヌー工房が再び稼働するだろうからだ。
私が作るビヌーがこの先も売れ続ける保証はないのだから。
数年後、ビヌの木が十分に成長すれば売れないこともないだろうが、もともと工房を離れる危険は冒したくなかった。
「でも、その人たちは今まったく収入がないんじゃないですか?」
隣で私の説明を聞いていたアシュリーが、納得できないという様子で尋ねた。
確かにそう考えればそうだ。
現時点で古いビヌ工房では稼ぎようがなく、そこに留まっているのは苦しいと感じているかもしれない。
「でも、ギルドは別だよ。あっちの工房を離れてうちの工房に来ることは、裏切りだと思われる可能性がある。」
ギルド――簡単に言えば組合だ。
あちら側は私をライバル視するかもしれない。
ビヌの木が病気で枯れてしまった今、私が新しいビヌを育てたことで立場が変わってしまったのだから。
「じゃあ、ギルドに属してなければ、私たちの方に来るかもしれないですね?」
アシュリーの言葉に、私は腕を胸の前で組んだ。必ずしもそうとは限らない。
「ギルドを怖がる人もいれば、仲間を信用できないと思う人もいる。それに、私たちの将来が不確かだと考える人もいるだろう。」
「複雑ですね。」
アイリスが鼻先をつまみながらつぶやいた。
複雑だ。
私は埃の積もった建物の中を見回し、苦笑した。
人の気持ちというものはそういうものだ。
同じ断りでも、理由はさまざまだ。
「人が少ないと工房は動かないんですか?」
リリーの問いに、私は首を横に振った。
関係ない。ビヌーは私一人でも作れる。
人が多ければ、その分たくさん作れるというだけだ。
「いや、ここを片付けて、集まった人だけでも雇ってすぐに始めるつもりだ。」
「じゃあ、私は何をすればいいですか?」
アイリスの質問に、私はにっこり笑って彼女の肩を抱き寄せた。
やることはたくさんある。
計算を手伝ってもらうこともできるし、近隣の人たちに使用をお願いする手紙を書くこともできる。
どんなビヌを作るか、私にアイデアを出してくれてもいい。
「お母さん、この建物の裏、空き地ですよね。何か使い道はありますか?」
アイリスに何を手伝ってもらうか話していると、アシュリーが近づいてきて尋ねた。
空き地?私は少し離れた場所にある林のある裏手を思い浮かべた。
どうやらこの建物は木材置き場のすぐ近くに建てられていたようだ。
そのせいで裏手はやや薄暗い。
野生動物の侵入を防ぐために柵は設けてあるが、特に使う予定はない。
「しばらくは使うことはないと思うけど、どうして?」
「じゃあ、お母さんとアイリスがここに来たときに…私も一緒に来て工房で弓を引いてもいいですか?」
「弓?関係ないけど、楽しいの?」
そういえば、アシュリーが最近弓に夢中になっていたのを思い出した。
初めてダニエルに教わったあと、二日間腕が上がらなかったと泣き言を言っていたっけ。
「はい。家の庭だと距離が短くて。」
そうだったか?そういえば長い方は屋敷の方に向かって撃たないようにと言っていたのを思い出す。
私は目を細め、できる限り厳しい表情で言った。
「私の視界に入っていなきゃだめだ。」
自由にさせてはいるが、それでもアシュリーが一人離れているのは心配だ。
アシュリーもまた、私の心配を察したのか、真剣な表情で答えた。
「はい、それは心配なさらないでください。」
かまわないだろう。私は肩をすくめた。
貴族社会の女性が弓を使うのは決して長所とはされないが、それを気にするならリリーが絵を描くことなど許されるはずがない。
リリーが絵を描けるなら、アシュリーも弓を引ける。
「そろそろ行きますか?」
周囲を見回して戻ってきたダニエルが近づき、尋ねた。
契約を済ませに行かなければならない。
ダニエルが見つけてくれた工房の主になる人にも会うことにしていた。
私たちは再び馬車に乗り、途中でリリーを降ろした。
彼女は路上の茶店に座って行き交う人々をスケッチしたいと言い出した。
路上カフェで多くの画家たちが行う練習だそうで、私は何も言わなかった。
「アシュリー、君はどうする?」
「私はお母様と行きます。何も持ってきていないので、リリーの隣では何もできませんから。」
私たちはリリーとエナを降ろして、再び馬車を走らせた。
馬車はすぐに妖精の小川のほとりに到着した。
「見覚えのある顔がありますね。」
小川のほとりに入った瞬間、ダニエルが低い声で言った。
何が?と彼を見やると、ダニエルは地元の者に目配せして言葉を続けた。
「あちらのバーに座っている人たちです。ギルド側の人間です。」
私はバーの方を直接見ないように、アシュリーとアイリスへと視線を向けた。
二人はどんなデザートを食べるかで盛り上がって話をしていた。
カステラは数に限りがあってもう残っていないだろうとアイリスが言うと、アシュリーは桃のパイにアイスクリームをのせたいと話していた。
「偶然でしょうか?」
「そうでしょうね。」
私の問いかけにも、ダニエルは静かだった。
彼は給仕の後について、小さな部屋へと私たちを案内した。
十人ほどが座ればいっぱいになるその部屋には、すでにグラント伯爵と彼の秘書が座っていた。
中へ入りながら、私はバーの方へ視線をやった。
すると、ダニエルの言った通り、この店に似つかわしくない男たちが座っているのが見えた。
似合わない、というのは服装や外見のことではない。
こういう店に来る客は、たいていそれなりの身なりをしている。
この店は雰囲気もよく、料理もおいしく、手の込んだ料理が出る。
デートかもしれないし、会食かもしれない。
だが、バーに座る男たちはまったく場に馴染んでいなかった。
彼らはどこか不穏な視線でこちらを窺っていた。
私と目が合った瞬間、彼らは慌てて…周りを何事もないふりで見回すのが、かえってぎこちなかった。
「アイリスとアシュリーを帰した方がいいでしょうか?」
私の問いに、ダニエルがふっと笑った。
彼はアシュリーとアイリスを内側に座らせるよう手で示して言った。
「私がいるのに、まさかバンス家の人間に手出しできるわけがないでしょう。」
私は目を細めてダニエルを見た。
以前はこれを大げさだと思って可愛いと感じていたが、今は大げさではないと分かっても、やはり可愛い。
ダニエルは「どうかしたのか」という表情で私を見て微笑んだ。
可愛い、本当に可愛い。
私は彼を思わず抱きしめたくなる衝動をこらえながら、向かい側に座っている人たちに挨拶をした。
「またお会いできてうれしいです。こちらは長女のアイリスと、三女のアシュリーです。」
グラント伯爵はすでにダニエルから紹介を受けていた。
彼は工房の許可を出す役目をしており、どことなくゲイリーに似ていた。
ただ、ゲイリーより少し背が高い。
ダニエルは、グラント伯爵が気に入った様子だった。
かなり几帳面な性格が気に入ったのだという。
ほとんどの貴族は無償で、名誉のためだけに職務に就く。
そして同じ理由で仕事をおざなりにする者も多い。
だが、グラント伯爵はそうではなかった。
どんな仕事も几帳面かつ徹底的にこなし、自分の仕事に誇りを持っていた。
「お会いできて光栄です。」
グラント伯爵は左右に分かれた髭をなでながら、アイリスとアシュリーに挨拶をした。
約束の時間よりずっと早く到着していたことからも、彼がどれほど仕事に忠実であるかがうかがえた。
腰を伸ばし、気を引き締めた。
最初にダニエルを通して、ビヌ工房をやりたいという話をしたとき、事業計画書はもちろん、雇う予定の人々の身元確認書まできっちり確認された。
事業を維持できる能力があるかどうかを確かめるため、初期資金をどこから調達するのかまで聞かれたものだ。
だから私は少し緊張していた。
グラント伯爵は非常に忙しく、そして几帳面に仕事をする人物だ。
この約束も、最短で予定を押さえたのが先週か、もしくは昨日だった。
今回もタイミングを逃せば、新しい約束を取るのに今日から一週間か、一か月かかるかもしれない。
「工房の主人はどこにいますか?」
すぐにグラント伯爵が尋ねた。
そういえば、主人がまだ来ていない。
不思議だ。私は時計を取り出して時間を確認した。
私たちは少し早めに着いたが、工房の主人はもっと前に到着しているはずだった。
「すぐに来るでしょう。」
ダニエルがにっこり笑って話題を変えたおかげで、少し場の空気が和らいだ。
やがて店員が、私たちのためのお茶と、アイリスとアシュリーが注文したアイスクリーム添えの桃のパイを持ってきた。
「遅れていますね。」
天気の話や最近風邪をひく人が増えた話をしているうちに、工房の主人はまだ現れなかった。
私は、グラント伯爵が不快そうな表情を浮かべるのを見て、唇をかみしめた。
「おかしいですね。」
ダニエルも表情を曇らせた。
彼は私に向かって、ためらいながらも打ち明けた。
「人を使いにやって、家まで様子を見に行かせたんです。彼が何も言わずに遅れるなんて、あるいは来ないなんて、ありえないことですから。」
ダニエルが雇った人だから、そういうこともあるだろう。
工房の主人に何かあったのではないかと心配していると、グラント伯爵が困ったような表情で言った。
「とにかく、今日はなかったことにしなければなりませんね。」
「申し訳ありません、伯爵。人を送ったのですか……?」
「バンス夫人、すべてにおいて約束が最も重要なのです。最も大事な主人が約束を守らなかったのに、何を信じて許可を与えられますか?」
もっともな言葉だ。
私はため息をついた。
グラント伯爵もまた私を見てため息をつきながら言った。
「人選を誤ったようですね。新しい人を雇ってから、改めて約束を取り付けた方がよさそうです。」
どうすればいいのだろう?私にも分からなかった。
ダニエルを見やった。彼の表情も硬くなっていた。
(魔法で工房主を呼び出すことはできないのだろうか?でももし怪我をして来られないとしたら?署名もできないほどの怪我だったら?)
ダニエルが人を見る目を誤るはずがない。
空から鳥が落ちてくることはあっても、ダニエルは違う。
そのとき、アシュリーが小さな声でたずねた。
「誰が来ていないんですか?」
私はグラント伯爵から視線を外さずに、アシュリーに答えた。
「工房の主人よ。書類に署名をしてもらうために来るはずだったのに、来ていないの。」
アシュリーの表情も曇った。彼女にも、この状況が良くないことが分かったようだった。
「では、これで。」
グラント伯爵が不快そうな顔で席を立った。
それに合わせて、アシュリーもすぐに立ち上がった。
「工房の主人がいればいいんですよね?」
皆の視線がアシュリーに向けられた。
普段は冷静なグラント伯爵の秘書までも、驚いた表情で彼女を見つめていた。
「でも、いないじゃないか。」
伯爵は落ち着いた表情で言った。
アシュリーにそう答えると、私たちを一瞥し、再び口を開いた。
「ここにいる者の中で、工房の主人になれる人間はいない。」
もちろんダニエルは論外だ。
アイリスも王子妃試験中だから絶対に無理。
じゃあ私がやるのか?と心の中で考えていると、アシュリーが再び口を開いた。
「私がやります。」
……なんだって?
私は思わず目を大きく見開いた。
グラント伯爵の表情も、私と同じように驚きに満ちていた。
彼は私を見てから、ダニエルを、そしてアシュリーを振り返って言った。
「馬鹿なことを言うな。」
「社長になるには条件があるんですか?年齢が高くないといけないとか、それとも……」
アシュリーの声はだんだん小さくなり、最後には自信なさげに私を見ながら尋ねた。
「女性じゃダメなんですか?」
そうなのだろうか?
私はダニエルを見た。
彼は興味深そうな表情でアシュリーを見ていた。
私の視線に気づいたダニエルは、にやりと笑って言った。
「それは違う。」
社長になること自体は特に問題ではないらしい。
ただ、収入を得ることが法律で禁じられているわけではないにせよ、簡単な話ではない。
ダビナだって、自分の店の社長でありデザイナーなのだから。
しかしアシュリーは貴族だ。
貴族が店の主人になるというのは、社交界を離れることと同義であり、しばらくの間、正気を失った貴族として名が上下するに違いない。
私はアシュリーを止めようと思い、彼女に向かって口を開こうとした。
だが私が言うよりも先に、アシュリーが再び口を開いた。
「それなら私がやります。どうせ署名だけすればいいんでしょう?」
グラント伯爵の表情がこわばった。彼は呆れた顔で言った。
「バンス嬢、それはそんなに簡単なことじゃない。工房の代表としてバンス嬢の顔を出すなんて、とんでもない話だ。」
グラント伯爵が何度も「とんでもない話だ」と言い張るのも当然だ。
本当にアシュリーが主人になれば、社交界はひっくり返るだろう。
アシュリーの叱責は、水を差す程度では収まらない。
もしかすると、私やアイリスに対しても、娘や姉妹が不作法なことをしたと陰口を叩くかもしれない。
そこまで考えると、アシュリーを止めることが本当に正しいのか疑問に思えてきた。
どうせ我が家は、リリーが画家になると決めた瞬間から、社交界の笑いものになっていたのだ。
「娘をどう育てたんだ」と陰口を叩かれるのは目に見えている。
もちろん、そんなことは私の知ったことではない。
陰口を言う連中は、リリーが不幸であろうと幸せであろうと気にしない。
彼らは、アイリスやアシュリーがウェスターと結婚して安定した生活を送っていれば、私の目に触れない限り「良い結婚をさせた」と言うような人間なのだ。
私が心配しているのは、そんな連中に非難されることではない。
アシュリーの可能性を奪ってしまうことだった。
リリーが画家になることを許したのは、彼女が確固たる意思を持っていたからだ。
結婚に興味がないことも、画家になりたいということも、リリーは私にしっかりと示してみせた。
しかしアシュリーは違う。
この子は、自分が何をしたいのか、何が得意なのかを今ようやく探し始めたところだ。
私はアシュリーの可能性を自ら潰してしまうのではないかと恐れた。
「アシュリー。」
私は静かにアシュリーを呼び、彼女に身を寄せてささやいた。
「私は、あなたが工房の主人になるのも悪くないと思っているわ。でも、もしそうなったら、これから本当にやりたいことができた時に、それができなくなるかもしれないの。」
「それが私の本当にやりたいことなら?」
「工房の主人になれば、社交界にはなかなか足を踏み入れられなくなるわ。だから、私も代わりに主人になろうかと思ったの。」
相手を見つけたとしても、結婚がうまくいくとは限らない。
私の言葉に、アシュリーの表情はかえって固くなった。
彼女は真っすぐ私を見つめて言った。
「私はアイリスみたいに王妃になりたいわけでも、リリーみたいにやりたいことがあるわけでもないんです。家族の役に立てるなら、それで十分なんです。」
なんて子なのだろう。
私はアシュリーの健気さに思わずため息をついた。
家族は大事だ。家族の役に立つことも素晴らしい。
でも、それが犠牲になることを意味するなら、それは本当の家族ではない。
一人の犠牲の上に成り立つ調和など、ただの自己満足だ。
私はアシュリーを説得するために口を開いた。
「私は嫌だ。君が幸せになることを願っているのであって、ただの都合のいい存在になることなんて望んでいない。」
アシュリーの目が大きく見開かれた。彼女は理解できないという表情で私を見つめ、それから言った。
「お母さまのお役に立てるなら、私は幸せです。」
「そう思っているのね。」
他人の助けになるだけで、全く自分に損がない人生が本当に幸せなはずはない。
本人も周りもそれを便利だと思うから幸せだと錯覚するのだ。
私はアシュリーが本当に幸せであってほしい。
多少疲れて傷ついても、自分が望む道を歩き、その過程で幸せをつかんでほしい。
他人の幸せを見て喜ぶだけでなく、自分の幸せも手に入れて喜べるようになってほしい。
そのとき、ダニエルが口を挟んだ。
「臨時でやればいい。」
「臨時ですか?」
部屋にいる全員の視線がダニエルに向けられた。
彼はテーブルに腕を置きながら言った。
「とりあえず臨時社長としてアシュリーを立てて、許可をもらうのはどうでしょう。私たちはまず工房を立ち上げる必要がありますし、アシュリーがずっと社長の座にいる必要はありません。一、二か月後に新しい人を見つければ、その時点で交代すればいいんです。」
「そんなことが許されるの?」
私は戸惑いながらグラント伯爵を見た。
彼
はダニエルの言葉が信じられないようにこちらを見てから、こう尋ねた。
「急ぎたい気持ちは分かりますが、一、二か月くらい待てないのですか?こんなふうに……こほん、半ば無理やり名前を出してまで許可を取る必要はないでしょう。」
「アイリスには時間がありません。」
アシュリーがはっきりと言った。
グラント伯爵はその言葉に驚いた表情でアイリスを見た。
視線を受けたアイリスは、ばつの悪そうな顔をした。
「ここにアイリス・バンス夫人は王太子妃候補の試験を受けているではありませんか。」
その間にダニエルが素早く口を挟んだ。
彼は慣れた様子でアイリスからグラント伯爵へと視線を移し、続けた。
「今回の試験課題は慈善活動です。もしバンス夫人が工房を運営するなら、その収益でアイリスが慈善財団を作るというのはどうでしょうか。」
驚いたことに、ダニエルの言葉にグラント伯爵の表情が真剣になった。
彼は「なるほど」という顔でアシュリーを見てから、席に腰を下ろした。
そして左右に割れた口髭をいじりながら、アイリスとアシュリーを交互に見比べ、ふっと笑った。
無愛想で、笑顔など見せないように思えたその顔に微笑みが浮かぶと、意外でありながら少し怖さもあった。
彼は普段まったく笑わない人間らしく、その笑顔はどこかぎこちなかった。
作り笑いのようにも見えた。
それでも、笑顔は笑顔だ。
好ましい笑顔に、少し気分が和らいだ。
伯爵は自分の笑みに戸惑っているアシュリーとアイリスを見て口を開いた。
「兄妹の仲が良いというのは、良いことだ。」
――私たち兄妹の仲は確かに良い。
私は何も言わず、グラント伯爵が次に話すのを待った。
彼は私たちを見回したあと、これまで存在を忘れていた秘書に視線を向けた。
「書類を。」
その言葉に、秘書は自分の存在感すら忘れていたようにハッとし、慌ててカバンから書類を取り出した。
さらにペンとインクも取り出して机の上に置く。
そして書類をめくり、指先であるページを示した。
指差しながら言った。
「署名する場所はこちらと、こちら、それからこちらです。」
「ちょっと待ってください。」
秘書に促されるままアシュリーがペンを取ろうとしたとき、私は必ずしもアシュリーがこれをやる必要はないと気づき、身を乗り出した。
グラント伯爵が何事かと私を見ているのが分かった。
私はダニエルに尋ねた。
「どうせ一、二か月程度なら、アシュリーではなく私がやったほうが良くないですか?」
少しでも社交界の噂に上る可能性があるなら、私がやったほうがいい。
彼女は私の娘ではないのだから。
しかし、ダニエルの考えは違ったようだ。
彼は子どもたちとグラント伯爵の顔をちらりと見てから、私に身を寄せて言った。
「アシュリーがいいと思います。何があっても、まだ若いという理由が通りますから。」
若さゆえの未熟さは、「知らなかった」で済ませられる――そういうことだ。
しかし、それが本当に良いことなのか。
若くて失敗する人間という印象がついてしまうのではないか、と反論しようとした時、アシュリーが私の腕をつかみ、頼むように言った。
「私がやります、お母さま。やってみたいんです。」
意外な言葉に驚いてアシュリーを見ると、彼女はさらにこう続けた。
「考えてみてください。私がいつ社長や代表になる機会がありますか?一度やってみたいんです。」
そう言われては反対できない。
心が揺れる私の横で、ダニエルが小声でつぶやく。
「しかも“姉のために立った”という勇敢さも、アシュリーの名前に付け加えられますよ。」
まるで心の中で天使と悪魔がせめぎ合っている気分だった。
もちろん天使はアシュリーだ。
私はため息をつき、覚悟を決めた。
腕を組んだままソファにもたれかかった。
「こちらです。」
秘書が再び書類に指を置きながら言った。
示された箇所に、アシュリーは緊張した面持ちで署名を始めた。
見ると、彼女の姿勢はずいぶんと良くなっていた。
もちろん、文字の練習を熱心にしたおかげで署名も非常に立派だった。
署名が終わると、アシュリーは誇らしげな表情でこちらを振り返った。
同時にアイリスが彼女を抱き寄せた。
「臨時ですか?」
私はグラント伯爵と約束を交わして部屋を出ながら、ダニエルに小声で言った。
臨時でなければならない。
アシュリーが将来貴族と結婚したくなるかもしれないし、社交界に残りたくなるかもしれないからだ。
「そうですね。」
ダニエルは、もっともだという表情で私とアシュリーを見た。
彼らを見回しながら、私は小さくため息をついた。
そして周囲に聞こえないほどの声量で、そっとつぶやいた。
「せいぜい一、二か月くらいでしょう。アシュリーなら、この程度は社交界でも大きな傷にはならないはずです。」
本当にそうであってほしい――そう願いながら、私は息を吐き、グラント伯爵に挨拶をした。
ふと視線を向けると、私の向かい側にいた人々が、私たちの表情が明るくなったのを見て、笑みを交わしながら席を立つのが見えた。