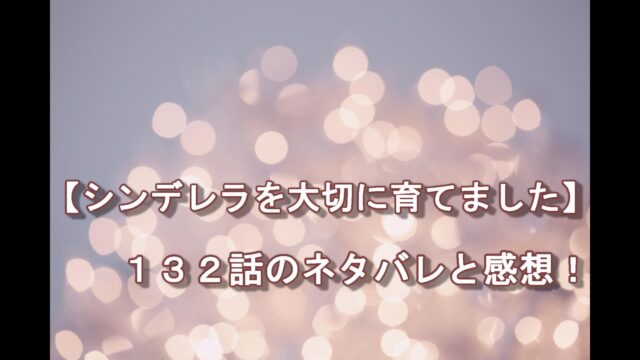こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

213話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 高貴な身分の謝罪
「プリシラ・ムーア伯爵令嬢の婚約者です。」
数日後、プリシラが近くの屋敷を訪れたという知らせに、ミルドレッドはくすっと笑った。
ダグラスが工房に駆け込んできたあの日、ダニエルがすぐさま城に異議を申し立てたからだ。
それは正式な抗議ではなかった。
ダニエルは、もし証人がおり、ムーア伯爵家が受け入れられないというのなら、証人を伴って正式に抗議すると告げていた。
非公式な抗議と公式な抗議では、対処の方法が異なる。公式に抗議する場合は面倒になれば裁判沙汰になり、それは家門の恥となる。
国王はムーア伯爵に、ウォルフォード男爵への嫌疑が事実かどうかを尋ね、ムーア伯爵は大いに慌てた。
そして家に戻るや否や、プリシラを呼びつけた。
「応接室へご案内ください。」
「率直におっしゃっているのですね?」
ジムの問いに、ミルドレッドは少し考えた後、顎を引いた。
こういう時は慎重に行動すべきだ。
プリシラは王妃から命じられる前に謝罪しに来たのだ。
わざわざ彼女を責め立てて、ムーア伯爵に告げ口する必要はない。
「誰が来たのですか?」
台所でクッキーをこっそり食べていたリリーが、驚いて飛び出してきた。
ジムは彼女の口元についたクッキーのかけらに気づかないふりをして言った。
「プリシラ・ムーア令嬢です。」
「ムーア令嬢?なぜですか?」
ジムは、自分が知っていることをリリーに話すべきかどうか少し悩んだ。
工房に暴れ込んできた傭兵たちを雇うための金がプリシラ・ムーアから出たという話は、この家でもごく一部の者しか知らないことだった。
ダグラスがミルドレッドとダニエルにだけ話し、アイリスやリリーには考えも及ばないようにしていたからだ。
ジムはそれが自分の口から言うべき話ではないと判断し、話題を巧みにそらして言った。
「奥様にお伝えしたいことがあると仰っていました。」
母に?
リリーは眉間にしわを寄せて尋ねた。
「アイリスもそのことを知っているのですか?」
ジムの視線は1階の書斎へと向けられた。
彼女はアシュリーと一緒に工房で石鹸を作って販売するという宣伝用の手紙を書くため、今日は朝から慌ただしかった。
手紙と一緒に、ミルドレッドが作って熟成を終えたハーブ入りの石鹸も、小さく切って送る予定だ。
「わかりません。」
察しのいいリリーの言葉に、ジムは何も言わなかった。
なぜ来たのだろう?
リリーは「わかりました」と言って廊下へ駆けて行った。
ジムはリリーに走らないよう注意しようとしたが、客を案内しなければならないことを思い出し、体を向けた。
「アイリス!ムーア夫人が来たって!」
「ムーア夫人?プリシラ・ムーア?」
ちょうど手紙を書いていたアイリスが、驚いて顎を引き上げた。
ペンを握ったまま、文字を連ねていたアシュリーも同じく顎を引き上げた。
「プリシラ・ムーアがここに?なんで?」
「奥様にお話ししたいことがあるって」
母に?
アシュリーとアイリスの顔にも、リリーの顔に浮かんだのと同じ表情が浮かんだ。
三人は、誰が先ともなく慌ただしく書斎を出て、足早に応接室へ向かった。
「お詫びを申し上げに来ました。」
プリシラは席に着くなり、用件から切り出した。
ミルドレッドの顔に微笑が浮かんだ。
しかしプリシラの表情は、謝罪のために来た者のそれではなかった。
ミルドレッドは、心から謝罪に来た人の顔を知っている。
スチュワート伯爵夫人は、自分の犯した過ちを真摯に詫びるために駆けつけ、その行動がどんな被害を与えたかを理解し、心から申し訳ないと謝った。
だが、プリシラは違っていた。
ミルドレッドには、彼女の表情から、これが謝罪ではないことがわかった。
理由は罪悪感からではなく、この状況を無難に終わらせるためだと読み取れた。
「どんなことですか?」
「工房を台無しにしようとしました。申し訳ありません、バンス夫人。」
「どうやって台無しにしようとしたんですか?」
続くミルドレッドの質問に、プリシラの表情がわずかにこわばった。
何なの、この人?
彼女は、自分が謝罪すればミルドレッドがそれを受け入れるか怒るか、どちらかだろうと考えていた。
どちらでも構わなかった。
彼女は謝罪をした、それで十分だった。
相手がそれを受け入れるか否かは問題ではない。
城に戻れば、「もう謝った」と言えば済む話だ。
しかし、ミルドレッドは彼女の思惑通りには動かなかった。
プリシラはミルドレッドの質問に一瞬戸惑い、口ごもりながら言った。
「き、ギルド長が私のところに来たんです。奥様が工房を開けられないようにするから、少しだけ力を貸してくれって。それで……」
そこまで話すと、プリシラの声は小さくなった。
彼女は口をつぐみ、ミルドレッドの顔を見つめた。
「それで?」
ミルドレッドは感情のこもらない声で尋ねた。
続けろという合図に、プリシラの表情はこわばった。
叱られているような気分だったが、夫人の表情が怒っているようには見えず、今まさに叱られているのかどうか判断がつかなかった。
もちろん、怒った表情であっても叱っているとは限らないのだが。
「傭兵を雇うお金が必要だと、何度も頼まれて断れなかったんです。」
プリシラは背筋を伸ばし、やや強気な口調で言った。
頼んだわけではない。ギルド長が先に提案し、彼女はそれを受け入れただけだ。
ミルドレッドはプリシラの態度からそれを読み取った。
単にお金を渡したのと、最初から後援したのとでは、その性質がまるで違う。
「でも、途中でやめるよう言ったんです。やめろという言葉を伝えるためにあの子を使うのはおかしいと思ったから、結果的に奥様のもとに行ったんです。」
プリシラの堂々とした態度に、ミルドレッドは目を細めた。
彼女は何も言わずにカップを持ち上げ、ゆっくりと紅茶を口に運んだ。
ミルドレッドが何も言わないので、プリシラは再び落ち着かなくなった。
怒るにしても許すにしても、早く決めてほしいのだ。
しかし、彼女はそれを口には出さず、黙ってミルドレッドが紅茶を飲み終えるのを待った。
「じゃあ、あなたは傭兵を雇うお金を渡したのですね?」
少ししてミルドレッドがそう尋ね、プリシラは自分の失言に気づいた。
本当は、ギルド長が何のためにそのお金を使うのか知らなかった、と言うべきだった。
彼女は慌てて言い直した。
「はい。でも奥様やバンスの羊たちに絶対に危害を加えないと約束したから渡したんです。」
「それで、どうやって工房を開けられないようにすると言っていたのですか?」
「そ、それは私も分かりません。」
ミルドレッドの目が細くなった。
もし従業員を脅して逃げさせれば、工房は開けられないだろう。
彼女は、本当にプリシラがそのことを知らなかったのか、それとも知っていて黙っていたのかを考え、じっと彼女を見つめた。
知らなかったとしても問題だし、知っていたとしても問題だ。
そんな短絡的な考えの人間が高い地位に就いてはいけない。
それほど他人の苦労を軽んじる者が高い地位に就いてはいけない。
「ムーア嬢、なぜ王太子妃になろうとしているのですか?」
思いもよらない質問に、プリシラは呆然とミルドレッドを見つめた。
なぜなら、それはただ一人の王太子の妻の座。
数年後には国で最も高い地位の王妃となる場所だからだ。
「王太子妃になりたい」という言葉に、プリシラの両親でさえ「野心があるな」や「分不相応ではないか」とは言ったが、なぜそうなりたいのかまでは尋ねなかった。
プリシラは口を開き、ミルドレッドを見つめながら、やがて柔らかな声で言った。
「王妃になれるからです。」
「なぜ王妃になりたいのですか?」
プリシラは、その時初めてバンス夫人が少し変だと感じた。
完全に愚かというわけではなく、少し足りないのではないかと考え始めた。
彼女は理解できないというように言った。
「なぜ王妃になりたいのですかって?王妃でしょう?」
「王妃って何ですか?」
「世界で一番高い地位です。誰にも無視されず、皆が気を遣ってくれる立場ですよ。」
ふむ。
ミルドレッドはソファの背もたれに身を預け、小さくため息をついた。
プリシラが人々をうまく治めたいとか、素晴らしい国を作りたいから王妃になりたいわけではないことは察していた。
ただ、誰にも無視されず、皆が気を配ってくれる立場を望んでいるのだ。
ミルドレッドの頭の中に、アイリスと一緒に出席したムーア伯爵夫人のティーパーティーの光景がよぎった。
娘のライバルをティーパーティーに招き、ミルドレッドに娘の欠点を見せつけたムーア伯爵夫人。
ムーア伯爵夫人は、それが自分の娘の欠点を見抜いたなどとは露ほども思わなかっただろう。
伯爵夫人が他人の前であのように振る舞ったということは、ムーア家の人々も日頃からプリシラをどう扱っているかが推して知れる。
彼女の兄や父であれば、なおさら遠慮なくそうするに違いない。
「ムーア嬢。」
ミルドレッドはゆっくりと口を開いた。
これは他人の家の事情であり、彼女が関わる理由も必要もない。
しかし、それでもプリシラが少し気にかかった。
「王妃になれば、本当に誰もあなたを軽んじたりしないと断言できますか?」
当然だと答えようとしたプリシラは、思わず口をつぐんだ。
果たして本当にそうだろうか?
もし彼女が王妃になっても、母や父、そして伯父が、これ以上野心が過ぎるとか、分別がないなどと言わない保証はあるだろうか?
彼女がやりたいことをしようとするとき、どうしてそんなくだらないことをしようとするのだろう、と笑われないだろうか?
そんなことはないだろうという考えがプリシラの頭をよぎった。
彼女もわかっていた。
そんなことはないだろうと。
「少なくとも、私をいらつかせる人たちに『黙りなさい』と言えるじゃないですか。」
貴族らしからぬ率直な言葉に、ミルドレッドの目が一瞬見開かれ、すぐ元に戻った。
彼女はくすっと笑いながら尋ねた。
「あなたをいらつかせる人たちに一言言うために王妃になりたいんですか?その人が王なら?王太后なら?」
プリシラの表情が引き締まった。
彼女はゆっくりと言った。
「逆に言えば、私をいらつかせられる人がその二人だけになる、ということですよ。」
まったく。
ミルドレッドはそのまま笑い声を漏らした。
プリシラ・ムーアは何歳だったか?
そうだ、彼女はアイリスより一つ年下だったことを思い出した。
リリーと同い年だ。
王妃候補試験を受けているとはいえ、伯爵家の令嬢とはいえ、まだ十代半ば。
ミルドレッドは、意外にも筋の通ったプリシラの考えに感心して、思わず小さく笑った。
たとえ理由がそれだけだったとしても、彼女は王妃候補になり、試験を受けているのだ。
「行動力だけは見事ですね、ムーア嬢。」
ミルドレッドは、王妃候補になったと聞いたとき、臆病で自信がなかったアイリスのことを思い出しながら、プリシラを褒めた。
母親からの扱いを思えば、プリシラは確かに大したものだ。
自分を支持してくれない家族の中で、それでも欲しいもののために動いているのだから。
それをするより、ずっと難しいことだ。
「それなら許してくださるんですか?」
ミルドレッドの雰囲気が和らいだのを感じて、プリシラは思い切って尋ねた。
ヴァンス夫人が許してくれるなら、城でも彼女を王妃候補から外すことはないだろう。
しかしミルドレッドは、笑みを浮かべたままきっぱりと言った。
「いいえ、それは違います。」
「でも、さっき私の行動力を褒めてくださったじゃないですか。」
「褒めることは褒めること、叱るべきことは叱るべきです。」
プリシラの表情が引き締まった。
彼女は、それが本音だとわかったように言った。
「いい人ぶる必要はありませんよ、ヴァンス夫人。私はヴァンス家の娘さんのライバルなんですから、私を落としたいんでしょう?」
「まあ、それも間違いではありませんね。」
ミルドレッドは茶杯を持ち上げ、プリシラの言葉に微笑んだ。
いずれにせよ、アイリスが王妃になろうとするなら、他の二人の候補が脱落しなければならない。
だから、自ら墓穴を掘ったプリシラの行動は、アイリスとミルドレッドにとっては好都合だった。
彼女は一口お茶を飲んでから、続けて言った。
「でも、良い人ぶろうとして言ってるわけじゃないんですよ、ムーア嬢。私は本当に、あなたは立派だと思っています。」
プリシラの目が細められた。
ミルドレッドは、自分の言葉の意味を理解していない彼女のために、ゆっくりと説明を加えた。
「アイリスは王子が好きなんです。王妃になりたい気持ちもありますし、王妃になってやりたいこともあります。でも、最初に王妃候補になったときは、野心を抱くべきか迷っていたんですよ。」
まったく、バカな子ね。
プリシラはアイリスをそう判断した。
彼女は王妃候補になるために父親に数日間の滞在を頼んだのだ。
王子を好きなわけでもなく、王妃になって何をどうしたいという気持ちもなかった。
ただ、この国で自分が就ける最高位の座に魅力を感じただけだった。
「でも、私はただ、私をいら立たせる人を減らすために王妃になろうとしているんですよ。」
「くだらない理由だと思うなら、笑えばいいわ。」
「いいえ、違います。私は今、あなたを褒めているんです。」
ミルドレッドはウィンクしながらそう言った。
彼女は本気でプリシラを大したものだと思っていた。
野心と行動力、その両方を備えたプリシラは同じ女性であっても、すぐに悪い女と誤解されてしまう。
しかしミルドレッドは、自分の子どもたちがその二つの資質を持つことを望んでいた。
特にアシュリーに。
「私は、あなたが野心を持っているのは良いことだと思います。それを叶えるために行動するのも素晴らしいことだと思います。」
「でも、あなたは私が叱られることを望んでいるじゃないですか。」
「間違っていたら叱るべきです。」
ぐっと、プリシラは口をつぐんだ。
誰かに自分の過ちを指摘されれば、認めざるを得ない。
プリシラはしばらく黙って座っていた。
彼女のために出されたお茶はすでに冷めていたが、彼女は手をつけていなかった。
「本当に、私が野心を持っていることを良いと思いますか?」
「ええ。」
少しのためらいもなく、ミルドレッドは答えた。
彼女は本気でプリシラの野心と行動力を素晴らしいと思いながら言った。
「正直に言うと、私の娘たちもあなたのように野心を持って行動してくれたらいいのにと思います。」
この家で野心を持っているのはリリーとアイリスだが、それをためらいなく行動に移すのはリリーだけだ。
だからミルドレッドが最も心配しているのは、野心すら持たないアシュリーだった。
ミルドレッドはアイリスのために工房長になると名乗り出たアシュリーを思い浮かべてため息をついた。
その様子を見たプリシラが慎重に尋ねた。
「私たちの家に反抗なさるおつもりですか?」
ミルドレッドの顔に微笑みが浮かんだ。
彼女は顎を上げ、こう答えた。
「もちろんです。」
——これは母上と激しい戦いになりそうだ、とプリシラは思った。
そう考えながら、彼女はため息をついた。
もしかしたら、普段は関心を示さない父も、今回は黙って見過ごすかもしれない。
彼女は少し変わった人だと思っていたミルドレッドをもう一度見やり、席を立った。
罵られるかもしれないと覚悟していた。
運が悪ければ、自分を候補から外すようにと城に抗議するかもしれない、とも考えた。
しかし予想に反して、不思議と気分はそれほど重くなかった。
家に抗議したというのに、二度目の深刻な事態が起きたのに、そう感じたのだ。
「分かりました。」
プリシラが素直に返事をして挨拶をすると、ミルドレッドは顎をなでた。
頭は悪くないようだ。性格がねじれているかどうかはまだ分からないが。
「バンス嬢。」
応接室のドアを開けて出た途端、プリシラはドアの前に立っていた三人と鉢合わせした。
アシュリーは慌てて逃げ出したが、リリーとアイリスは残った。
怒りで緑色の瞳を燃やすリリーとは対照的に、アイリスは冷淡な表情でプリシラを見つめていた。
自分のしたことを知られて衝撃を受けているのだろうと考え、プリシラは口元をわずかに緩めた。
「他人の会話を盗み聞きするのは恥ずかしい行為ではありませんか?」
プリシラの穏やかな指摘に、アイリスの顔色がさっと変わった。
その瞬間、リリーが前に出て叫んだ。
「よくもそんなことを!」
おかげでアイリスの頭は冷えた。
彼女はリリーの手を取り、落ち着かせたあと、再びプリシラを見据えて言った。
「他人をいじめるために傭兵を雇うよりも、もっと恥ずかしいことだと思う?」
「私は王妃になるためなら、この手を血で汚す覚悟もしたわ。」
「その血が、あなたが守るべき人々の血だったら?」
アイリスの言葉に、プリシラは動きを止めた。
何を言っているのかと眉をひそめる彼女に、アイリスは腰に手を当てて続けた。
「うちの家族には危害を加えないって言ったわよね?じゃあ、そこにいた人たちは?他の人たちが傷つくのは構わないってこと?」
プリシラの表情がこわばった。
そこまで考えてはいなかった。
いや、プリシラだけではない。
大多数の貴族は、貴族でない人々のことを気にかけない。
しかし、だからといってアイリスに何を言われても気にしない、とプリシラは思っていた。
代わりに、彼女はアイリスを見つめ、その優しさを感じ取った。
「私を妨害したいなら、私だけを攻撃してください、アイリス。罪のない他の人たちを苦しめないで。」
アイリスの続けざまの非難に、プリシラは皮肉を込めて叫んだ。
「優しいふりはやめなさい。あなたも結局、そういう人たちのことなんて気にも留めていないじゃない。」
「優しいふり?」
アイリスの瞳に怒りが宿った。
彼女は右手を上げ、プリシラを指差しながら怒鳴った。
「これのどこが優しいふりよ?気にしなくてもいいことを気にするのが、あなたの立場じゃないの?その程度の責任感もなく王女になろうとしてたの?」
急所を突かれ、プリシラの表情がこわばった。
彼女はアイリスをじっと見つめ、低い声で言った。
「あなたがどれほど責任感を持っているのか、気になりますね、バンス嬢。」
「少なくとも、それを善人ぶっているとは思っていません。」
「では、何だと思っているのですか?」
アイリスの顔に静かな表情が浮かんだ。
「高貴な身分には、それに見合った責任があります。」
プリシラの目が細められた。
それは彼女も知っていることだった。
幼い頃、家庭教師から聞いたことのある話だ。
だが、それを今まで忘れていたのだった。
妙な気分になった。
プリシラは新鮮な視線でアイリスを見つめた。
同じ王太子妃候補になったものの、自分のほうがアイリスよりもずっと良い家柄で、容姿も優れており、比べものにならないほど裕福だと思っていた。
ロレナやクレイグはともかく、アイリスと比べたら自分のほうがはるかに勝っている――そう信じていた。
でも本当にそうだろうか?
プリシラは、アイリスの持つ何かが、自分よりずっと上だということに気づいた。
こんな考えや態度を持った人間だっただろうか?
その気づきに、彼女は思わずアイリスをじっと見つめた。
彼女は王子妃や王妃になって何かをしたいわけではなかった。
ほとんどの人がそうではないだろうか?
まるでそこに山があるから登るように、王妃という地位はすべての貴族令嬢の憧れの場所だったのではないか?
しかし、プリシラは少なくともアイリスにとって、その地位は単なる夢の場所ではないのだと悟った。
その事実は彼女の自尊心を傷つけた。
何も考えずに生きているように感じられた。
彼女はそのままくるりと背を向け、ふくれっ面で邸宅を出ていった。
「腹立つ!」
アイリスの静かな表情が、なぜか何度も頭の中に浮かんだ。
そして「高貴な身分には、それに見合う責任がある」という言葉も。