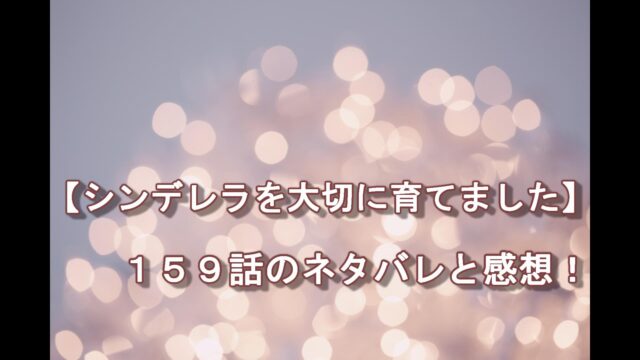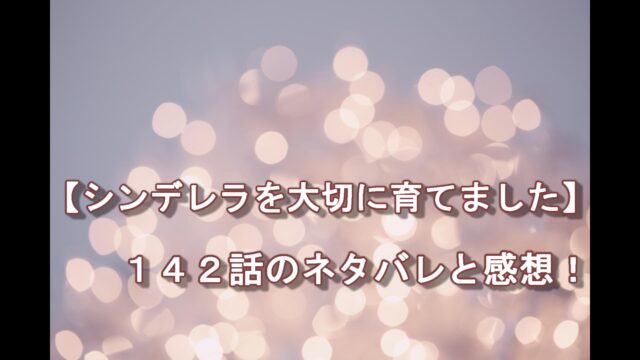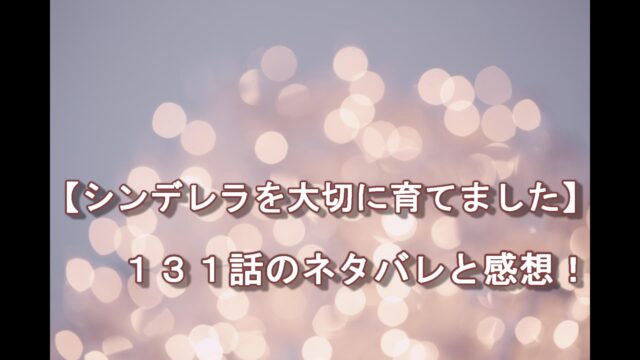こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

215話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 鏡の中の別荘
「明日、もしお時間があれば…お約束はございますか?」
その晩、外から帰ってきたダニエルは、工房の帳簿を整理しているミルドレッドに声をかけた。
材料費や従業員の給料でどれくらい出費があるのかをまとめ、さらに追加でかかる費用まで計算していたので、頭がこんがらがっていたミルドレッドは、彼の言葉をよく聞き取れずに聞き返した。
「え?明日、なんですって?」
ダニエルは、ミルドレッドが紙にペンで計算式を書き込んでいるのを見て片眉を上げ、机の上に身を乗り出して尋ねた。
「電卓が壊れたのですか?」
「いえ、そうじゃありません。出すのが面倒で……これ一つだけ計算すればいいので。」
ダニエルはしばらく、ミルドレッドが紙の上でペンをトントンさせながら計算している様子を見ていた。
彼は、ミルドレッドが時々こんなふうに手計算しているのを見るのが好きだった。
「それで、なんて言いましたっけ?」
ミルドレッドは計算の最後に出た数字を帳簿に書き込み、顧客を見ながら尋ねた。
そのときまで机に寄りかかって立って待っていたダニエルが、微笑みながら言った。
「明日、お時間はありますか?」
「あなたのための時間なら、いつでもありますよ。」
「一日中空けておくことはできますか?」
一日中?ミルドレッドの顔に少し戸惑った表情が浮かんだ。
彼女は椅子から立ち上がり、机の周りを回りながら尋ねた。
「なぜです?どこに行くんですか?」
「はい、一日ほどで済むはずです。」
「どこへ行くんです?」
一日ならそれほど遠くない場所だろう。
ミルドレッドは近くの湖でピクニックをするのかもしれないと予想し、ダニエルの後について机にもたれかかった。
ダニエルは胸の前で腕を組み、微笑んだ。
そしてゆっくりと言った。
「まずは私の作業部屋に行きましょう。」
「この家にあるあなたの作業部屋のことですか?」
ダニエルには作業部屋が二つあった。
元々使っていた作業部屋と、この家に引っ越してきたときにミルドレッドが用意してくれた作業部屋だ。
彼は両方の部屋を使っていたが、最近は街中にある自宅の作業部屋を使うことが多かった。
「ええ。」
ダニエルは顎を軽くしゃくって手を差し出した。
その誘うような仕草に、ミルドレッドは顎を引いて時間を確認した。
夕食を終え、子どもたちはすでに床についている。
彼女も食後に一度片付けを済ませてから帳簿を見直し、その後寝室に戻るつもりでいた。
「この時間に行っても大丈夫かしら。」
慎重なミルドレッドの言葉に、ダニエルの眉がぴくりと動いた。
彼は理解したという表情で言った。
「嫌なら行かなくてもいいですよ。」
「嫌ってわけじゃないけど。」
少し考え込んだミルドレッドは、顧客を見送るふりをしてからダニエルの手を取った。
彼は彼女の真剣な表情を見て笑みを浮かべ、こう言った。
「心配しないで。嫌ならいつでも出て行けますから。」
「自分の家だから、その心配はしてないわ。」
「たとえあなたの家じゃなくても。」
それはどういう意味?と戸惑うミルドレッドを伴い、ダニエルは自分の作業室へと向かった。
屋敷の奥の端にあるその作業室は、灯りが点っているのか、扉の隙間からかすかな光が漏れていた。
しかしドアを開けた瞬間、ミルドレッドはその光がランプから漏れたものではないことに気づいた。
作業部屋の中央に立てられたイーゼルの上に、大きな絵が一枚置かれていたのだ。
光はそこからあふれ出していた。
布で覆われていたのに、その内側が明るく光っているのを見て、ミルドレッドの目は大きく見開かれた。
「これは何ですか?」
「以前、私の絵を見たいとおっしゃったでしょう?」
そう言われ、以前そんな話をしたことをミルドレッドは思い出した。
ダニエルはミルドレッドを絵の前に立たせると、覆っていた布を勢いよく取り払った。
巨大なキャンバスにはある風景が描かれていた。
「どこですか、ここは?」
ミルドレッドは絵の中の景色を見て、思わず問いかけた。
それは窓越しに見える景色を描いた絵だった。
窓の向こうには湖が広がっている。
見事な透明感を湛えた湖だった。
湖面はまるで風に揺れて水面が波立っているかのように見え、そして大きな月が水面に反射して映っていた。
まるで夢のような光景だった。
星ひとつ見えないほど明るい月明かりが、湖面に降り注いでいるのが窓から見える。
ミルドレッドは「なんて素敵な場所なの」と感嘆した瞬間、部屋を照らす光が湖に映る月光だと気づいた。
こんなことがあり得るの?と驚いたミルドレッドはダニエルを振り返った。
彼はまだ彼女の手を握ったまま、そばに立っていた。
「これも魔法なんですか?」
「似たようなものです。」
ダニエルがそう言った瞬間、絵の中から蛍の光が現れた。
まるで誰かが急いで描き加えたかのように、すべてはそのままで、蛍の光だけがふわりと現れたのだ。
「えっ、あれ?」
ミルドレッドが小さく驚いた途端、蛍の光は絵の外へと抜け出し、作業室の中を何かが飛び回り始めた。
小さな光が点滅しながら部屋を漂い、やがてミルドレッドの目の前まで近づいてきた。
ダニエルは微笑みながら、彼女の反応をじっと見つめていた。
感嘆の表情、戸惑いの表情、驚きに目を見開く表情。
ミルドレッドの顔に次々と浮かぶ色とりどりの表情を、彼は楽しげに眺めていたが、やがてこう尋ねた。
「入ってみますか?」
「えっ、中に入れるんですか?」
「もちろん。」
「また出てこられますか?」
「あなたが望むなら、いつでも。」
ならば、とミルドレッドは再びダニエルの差し出した手を取った。
そして、彼が一歩を踏み出したのを見た瞬間、思わず目をぎゅっと閉じた。
次の瞬間、涼しい風が顔をなでるのを感じた。
それはまるで、近くの湖畔の家から漂ってくるような、風と水の匂いだった。
頬に少し湿り気を帯びたような風が、顔と髪をなでて通り過ぎた。
ミルドレッドははっと目を開け、自分がある邸宅の寝室に立っていることに気づいた。
「まあ……」
絵の中に描かれていたものと全く同じ窓が目の前にあった。
白いカーテンが風に揺れ、窓の向こうでは月明かりを受けた水面が金色にきらめく湖が広がっている。
別荘を手に入れるのは難しいことではなかった。
ただ、別荘の近くに湖があり、それが寝室から見下ろせるという条件が必要だったが、それもお金をかければ解決できることだ。
ダニエルが最も多くの時間を費やしていたのは、その絵を描くことだった。
彼は完璧な別荘を見つけ出し、ミルドレッドに見せるための最も完璧な絵を描き上げた。
「気に入りましたか?」
「何がです?」
絵?それとも絵の中に入り込んだということ?それとも、この寝室?あるいは窓の外に広がる風景?
戸惑いを隠せないミルドレッドを見つめながら、ダニエルは再び微笑んだ。
そして軽くうなずきながら言った。
「ここですよ。」
「ええ。素敵ですね。」
ミルドレッドは窓の外に身を乗り出しながら答えた。
月明かりに照らされた湖と、その周囲を囲む木々。
そして、彼女がいる家へと続く道には、磨かれた石のような岩が月光を浴びてキラキラと輝いていた。
「不思議ですね。」
ミルドレッドは再び感嘆の声をもらし、ダニエルを見やった。
体を回すと、背後には立派な寝台が置かれた寝室があった。
古風で高貴な雰囲気の、近くの湖畔の家とは違う寝室だった。
部屋は新しく建てられた雰囲気があった。
「何がです?」
ダニエルが彼女の手を握りながら尋ねた。
ミルドレッドは月明かりで明るく照らされた寝室を見回しながら言った。
「これ、あなたが想像したものなんですか?私はもっと田舎の邸宅に似た感じを想像しているのかと思っていました。」
「田舎の邸宅に似てほしいと?」
「いえ、これも好きです。完璧です。」
まるで絵の中にいるようで、本物のように感じられた。
ミルドレッドは窓枠にもたれ、手のひらで窓枠をなぞった。
堅い木の感触が手のひらに伝わってきた。
「本物みたいですね。」
その時、ダニエルはようやくミルドレッドが最初からこれほど感嘆を抑えられなかった理由を理解した。
彼はくすっと笑って言った。
「本当なんです。」
「えっ?本当だって?」
「はい。本当に存在する家です。ここから湖畔の家まで、馬車で一週間ほどかかりますよ。」
ミルドレッドは思わず口をぽかんと開けた。
そして体をくるりと回して窓の外を見やり、どうして夏の空気を肌で感じられるのかに気づいた。
「でも、私は移動なんてしていませんけど?」
「絵を通って来たんですよ。」
ダニエルは窓辺に寄りかかりながら、穏やかに答えた。
だからこそ、彼はめったに絵を描かない。自分が描く全ての絵は命を帯びるからだ。
妖精が描いた絵は力を持つ。
鳥を描けば本物の鳥となって飛び立ち、
風景を描けばその場所へ移動できる。
「じゃあ…空想画を描いたらどうなるんですか?」
ミルドレッドは信じられないという顔で、つい口をついて質問した。
ダニエルは窓辺に寄りかかったまま肩をすくめるようにして言った。
「老けない男の話、知っていますか?」
それは何の話だろう?
ミルドレッドが首をかしげると、ダニエルは静かに口を開いた。
「ある若く美しい青年が、自分の肖像画が年を取り、自分は永遠に若いままでいることを望むんです。」
「それでどうなるんですか?」
「いい結末にはなりません。」
ミルドレッドの眉間にしわが寄った。
話を聞いただけで、あまり良い結末を迎える話ではなさそうだ。
永遠の若さというものは、利点より欠点の方がずっと多いものだ。
ミルドレッドはもう一度周囲を見回し、ダニエルに視線を向けた。
これが本当に存在する家だなんて。
しかも、自分の家でまるまる一週間も過ごせるなんて?
そこまで考えたミルドレッドの頭の中にひとつの疑念が頭に浮かんだ。
彼女は以前にも似たような出来事を経験したことがある。
「まさか……買ったんですか?」
ダニエルの顔に笑みが広がった。
彼は片膝をつき、座ったまま尋ねた。
「ミルドレッド、僕と結婚してくれますか?」
信じられない。
ミルドレッドは三度目の口をぽかんと開けた。
言葉が見つからず、思わず聞き返す。
「指輪じゃなくて、家でプロポーズするつもりなんですか?」
「指輪も用意してありますよ。」
そう言ってダニエルは懐から指輪を取り出した。
今回も星ではないだろうと、ためらう彼女の手をそっと取って、再び尋ねる。
「はめてもいいですか?」
彼が差し出した指輪は、一見すると普通の宝石のように見えたが、ミルドレッドは疑わしげに、ダニエルが差し出した指輪をちらりと見てから彼の顔を見上げ、そして一息ついた。
「いいわ。」
ダニエルの顔がぱっと明るくなった。
彼は慎重に指輪をミルドレッドの左手の薬指にはめ、すっと立ち上がった。
そして彼女にキスしてもいいか尋ねようとした。
「キスしてもいい?」
ミルドレッドはダニエルの首を引き寄せながら答えた。
自然と彼の手が彼女の腰に回された。
「もちろん、いくらでも。」
ミルドレッドが背伸びをすると同時に、ダニエルは彼女を抱き上げた。
彼は彼女を窓辺に乗せ、自分の腕の中に抱き込み、まるでじゃれるように唇を重ねた。
冷たい風がまた吹き始めたのに、ミルドレッドは寒さを感じなかった。
二人がキスを終えて目を開けたとき、ミルドレッドは雲が月を覆い、周囲が暗くなっていることに気づいた。
しかし、ダニエルの金髪と金色の瞳が彼女の目の前で輝いていた。
「絵を通してなら、いつでも家に帰れるってことですか?」
「あなたが望むなら、いつでも。」
「距離も関係なく?」
「距離も関係なく。」
――悪くない。
ミルドレッドはくすっと笑い、再びダニエルの唇を奪った。
そして、彼の肩越しに見える寝室を一瞥し、尋ねた。
「明日行ってもいいですか?」
「あなたが望むなら、何でも。」
外に出てくるダニエルを見て、何事かと互いに目を見交わした。
彼はピクニックバスケットの上に、果物をのせていないパンケーキと少しのサラダ、ジュースと紅茶を入れて運んでいた。
「旦那様?」
リリーが戸惑いながら呼びかけた。
ピクニックバスケット?
こんなにきれいに整えて、朝からどこへ行くの?
アイリスの顔にも同じ疑問が浮かんだ。
ダニエルは二人が戸惑っていることを分かっていながらも、あえて何も知らないふりをして無表情に言った。
「何の用かな?」
「えっと、どこへ行かれるんですか?」
「うん、ちょっと。」
再びアイリスとリリーの視線が交わった。
今度はアイリスが心配そうな表情で尋ねた。
「朝食は外で召し上がるのですか?」
――それなら、使用人たちにバルコニーのテーブルへ用意させればいいのでは?
そんな同じ疑問が、アイリスとリリーの頭に同時に浮かんだ。
そのとき、ジムが食堂の前に立っている三人を見つけ、挨拶をした。
「おはようございます、旦那様、お嬢様方。」
「おはようございます。」
アイリスが礼儀正しく挨拶すると、ジムの顔に、食堂の中を見回したときの戸惑いの表情が浮かんだ。
彼は再びアイリスとリリー、そしてダニエルを見比べてから尋ねた。
「奥様をご覧になっていませんか?お部屋にいらっしゃらなかったのですが。」
ミルドレッドの朝食を運ぶために部屋へ向かったジムが、空っぽの寝台を見つけたというのだ。
アイリスとリリーの視線が同時にダニエルに向けられた。
彼は無表情で言った。
「散歩に行ったようです。私が朝食を運びましょう。」
散歩だって?こんな朝早くに?
アイリスとリリーの視線が再び交わった。
しかしダニエルは気にも留めず、バスケットを手に家の外へ出て行ってしまった。
「それで、こんなに濡れているんですか?」
ベッドに座って、ダニエルが持ってきた朝食を食べながら、ミルドレッドは声を上げて笑った。
彼の体は、彼が歩いてきた芝生と露のおかげで草の匂いがし、しっとりしていた。
「散歩に行ったと言って、そのまま作業室に入るわけにはいかないでしょう。」
自分でも少しおかしいと思ったようなダニエルの声に、ミルドレッドはまた笑い声を漏らした。
彼女は手を伸ばして彼の首を抱き寄せ、軽く唇を重ねた。
「私のために、朝からわざわざ朝食を運んでくれて…遠くから戻ってきてくれてありがとう。」
ダニエルの唇がやわらかく弧を描いた。
「何でも、いつでも。」