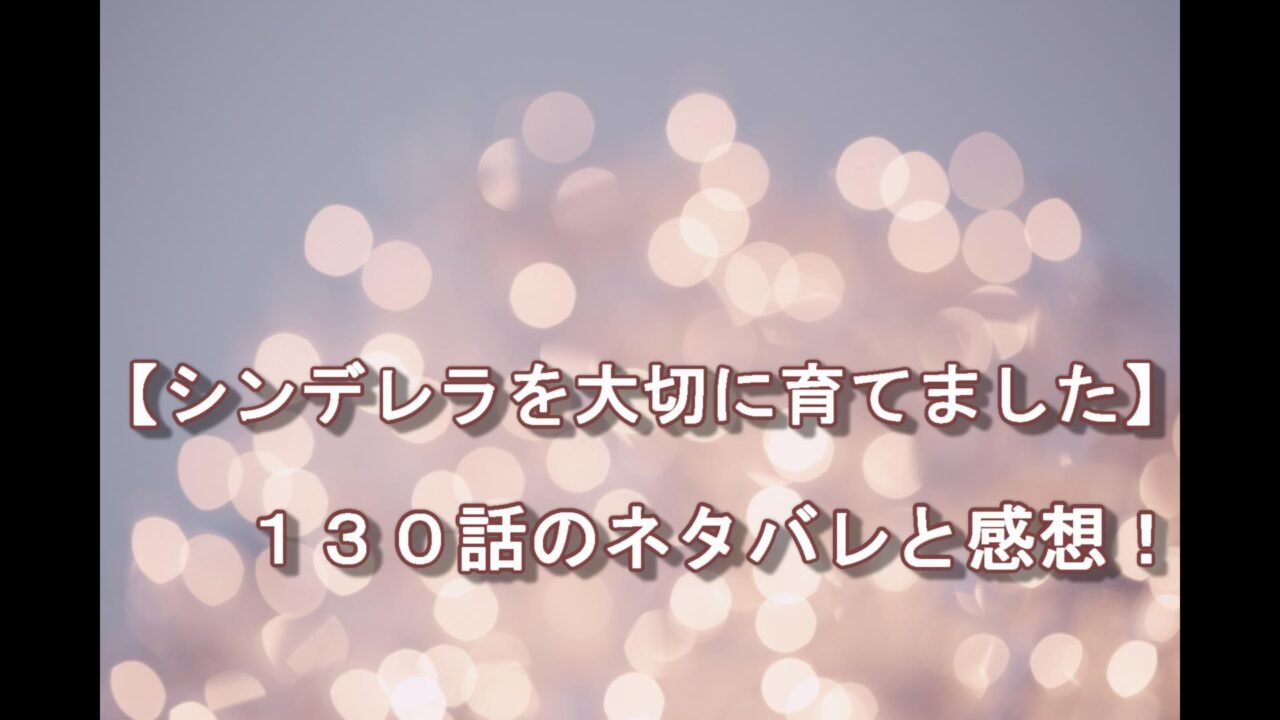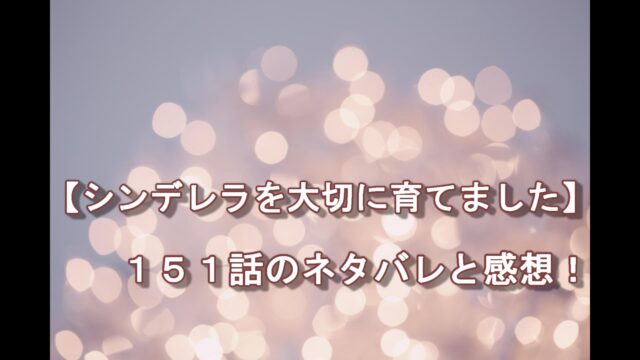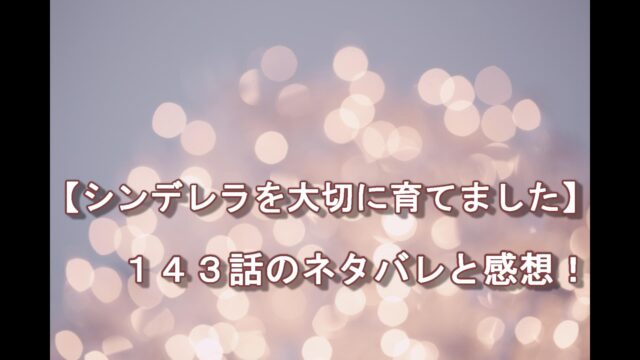こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は130話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

130話 ネタバレ
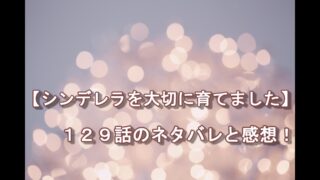
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 妖精③
考える時間が必要だった。
私はダニエルが自分の手を握っている手に全く力を入れていないことに気づく。
彼はいつでも私が手を引くのを止める力を与えていなかった。
「向こうの私は死んだかもしれないということですね」
私はダニエルの手を握って囁く。
死に至る絶望。
それに加護が反応すると言った。
それなら向こうの私は死んだはずだ。
むっとして何かが流れ出た。
「ミルドレッド」
ダニエルは複雑な表情をした。
切なさと罪悪感。
腹が立ち、同時に悲しかった。
彼に向けられた怒りではない。
ただ悔しかった。
どうりですべてがとても簡単に感じられた。
まるで夢を見るように。
「ミルドレッド、ミルドレッド」
ダニエルは私をなだめるように私の頬を包んだ。
そして囁く。
「ごめんなさい。私の過ちです」
そうだ。
彼の過ちだ。
私はダニエルの頬を殴りたいという気持ちと、彼の顔に悪口を吐きたいという気持ちの中でぼんやりと座っていた。
心はむかむかしたが、頭はとても疲れている。
ひどい疲れが押し寄せてきた。
すぐに手を動かしたくない無気力が私を蚕食する。
私はダニエルをぼんやりと見つめ、弱々しく言った。
「考える時間が必要です」
ダニエルの顔には痛々しい表情が浮かんでいた。
私はため息をついて、そのまま横になってしまう。
考える時間が必要だ。
あまりにも多くの情報が殺到し、それを整理する時間が必要だった。
そして、もう死んでしまったはずの向こうの私に弔意を表す時間も。
ダニエルが静かに立ち上がるのを感じる。
「静かに休む時間を持たせてあげようと」
ダニエルは外に出るときに誰かに話しかけた。
相手が誰なのか気になることもなかった。
私は横向きになって考えを整理する。
ここはシンデレラの世界の中ではなかった。
アシュリーはシンデレラではなかった。
それはよかったね。
私はため息をついて目を閉じる。
少なくともアシュリーがシンデレラでなければ、私が彼女の決まった人生を台無しにしたことが違うという意味だから。
私は妖精と何の契約をしたのだろうか。
私がミルドレッドになる代わりに得たものは何だろう?
頭の中に真っ先に子供たちが思い浮かんだ。
アイリス、リリー、アシュリーを得た。
そしてダニエルも。
そんな中でも笑いが出た。
ダニエルが妖精だって、何だか面白い。
妖精は綺麗でキラキラした女性じゃないといけないんじゃないの?
ダニエルはどう見ても妖精には見えない。
いや、違うよ。
私は自分の中の偏見に気づき、再びため息をついた。
妖精かもしれない。
私より少なくとも頭一つは大きくて体格も良い男が妖精かもしれない。
アイリスが王子妃になり、リリーが画家になれるように。
「そうなんだ」
その瞬間、私は席から飛び起きた。
ミルドレッドが何を望んでいたのか分かる気がする。
彼女は2番目の夫を亡くし、同時に財産のほとんどを失った。
3人もいる娘をきちんと育てて嫁に行かせる方法がなくなったという話だ。
ミルドレッドが望んだのは、子供たちが幸せになることだったのだろう。
正確に言えば、3人とも無事に結婚することだっただろう。
もちろん、その三人にアシュリーも入っている。
ミルドレッドはアシュリーが好きではなかったが、とにかく彼女が自分の責任だということを認識していたからだ。
だから女中としてこき使っても追い出してはいないのだろう。
「ああ、どうしよう。アシュリーは結婚せずに一生私と暮らしたいって」
「ダニエル」
翌朝早く。
私はダニエルの部屋のドアをノックする。
あまりにも早朝だという気がしなかったわけではなかった。
誰かの部屋に行くには早すぎる。
それが男性ならなおさらだ。
しかし、今でなければならない。
もう少し時間が経てば、使用人たちが歩き始めるから。
ダニエルはまるで待っていたかのようにドアを開けた。
彼の身なりが昨日私と話していた通りだったので、私は眉をひそめて尋ねる。
「寝なかったんですか?」
「あなたは?」
私はあたりを見回して、誰もいないことを確認した。
そして彼を押しながら言った。
「お入りください」
「え?」
ダニエルは当惑しながらも、従順に私の要求通りに後ずさりする。
私は彼の部屋に入り、ドアを閉め、パジャマの上にローブを整えた。
そしてあごを上げて言った。
「子供たちに何も言わないでください」
「何をですか?」
「私が本当のミルドレッドではないということです。子供たちには死ぬまで秘密です」
ここで死ぬまでとは、私が死ぬ時ではなくダニエルが死ぬ時だ。
子供たちはそれぞれすでに一度以上ずつ親の死を経験している。
アシュリーは2回も経験した。
あの子は私が倒れた時、すごくショックを受けた姿を見せた。
ミルドレッドの顔と体をした私がミルドレッドではないことを知らせる必要はない。
母親が今そばにいたらどうだっただろうかという悩みを一生させたくなかった。
「分かりました」
ダニエルは従順に言った。
良かった。
私はため息をつく。
もう思う存分ダニエルの足を蹴飛ばすことができるね。
「他には?」
その時、ダニエルが尋ねる。
私は頭を上げて彼の顔を見て、そこに浮かんだ罪悪感を発見した。
正直に言うと、ほんの少しはダニエルの過ちではないという気もする。
私をここに連れてきたのは彼ではない。
そしてダニエルは私によくしてくれた。
そんな人に憎しみを持つのは容易ではないことだ。
私はダニエルの顔をぼんやりと見てガウンをつかんだ。
そして、最も難しい質問をする。
「私によくしてくれたのは、罪悪感のためですか?」
「・・・」
ダニエルの表情はこわばった。
しかし、彼はすぐに堅苦しく答える。
「いいえ」
「うちの子を好きだと言ったのは?それは罪悪感のためですか?」
心臓の鼓動が速すぎて破裂しそうだった。
一瞬ダニエルが怒ったように見えた。
しかし、彼はすぐに息を吐いて言った。
「いいえ」
「・・・今も私のことが好きですか?」
ダニエルは私の質問に一歩後退して、腰に手を当てて尋ねる。
「何をお望みですか?」
「何を望んでいるというんですか?」
「好きなことを言ってください。何でも聞いてあげるから」
彼は右手を上げて尋ねた。
「星を取ってきましょうか?」
ダニエルの手の中に光る何かができた。
私は口を大きく開けてそれを見て、彼の方を向いて言った。
「そうじゃなくて、私はミルドレッドじゃないじゃないですか。だから体はミルドレッドだけど、中は彼女じゃないじゃないですか。あなたは私がミルドレッドだと思って私を好きになったのです」
ダニエルの片眉が私の言葉に浮かんだ。
彼は光るものを手中に閉じ込めて、私の前にまた近づいてきた。
そして私の手を左手で握って、その上を右手で柔らかく掃いて言った。
「私が大好きなのは、ミルドレッド。あなたです。今私の目の前にいる人」
彼の右手が離れると、私の手の甲の上が輝き始める。
私はびっくりして私の手を見た。
「私が会って対話して知り合った人です」
ダニエルが右手に掴んだものとは?
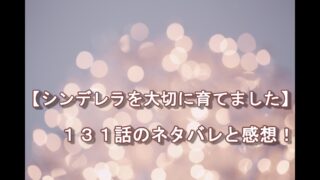





https://recommended.tsubasa-cham.com/matome/