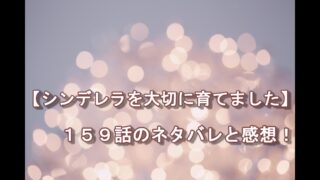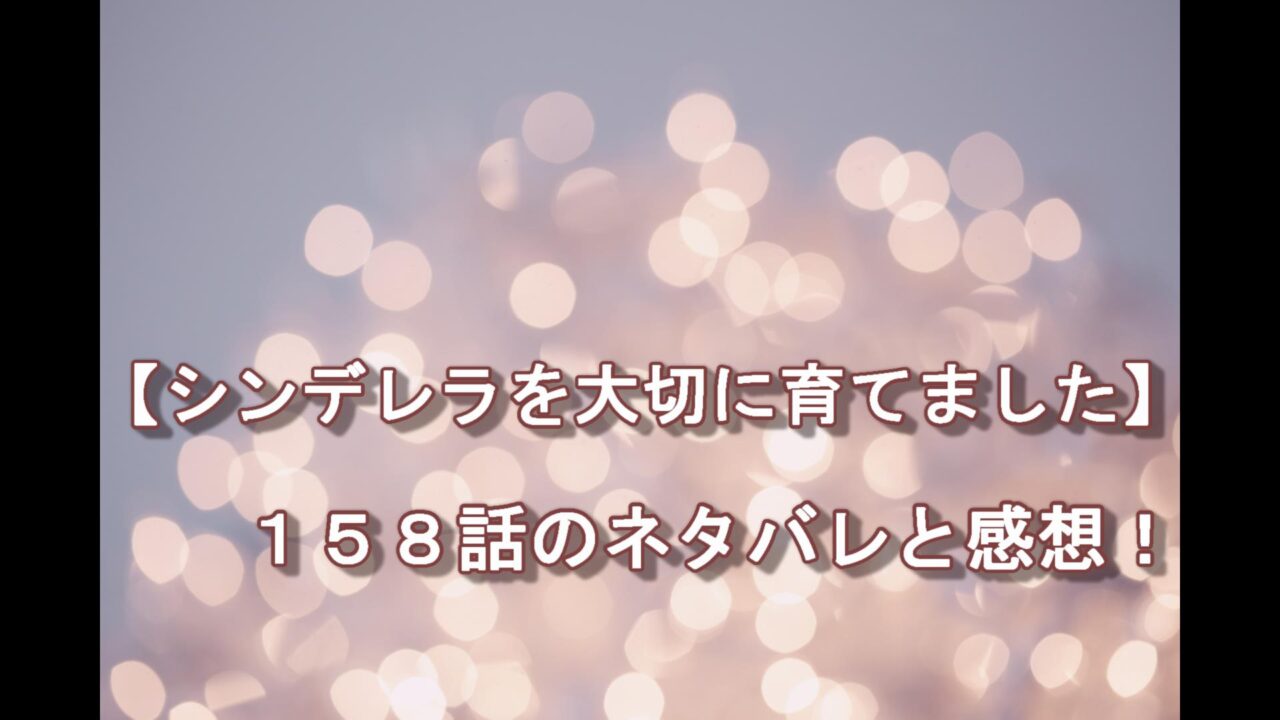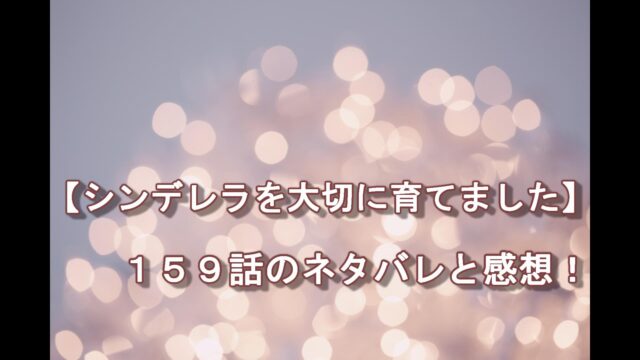こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は158話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

158話 ネタバレ
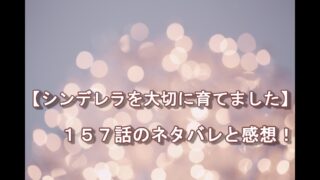
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ティーパーティーのお誘い
「これ何ですか?」
リリーの隣で横になりながら本を読んでいたアシュリーは、召使いたちに命じて大きな樽を洗濯室に運んでいる母を見て尋ねた。
アシュリーはそっと立ち上がり、母に甘いお菓子を作ってもらおうと考えていた。
「うん、ビヌを作ってみようと思って。」
「ビヌ?」
ビヌは普通に買えばいいんじゃないの?
アシュリーはそう考えながら、召使たちが運んできた樽の中を覗き込んだ。
しかし、当然ビヌの木の葉や樹皮が入っていると思っていたその樽には、再生素材がぎっしり詰まっていた。
「これ、再生素材なんですか?」
アシュリーは困惑して尋ねる。
再生素材を使った話は聞いたことがある。
しかし、詳しいことは知らなかった。
母親は彼女に向かってこう言った。
「そうよ。これでビヌを作ってみるの。」
「それって可能なんですか?」
ミルドレッドはアシュリーの質問に何も答えなかった。
彼女が住んでいる場所には、「公爵夫人が舶来品を飲む」という冗談がある。
舶来品とは外国から来たもので、再生素材にそのまま水を混ぜたものを指している。
ミルドレッドは、自分が住んでいた場所では、昔ジャムのような素材で洗濯をしていたという話を思い出した。
そうだとしたら、ジャムには洗浄力があるということではないだろうか。
「可能かどうか試してみないとね。」
彼女はビヌを作る方法を知っていた。
聞いたことがあるだけで、実際に誰かが作っているのを見たわけではないが、油に苛性ソーダを加えて作るものだ。
ミルドレッドは、苛性ソーダが危険なものであるため手袋を着用しなければならないことも知っていた。
苛性ソーダの役割をジャムが果たすのではないだろうか?
そうだとすれば、油にジャムを加えてビヌを作ることができるかもしれない。
「試してみたことはないのですか?」
「うん。でも、作り方はだいたい分かるよ。」
ミルドレッドの質問にアシュリーは再び困惑した表情を浮かべた。
彼女は樽の中に入った再生素材に水をかけている母の様子をじっと見つめていた。
「どうしてそれを知っているんですか?」
「うん、まあ、本で見たりもしたし。」
ミルドレッドの言葉は簡潔だった。
おそらくテレビやインターネットで見たのだろう。
しかし、アシュリーはテレビやインターネットが何なのか知らないので、それで見たとは言えない。
続けてミルドレッドは木の枝を持ってきて、樽の中に入ったジャムのような素材を混ぜた
このまま数日間寝かせて固まったら使えるだろう。
「素手で触ったら絶対ダメよ。」
アシュリーは木の枝を握り、少し離れたところで泡立ったジャムをじっと見つめた。
母親が時折奇妙なことをするのは知っていたが、大抵その結果は良いものだ。
「キッチンにカステラがあるわよ。」
ミルドレッドは自分の部屋に上がりながらアシュリーにそう告げた。
「食べたければ食べなさい」という意味だ。
それでもそっと階下に降りてきたアシュリーは、興味津々でキッチンへ向かう。
キッチンへと続く廊下から、すでに甘い香りが漂ってきていた。
美味しそうだ。
小さく切ってお茶と一緒に持っていこうと考えながら、鼻歌を歌いながらキッチンに入ったアシュリーは、思いもよらない光景に立ち止まる。
彼女が思い描いていたのは、キッチンの食卓に載っているはずの大きなカステラひとつだった。
棚までぎっしり詰められた、十個以上あるように見えるカステラではなかった。
「お母さん?」
母の姿は見当たらない。
不思議だ。
アシュリーは一番近くにあったカステラをそっと触り、それがまだ温かいことを確認した。
ということは、作ってからそれほど時間が経っていないということだ。
「お母さん、これ食べてもいいですか?」
「ダメよ!」
その瞬間、調理台の下から母が飛び出してきた。
彼女は相手がアシュリーであることを確認すると、素早く近づいて一番形が綺麗なものを選び取りながら言った。
「これを食べなさい。切り分けてあげるから。」
キッチンを埋め尽くすカステラの中には、見た目が完璧なものからひどく焼きすぎたものまで様々だった。
焼きすぎて焦げたものもあれば、オーブンから出してすぐに萎んでしまい、形が崩れたものもある。
母は震える手でカステラを慎重に取り分けて皿に載せた。
そして、フルーツソースをその上にかけてフォークを添え、キッチンの食卓に置いた。
「食べて。」
生クリームを使いたかったが、この手持ちではとても贅沢をする余裕はなかった。
母はアシュリーに視線を向けながら、食べるよう促した。
震える腕を背中に隠した。
このままだと、翌朝になっても腕を上げられないかもしれない。
昼食を終えた後、ダニエルがミルドレッドに、昨日アイリスのティーパーティーで出されたカステラの味を試したいとお願いした。
そこでミルドレッドは母に作り方を改めて教えるよう頼み、ダニエルと母に生地の攪拌を指導した。
その結果がこれだ。
見事に完成した一つをミルドレッドとダニエルがダイニングルームへ運び、母はミルドレッドから教わったことを忘れないようにとばかりに熱心にカステラを作り始めた。
そして、キッチンをいっぱいにするほどのカステラを焼き上げた。
「どう?」
母はアシュリーが味見をするまで、その場を離れられずに不安そうに尋ねた。
たくさん作ったので、彼は甘い香りに包まれて気もそぞろの様子だ。
驚いたことに、アシュリーはキッチンいっぱいにあるカステラを見渡し、母を見た。
彼女が自分の仕事に誇りを持っていることをアシュリーも感じている。
その誇りが自分に自信のない方向に向かい、母に気を使いながら争っていたという話もアイリスから聞いて知っていた。
しかし、彼の母はためらいなく彼の幸福を受け入れ、昨日からミルドレッドに完全に献身するようになった。
かつて卵焼きを頼むと面倒がっていた人が、今朝はミルドレッドの好みに合わせて塩と胡椒を軽く振っただけの薄焼き卵を、老人が食べやすいように仕上げて出してきた。
「おいしいです。」
本当においしかった。
口に入れるとまだ温かいカステラがふんわり柔らかく溶けた。
しかし、ゴシンはその反応に満足しなかった。
具体的にどこがどうおいしくて、どこがどう足りないのか教えてほしかったのだ。
誰かが自分を軽視していると敏感に察するアシュリーは、自分の返答がゴシンの気に入らないことをすでに理解していた。
彼女は皿を持ち上げながら言った。
「もう2切れ切ってくれますか? リリーやアイリスにも渡して、どんな反応か聞いてみます。」
「はい、お嬢様。」
ゴシンは急いでお皿を取り出し、カステラをさらに2切れ切った。
そして、それぞれのお皿に盛り付けた後、最後に生クリームとコンポートを添える。
「私が持っていきますね。」
呼ぶ必要はなかった。
アイリスは応接室にいるだろうから、リリーを応接室に呼んでくればいい。
アシュリーはトレーを持って応接室に向かってゆっくりと歩いていった。
アシュリーが応接室にほぼ到着したとき、誰かが屋敷の門をノックする音が聞こえた。
「アイリス・バーンズ様の使いの者ですか?」
家は訪問者がどの貴族の使用人であるかを悟り、無表情な顔でドアノブをつかんでいた。
制服を着た使用人は封がされた招待状を差し出しながら言った。
「ムーア伯爵家から参りました。アイリス・バーンズ様を招待する招待状でございます。」
ムーア伯爵家?
屋敷の使用人は疑わしげに訪問者を見ながら招待状を受け取り、そしてドアノブを握りながら言った。
「お嬢様にお伝えします。」
「すぐにお返事をいただけると助かります。」
「何だって?」
執事は不審に思ったように招待状を確認し、一度待つように伝えた後、応接室へ向かった。
アイリスはアシュリーが持ってきたカステラを食べようとしていた。
リリーは侍女に紅茶を持ってくるように頼んだため、アシュリーも気を緩めてカステラを食べていた。
二人の後ろでは別の侍女が紅茶を淹れていた。
「アイリスお嬢様、ムーア伯爵家から招待状が届きました。」
「ムーア伯爵家?」
アイリスの顔には不思議そうな表情が浮かんだ。
ムーア伯爵家とは何の縁もない。
伯爵令嬢であるフリシラ・ムーアがアイリスと同じ王太子妃候補だということ以外は。
「すぐに返事をします。」
執事の言葉に、アイリスはすぐに招待状を開く。
そして、即座に返事を求めている理由を悟った。
「明日ですね。」
ムーア伯爵夫人がアイリスを招待したティーパーティーは、ちょうど翌日だった。
明日だって?
アイリスは驚きながら招待状を広げて見る。
このような場合、招待状が意味することは一つだけだ。
アイリスにはこれまで興味を持っていなかったが、昨日の彼女のティーパーティーに興味を持ったため、急いで彼女を招待したということだ。
アイリスはすでにこうした経験があった。
社交界の初めに、アシュリーが出来の悪いドレスを直して身にまといデビュタントに出た際、ファッションに関心があると称する夫人たちがこぞってミルドレッドやアイリスを招待していたから。