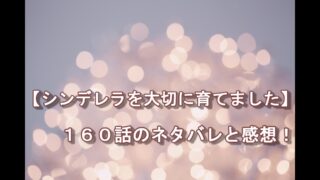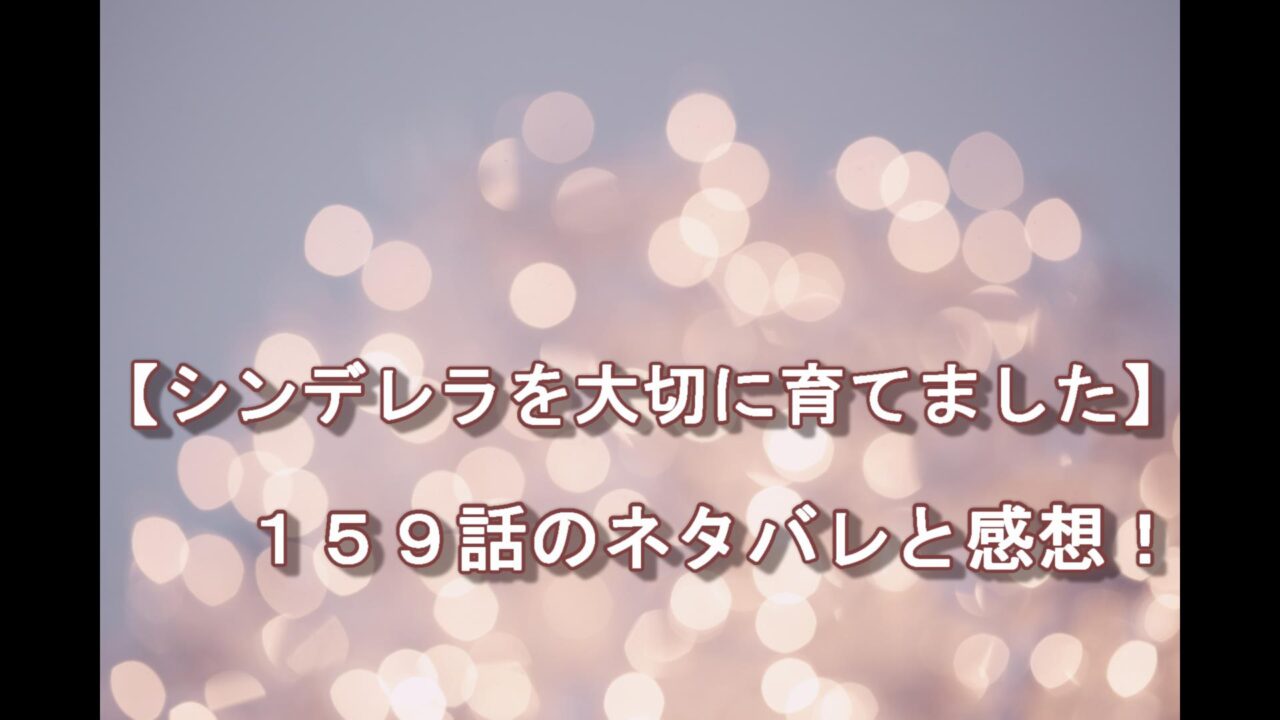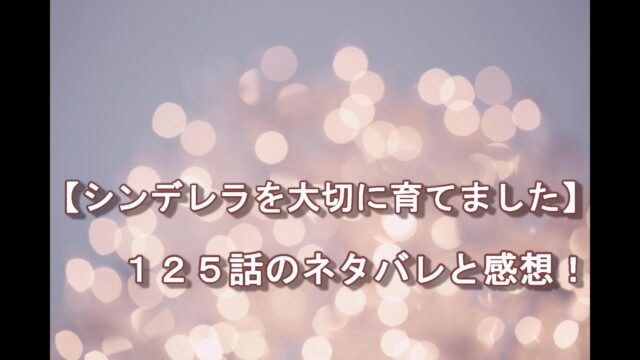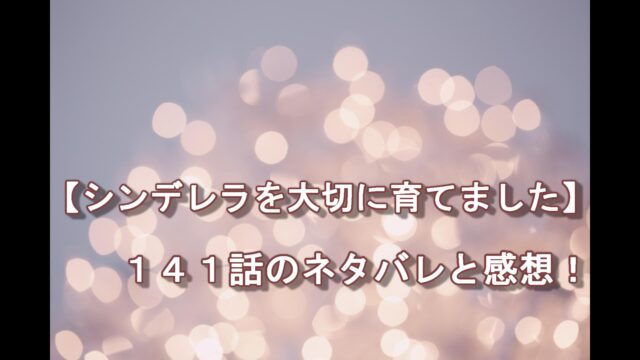こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は159話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

159話 ネタバレ
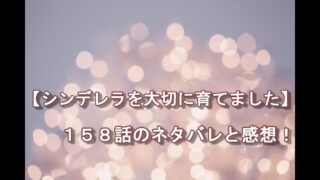
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ティーパーティーのお誘い②
「断りますか?」
執事の質問に、アイリスがそうしようと答えようとした瞬間、いつの間にか執事の背後に立っていたミルドレッドが彼女に尋ねる。
「あなた一人で行くつもり?」
「え? あ、いいえ。一人連れて行ってもいいそうです。」
アイリスの返事に、ミルドレッドが執事に言った。
「行くと伝えてください。私も一緒に。」
「承知しました。」
執事が軽くお辞儀をして部屋を出ると、アイリスは少し戸惑った表情でミルドレッドを見つめた。
玄関に立っていた別の家の召使いを目にして下りてきたミルドレッドは、そのまま応接室に入り、ソファに深く腰を下ろす。
本当は寝室で横になっていたかったが、彼女はやはり子どもたちと一緒にいる方が好きだった。
「どうして断らなかったんですか?」
女中がお茶を運んでくると、アイリスが慎重に尋ねた。
茶杯を手にしたミルドレッドは、少し戸惑いながら聞き返した。
「もしかして行きたくなかった?」
「ムーア伯爵家なら競争相手じゃないですか。最初から参加する必要がないと思いました。」
「でも、断ったらあなたが避けたと考えられるんじゃない?」
アイリスの顔が少し不満げな様子になった。
彼女もそのことを考えなかったわけではない。
ただし、それでも断ろうとしたのは、純粋な理由で自分を招待したのではないのなら、むしろ行かない方がいいと考えたからだ。
もちろん、ティーパーティーはフリシラ・ムーアが主催ではなく、ムーア伯爵夫人が開くものである。
しかし、だからといって、招待された人々はみなムーア伯爵家と親しい人々であるだろう。
むやみに他人のホームグラウンドに一人で行って、嫌な思いをする必要はないと考えたのだ。
「向こうで余計なことを起こしたくないです。」
アイリスの言葉に、ミルドレッドは胸の前で腕を組み、顎に手を当てながら彼女をじっと見つめた。
彼女が何を言おうとしているのか察し、それも理解した。
「招待状を見せて。」
ミルドレッドの言葉にアイリスはムーア伯爵の招待状を差し出した。
ミルドレッドはその招待状を確認しながら、アイリスが気づいていない点があるかどうか確認した。
通常、テーマを決めてティーパーティーを開く場合、ゲストにテーマに合ったアイテムや服装を持参するよう求めることがある。
しかし、ムーア伯爵夫人の招待状には、特定のアイテムや服装、あるいは色に関する記載は全くなかった。
これには二つの意味がある。
一つは、ゲストが準備しなければならないアイテムや着用するべき服装が存在しないこと。
もう一つは、ムーア伯爵家がアイリスに恥をかかせるために、わざと何も知らせていない可能性があることだ。
「ハプニングだったらどうするんですか?」
アイリスの質問に、アシュリーが暗い表情を見せる。
靴を脱いでソファの上に足を上げていたリリーも視線を上げた。
ミルドレッドは再びソファに体を預けながら言った。
「ハプニングなら抜ければいいじゃない。」
「え?どうしてですか?」
「アイリス、ムーア家のティーパーティーは明日だよ。仮に準備するものがあったとしても、今日招待されたのに私たちがどうやって準備できると思う?」
つまり、ミルドレッドとアイリスが準備不足だと批判される筋合いはないという意味だ。
もし批判されるとしたら?ミルドレッドはそれも特に気にしないと思った。
ムーア家とバーンズ家が王妃候補として競争関係にあるということは、社交界で知らない人はいない。
この時点で急にティーパーティーの前日に招待されて、準備不足だと批判されても、多くの人は納得しないだろう。
「向こうは戦いを挑んできているのに、こちらが避ける必要はない。」
ミルドレッドはそう言って肩をすくめた。
ムーア家がクレイグ侯爵令嬢も招待したのならともかく、アイリスだけを招待したのなら、こちらを軽く見ているということだ。
「こちらが軽く見られていないことを見せるべきだわ。」
「そうね。アイリス、もし姉さんが王妃になるなら、あらかじめ先手を打っておく方がいいと思う。」
リリーの言葉にアイリスの表情にも同意するような表情が浮かんだ。
やはり、不満そうな表情が混ざっていたが。
結局その翌日、ミルドレッドはアイリスと一緒にムーア家に向かう準備を進めていた。
リリーも参加する予定だ。
アシュリーはダニエルと一緒に、ある画家のギャラリーに出席することにしていたため、その前まではのんびり過ごせそうだ。
ミルドレッドの寝室では、リリーとアシュリーがベッドに座ってこのような話をしている間に、アイリスは書斎にいるダニエルを探した。
「男爵様。」
ダニエルは報告書を読んでいて、アイリスに目を向けることもなかった。
それは石鹸の原料であるパーム油を輸入するための貿易路について調査した報告書だ。
この報告書に興味を持っているのはダニエルだけではなく、日に日に高騰する石鹸の価格に国中の関心が集まっていた。
「少しお時間をいただけますか?」
アイリスの頼みにもかかわらず、ダニエルは視線を上げなかった。
彼は眼鏡をかけたまま、読んでいたページの最後の部分を読み終えてから、ようやく彼女に向き直る。
そして眼鏡を外しながら尋ねた。
「何ですか?」
「ウィリアムのことです。」
しばらく前に解雇された召使いの名前を聞いて、ダニエルは目を細めた。
ウィリアムは執事の命令を怠った罪で最終的に解雇された。
執事は、怠惰な人間を自分の管理下に置いておくわけにはいかないと判断し、ダニエルに彼のために別の職場を探すよう要請した。
アイリスがその事実を知った時、ダニエルはすでにウィリアムを連れて出かけた後だった。
「私があの子に失礼なことをしてしまって・・・そのせいでずいぶんと遅れてしまいましたけど・・・」
アイリスはそう言いながら、手に持っていた袋を差し出した。
ダニエルは依然として無言で彼女を見つめていた。
何かを問うような彼の沈黙に、アイリスは袋の中身を取り出して見せた。
「私の貯金を集めました。あの子には大きな迷惑をかけてしまいましたから。これでは十分ではないと思いますけれど、補償として・・・」
ダニエルの目が細くなった。
彼はアイリスが何を指しているのかを察する。
それは彼と彼女がウィリアムを叱責していた時、アイリスがウィリアムをかなり痛い目に遭わせたということだった。
どれほどの力で叩いたのか、瞬間的にダニエルの記憶の中でその場面が再生され、ウィリアムが元の姿に戻ったかのような錯覚を抱いた。
ダニエルは微笑みながら言った。
「それは私がすでに補償したから、君が気にする必要はない。」
「でも、それは男爵様が補償したんですよね。加害者は私なんだから、ちゃんと私が謝罪すべきだと思います。」
アイリスはまだきちんとした謝罪をしていないことが気にかかっていた。
もちろん、その場ではすぐに謝り、医者を呼んで必要な手当てを受けさせた。
そしてその後も様子を尋ねたが、それでもなお、彼女の気持ちは落ち着かなかったのだ。
彼女は少し戸惑いながら再び話し始めた。
「あまり大したことではないですが、ウィリアムの助けになればいいと思います。」
ダニエルは目を細めてアイリスを見つめる。
アイリスがこれほどまでにウィリアムに対して罪悪感を持っているとは思わなかったのだ。
いや、そうではないのか。
手に持った眼鏡で机を軽く叩いたダニエルは、低い声で尋ねた。
「ウィリアムに興味があるのか?」
アイリスの目が大きく開かれた。
彼女はダニエルがそんな質問をするとは思ってもいなかった。
怒りが湧き上がる寸前だったが、アイリスはこの数ヶ月間、母から学んだ忍耐でその怒りを抑えた。
「いいえ。あの子に申し訳ない気持ちがあるだけです。それに・・・。」
「それに?」
「なんとなくリアンを思い出すんです。」
ダニエルの目が大きく見開かれた。
アイリスは彼が驚いている理由を別のことだと考え、顔を赤らめながら釈明する。
「分かっています。ウィリアムを見てリアンを思い出すなんて、おかしいですよね。でも彼はリアンと年齢も同じくらいで、背丈も似ているんです。そして・・・。」
なんとなく似ていると感じた。ただ、その理由は分からない。
言葉に詰まるアイリスを見つめながら、ダニエルは薄く微笑んだ。
特に驚くようなことではないと思ったのだろう。
彼はそう思いながら、ぽつりとつぶやいた。
「リアンを愛しているんだな。」
アイリスの顔がその瞬間、真っ赤になった。
彼女は自分でも驚くほど怒りが込み上げたが、ぐっとこらえて口を閉じる。
図星を刺されたように感じたのだ。
怒ってはいけない。
アイリスは深く息を吸い、落ち着いた口調で言った。
「男爵様がお母様を愛しているようにですね。」
ダニエルの目が見開かれた。
彼はアイリスがそれを皮肉と受け取ったと考えていることに気付き、思わず笑みがこぼれた。
口元を抑えながら、少し笑いを漏らし、紅潮したまま立っているアイリスを見つめた。
「分かった。私が伝えておく。」
「ありがとうございます。」
余計な言葉を添えずにアイリスはすぐに部屋を出て行く。
ウィルフォード卿の態度は母がいる時といない時では大きく違っていた。
しかし、最近は少しずつ母がいた頃の様子に近づいている気がした。
「愛か・・・。」
ダニエルはアイリスが去った後、机に向かいながらそう呟いた。
彼女が置いていった小銭入れを手に取る。
明らかに、アイリスが数週間かけて貯めたお金が入っていた。
実は、ダニエルはアイリスがウィリアムに謝罪のしるしとしてお金を渡したことよりも、ウィリアムの姿にリアンを思い出しているという事実に驚いていた。
「妖精ほど愛を求める存在もいない。」
ダニエルは小銭入れの中身を覗きながら呟いた。
妖精は愛を求める。
真実の愛に出会えるという祝福。真実の愛でなければ離れるという呪い。真実の愛を持つ者だけが本来の姿を見られるという条件。
それら多くの愛にまつわる祝福と呪いは、皮肉にも愛の存在を確かめたいがために生まれたものである。
ダニエルは王族や貴族に施されたこのような祝福がその証拠であると考えていた。
王になる者は必ず愛する人と結婚するという祝福。
ケイシー家の男性には、一世代に一人ずつ、彼と婚約する女性が真実の愛を見つけるという呪いがかけられている。
愛は果たしてあなたをどれだけ揺さぶることができるだろうか。そして、あなたはその愛のためにどこまでできるだろうか。
忘れたと思っていた幼少期の記憶が蘇り、ダニエルは眉をひそめた。
彼の母親は夫とまだ幼いダニエルを残して妖精界に戻ってしまった。
戻る前、彼女はダニエルの手を握り、嬉しそうに語った。
—やっと帰れる。
妖精は百の絶望を味わい、願いを叶えることができれば妖精界に戻れる。
しかし逆に・・・願いを百回叶えるまで、この世界に留まらなければならない。
愛し合って結婚し、爵位まで与えた男性だったが、妖精界に戻ることと愛は別問題だった
当時は理解できなかったが、今ではダニエルも理解できる。
「お父さんを愛していなかったの?」と幼い息子が尋ねたとき、彼の母親は穏やかで優しい声で答えた。
—愛していたわ。そして今も愛している。ただ、全てがそうであるように、それが私の本質を諦める理由にはならなかった。