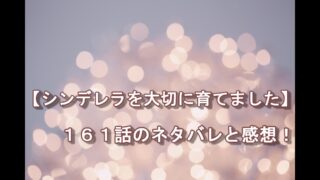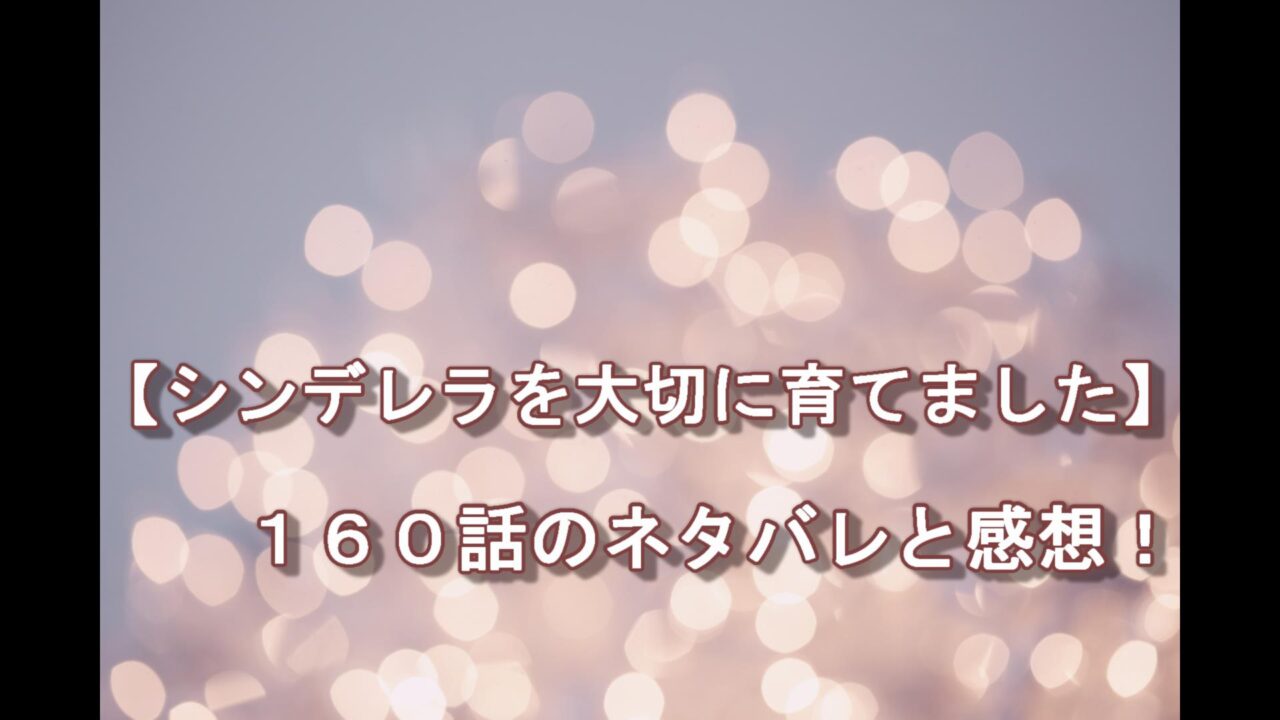こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は160話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

160話 ネタバレ
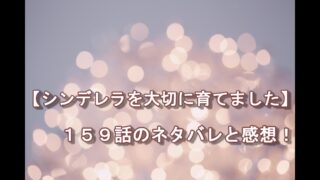
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ムーア伯爵夫人のお茶会
「いらっしゃいませ。」
ムーア伯爵夫人は親切にミルドレッドとアイリスを出迎えた。
アイリスが想像していたようなぎこちなさもなく、彼女とミルドレッドを見た瞬間、冷ややかな表情を浮かべることもなかった。
彼女はただ親切に二人を応接室に案内しただけだった。
そして客人たちを紹介する。
ここでミルドレッドとアイリスが驚く出来事が起きた。
「こちらはダグラス・ケイシー卿です。」
ムーア伯爵夫人がダグラスを紹介すると、ミルドレッドとアイリスは驚きの表情を隠せなかった。
ここで彼に再会するとは思っていなかったのだ。
ミルドレッドは、彼がリリーを探しに来たことを知っていた。
当然、リリーが教えてくれたわけではなく、ジムが話してくれたのだ。
ジムが言うには、リリーが描いた絵の衣装をそのまま着てイゼルに会いに行き、そこでダグラスに挨拶をしたという。
その後、彼が訪れなかったため、ミルドレッドはダグラスがリリーに対して冷めた気持ちを抱いているのではないかと考えた。
その考えが頭をよぎると同時に、不快感を覚える自分に気づく。
(まさかケイシー卿がムーア夫人に気があるの?)
「こんにちは、ムーア夫人。ムーア嬢。」
この場にミルドレッドとアイリスがいるとは思わなかったダグラスも、驚きを隠せなかった。
彼は席を立ち、近づいて挨拶をする。
その様子にムーア伯爵夫人は微笑みながら言った。
「皆さん、もう顔見知りなのですね。それは良かったです。」
そして、ミルドレッドとアイリスをダグラスの隣に座らせた。
微妙な空気が漂った。
ダグラスはどうしていいかわからない様子で、ミルドレッドの隣に腰を下ろした。
彼は自分が招待されるにふさわしいのか、このムーア伯爵家のティーパーティーでミルドレッドとアイリスがこの場にいることに驚いたダグラスは、少し戸惑いながらも言葉を発した。
「お久しぶりですね。」
ミルドレッドは、ダグラスが戸惑っている様子を特に気にせず挨拶を返した。
「本当にお久しぶりです。」
ダグラスがリリーを訪ねた後、ミルドレッドは子どもたちを連れてティーパーティーやギャラリー、音楽会などに出席していたが、ダグラスに会ったことは一度もなかった。
忙しかったせいか、それともリリーへの興味が薄れたからかと考えていたが、今思えば自然な理由だったのだろうと微笑んだ。
「ええ、お久しぶりです。お元気でしたか?」
ダグラスは、リリーがどうしているのかを知りたい気持ちを隠しつつ、礼儀正しく挨拶を続ける。
そして、もしかしたらミルドレッドからリリーの近況について何か聞けるのではないかと少し期待していた。
「ムーア伯爵家と親しいとは知りませんでした。」
思いがけず、ミルドレッドはダグラスがリリーの近況を知りたいと思っていることを察した。
しかし、彼女はあえてダグラスが求める答えを与えなかった。
彼女はダグラスが誰を気にかけているのか興味を抱いていたのだ。
プリシラ・ムーアが王妃候補ではあるものの、彼がリリーを好いていることを知っていたから。
そうであれば、気に留める理由もあるのだろう。
「ええ、母に代わって出席しました。」
「ムーア伯爵家とケイシー侯爵家が親しいとは知りませんでした。」
母親たちの親しい関係というよりも、むしろ父親たちの事業関係の親しさに近いものだ。
しかし、ダグラスは簡単に説明し、アイリスを一度見やった後、ミルドレッドに問いかける。
「ところで、ムーア伯爵夫人とは親しい間柄なのですか?」
「いいえ、昨日招待状を送っていただいたので、失礼だと思い出席しました。」
「昨日招待状を送ったですって?」
ダグラスの目が大きく開かれる。
その瞬間、隣にいたワッスン伯爵夫人が身を乗り出して話に割り込んだ。
「あら、突然の招待状を受け取られたのですね。お会いしたいと思っていたので、こうしてお目にかかれて嬉しいです。」
「こんにちは、ワッスン伯爵夫人。」
ミルドレッドは微笑みながら挨拶を返す。
それを契機に、ミルドレッドの周囲にいた人々が待っていたかのように彼女に話しかけ始めた。
皆、ミルドレッドと親しくなりたいという機会を窺っていたのだ。
彼女はいつか自分の家に招待してほしいという人々の話を笑顔で受け流し、適当に返答していた。
その様子を見て、ムーア家の召使たちがサービングカートを押しながら入ってきた。
ミルドレッドは召使いが客人たちにお茶を注ぐ様子を見守る中、プリシラが席を立ち、今日用意したデザートとお茶について説明するのを静かに見ていた。
「5種類のお茶を用意しました。王室でも納品されるところの品で、今日はこの場のために最高級ランクの茶葉を特別注文しました。」
灰色の髪に青い目を持つプリシラは、その後も今日味わうお茶がいかに優れたものであるかを説明した。
ミルドレッドは焦りを見せないよう、アイリスに肘を軽く突き、落ち着いて見せかけた。
「賢そうな子ね。」
「知識も豊富そうに見えます。」
その時、プリシラがミルドレッドとアイリスに視線を向ける。
灰色の髪に青い目を持つ彼女は、静かな声で話し始めた。
彼女は微笑みながら侍女を見つめた。
今日のムーア伯爵夫人のティーパーティーは1ヶ月前から予定されていた。
そのため、事前に準備された茶葉があったが、一週間前に開催されたティーパーティーの準備のために、プリシラは高価な茶葉を購入した。
そもそも貴族のティーパーティーとは親交や自慢の場である。
王室にも納品される高価な茶葉を自宅のティーパーティーで振る舞うムーア伯爵夫人の提案により、プリシラは奮発して茶葉を購入した。
そして、一部の人々にアイリスを招待するよう提案した。
最近の試験でアイリスが最も高得点を取ったという話を聞いたからだ。
それは、彼女のティーパーティーよりも、アイリスのティーパーティーで使用されている材料や格式が興味深かったためだろう。
プリシラがアイリスを招待したのは、自分の水準がこの程度であることを誇示するためだった。
最初の試験は形式的に点数を確認するものである。
それが良かったかもしれないが、二度目からはそう簡単にはいかないだろう。
彼女は侍女が差し出したお茶を一口飲みながら、つまみをいじっているミルドレッドとアイリスを見て満足そうな笑みを浮かべた。
「お味はいかがですか?」
ムーア伯爵夫人の質問にミルドレッドは自分のお茶を見つめた。
プリシラの意図とは裏腹に、ミルドレッドは馴染みのあるお茶の味と異なる意味で驚いていた。
「美味しいです。」
ミルドレッドは、自分が飲んだお茶が王室に納品される高級茶である事実に、ダニエルと話し合おうと考えながら答えた。
邸宅では、ダニエルが来てから家で飲むすべてのお茶が最高級品に置き換わった。
値段はミルドレッドが元々飲んでいたものの数倍高価だが、その流通はすべてダニエルの手に握られている。
その金額がほぼ元価に近いことから、ミルドレッドはそれが高級品だと知っていたが、これほどまでに高級だとは思っていなかった。
「バーンズ夫人、デザートについて詳しいと伺いました。このお茶にはどんなデザートが合うと思いますか?」
その時、少し離れたところにいた貴族の夫人がミルドレッドに尋ねる。
ミルドレッドは彼女を一瞥し、自分の飲んでいるお茶を再び見た。
正直に言うと、彼女は何でも適当に合いそうだと考えていた。
パウンドケーキ?ティラミス?
いずれでも適当に合わせられそうだと思っていたが、プリシラの顔が険しくなっているのを見て、自分が気を抜いていたことに気づいた。
プリシラの目が輝いており、ミルドレッドが何と答えるのかを待ち構えているようだ。
彼女は一瞬間を置き、迅速に答えた。
「ムーア伯爵夫人が最もお似合いだと思うものを選ばれたに違いありません。そうでしょう?」
応接室に漂っていた微妙な緊張感が一瞬で和らいだ。
部屋の雰囲気は穏やかで和やかなものに変わる。
「まあ、そうなんですね。伯爵夫人、どんなデザートを準備されたのですか?」
「楽しみです。」
待機していた使用人たちがゲストたちの前に小さな皿に乗せたパウンドケーキを一つずつ並べ始めた。
これが正解だ。
ミルドレッドはお茶を一口飲みながら、自分の返答が適切だったことを再確認してほっとする。
隣でアイリスも落ち着いた表情を見せていたが、内心では安堵の息を吐いていた。
(危ないところだった。)
ダグラスは雰囲気が一転したのを感じ、一息ついた。
そしてようやく、さっきの伯爵夫人への質問が一種のテストだったことに気づいた。
もしその質問が自分に向けられていたら?
背中が冷たくなるのを感じた。
ダグラスだったら平静を装えなかったかもしれない。
「最近シュガーが流行っているんですね?はは。」と答えた後、場の雰囲気がなぜかぎこちなくなり、居心地が悪そうな感じが漂っていたことだろう。
「パウンドケーキの香りがとても良いですね。」
「茶葉を入れたんですよ。」
再び和やかな雰囲気に戻った中で、伯爵夫人とプリシラは、茶葉を練り込んだパウンドケーキについて人々と会話を交わし始めました。