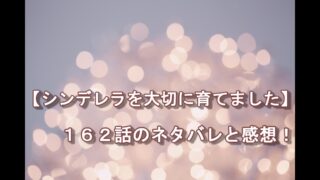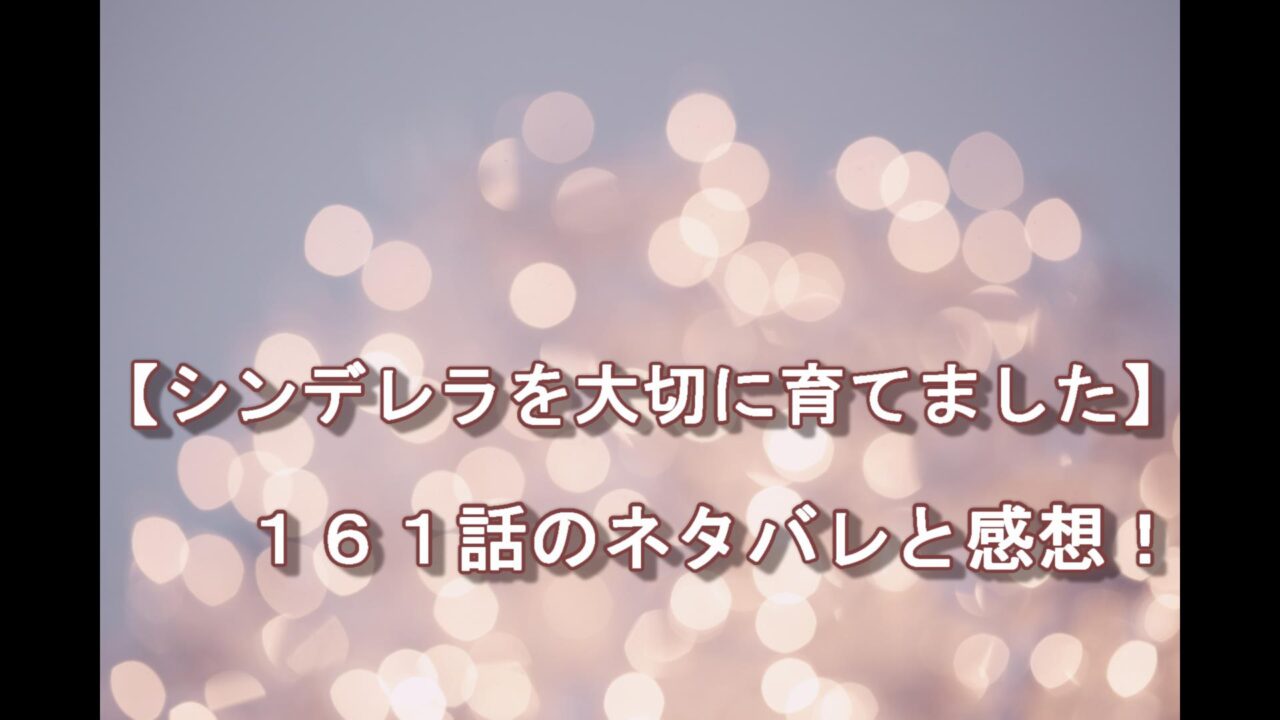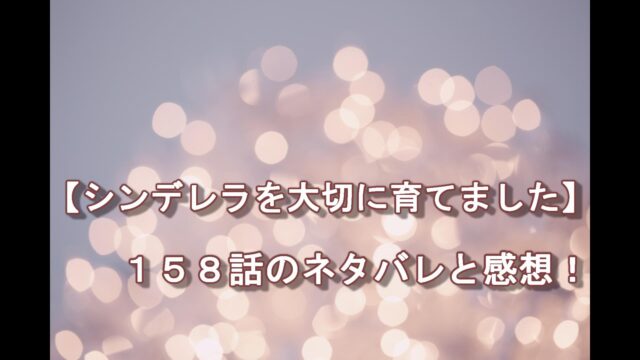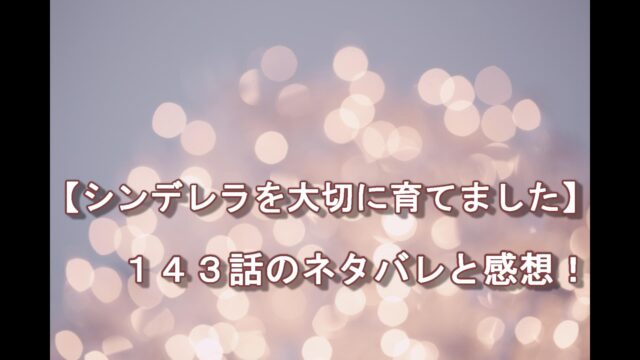こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は161話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

161話 ネタバレ
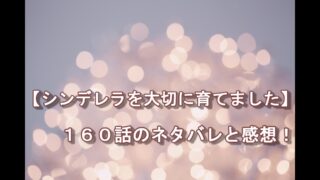
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ムーア伯爵夫人のお茶会②
ダグラスはパウンドケーキを一口味わい、ミルドレッドに目を向ける。
彼女は静かにケーキを食べていた。
彼は慎重に低い声で尋ねる。
「他の方々は一緒にいらっしゃらなかったのですか?」
ミルドレッドはダグラスを見つめ、彼が緊張していることを確認する。
ダグラスが本当に聞きたいのはリリーについてだろう。
しかし、彼女は侯爵家の後継者として生まれ、今まで育てられてきた自分に向けた質問だと理解した。
彼は直接的に尋ねることに戸惑った。
「ええ。ウィルフォード男爵は予定があって、私とアイリスだけが来ました。」
ミルドレッドの答えにダグラスの口が半開きになった。
まさか、他の誰かとダニエルが同行しているとは思わなかったのだ。
彼は一瞬言葉を失った後、再び口を開いた。
「そ、それでは、アイリス嬢の妹たちはどうでしょうか?その方々も予定があるのですか?」
「ええ、リリーとアシュリーは男爵と一緒に行く予定でした。私とアイリスも一緒に行こうと思っていましたが、ありがたいことに伯爵夫人がアイリスを招待してくださったので、こちらに来ました。」
そうだったのか。
リリーがどこか体調を崩しているわけではないと聞いて、ダグラスの表情は明るくなる。
しかし一方で、彼女が自分と無関係に社交界を楽しんでいることを思うと、ダグラスはどこか寂しさを感じた。
「ところで、ケイシー卿はこのティーパーティーに興味があるようですね。」
ダグラスが感じた寂しさを表に出す間もなく、ミルドレッドが言葉を発した。
ティーパーティーにダグラスが参加するとは思わなかったと聞いて、彼の表情が少し柔らいだ。
ミルドレッドの反応も驚きだった。
彼は今年、いや少なくとも先月までティーパーティーに関心を示したことがない。
ティーパーティーは普通、女性の集まりであり、参加する男性はほとんどが招待された芸術家や挨拶を目的とする外交官だった。
時々、恋人をエスコートするための男性が参加する場合もあったが、ダグラスはいずれにも該当しないため、ミルドレッドが彼の参加を珍しいと感じるのも無理はなかった。
「それは・・・」
ダグラスはどう答えるべきか分からず、言葉を探した。
この月に入ってから彼は招待されたすべての集まりに参加していた。
その理由はただ一つ、リリーのためだ。
もちろん、リリーに会うためではない。
リリーが参加しない場所ばかり選んで参加していたからだ。
ダグラスはリリーが自分と結婚は釣り合わないと言ったことを理解していたが、それでも彼女を諦めたくなかった。
「きゅうりのサンドイッチです。」
その時、使用人たちがまた客の前にサンドイッチが乗った皿を置き始めた。
薄切りのパンにバターを塗り、その上に薄くスライスしたきゅうりを重ねたものだ。
ミルドレッドは最近、きゅうりのサンドイッチが社交界のティータイムで人気があると知っていた。
しかし、野菜をあまり食べない彼女にとって、きゅうりがこれほど人気の理由はよく分かっていない。
どう見ても、それもまたミルドレッドが原因だった。
彼女はいつも新鮮な野菜を用意して食べていた。
サラダだけでなく、サンドイッチやステーキ、パスタを食べる時も野菜を添えていた。
彼女は食事で、子どもたちにも同じように食べさせた。
彼女の食習慣を支えるため、家政婦は台所から常に新鮮な野菜を購入し、それが商人たちに影響を与えた。
ある地位の高い貴婦人が野菜を大量に消費しているという噂が広まり、それが東郡地方の屋敷であることを知った料理人たちは野菜に興味を示し始めたのだ。
彼らは特に、ミルドレッドとアイリスがあまり好きではないために、売れ残っていたきゅうりに注目し、その結果がきゅうりサンドイッチの流行に繋がった。
もちろん、それ以前にもきゅうりは流通している。
しかし、ほとんどがピクルスに加工され、生のきゅうりは人気がなかった。
流通も難しく、栽培も大きな利益を生まなかったためだ。
そして皮肉なことに、そういった点が貴族たちにとっては自分たちの裕福さや余裕を誇示する手段となり、きゅうりが人気を得る要因となった。
「バターの代わりにクリームチーズを塗ったんです。一度召し上がってみてください。新しく雇った料理人がこれをとても上手に作るんですよ。」
ムーア伯爵夫人の言葉に促され、ゲストたちはそれぞれサンドイッチを一口取り、口に運んだ。
ダグラスもなぜこれを食べているのかわからないと思いながら口に入れる。
しかし、きゅうりサンドイッチは特別にお腹を満たすものでもなく、際立った味わいがあるわけでもない、ただきゅうりを挟んだパンにすぎなかった。
それでもアイリスはきゅうりサンドイッチを丁寧に切り分けていた。
彼女はゲストがその味をどう感じるかを確認する必要があったので、ナイフで一切れをきれいに切り取り、口に運ぶ。
その時、プリシラが不思議そうに尋ねた。
「まあ、バーンス夫人。このきゅうりサンドイッチ、少し味が変じゃありません?」
(ええ、少しそうですね。)
しかしそう言うわけにもいかず、アイリスは困った表情を浮かべながら答えました。
「いいえ、美味しかったです。ただ、私はきゅうりがあまり好きではないんです。別に悪いわけではないんですけど、それでもこう感じますね。」
「そうですか?不思議ですね。きゅうりってそれほど強い風味もないと思うのですが。」
プリシラの質問に対して、ミルドレッドにお茶と合うデザートについて尋ねた夫人が会話に加わり、こう答えた。
「そうですね。きゅうりは味が主張しないので、お茶と一緒にいただくのにとても良い食材なんですよ。ただ、バーンス夫人には合わなかったようですね。」
場の雰囲気が一瞬、不思議な方向に流れた。
ミルドレッドはプリシラの発言に続いた若い夫人がラストン夫人であること、さらに彼女がラストン伯爵の孫嫁であることを思い出た。
ラストン夫人と彼女の隣に座っている他の人々が、互いに耳打ちしながらクスクスと笑い始める。
きゅうりのサンドイッチは社交界では高貴な食べ物として扱われていましたが、その一方でその場の話題を占めつつある。
アイリスが高級なスイーツに合わない、田舎っぽい味覚を持っていると囁く声が聞こえてきた。
雰囲気が悪くなる中、ダグラスが言った。
「きゅうりにも香りがありますよ。」
特有の香りがする。
それをどう説明するべきかわからないが、プリシラはダグラスの発言を軽く受け流した。
「確かにそうですね。でも、気になるほどではないんじゃないですか?」
プリシラの発言に、ティーパーティーに招待された客たちは控えめに笑う。
彼らもアイリスを直接攻撃したいわけではなかったが、確かにきゅうりは突出した食材ではない。
「プリシラ、誰にでも合わない食べ物があるものだよ。君にだって食べられないものがあるだろう?」
逆にプリシラをたしなめたのはムーア伯爵夫人だった。
彼女は自分の娘が野心的すぎることを心配していた。
彼女が競争心が強いことを知っている。
だからこそ、今日アイリスを招待しようとしたのだということも理解していた。
それでもアイリスを招待したのは、彼女がティーパーティーで用意した装飾とケーキについて知りたかったからだ。
彼女は、娘のせいでアイリスの気分を害し、装飾やケーキについて話してもらえないのではないかと心配していた。
その時、ミルドレッドが口を開いた。
「申し訳ありません。娘が雰囲気を壊してしまったようですね。きゅうりってちょっと独特な味わいがありますよね?繊細な味覚を持つ方には理解いただけると思います。」
その瞬間、応接室に漂っていたざわざわした空気が一瞬止まる。
皆がミルドレッドが何を言い出すのか注目していた。
ムーア伯爵夫人もまた不思議そうに尋ねた。
「きゅうりが苦いと?」
「少しだけ。このサンドイッチにはクリームチーズが塗られていて隠されていますが、よく噛んでみると最後に苦味が感じられませんか?やっぱり、これはどうしようもないですね。」
「苦いですって?」
ラソン夫人は、自分でも気づかないうちに手に持っていたきゅうりサンドイッチを口に運び、ゆっくりと噛み始めた。
しかし、彼女にはその苦味は感じられなかった。
「バーンス夫人が嘘をついているのでは?」とラソン夫人が考えた瞬間、ワッソン子爵夫人が手を打って口を開く。
「そうですね。確かに最後の味が苦くて不思議だと思いました。やはりきゅうりは少し苦いところがありますね?」
ミルドレッドの顔に微笑みが浮かぶ。
彼女は相手の顧客を励ますように言った。
「ワッソン子爵夫人はやはり味覚が鋭いですね。他の皆さんも理解していただけますよね?皆さんの味覚も非常に優れていますから。」
そんなはずはない。
しかしここで「違う」と言えば、自分の味覚が鈍感だと言っているようなものになりかねない。
そんなことを言える人などいるはずがなかった。
ダグラスは黙ったままミルドレッドをじっと見つめた後、テーブルに置かれたきゅうりサンドイッチを一口食べた。
しかし、彼にとってそれはただの淡泊なきゅうりの味であり、特に苦みを感じることはなかった。
「実は私も、きゅうりが少し苦いと感じました。」
端に座っていた一人がそう言い、ミルドレッドに同意の意を示すような表情を浮かべた。
すると場の雰囲気が一転する。
人々は自分を品位ある存在に見せたい、また味覚が鋭いと思われたいと考えていた。
特に、富と高貴さを誇りたい社交界の人々にとって、それは顕著だった。
ムーア伯爵夫人のティーパーティーに招かれた人々は、みな自分の味覚が鋭いと思われたい、またはそのように見せたいと願っていた。
ミルドレッドとアイリスは、慌ててきゅうりサンドイッチを置く人々を見て心の中で微笑んだ。
それはダグラスも同様だった。