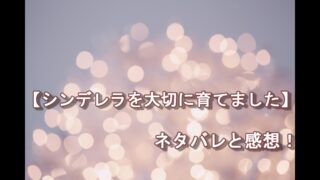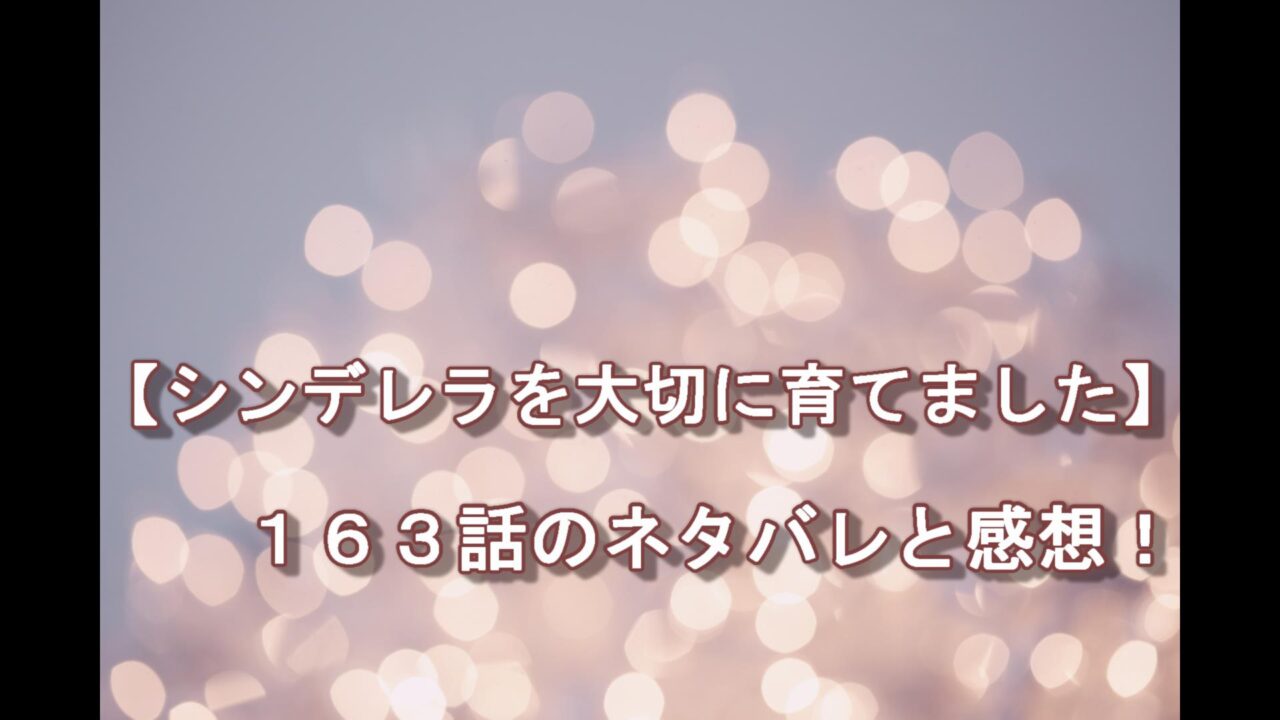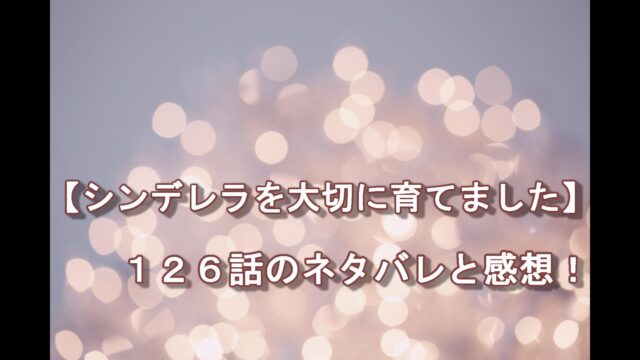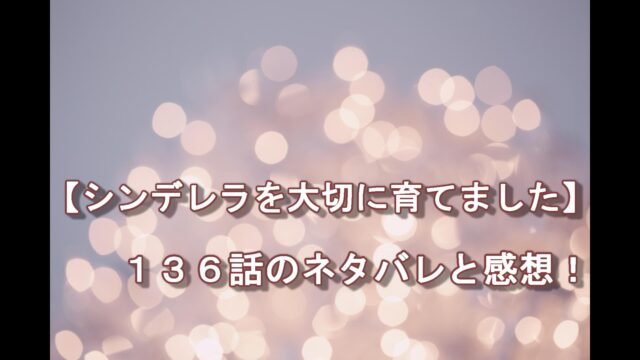こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は163話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

163話 ネタバレ
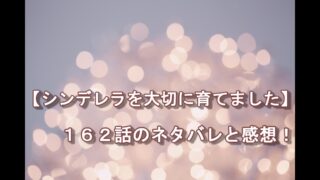
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 葬儀
フレッドの葬儀は静かで質素だった。
豪華にしようと思えばできただろうが、アシュリーはこれで十分だと言った。
実際、参列者がいないため豪華にすればむしろもっと悲しくなっただろう。
フレッドのためではなく、アシュリーのために。
私は閉ざされた棺の前でぼんやりと立っているアシュリーに近づき、彼女の肩を優しく抱いた。
今日に限ってアシュリーの肩がさらに小さく感じられる。
「蓋を開けたら後悔するかな?」
小さな声でアシュリーが尋ねた。
「たぶんね」
実際、私にも分からなかった。
私はため息をついて言った。
「分からないよ。でも、君には見てほしくない。ただ、最後に見た姿のまま、君のお父さんを覚えておいた方がいいんじゃないかな?」
フレッドの遺体は、遺体と呼ぶのもどうかと思ったが、とにかく遺体は骨だけが残っていたと聞いている。
彼はすでに行方不明になっていた2年前に死んでいたのだ。
おそらく強盗に遭ったのだろうと、ロニーが持ち帰った死亡診断書には書かれていた。
財布のお金はもちろん、金の歯や靴まで剥ぎ取られたという。
しかし服は残っていたが、それを持ち去らなかった理由は、ナイフで刺されたために服に穴が開き、血が染み込んでいたからだろうと。
そして、数日が過ぎてから通りすがりの人の通報で、街の治安官がフレッドの遺体を発見したのだった。
運良く、治安官たちはフレッドの服装が高級だと気づき、彼の行方を探している人がいるかもしれないと考え、医師に死亡確認書を発行してもらっていたようだ。
本当に運が良かった。
私はアシュリーを抱きしめたまま、深く息をついた。
もし少しでも手違いがあれば、フレッドの遺体を見つけることはできなかっただろう。
治安官たちが死んだフレッドを行き倒れの兵士と誤解して、共同墓地のような場所に埋めてしまっていたかもしれない。
「見なきゃいけない気もするけど、見たくないし、見なくてもいい気がするけど、見たいとも思うんです。」
ため息をつきながらアシュリーが言った。
何となく彼女の気持ちが分かったので、私は彼女のために言った。
「見ても、君のお父さんの姿は何一つ残っていないよ。もう時間が経ちすぎて骨しか残ってないんだ。それでも見たければ、見てもいいよ。」
あまりにも生々しくて残酷だから見ないようにと言っているわけではない。
アシュリーが見ないことを望むのは、彼女の中にあるフレッドの記憶が、今棺の中にある骸骨で塗り替えられるのではないかと思うからだ。
後でアシュリーが父を思い出す時、彼女を置いて去って行ったハンサムなフレッドを思い出せたらいい。
棺の中に横たわる骸骨ではなく。
「もう少し考えてみます。」
私の言葉に、アシュリーは小さくうなずきながらそう言った。
考えてみるのも悪くない。
まだ数時間は残っているのだから。
葬儀が終わったら棺に釘を打ち、墓地に持って行って埋葬するつもりだ。
「どれだけ悩んでも大丈夫だよ。」
そう言って私はアシュリーを抱きしめたまま、彼女と一緒に静かに立っていた。
私がここにいるのだから、悩んでいい。
アシュリーの悩みだから。
明日になっても墓地に運ぶのが遅れるなら、明日にすればいい。
そう考えながら立っていると、アイリスがそっと近づいてきて囁いた。
「お母様、ケイシーからいらっしゃいました。」
「ありがとう。」
アシュリーがフレッドの棺の前に立っている間、アイリスとリリーが参列者を迎えることにしておた。
本来、息子や男兄弟がする仕事だが、フレッドには男兄弟も息子もいないので仕方ない。
だからといって、ゲリやダニエルに頼むわけにもいかないだろう。
私はアイリスにアシュリーを任せ、体を向け直した。
開いた玄関の前には、ダグラスが中年の夫人と一緒に立っているのが見えた。
「ようこそいらっしゃいました、ケイシー侯爵夫人。ケイシー卿。」
ひと目見ただけで、ダグラスと一緒に来た夫人がケイシー侯爵夫人だと分かるほど、ダグラスは母親にそっくりだった。
赤い髪に緑色の瞳。
ケイシー侯爵夫人も背が高かった。
フィリップ・ケイシー卿も背が高かったことを考えれば、ケイシー侯爵も背が高いだろう。
やはりダグラスは背の高い血筋を受け継いだようだ。
「こんにちは、バンス夫人。私の母、ジェネビブ・ケイシー侯爵夫人です。お母様、こちらはミルドレッド・バーンス夫人です。」
ダグラスの紹介に、ケイシー侯爵夫人は微笑みながら言った。
「紹介されなくても、私の息子は私によく似ていますでしょう?」
「誰に似てこんなにハンサムなのかと思いましたが、侯爵夫人に似ていたんですね。」
軽い冗談にケイシー侯爵夫人の顔が明るくなる。
ダグラスは何となく恥ずかしそうにしていた。
表情を崩して、私は侯爵夫人ともう一度笑う。
「急に訪ねてきて申し訳ありません。昨日、ケイシー卿が来られたと聞いたものですから。今日はダグラスが行くと言うので、私も一緒に来ようと思いまして。」
「よくいらっしゃいました。」
私は軽くうなずいて、ケイシー侯爵夫人を応接室に案内した。
フレッドは友人よりも知人が多かったため、彼の葬儀に参列する人はほとんどいなかった。
むしろ私とダニエルの知人の方が多く来たくらいだ。
フィリップも私とダニエルの知人として昨日来て帰ったが、今晩、墓地に埋葬する時にはまた来ると言っていた。
私はジェネビーブを応接室に案内しながら、ダグラスをちらっと見た。
彼は少し立ち止まり、リリーに向かって歩いていった。
「ダグラスがこの家を褒めているのが、もう止まらないみたいです。」
「そうなんですか?」
ルーインが入ってきて侯爵夫人の前にお茶を置き、戻っていく。
私はお茶を飲もうと手を伸ばし、自分の茶碗を持ち上げた。
「とても面白くて素敵な方々だと、昨日お褒めになっていましたよ。夫人の長女が王太子妃候補の試験中だとか? その最初の試験を最優秀で通過されたと聞きました。」
ケイシー侯爵夫人の言葉に、私は黙って微笑んだ。
驚くことではない。
目の前の女性は他でもない侯爵夫人だ。
当然、アイリスが王太子妃候補であり、最初の試験を通過したことも真っ先に知っていたのだろう。
つまり今こうして話をするのは、今さら知ったからではなく、アイリスが王太子妃になる可能性が高いと考え、関係を築こうとしているからだ。
そのように考える可能性は高い。
あるいは、弟や息子たちが我が家のことを話したので気になって訪れたのかもしれない。
だが、私はそれよりもリリーが気になって来たのだろうと考えた。
自分の息子が結婚を申し込んだが断られ、それでも再び結婚を申し込もうとしているので、一体どんな女性なのか知りたいのだろう。
「私も夫人のご子息がどれほど優秀なのか伺いましたよ。王子様の剣術指南だとか。」
私の言葉に侯爵夫人の顔が一瞬誇らしげな表情に変わったが、すぐに心配そうな顔で言った。
「結婚さえすれば心配がないのに、本当に。」
「ダグラス・ケイシー卿は一人息子ですよね?」
「その通りです。こんなことなら、苦労してでももう一人産んでおけば良かった。夫人は子どもが三人もいらっしゃるから、羨ましいですね。」
「孤独にならなくて済むのでしょうね。」
その末っ子は、私が産んだ子ではなく幸運にも得た子だ。
私は自分がどれほど幸運だったかをジェネビーブに打ち明けることはなかった。
その時、ジェネビーブが声を落として尋ねる。
「もしかして、夫人の次女は特別に心を寄せている方がいらっしゃるのですか?」
そう来ると思っていた。
私はついにリリーに関する質問が出たことに気付き、冷静さを保ちながら答えた。
「いいえ、特に心を寄せている方はいないはずですよ。」
「社交界にはいつデビューされたのですか?」
「18歳です。上は19歳、下は17歳です。社交界には今年3人が一緒にデビューしました。」
「それなら、まだ余裕がありますね。」
そう話すジェネビーブの顔には余裕が浮かんでいた。
自分の息子が優れていると自信があるのだろうか。
私は茶碗を持ち上げ、微笑みを堪えた。
ダグラス・ケイシーの母親なら、その反応も理解できる。
ケイシー侯爵家には王子の剣術指南役を務める、背が高く端正な顔立ちを持つ男性が息子としているのだから。
色々と計算は済んでいるのだろう。
今年、3人の娘を一度にデビューさせたことや、フレッドが亡くなったことも既に把握しているに違いない。
つまり、この会話はリリーの状況を再確認するためであり、同時にダグラスがリリーに夢中になっているが、ケイシー家としては何も惜しいところがないと見せているのだ。