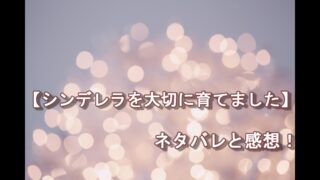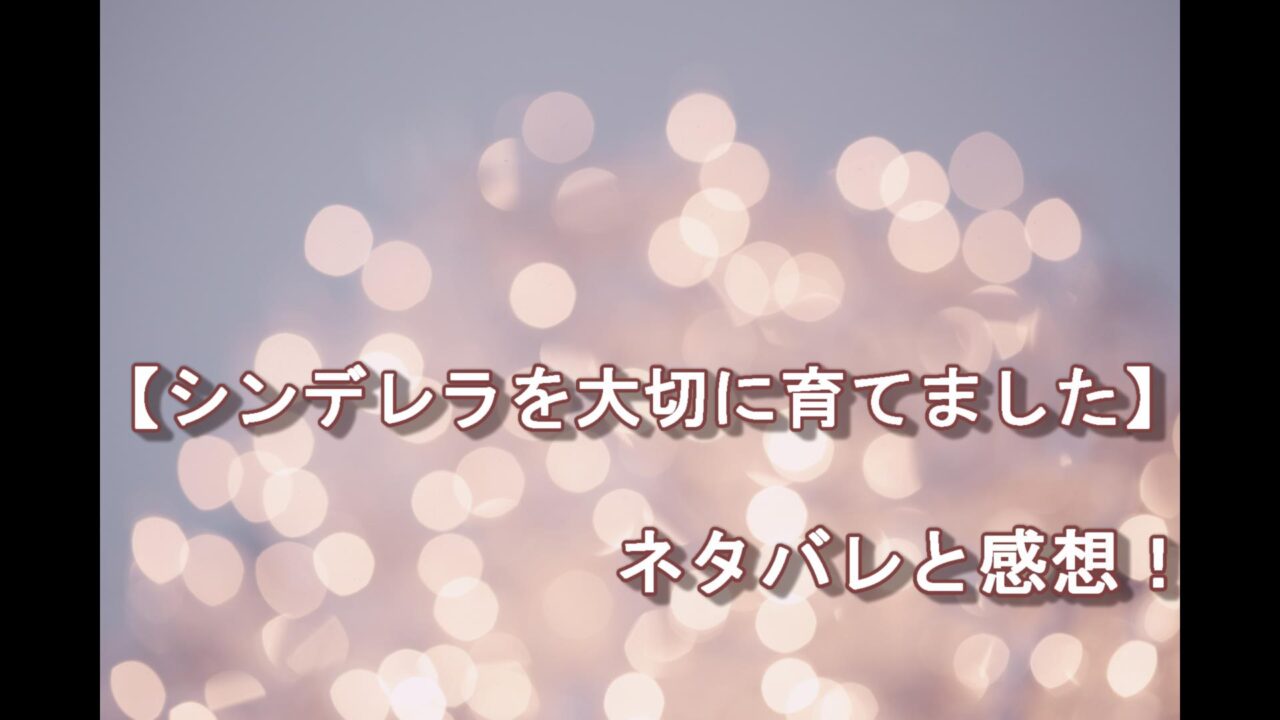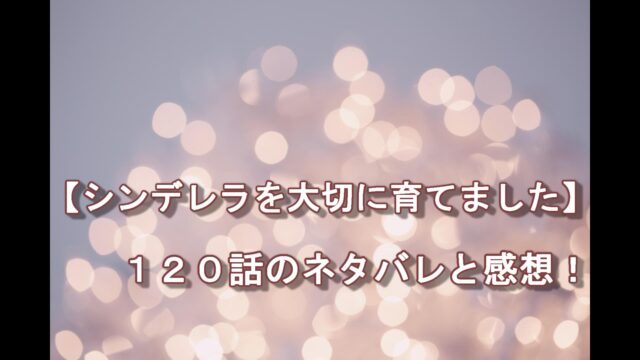こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は164話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

164話 ネタバレ
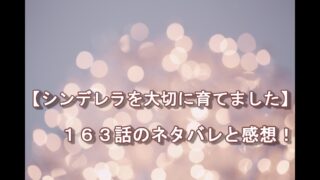
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 結婚観
私は茶碗を置いて言った。
「実は、リリーは結婚するつもりがないと言っています。私もあの子の意見を尊重していますから。」
「結婚する気がないんですか?」
ジェネビーブの顔には驚きの表情が浮かんだ。
まるで私が人を殺したとでも言ったかのように、これ以上ないほど驚いている。
私は何も知らないふりをして言った。
「幸いなことに、私は娘たちを育てる余裕もあるし、娘が3人もいるんですから、そのうち1人くらいは一生独身でもいいんじゃないかと思いますけどね。」
「一生独身でもいいんですか? 本気ですか?」
まるでリリーが人を殺しても構わないと言ったかのような反応だ。
私は当然という顔で答える。
「あの子の人生ですからね。リリーが幸せだと思う道を応援してあげるべきです。」
「なんてこと、バーンス夫人。女性は結婚しなければならないんですよ。」
「そうですか?」
私はお茶を持ち上げながら、本当にそう思うのかという表情を浮かべた。
「 絶対に結婚しなければならないのですか?」
ジェネビーブは一瞬私の表情に動揺したが、すぐに興奮し、情熱的に言った。
「当然です! 人は結婚しなければならないんです。結婚して爵位を受け継ぎ、家門の未来を担う子供を産むべきです。」
「それは男性に当てはまることでしょう。」
私は冷ややかに言い放った。
爵位は男性のものだ。
家門の未来?
それも男性たちが考えるべきことだ。
私はリベラ男爵夫人だったが、リベラ男爵家が今どうなっているのか、まったく分からない。
彼らは私に何も知らせないし、支援もしてくれない。
それなのに、家門の未来だなんて。
もしバーンス家に未来があるのなら、今日がバーンス家の葬式だとでも言ってやりたい。
ジェネビーブは私の答えに衝撃を受けたような表情をした。
冷たすぎたかしら?
それでも私は無理に微笑んでみせる。
フレッドの死が私とは何の関係もないと思っていたが、そうではなかったようだ。
考えてみれば、今日から私は正式に未亡人になったのだから、少し冷静になる必要がある。
ジェネビーブの言う通り、家門の主である男たちには妻が必要であり、息子がいない私は再婚相手としてちょうどいいのだろう。
「本当に、夫人の娘を一生寂しく老いて死ぬまで放っておくつもりではないでしょうね?」
少し慌てたのか、ケイシー侯爵夫人はかなり無遠慮な言葉を使って問い詰めてきた。
ふん、一生寂しく老いて死ぬだなんて。
私は笑顔を浮かべて尋ねた。
「結婚しないと一生寂しく老いて死ぬのですか?」
ジェネビーブの顔には、驚いた表情が浮かんだ。
私はお茶のカップを置き、言葉を続ケル。
「私が知っている方は、侍女を連れてあちこち旅をして、楽しく過ごしていましたよ。」
「でも、帰りを待つ子供もいないでしょうね。」
「ケイシー侯爵夫人。」
カチャッとティーカップがテーブルに触れる小さな音がした。
私は心配そうな顔をして言った。
「ケイシー卿のお顔を立てるため、今日の侯爵夫人との会話はなかったことにいたします。」
それを聞いてジェネビーブの顔が青ざめる。
彼女は今、リリーが結婚すべき理由を話そうとしたが、それはフィリップ・ケイシーへの攻撃にしかならない。
彼もまた結婚せず、子供もいないのだから。
「し、失礼をいたしました。」
唇を軽く震わせながら侯爵夫人が言った。
大丈夫だと、私は笑顔でこたえる。
まるで問題がなかったふりをしたが、リリーがダグラスを拒む道を選ぶだろうと確信していた。
心中で苦しんでいる様子だった。
ケイシー侯爵夫人が理解してくれたのか、私は何も言わなかった。
ダグラスは二度も離婚していて、気軽にリリーに付きまとうが、リリーには結婚するつもりはない。
仮にリリーがダグラスの求婚を受け入れたとしても、二人が結婚できるかどうかは分からない。
そう考えると、侯爵夫人が不憫に思えてきた。
家門を継ぐ義務がある侯爵の後継者が、果たして自分の娘と結婚するかも分からないのだ。
私にとっては関係のないことだが、ケイシー侯爵にとっては絶望的な状況だろう。
「お母様。バーンス夫人。」
幸いにも、重苦しい雰囲気を破るようにダグラスが現れた。
彼は開かれた応接室の扉から姿を見せ、私とジェネビーブの気まずい空気に気づくことなく言った。
「王子がいらっしゃいました。」
リアンが?
彼が来るとは思わなかった。
私が驚いて立ち上がるのと同時に、ケイシー侯爵夫人も驚いて立ち上がった。
彼女はダグラスに歩み寄り、小さな声で問い詰めた。
「あなたが王子様に話したの?」
「いいえ。ウィルフォード男爵様と一緒に来られたようです。」
その瞬間、侯爵夫人の視線が私に向けられた。
私は彼女の表情を見て、ケイシー侯爵夫人もアイリスとリアンの仲が近いことに気づいたのだと分かった。
もちろん、ダグラスが話したのだろう。
ただ、表立って騒がないのは、男女の関係がどうなるか分からない上に、アイリスが王太子妃になるかどうかは候補者選抜の試験中だからだ。
そんな噂話を持ち出すようでは、周囲の人々から軽はずみだと陰口を叩かれるだけだ。
そういうこともあるだろう。
「お母様。」
続いてアイリスがダグラスの後ろから声をかけた。
ダグラスが横にどくと、アイリスが王子の腕の内側に手を置いているのが見えた。
「王子様がお越しです。」
ジェネビーブの顔に再び驚きの表情が浮かんだが、すぐに消えた。
彼女は私を一度見てから王子に向かって優雅に頭を下げて言った。
「ようこそ、殿下。こちらでお目にかかるとは。」
「ケイシー侯爵夫人。」
リアンは侯爵夫人を見て一瞬驚いたが、すぐに侯爵夫人と同じように冷静さを取り戻して挨拶をした。
その間、私はアイリスの表情を窺った。
アイリスの顔は明るく、彼女もリアンが来るとは思っていなかったようだ。
考えてみれば、アイリスがリアンにフレッドの葬儀に来るよう頼むはずがない。
フレッドは貴族ではなく、アイリスの実の父親でもないのだから。
それにアシュリーがリアンに手紙を書くはずもない。
今、リアンがここに来た理由は、彼がアイリスのことを思って来たとしか言えないだろう。
「亡くなられた方とご親交があったのですか?」
ジェネビーブの問いに、リアンは微笑んだ。
そして、私とアイリスを見つめながら答えた。
「アイリス嬢は王太子妃候補ですからね。彼女の父親の葬儀なら、当然出席すべきです。」
言うことがうまいものだ。
私はリアンを見つめながら薄く笑った。
ここで彼がアイリスや我が家と親しいから来たと言えば、状況はおかしくなるだろう。
アイリスは王太子妃候補であり、試験中の候補者を王子が特別に優遇しているという印象を与えかねない。
「本当にお心が広いのですね。」
ケイシー侯爵夫人はリアンの返答に感銘を受けた様子だった。
私はリアンの後ろに立っているダニエルを見つけて、微笑んだ。
「お入りになってお話しください。」
私はリアンとジェネビーブを再び部屋の中へ案内した。
応接室のソファに皆が座ると、使用人が再びお茶を運んできた。
「ところで、侯爵夫人もバンス家とご親交があるとは存じませんでした。」
リアンはティーカップを持ち上げながら言った。
アイリスとリリーは客人を迎えるために再び廊下へ出ていった。
リアンの言葉にジェネビーブは顔を軽く赤らめながら答えた。
「ダグラスが大変お世話になったようですので、ご挨拶に伺いました。」
リアンの顔に、なるほどという表情が浮かんだ。
彼はなぜか落ち着かない様子のダグラスを一瞥すると、微笑んだ。
「これがその表情なのですね。」
その時、ダニエルが私に小声で囁いた。
何?と私が何のことか分からない顔をすると、彼はさらに小声で言った。
「ケイシー卿はまだリリーと手紙のやり取りもしていませんよね?」
不意打ちの質問だった。
私は驚いて、思わず小声で返した。
「アイリスとリアンは手紙をやり取りしているの?」
「一度だけです。ティーパーティーが終わった後、リアンが手紙を渡してほしいと頼んだので、私が届けました。」
「アイリスは返事をしたの?」
「その翌日です。」
なんてこと。
私は呆然として口を開いたまま固まった。
それはつまり、ダニエルがリアンの手紙を届けていたということだ。
ああ、どうして私の男が弟子の郵便配達係になってしまったのだろう。
「ごめんなさい。アイリスは感謝の気持ちを伝えたの?」
「それ以上のことをする約束をしましたよ。」
なんですって?私は何のことか気になる表情を見せたが、それよりも先にダニエルが続けた。
「それにリアンもですよ。」
手紙のやり取りは二人がしているのだから、二人とも恩義を感じているようだ。
私は心の中で、アイリスに対して、ダニエルをあまり困らせないようにと注意をしようと決め、軽く首を傾げた。