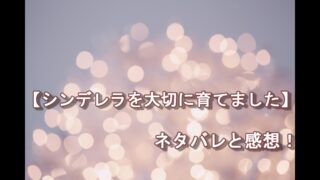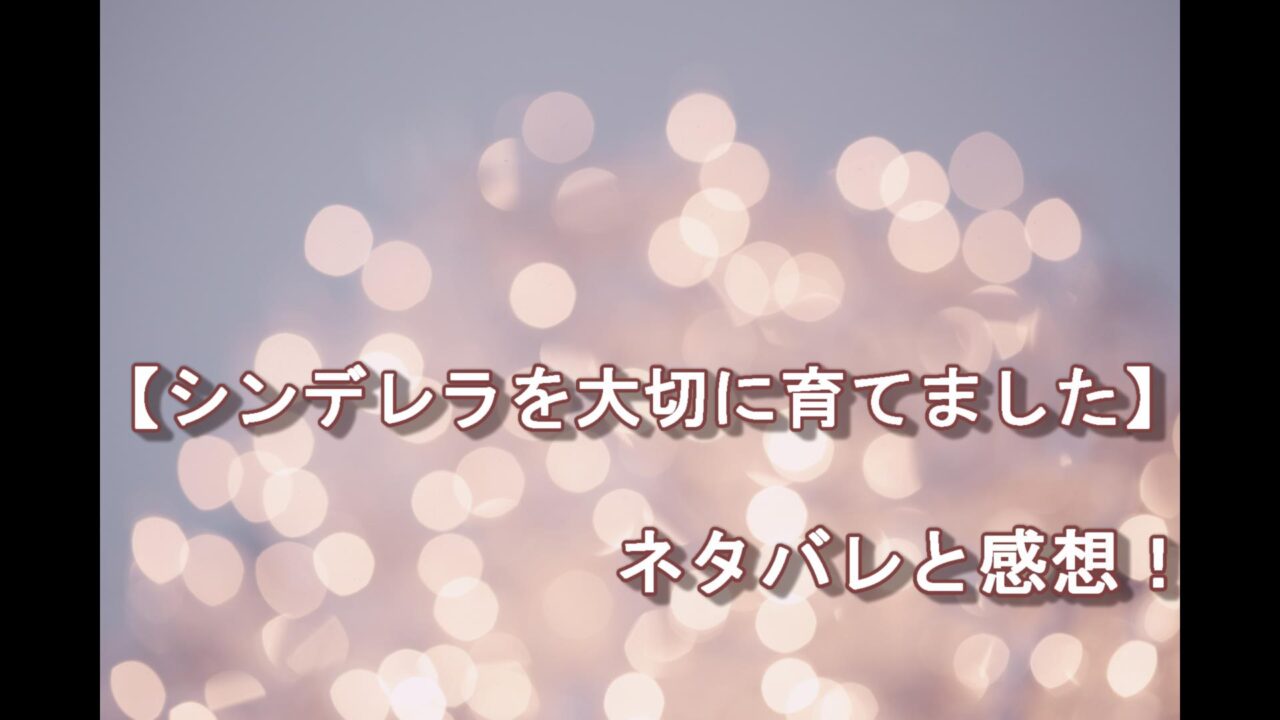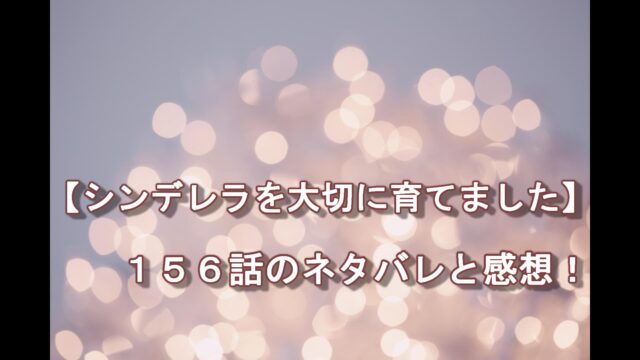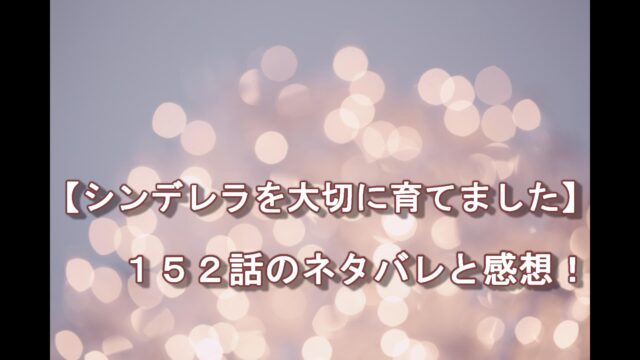こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は166話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

166話 ネタバレ
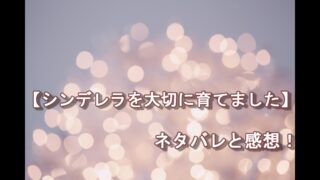
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 結婚観③
ひたすらリリーを見つめる時間が流れるにつれて、彼女が本当に招待したい人が誰なのかが分かってきた。
今日はリリーが大人気だ。
さらにフィリップもリリーに何かをささやいており、私は胸の前で腕を組みながら考えた。
こういう日もあるだろう。
いつも無道会や音楽会に行けば、アシュリーの周りに人が集まっていた。
最近では王妃候補の試験のせいでアイリスが注目を浴びていた。
リリーが微笑みながらフィリップに「ありがとう」と言うのが聞こえた。
何の話をしているのだろうかと気になったが、彼は私と子どもたちを振り返って挨拶した。
「次回またお会いしましょう。」
後でリリーに聞いてみなければ。私は軽くお辞儀をして、ダグラスの感謝の言葉を受け取った。
「食事に招待していただき、ありがとうございました。本当に美味しかったです。」
ダグラスは礼儀正しく挨拶を交わした後、すぐにリリーを見つめた。
そして何かを言おうとしたかのようにためらったが、黙ってリリーの左手を取った。
「バーンス嬢。」
ケイシー侯爵夫人やフィリップに対しては緊張しなかったリリーが、ダグラスの言葉と行動に少し緊張しているのが分かった。
彼は我が家族の視線を浴びながらも、ゆっくりとリリーに体を傾け、リリーの手の甲に軽く口づけしながら挨拶した。
「次にお会いする幸運をお待ちしております。」
可愛いな。
私は思わず笑みをこぼした。
アイリスとアシュリーもダグラスの礼儀正しい挨拶に目を向けたが、特に声を出すこともなく微笑んでいた。
幸い、アイリスとアシュリーはケイシー家の関心がリリーに集中していることをそれほど気にしていないようだ。
私たちはケイシー家の人々に別れを告げた後、ゆっくりと体を回して2階の階段へと歩き始めた。
「リリー、ケイシー卿があなたに何を話したの?」
私はアシュリーとアイリスが何かを話しながら笑っているのを見て、リリーに近づいて尋ねた。
ダニエルは少し周囲を見渡しながら付いてくる様子で、ジムは黙って着いてきた。
「ああ、他の画家に会ってみてはどうかっておっしゃったんです。」
「他の画家?」
「ケイシー卿が知っている画家が何人かいらっしゃるそうです。小さな集まりみたいなものがあるらしくて、会ってみたらどうかって勧められました。」
悪くない提案だ。
私たちは絵について知っている人がまったくいないのだから。
いや、まったく違う話だ。
ダニエルがいる。
しかし、ダニエルは画家というよりも商売人に近いので、リリーにとってそのような集まりが役に立つのか分からない。
私はリリーと腕を組んで真剣に尋ねた。
「ケイシー卿があなたと一緒に行くんでしょう?」
「ええ。会う前に母に確認してみるとも言っていました。」
それなら安心だ。
フィリップが何も言わずに、他人の家の大切な子を危険な場所に置いてくるような人ではない。
その時、アイリスが私とリリーを振り返り尋ねた。
「リリー、今日アシュリーの部屋で一緒に寝ない?」
「うん!行く!」
リリーは手を挙げて答えた。
そうだ、彼女はアシュリーとアイリスと一緒に過ごすのだろう。
私は腕をほどき、少し私も一緒に寝たいという言葉が喉まで出かかったが、今日は子供たちだけで寝るのが良いだろうと思いとどまった。
姉妹が仲良くするのは良いことだ。
アシュリーがアイリスやリリーと親しくなる機会を与えないといけない。
私は余裕のある態度で腰に手を当てながら言った。
「髪を洗ってきちんと乾かして寝なさいよ。」
「はい。」
返事はしっかりしている。
アシュリーとリリーは喜んでこの階を駆け上がっていった。
私は遅れを取ったアイリスが私を待っているのを見て、彼女に近づき尋ねた。
「どうしたの?」
「今日はアシュリーのお父さんをお墓に埋葬しましたよね。」
そうだな。
私はうなずいた。
私を見るアイリスの表情にはかすかな哀しみが浮かんでいた。
何だって?
私が「もっと話せ」という表情をしているのに、彼女は視線を避けて尋ねた。
「それじゃあ、ウィルフォード男爵様と結婚されるんですか?」
「うーん、どうかしら。」
分からない。
私の返事にアイリスは驚いた表情を浮かべた。
それがそんなに驚くことか?
私は彼女がなぜ驚くのか不思議に思い、やがて理由を悟った。
この程度の礼儀を守っていれば結婚を考えてもおかしくはない。
貴族社会では女性は必ず結婚するものとされている。
もちろん結婚しない者も稀にいたが、それは婚約者が結婚前に亡くなったりと、大きな理由がある場合だけだった。
「考えたこともないわ。結婚することも、しないこともあるでしょう。」
「でも、ウィルフォード男爵様はお母様と結婚したいと思うかもしれないじゃないですか。」
結婚することもできるし、しない選択だってある。
私がため息をつくと、アイリスは再び戸惑いながら尋ねた。
「それじゃあ、もしお二人が結婚なさったら、お母様は・・・つまり・・・」
つまり何だって?
私は彼女が何を言いたいのか分からず、困惑して答えた。
「私がダニエルと結婚したら、ミルドレッド・ウィルフォード男爵夫人になるわね。」
その瞬間、アイリスの顔が一気に赤くなった。
え?なんで顔が赤くなるの?
私は驚いて彼女を見つめた。
アイリスは恥ずかしそうに目を逸らしながら聞いた。
「それじゃあ、私はアイリス・ウィルフォード男爵令嬢になるんですか?」
「そうなるわね。」
話がどこでこんなに恥ずかしい方向に進んだのか分からない。
アイリスはどうしようもないくらい戸惑っている様子で、そのうちリリーとアシュリーが完全にこの階にやって来た。
上がってきたことを確認し、彼女は声を抑えて尋ねた。
「私がウィルフォード男爵の令嬢だとすれば、王太子妃の試験で有利になると思いますか?」
ああ、そんなことを考えていたのか。
私は思わず立ち止まり、アイリスを見つめた。
そうだろうか?
正直なところ、分からない。
これはダニエルに一度聞いてみなければ。
ダニエルが戻ってきたら確認しようと考えながらも、再びアイリスの表情が暗くなった。
彼女はうつむき、落ち着いた声で言った。
「申し訳ありません。私の利益のためにお母様の再婚を望んでいるわけではないんです。私はただ、お母様がウィルフォード男爵様と幸せになることを願っています。」
「え? 私は怒ってないわよ。」
私は驚いてアイリスの手を取り、彼女をなだめた。
アイリスがそう考えるのも当然だ。
彼女は王太子妃候補として試験を受けているが、他の候補に比べて環境的な条件が少し不利だからだ。
私とダニエルが互いに想い合っていて、フレッドの視線を止めたことで、私が完璧な嫁候補となり、ダニエルと結婚することになるかもしれないと考えるのも無理はない。
「ねえ、考え込んでて話してなかったの。怒ってるわけじゃないから心配しないで。」
「でもお母様は男爵様と結婚するか分からないって言ってましたよね?」
「結婚するのも悪くないわよ。ただ、問題はダニエルと結婚したら、私がウィルフォード男爵家の後継ぎを産まなきゃいけないかもしれないってこと。」
この年で子どもを産むなんて、とんでもない話だ。
でも、ダニエルの考えはまた違うかもしれない。
もし私がダニエルの恋人ではないなら、彼の優れた血筋を世に残さなければいけないと誰かが言うかもしれない。
でも皮肉なことに、その子を産むのが私だとしたら、それはまた別の問題だ。
「後継者・・・」
アイリスは考えもしなかったという表情だった。
それもそうだろう。
彼女はまだわずか十九歳だ。
好きな人と結婚して新婚生活のような甘い夢に浸る年齢だ。
王子妃や王妃としての責任感など、想像すらできないだろう。
しかし、子供を産むというのはまた別の問題だ。
「じゃあ、別れるんですか?」
「うーん、分からないわ。ダニエルとまだその話をしていないから。」
そう考えると、こういうことも話し合わなければいけない。
後継者を望むのかどうか。ダニエルは気にしないかもしれないし、逆に自分の子供にこだわるかもしれない。
正直なところ、私にもまだ分からない。