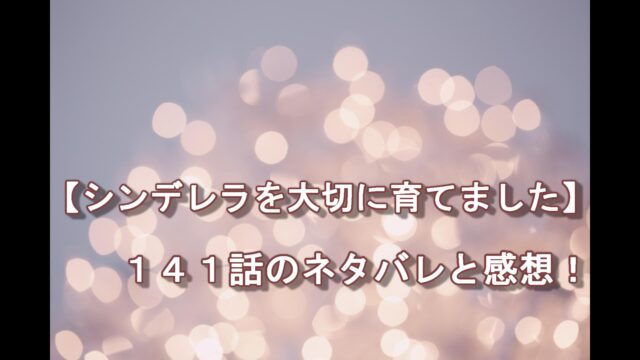こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

169話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 新しいドレス
石鹸の価格が上昇したため、クリーニング店だけでなく一般家庭でも困難な状況が続いていた。
そんな中、近所にある屋敷で石鹸を分けてくれるという噂が急速に広がった。
「一人につき一個だって。」
石鹸を受け取った女性が、堂々とした様子でそれを隣人たちに見せながら言った。
その石鹸は、彼女が偶然屋敷を掃除する手伝いに行った際に得たものだ。
彼女は、ミルドレッドが言った注意点を人々に自慢げに話していた。
風が吹く場所にこの材料を置くと何か変なことが起きるかもしれない。
肌に直接つけるのはやめておいたほうがいい。
「肌には毒になる可能性があるから洗濯にだけ使えと言っていた。でもそれも裕福な貴族たちに限った話だろう。」
「ただでくれるの?一つだけ?」
「代わりに余った油があれば持ってこいって。」
「油?余った油なんてどこにあるの?」
「獣脂みたいなもののことを言っているみたい。」
動物の脂肪分はろうそくを作るのに使われることがある。
時には肌に塗ることもあるらしい。
人口が多い屋敷のような場所では料理人たちがそのような脂肪を集めて売り、個人的な収入を得ることもあった。
しかし、一般家庭では売るほどの量は出ないため、通常は料理をする際に脂肪を利用する程度だった。
廃油は他の用途で使うか、少量であれば捨てることもあった。
「それを持ってくれば石鹸をくれるって?」
人々の顔には信じられないという表情と、信じ難い話だという表情が浮かんだ。
「信じてみなよ、本当なんだから。」
石鹸を受け取った女性はそう言い残して立ち去った。
石鹸が手に入ったおかげで、たまった洗濯をすることができるようになったので、急いで家に戻る必要があったのだ。
「綺麗だわ。」
アイリスの部屋で、アシュリーが感嘆しながら言った。
彼女は今朝完成したアイリスのドレスを見て感激していた。
隣に座って一緒に見ていたリリーは、ドレスを身に纏ったアイリスの姿に触発され、すぐにその姿をスケッチし始めている。
「髪をこんな風にまとめようとしているの。」
ドレスを身に纏ったアイリスが、自身の髪を一束取り上げて上に持ち上げながら言った。
隣でドレスの仕上がりを確認していた侍女が、素早くアイリスの髪を掴み直して助けた。
「首を見せたいなら、髪を上げるのがいいかもしれません。」
アシュリーの言葉に、アイリスも頷きながら髪を整えた。
しかし、リリーは納得がいかない様子で口を開いた。
「サークレットを付けた方がいいんじゃないかしら。」
「リリー!」
サークレットと言えば、結局は冠のことだ。
時には結婚式で新婦がベール付きの冠を使用することもあるが、基本的には冠は王族が使用するものだ。
アイリスは呆れたようにリリーを見つめ、大きなため息をついて言った。
「王妃候補がそんなものをつけて現れたら、どう思われるかしら?」
「きっと見下されると思うわ。」
「私のデザインが惜しいからそうするのよ。」
リリーはため息をつきながらノートをめくり、自分がデザインしたサークレットを探した。
それは、アイリスがイマイチと評価した宝石があしらわれた王冠のスケッチだ。
「リリーが惜しむ気持ちもわかるわ。本当に美しいものね。」
隣にいたアシュリーがリリーのノートを覗き込みながら言った。
城の宝石を使ってデザインしたサークレットは、アシュリーが見てもとても魅力的だ。
アイリスも思わず髪飾りを手に取り、じっくり眺める。
スケッチの中で彼女は髪を下に結び、背後にサークレットをあしらっていた。
その姿はあまりにも美しく、思わずため息が出た。
「本当に美しいわ。彼女にふさわしいものよね。」
そのとき、アシュリーはアイリスに髪飾りを手渡しながら微笑みかけた。
リリーが尋ねる。
「アイリス、結婚式のときにリアンにこのデザインを使って一つ作らせてみたらどう?」
「それもいい考えだと思う!」
リリーの提案に、アイリスはため息をつきながら応えた。
王子をリアンと呼ぶのは果たして適切かどうか、そして結婚式でリリーがデザインしたサークレットを使うことを提案するべきかどうか、アイリス自身も迷っていた。
「ダメよ。王妃になる人はベラの冠を使うもの。」
アイリスの指摘に一瞬沈黙していたリリーとアシュリーの顔が明るくなった。
2人はベッドから降りてアイリスの隣に座りながら口々に言った。
「そうよ!ベラの冠があるじゃない!」
「素晴らしいわ!」
城に代々伝わる宝物だ。
それは将来の王妃だけが身に着けられるもので、アイリスはもちろん、リリーやアシュリーもその話を聞いたことはあっても、実際に見たことはなかった。
「まだドレスを眺めているの?」
そのとき、ミルドレッドがアイリスの部屋に入って尋ねた。
すでにアイリスのドレスは午前中に到着して確認済みだ。
今、リリーがアイリスに頼んでドレスを着せてもらい、それを眺めているところだった。
母の登場に、リリーが慌てて駆け寄り、ノートを拾い上げる。
彼女は再び集中して鉛筆を動かしながら言った。
「ほぼ完成しました。」
「でも、ベラの冠はどうして?」
ミルドレッドの質問に、アイリスの顔が赤く染まった。
首まで真っ赤になっている様子だった。
彼女はうろたえながら答えた。
「リリーがサークレットをデザインしたみたいね。」
サークレット?
ミルドレッドが戸惑った表情を浮かべると、リリーが急いでノートをめくり、自分がデザインしたサークレットを彼女に見せた。
実際よりも少し美しく描かれたアイリスが正面を見つめているスケッチだった。
その頭上には城から送られた宝石があしらわれたサークレットが描かれていた。
「まあ、素敵ね。」
「そうでしょ?」
母親までもが賞賛すると、リリーの顔は輝きを増した。
彼女はミルドレッドのそばに急いで戻り、興奮した声で続けた。
「この宝石は特別ですけど、他の家でも同じようなネックレスを作れると思うんです。しかも、アイリスのドレスには胸の部分に小さな宝石が飾られているから、その上に宝石のネックレスを重ねたら、せっかくのドレスの飾りが隠れちゃうじゃないですか。」
「それもそうね。」
ミルドレッドが軽くうなずきながら、眼鏡を少し直した。
するとリリーがそれを見たようにアイリスをじっと見つめ、彼女が描いたサークレットを取り出して言いました。
「だから、こんな風にサークレットをデザインしてみたらどうかと思ったの。」
「とんでもないわ。」
母親がリリーに渡しそうになったその瞬間、アイリスは素早くそれを手に取り、腰に手を当てながら言いました。
「私がサークレットを付けていきます。みんな建前だけでしか褒めないでしょうから。」
その言葉も一理ある。
しかし、リリーが言ったようにネックレスは少し古臭いという意見もあって、ミルドレッドは納得した。
彼女はリリーのスケッチを眺めながら少し考え、ふと提案した。
「後ろに回したらどうかしら?」
「後ろ?」
アイリスとリリーは目を丸くする。
ミルドレッドはスケッチの装飾部分を指しながら言った。
「この部分をアイリスの背中側に配置するのよ。」
「それだと人の目に見えないじゃない?」
「背中を見せれば見えるわ。」
「でも、せっかく作ったのに後ろに飾るなんて、もったいないと思いませんか?」
「何を言っているの。」
ミルドレッドはそう言いながらハサミを手に取る。
彼女は微笑みながら話を続けた。
「その方が上品に見えるわ。人目に触れない場所に飾ることでね。」
アイリスは驚きで口を開けたまま、アシュリーも同じく驚愕していた。
ただリリーだけが大きく目を輝かせて言った。
「面白そう!」
続けてアシュリーも声をあげた。
「素敵!アイリス!それでいこう!」
しかし、アイリスはしばし呆然としたままミルドレッドを見つめたあと、リリーのスケッチに視線を移した。
これは単なる面白半分で終わる話ではない。
でも、彼女もリリーのデザインが本当に美しいことを認め、自分でもそれを身につけたいと感じていた。
「まだネックレスとしては完成していないんですね?」
アイリスの質問にミルドレッドは微笑みながら答えた。
「始まってもいないのよ。ウェルフォード卿が持って行っているから。」
ダニエルがよく知る細工師に頼むつもりだと説明した。
ミルドレッドはすぐに1階へ降り、書類を読んでいたウェルフォード卿に近づいて軽くノックをする。
彼はすぐに立ち上がり、ミルドレッドのためにドアを開けた。
「緊急の用事でも?」
ダニエルの質問に対して、ミルドレッドは興味深いという表情で微笑んだ。
それは貴族ではなく、まるで執事に向けられるような質問だった。
しかし、彼女はそれを気にすることなく、軽く肩をすくめた後、自分の考えを述べた。
「アイリスのネックレスを作り直してみてはどうでしょう。それをヘアアクセサリーに変える形で。」
「ヘアアクセサリーというのは、どのようなデザインをお考えですか?」
ミルドレッドはすぐにリリーが描いたスケッチを取り出して見せた。
それはヘアアクセサリーというよりはティアラに近く、やや派手すぎる印象を与えるデザインだ。
ダニエルはその瞬間にそう感じたが、彼女はそれに気づかず続けた。
「両側にピンを付けて、これを使って後頭部を飾るんですよ。」
「なるほど。」
彼はその意味を理解した。
斬新で面白いアプローチだ。
ダニエルはミルドレッドに一度目を向け、リリーのスケッチを手に取りながら言った。
「今晩、裁縫職人を訪ねるつもりです。」
「よろしくお願いします。」
ミルドレッドの頼みに応じて、ダニエルはスケッチを丁寧に折りたたみ、小包の中に収めた。
そして彼女に向かい合いながら話し始めた。
「リリーが画家たちに会いに行くそうですが、それをご存じですか?」
知っている。
ミルドレッドは再びダニエルを振り返りながら答えた。
「ええ、リリーから聞きました。ケイシー卿に会いに行くつもりだと言っていました。」
彼がそれを知っているなら、もう少し話を進めるのが簡単だろう。
ダニエルはミルドレッドを手招きしながら内側に誘導し、扉を閉めた。
何の話だろう?
少し緊張している彼女に、彼は穏やかに言葉を続けた。
「あなたなら、きっと上手くやれると思います。ただ、念のためにお伝えしておきます。」
「何のことですか?」
「リリーをケイシー卿が画家たちに紹介する予定だと聞きました。」
ミルドレッドは彼が何を言おうとしているのか察し、穏やかに微笑んだ。
若く才能のある女性画家を紹介する裕福な貴族。
画家たちの集まりに質をもたらす存在。
それがリリーの能力を広めるきっかけとなるかもしれないし、逆に妨げになることもある。
ミルドレッドは胸の前で腕を組み、一息ついた。
リリーが傷つくのは望まないが、だからといってそれを阻止する理由はない。
「それは仕方のないことです。リリーが挑戦すべきことですから。」
「でも、少し警戒するよう伝えておいたほうが良いのではありませんか?」
「他の人たちが彼女に嫉妬する可能性があるということ、彼女ももう分かっているのでは?」
ダニエルはミルドレッドの言葉に眉をひそめた。
彼が言いたかったのは、そういうことではなかったのだ。
リリーが画家たちの集まりでフィリップの紹介者として出席すれば、何人かの画家たちから嫉妬を受けるだろうということは分かっていた。
しかし、それはリリーが対処すべき問題だ。
彼女は才能ある若い画家だ。
たとえフィリップの紹介ではなくても、いつかは他の人々の嫉妬や批判に直面することになるだろう。
ダニエルが懸念しているのはそれではなかった。
「そうではなく、裕福な後援者を持つ未婚の女性が、経済的に困窮した男性たちの集まりに紹介されるというのが問題なのです。」