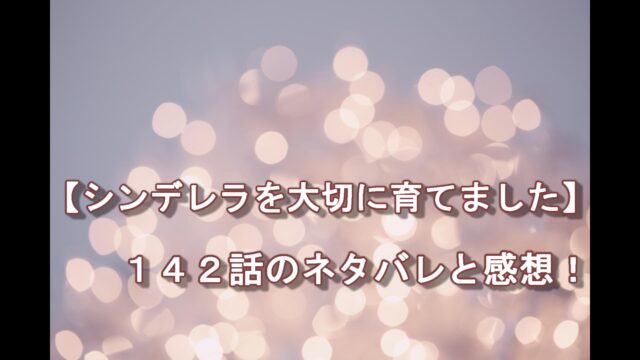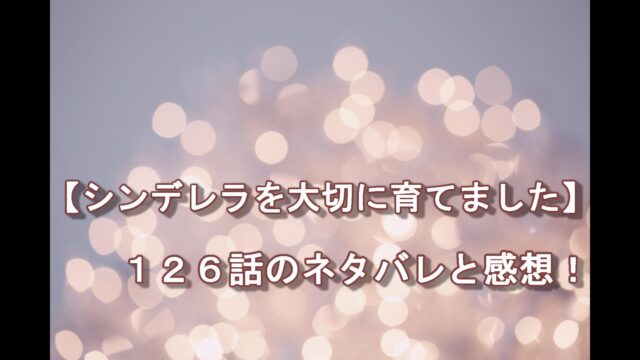こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

171話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 3姉妹の悩み
「ウォルフォードの男爵様が妖精だって知ってた?」
イートンの日、ケイシー侯爵家の教会別荘でどうやって行動すべきかについて話していたミルドレッドに、アイリスの表情がやや曇った。
彼女は、ミルドレッドが手洗い場で汚れを確認しようとしたとき、リリィを呼び止めて尋ねた。
「ええ、まあ、なんというか…察しはついてたけど。」
「知ってたの?」
リリィの震えるような態度に驚いたのはアイリスだけではなかった。
アシュリーもまた驚いてリリィを見つめた。
机の前に座っていたリリィは、やむを得ず筆を置いた。
「はぁ…」
彼女は深いため息をつき、口を開いた。
「時々お話する時にそれができるかしら?しないお話をする時もあるのよ。絵を見るためにハメルに行ったって話も、イートンの日には首都に着いたなんていう話も。」
ハメルから首都まで一日で馬を走らせるなんて無理だ。
休むこともなく走らせれば可能かもしれないが、ダニエルがそんな無謀なことをするとも思えないし、リリィもそのような危険を冒すとは考えにくかった。
彼女の話を聞いたアイリスとアシュリーは、お互いに視線を交わした。
ダニエルと最も多くの時間を共にしているのは、この三人の母親であることは明らかだ。
ミルドレッドを除けばリリーだ。
彼女がダニエルから絵のレッスンを受けているのだから、それは当然のことだった。
「それに、時々世界についてよく知っているかのように話していましたよ。」
「世の中に。」
アイリスは言葉を失い、額に手を当てた。
思いもよらなかった。
ただ、とても裕福でハンサムな男性だとしか考えていなかった。
その姿を見たリリーは、彼女が知っている他の情報は決して話さないと決心する。
ダニエルが首をがっしり掴んでいるということ。
これはフィリップがケイシー公爵夫人に話したことだ。
具体的にそう言ったわけではなく、彼女が絵の道具を売る通りに行きたいと言い、ウォルフォードの青年と一緒に行こうと言っただけだった。
リリーが自分でもお金を持っているのだから自分のお金で買うと言い返すと、フィリップはこう答えた。
『お金の問題ではなく、その通りの近くは少し危険だよ。ウォルフォードの青年はその辺りをよく知っているから、一度一緒に行って、彼が知り合いだと分かるようにしておいた方がいいだろう。』
危険な通りに裕福な人が行き、彼の知人がいることを知らせるのは普通のことであり、リリーも裕福だからといって、ひやかしを受けたりしないためにはその方がいいとフィリップは考えた。
しかし、フィリップは「ダニエルに知人がいる」と知らせるのがいいと提案した。
それは、その通りがダニエルと知人がいる人にとって安全だという意味であり、結局、ダニエルがしっかりと守られているということを示している。
ただし、これをアイリスやアシュリーに話す必要はないだろう。
余計な心配をさせるだけだから。
「彼が貴族様に呪いをかけたりするわけないよね?」
アシュリーの言葉にアイリスとリリーは目を合わせた。
それは全く予想していなかった視点だった。
一瞬気まずい沈黙が流れたが、リリーが先に笑い出し、言った。
「もう、あり得ないって!」
「でも話の中では、悪い妖精たちがハンサムな男性を誘惑してたじゃない?」
「とにかく、ウォルフォードの旦那様は悪い妖精じゃないし、お母様だってハンサムな男性じゃないわよね?」
リリーの反論にアシュリーは口を閉じた。
しかし、アイリスはそうではなかった。
彼女は真剣な表情でじっくり考えた後、言った。
「逆に考えると、そうかもしれない。女性の妖精がハンサムな男性を誘惑するように、男性の妖精がハンサムな女性を誘惑するなんて。」
「アイリス!」
瞬間的にまた場の空気が沈んだ。
リリーは予想もしていなかった発言に驚き、アイリスを見て驚愕の表情を浮かべて口を閉じた。
そんなはずはない。
彼女が知るウォルフォードの旦那様は、少し気難しいところがあり、どことなく人を遠ざける傾向があるけれど、母を大切にしている。
でも、そんな全てが話の中の邪悪な妖精の姿と重なるのだろうか。
「必ずしも母が旦那様の誘惑に落ちる必要があるの?」
リリーの問いかけで再び場が静けさを取り戻した。
ウォルフォードの旦那様は母にとても親切にしている。
3人全員、彼が母のためなら何でもすると知っている。
そうであれば、そのまま見守る方がいいのではないだろうか。
その時、アイリスが尋ねた。
「妖精に誘惑された人はどうなるの?」
「妖精が自分たちの国に連れて行くって話だけど。」
3人の子どもたちは顔を見合わせた。
母親が妖精の国に連れて行かれる?
絶対にダメだ。
アシュリーは急に立ち上がって駆け出した。
その後をアイリスとリリーが追いかけた。
「誰が走っているの!」
洗濯室からちょうど出てきたミルドレッドが声を上げたが、子どもたちには今それが重要ではなかった。
一番最初にアシュリーが家のドアを蹴り開け、妖精が現れる部分を探して回り始めた。
その後ろをアイリスとリリーが続いた。
「鉄で作った剣で刺しなさいって聞いたことがある!」
アシュリーの興奮に対してリリーが冷静に尋ねた。
「ここで男爵様を倒せる人っているの?」
静かな表情でアシュリーが再び本をめくり始めると、今回はアイリスが口を開いた。
「贈り物を渡して。」
「贈り物を渡したら魔法が解けるの?」
「うーん、妖精が消えるなら魔法が解けるんじゃない?」
「男爵様が消えたらダメでしょ!」
リリーの指摘にアイリスとアシュリーの視線が重なった。
そうだ、男爵様が消えたら母親が悲しむ。
しかし、アイリスの頭の中に一つの疑問が浮かんだ。
「でも、どうせ母さんが男爵様に誘惑されたのなら、男爵様が消えても関係ないんじゃない?」
「そうかもしれないね。」
そうだね。
再び部屋に静寂が訪れた。
少しして、今回静けさを破ったのはアシュリーだった。
「それじゃあ、男爵様に何かをするなんて無理なんじゃない?」
「うわぁ!」
アシュリーの質問を聞いたリリーが頭を抱えて叫んだ。
「なんてこと!」
驚いて声を上げる彼女を見たアイリスとアシュリーも同じように驚き、目を見開いた。
リリーは彼女らの前で髪を掻きむしりながら叫んだ。
「こういう答えがないのが一番嫌い!もう男爵様に直接聞いてみる!」
え?
アイリスとアシュリーはそのまま固まったが、急に立ち上がり部屋を飛び出していったリリーを呆然と見つめ、遅れて慌てて追いかけ始めた。
「リリー、男爵様に尋ねたら答えてくれると思う?」
アイリスの質問に、リリーは2階の階段を駆け上がりながら、透き通る声で答えた。
「それは聞いてみないと分からないよ。」
それもそうか。
アイリスとアシュリーの視線が交差する。
今度はアシュリーが尋ねた。
「それで、お母さんを連れて行くとなったらどうするの?」
「連れて行かないでって言うしかない。」
リリーの言葉にアイリスが呆然とした表情を見せた。
妖精が「連れて行かないで」と言ったら「わかった」と言って連れて行かないわけがない。
アシュリーもまたアイリスと同じ考えだった。
もし男爵様が必ず誰かを連れて行かなければならないと言ったら、いっそ自分を連れて行くようにお願いしたらどうだろうか。
アシュリーの表情が決然と固まった。
「男爵様。」
アイリスとリリーがそれぞれの考えで忙しい間に、リリーはダニエルの作業室のドアをノックしていた。
中に入る許可を待っていると、アイリスは緊張した表情でアシュリーを振り返った。
リリーもまた、緊張した面持ちでドアを見つめていた。そしてついに、中からダニエルの声が聞こえた。
「入って。」
ダニエルは相変わらず机の前に座っており、視線を上げることなく何かを手にしていた。
その姿は見慣れていた。
リリーは静かに部屋に入り、慎重に尋ねた。
「何かお手伝いできますか?」
その声にようやくダニエルが顔を上げ、眼鏡を外す。
リリーは彼の顔を見つめ、心の中で思った。
もしかして、この顔だけでお母様を妖精の力で魅了してしまったのではないか、と。
ただその顔だけで十分だったのではないか?
「旦那様が妖精だと聞きました。」
「誰から?」
「お母様からです。」
「そうか。」
誰から聞いたのかと尋ねるまでぎこちなかったダニエルの雰囲気が、「お母様から」という言葉を聞くやいなや一気に和らいだ。
その様子を見たアイリスとアシュリーの視線がまたぶつかった。
だからこそ、ダニエルに直接聞きたいとは思わなかったのだ。
彼がミルドレッドにすっかり夢中であることを知っていたから。
ダニエルが母親を愛し、母親が彼を愛しているなら、それだけで十分だ。
彼の傍で、彼がどれだけ母親に良くしているのかを見てきた。
そうなら、そのままにしておきたい。
これまで子どもたちを育てるのに苦労してきた母親が幸せなら、それを祝福してあげたい。
問題は、ダニエルが母親を連れて妖精の国に行くかもしれない、ということだ。