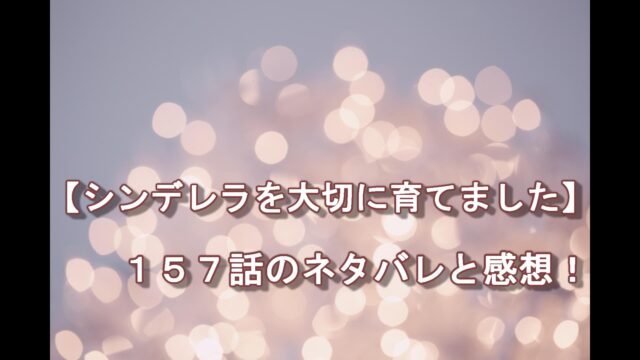こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

200話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 後継者③
「どうしてそんな最悪の状況ばかり考えるの?二人くらい産めば、少なくとも一人は男の子でしょう。」
王太妃の無神経な言葉に、ダニエルは苦笑した。
そんなふうに他人事のように軽く話せていいですね、という言葉が喉元まで出かかったが、彼はそれをぐっと飲み込んだ。
「陛下、私は子どもを必要としていません。」
ダニエルの言葉に、王太妃の表情が再び険しくなった。
彼女はわずかに顔をしかめ、彼をじっと見つめたあと、まるで吐き捨てるように言った。
「バンス夫人の年齢が心配でそう言っているのなら、あなたが彼女の願いを叶えてあげてもいいのでは?」
王大妃の言葉が一体何を意味しているのかと一瞬考えたダニエルは、ふっと笑った。
彼はミルドレッドも他の人々のように「必ず息子を産まなければ」と思っていると考えていた。
つまり、まるで妖精が願いを叶えるように、ミルドレッドが「息子を授けてほしい」とダニエルに願えば、その願いを叶えればいいのではないか、という話なのだ。
不可能なことではない。
ダニエルにはそれが可能な能力がある。
とてもデリケートな話ではあるけれど。
「いいえ、陛下。彼女はもう妊娠するつもりはありません。」
王大妃の目が大きく見開かれた。
ダニエルは彼女がこれから何を言おうとするのか察して、すぐに口を開いた。
「そして、それもまた同じ理由です。バンス夫人が望まないから必要ないというのではなく、そもそも私が子どもを望まなかったから結婚しなかったのです。」
「それはどういうこと?」
王太妃はあまりの驚きに口を開けたまま固まり、まるで初めてダニエルを見たかのように彼を見つめながら問いかけた。
「つまり、バンス夫人が子どもを望まないから気に入ったということか?」
ダニエルと意見が一致するから戦略的に会っているのか、という問いだ。
それは違う。
ダニエルは王太妃の短絡的な推測に思わず笑ってしまった。
彼がミルドレッドに関心を持ち始めたのは、彼女が近くの邸宅の主であり、その邸宅で護衛が誰かの願いを聞き入れたことがきっかけではあったが、彼女に心を惹かれた理由はそれだけではなかった。
ダニエルは椅子の背もたれに体を預け、余裕を持って答えた。
「ただ、私たちは生まれつき縁があったというだけのことです。」
彼のふざけたような返答に、王大妃の目が細くなった。
彼女はすぐにダニエルの表情と態度を確認し、これ以上ミルドレッドとの関係については話さないと判断した。
これはもう話にならない。
王大妃は大きくため息をつき、尋ねた。
「では、あなたの爵位は?あなたの父上が望んでいた爵位と領地ではないの?それを他人の手に渡すつもりかい?」
「陛下、私の子であっても、厳密に言えば他人です。」
「でも血筋でしょ。血縁で。」
「そうでしょうか?」
ダニエルの目が細められた。
一瞬、彼の言葉の意味がわからなかった王太妃のために、ダニエルは口を開こうとしたが、すぐに言葉を飲み込んだ。
王太妃の父は、王太妃を生んだ亡き正妻の代わりに、娘を二人連れた平民の女性と再婚した。
そしてその女性が自分の娘を迫害しているのを知っていながら、知らぬふりをしていた。
その絶望の中で王太妃を救ってくれたのが、ダニエルの母だった。
王子と運命的な恋に落ちた王太妃は、すぐに王太子妃となり、自分を迫害した継母と異母姉妹たちを遠くの地方へ追放した。
父は彼女が王子に出会う前に亡くなっていたため、追放されることはなかった。
本当に血縁がすべてなら、王太妃の父は継母の迫害から娘を守らなければならなかった。
守るべきだった。
「家族は血縁だけで成り立つものではありません。」
数十年前の王大妃の傷をむやみにえぐりたくなかったダニエルは、あえてそう答えた。
だが一方で、彼は本気でそう思っている部分もあった。
家族とは血筋だけで成り立つものではない。
歴史的にも、数多くの親と子が互いに命を奪い合ってきた。
そして血のつながらない親族のために命を捧げた者も数知れない。
父が亡くなり、継母と姉妹たちに追い出された王大妃は、ダニエルの母を「親友」だと考えていた。
果たして彼女(ダニエルの母)が王大妃を同じように親友と思っていたかはわからない。
だが、王大妃にとって彼女は間違いなく親友であり恩人だった。
その親友がこの世に残していった唯一の存在が、ダニエルという息子なのだ。
王大妃がダニエルを特別視するのは、ある意味当然のことだった。
「ウェルフォード子爵。いや、ダニエル。」
王大妃はゆっくりと再び口を開いた。
彼女はまるでダニエルが幼い頃のように、彼の名前を呼びながらまっすぐ彼の目を見つめた。
幼い頃のダニエルも本当にハンサムだった。
彼女の息子もハンサムだったが、王太妃はそんなことを考えながら話を続けた。
「そう、あなたの言う通りね。家族は血縁だけで成り立つものじゃない。私があなたを息子のように思っているように。」
王太妃の突然の告白に、ダニエルの表情は一瞬驚きに固まったが、すぐに穏やかに和らいだ。
彼もまた、彼女が自分を友人の息子として、甥のように思っていることは知っていたが、息子のように思っているとは思っていなかった。
「あなたがこの場所に心を寄せていないこと、私は知っている。」
そこまで話した王太妃は、しばらく口を閉ざした。
彼女がそれを見抜いていたとは、思ってもみなかった。
ダニエルは眉をわずかに上げたが、何も言わなかった。
「あなたのお母様が旅立つ前に、私にあなたを託したのよ。」
「存じております。」
当時、王大妃は「どうしてまだ成人もしていない息子を残して逝けるのか」と憤っていた。
そのとき、彼女が理解できないという表情を浮かべていた妖精(=ダニエルの母)の顔が、今でもはっきりと思い出された。
妖精だったからなのか。
王大妃は、まるで彫刻のようなダニエルの顔をしばらくじっと見つめた。
それで、自分の子を望む気持ちがまったくないのか?
この地に命を残し、繁栄を願う本能的な欲求がないのか?
「私は、あなたに奥方との間に子どもがいてほしいのよ。それがもしかしたら、あなたの居場所をどこかに定める助けになるかもしれないから。」
そうだったのか。
ダニエルは王大妃の言葉から、なぜ彼女が自分に結婚と子どもを望んでいたのかを理解した。
ダニエルは成人するやいなやこの国を離れ、あちこちを転々としていた。
王太妃はそれを心配していたようだ。
「無礼な言い方はしたくありませんが、陛下。私の母も夫と子を持っていましたが、この地に定着することはありませんでしたよね。」
「そう、そうだったわね。」
王太妃はダニエルの的確な指摘にため息をついた。
妖精は百の願いを叶えれば、自分の世界に戻れると言われていた。
しかしダニエルは、人間として生まれた身だから、それが叶うかどうかは分からないと考えていた。
「もしかして、ダニエル。だからバンス夫人が好きになったの?あなたのお母様とは正反対だから?」
王太妃の頭の中にふとそんな仮説が浮かんだ。
成人もしていない息子二人を置いて、自分の世界に戻ってしまった母親とは違い、ミルドレッドは自分が産んだわけではない前夫の娘二人を立派に育てているのだから。
それは、ダニエルのどこか感情的な急所に触れたのかもしれない。
だが、ダニエルは王大妃の言葉を聞いた瞬間、すぐに不快だという表情を浮かべた。
ミルドレッドが母を重ねて好きになっただって? そんなの想像するのも嫌だ。
彼はすぐに冷たく返答した。
「まったく似ていません。私の母と彼女は、まったく違います。」
「でも完全に否定するわけでもないのね。」
「完全否定ではありません。母もあの人のように、自分の子どもを心から愛していましたから。」
ふむ、と王大妃はテーブルの上に肘をつきながら考え込んだ。
そして目を細めて尋ねた。
「彼女のどんなところが、そこまで気に入ったの?」
「そうですね。やっぱり美人だから、でしょうか。」
嘘ではなかった。
やや口元のほころんだダニエルの顔に、かすかな微笑みが浮かんだ。
その笑みを見た王太妃は一瞬眉間にしわを寄せたが、すぐにくすっと笑いながら口を開いた。
「私もね、初めて夫に会ったときは一目惚れだったの。あの人、本当にハンサムだったわ。」
わかっている。
ダニエルは亡き王の肖像画を思い浮かべながらカップを傾けた。
リアンの整った顔立ちは偶然ではない。
この国の王たちは代々容姿に恵まれてきたのだ。
なるほど、だからこそ、妖精のベラがあの英雄に一目惚れして、冒険を助けたのだろう。
「でもね、王太子妃になって気づいたの。夫くらいハンサムな男の人って、他にもけっこういたのよ。」
「そうなんですか?」
驚いたように片眉を上げるダニエルを見て、王太妃は愉快そうに笑った。
もしかすると、彼女が普通に社交界にデビューしていたら、王子が一目で惚れるようなことはなかったかもしれない。
彼女の夫もまた、初めて見たときの彼女の姿に心を奪われなかったかもしれない。
だから彼女は、運命的な出会い、愛というものを信じていた。
「でもダニエル、お前は多くの国を巡って、多くの美女を見てきただろう?バンス夫人が美しいのは間違いないけれど、お前の目をこれほど惹きつけたほどの美女だったのかい?」
「はい。」
一瞬の迷いもなく、ダニエルは答えた。
ミルドレッドは美しい。
星が流れる真夜中の空のように黒く輝く髪、月の光のように白く透き通った肌、そして情熱と意志を秘めた緑の瞳。
王大妃の顔に、かすかな驚きの表情が浮かぶのを見て、彼はくすっと笑った。
椅子の背にもたれながら、ゆっくりと口を開いた。
「私は、人々が見られないものを見て、感じられないものを感じる時に、自分を実感します。」
嘘を見て、絶望を感じる。
あの日。城でデビュタント舞踏会が開かれる前日、ダニエルは東の邸宅で、二つの大きな絶望が生まれたのを感じていた。
それが誰のものだったのかは分からない。
その二つの絶望は静かに消えていき、翌日城で、ダニエルは何ヶ月も人々の口にのぼる、ドレスを着たアイリスの姿を目にした。
「バンス家の女性たちはみんな幸せそうに見えるね。」
絶望は幸福へと変わった。
そして、それと似た出来事が、城で再び起こった。
王太妃はカップを傾けながら言った。
「そうね。あのドレスの顔立ちは魔法のように際立っていたわ。」
それまでダニエルがミルドレッドや彼女の家で何が起こったのかを調べようと関心を持っていたのは、「ミルドレッド」という人間に興味を持つきっかけにすぎなかった。
ダニエルは、ミルドレッドが本物のミルドレッドではないことを王大妃に知られないように、一瞬口を閉ざしてから再び話し出した。
「人々を助ける姿が心に残ったのです。」
「そうかい?」
王大妃は驚いたような顔をしながらも、すぐに納得したように頷いた。
そして箸を動かした。
他人を助ける慈愛に満ちた姿に心を打たれる人は多い。
ダニエルもそのような姿に惹かれたのだろうか――そう考える彼女だったが、それもありえるかもしれないと思った。
もちろん、それは王大妃の矢継ぎ早な質問をかわすための嘘だった。
「お帰りなさいませ。」
王太妃との昼食を終えて、再び近くの邸宅に戻ると、ジミーがダニエルを出迎えた。
ダニエルが帽子と上着を脱いでいると、ふと応接室の方から耳を澄ませた。
特に妖精の力を使わずとも、応接室では数人の女性が笑いながら話している声が聞こえてきた。
アイリスのお茶会。
そこでようやくダニエルは、アイリスがまた貴族の令嬢たちを招いていたことを思い出した。
試験のための慈善活動に一緒に取り組むメンバーを集めているのだ。
その中にマーシャとパトリシアがいるのは理解できるが、エレナまで招かれていたとは、ダニエルは思ってもみなかった。
「奥様は?」
「1階の書斎にいらっしゃいます。」
「食事は?」
その一言で、夫人を深く想う夫の姿を思わせるダニエルに、ジムは思わず微笑んだ。
彼は頭を下げながら答えた。
「召し上がりました。お越しになったことをお伝えしましょうか?」
「いい、私が行く。お茶だけ用意して。」
ダニエルの言葉に、ジムは彼のジャケットと帽子を近づいてきたルインに渡すと、お茶の準備のために厨房へ向かった。
その間、ダニエルはミルドレッドに自分が来たことを伝えるために書斎へ向かった。
“来た”と伝えるためというのは、口実だった。
ジムを通して知らせるだけでも十分だった。
ただ、ミルドレッドの顔が見たかったのだ。
ダニエルは期待に胸を躍らせながら書斎の扉をノックした。
「少しだけ、いいかな。」
当然「お入りください」と言われると思っていたのに?
「お待ちください」との返事に、ダニエルは片眉を上げた。
書斎の中にミルドレッドが一人ではないということだ。
するとやはり、中から誰かがドアに向かってくる音がして、見知らぬ女性がドアを開けて挨拶をした。
「こんにちは。」
女性はダニエルを見るなり顔を赤らめた。
誰だろう?とダニエルが彼女の正体を思い出そうとしていると、ミルドレッドが近づいてきた。
「こちらはジェニー・オスボーン伯爵令嬢です。オスボーン嬢、こちらはダニエル・ウィルフォード男爵です。」
「ダニエル・ウィルフォードです。」
「ジェニー・オスボーンです。」
ミルドレッドの紹介で、ジェニーとダニエルは改めて挨拶を交わした。
「ハンサムね」とジェニーは思わずダニエルの顔をじっと見つめながら感じた。
ダニエルが遠くから見たときは、まるで絵か彫刻のように見えたが、近くで見るとさらに美しかった。
そこまで思ったところで、彼はジェニーの顔が思い浮かんだ。
自分は何を考えているんだと呆れながらも、彼は冷静な表情でミルドレッドに目を向け、さっと挨拶をした。
「ご相談に乗ってくださって、ありがとうございました。」
相談?
その言葉に、ダニエルの表情に疑問が浮かんだ。
その間に、ミルドレッドは特に表情を変えることもなく軽く会釈し、ジェニーはミルドレッドとダニエルの間にできた隙を利用して、すぐに控え室へと戻っていった。
ダニエルは走らず、可能な限り早い歩幅でジェニーが離れていくのを見送りながら、一度彼女を見やったが、すぐに体の向きを戻した。
そして書斎の中へと足早に入りながら尋ねた。
「何かご用でしょうか?」
「お城では、うまくいきましたか?」
ミルドレッドの質問に、ダニエルの動きが止まった。
先に「ただいま」と挨拶するべきだったのだ。
彼は照れ笑いを浮かべて答えた。
「戻りました。王太妃殿下は、僕に安否を尋ねていらっしゃいました。」
王太妃が尋ねたのは、それ以上にもっと個人的なことだったが、ダニエルは自分なりにうまく切り抜けた。
ミルドレッドはダニエルの腕を引いて扉を閉めると、彼の頬にそっとキスして言った。
「オズボーン伯爵令嬢です。アイリスが招待したんです。音楽会で挨拶したらしいですよ。」
「奥様はどんなご用件だったんですか?」
ミルドレッドの肩が小さく揺れた。
大したことではないというふうに言った。
「ちょっとした話よ。相談ね。」
「相談って?普段から親しかった人なの?」
「そういうわけではありません。」
ミルドレッドはダニエルに合わせるようにして、素直にソファに腰を下ろした。
だが彼はすぐに彼女の隣に座り、体を少し彼女の方へ傾けた。
「私が妖精の大母だっていう噂を聞いたのですね。」
「ミルドレッド。」
ダニエルの顔が曇った。
彼はため息をつき、申し訳なさそうな表情で言った。
「噂はすぐにおさえます。」
「その必要はありません。違うと言えば、それで終わりです。どうせ人々は本気で信じているわけでもありませんから。」
ただそう言いたかっただけ。
ミルドレッドに「あなたは妖精の大母なのか」と尋ねてくる人々全員に対して、ただそう返してきただけだった。
「そうじゃない」という彼女の答えに、ダニエルが大きく落胆していなかったのが、その証拠だ。
ミルドレッドは罪悪感の混じったダニエルの表情を見て、苦笑した。
そして彼の頬に手のひらを添えて言った。
「オスボーン伯爵令嬢は、ただお話がしたかっただけなんです。自分の恋愛の話を。」
特別な意味はないというミルドレッドの態度に、ダニエルは安堵の息を吐いた。
そして彼女の思うように、ジェニーの恋愛相談の話題に合わせた。
「何を相談してきたんですか?」
「二人の男性がいるらしいです。一人は両親が気に入ってる人で、もう一人は自分が気に入ってる人だそうですよ。」
「それで、何て答えたんですか?」
「何も。」
ミルドレッドの返答に、ダニエルの目が細められた。
彼女はくすっと笑って言った。
「オスボーン嬢が結婚する相手のことですもの。私が選べるわけじゃないわ。それに、私はその二人の男性のどちらもよく知らないし。」
「それで、なんて答えたんですか?」
「どこが気に入ったのか、どこが気に入らなかったのか、を聞いただけよ。」
気に入った方の男性はハンサムだけど家が少し貧しい、逆にご両親が気に入った方は別の男性で、もう少し見た目は劣るけれど裕福で申し分のない家柄だと言っていた。
「それで、彼女は納得してましたか?」
その答えに納得できないダニエルの反応を見て、ミルドレッドはソファの背もたれにもたれかかり、遠くを見つめながらこう言った。
「人はただ、誰かに自分の話を聞いてほしいだけなんですよ。ただ話を聞いてもらうだけでも十分に満足できるんですよ。それによって、自分の状況を客観的に見る手助けにもなりますし。」
必ずしも自分の問題を解決してもらいたいわけではない、ということだ。
「あなたもそうだったんですか?」
ダニエルがそう質問した瞬間、ジミーがお茶を運んできた。
彼が無言で菓子をテーブルに置く間、ミルドレッドが尋ねた。
「何がですか?」
「あなたも誰かに話したくなったことがありますか?その……」
そこまで言って、ダニエルは一瞬口をつぐんだ。
ジミーが手早く菓子を置き、退室するのを待ってから、言葉を続けた。
「あなたのことです。」
彼女――ミルドレッドの身に起こった出来事。
それを誰かに相談したいと思ったことがあったのではないかという問いだった。