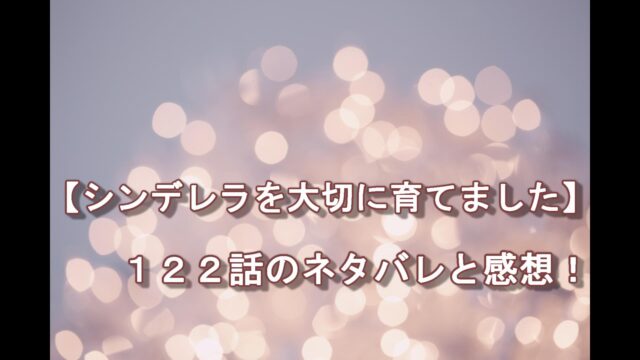こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

201話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 将来
ミルドレッドは目を細めながら、そっと茶杯を持ち上げた。
「わかりません。正直なところ、私はこの身体から出なければならないという考えすら浮かびませんでした。それが加護の力のせいだったのかはわかりませんが。」
ダニエルの顔に、寂しげな表情が浮かんだ。
「加護の力のせいでしょう。」
加護は契約者との契約を最優先する。
意志はあるものの、それはシステムのように動くもので、ダニエルや他の妖精のように感情や関係に応じて柔軟に行動するわけではない。
だからこそ、加護はミルドレッドがミルドレッドとして生きていくように、強制的に制約を課していたのだ。
彼女が別のことを考えないように。
「私が今こんなことを考えられているのも、全部あなたのおかげなんでしょう?」
ミルドレッドの問いに、ダニエルはため息をついた。
もう少し早く気づいていればよかった。
彼女の本当の名前を知っていれば。そうすれば、彼女の守護者との契約を引き継ぐことができたはずだったのに。
「それは当然、僕がやるべきことです。」
守護者とミルドレッドの契約において、ダニエルは調整者のような立場だった。
彼は、守護者がミルドレッドに対して行おうとする強制を阻止していた。
もちろん、その強制力をすべて自分で引き受ける、ということは彼女には伝えていなかった。
「ありがとう。」
ミルドレッドはそう言いながら、ダニエルの肩に寄り添った。
暖かくて小さな重みが彼の肩にかかったその瞬間、ダニエルは「別にどうでもいい」と思えた。
少しぐらい強制的な力を受けたって構わない。
ミルドレッドが自分に「ありがとう」と言ってくれるのなら、それでいい。
ダニエルはにっこり笑いながら腕を伸ばし、ミルドレッドの肩を引き寄せて抱きしめた。
そして彼女の額にキスをして、そのまま目を閉じた。
ふと、加護が別の世界から誰かを呼び寄せたのではないかという考えが頭をよぎった。
その可能性が最も高いのはミルドレッドだった。
彼が知らない新しい何かを彼女が知っていると感じていたからだ。
「ミルドレッド。」
ダニエルは優しく彼女を呼んだ。
彼の肩にもたれていたミルドレッドがわずかに身をよじるのを感じたが、ダニエルは彼女の顔を見ずに問いかけた。
「僕がどれほど君を好きか、わかってる?」
彼の腕の中でミルドレッドの体がぴたりと止まった。
ダニエルはそっと顎を持ち上げて彼女の顔を見た。
ほんのり照れたような、それでいて戸惑ったような表情が、ミルドレッドの顔に浮かんでいた。
ダニエルの脳裏に、ミルドレッドが初めて王太妃に会ったときのことがよみがえった。
あの日、彼女は礼儀正しく振る舞いながらも卑屈になることはなく、堂々としていた。
決して萎縮することはなかった。
自分よりもはるかに高い地位や権力を持つ者の前に立つと、人はどうしても平常心を保つのが難しいものだ。
必要以上に卑屈になったり、逆に無理に強がってしまったりもする。
だが、ミルドレッドは違っていた。
彼女は常に自分を保ち、どんな状況でも卑屈にならなかった。
そんなところが、ダニエルの目にはミルドレッドが輝いて見えたのだ。
貧しい未亡人が娘三人をきちんと育てるのは、決して容易なことではない。
そんな困難を乗り越えてきたミルドレッドは、ダニエルにとって非常に立派に思えた。
そして、人の好意を欲しがらないこと、それを渇望しないことが、とても格好良く思えた。
余裕があるということは、何よりも価値のあることだった。
その関心すら拒めるということが、かえって素晴らしいことのように思えた。
「私を独占したいほど好きなんですね。」
しばらくしてから、ミルドレッドは微笑みながらそう答えた。
それもまた事実だったので、ダニエルも無言で微笑んだ。
まるで鋼のように強く見えたその人が、実は加護によって無理やりこの世界に連れてこられたのかもしれないと知ったその瞬間、彼は初めて、自分の足元の大地が崩れていく感覚を知った。
「実は、今もそうなんです。」
ダニエルは再びミルドレッドを抱きしめて言った。
どうしてそんなことができるのか。
彼の心の中に同じような立場でいたなら、やはり自分も同じことを言っただろうと、ミルドレッドの言葉が思い浮かんだ。
彼はそんなふうにはできなかった。
不思議なことに、ダニエルは自分が持っているものがいかに多いかを知っていた。
彼は裕福で、容姿も整っていては貴族であり、優れた教育を受けて育った。
それにより多くのことを学んだ。
背が高く体格が良いのも、彼の長所であり、何でも素早く簡単に習得するのも、彼の強みだった。
彼が妖精であるという点を除いても、ダニエルはこの地で自分がどれほど有利な立場にいるかを理解していた。
ミルドレッドは、彼が持っているものを持たず、自分が生きていた場所よりも遥かに技術的に遅れた場所に連れてこられたのに、後悔していなかった。
彼女が彼の前で後悔の言葉を口にしたのは、たった一度――かつて彼女が死んだかもしれないという話を聞いたときだけ。
彼は今も、彼女をどこかに連れて行って隠してしまいたいと思っていた。
誰にも彼女を見せず、誰にも彼女を傷つけさせないようにしたかった。
アイリスの点数が最も高いと知られたのは、三人の候補が慈善活動を開始してしばらくしてからのことだった。
ロレナやプリシラの立場では、気分がよくないのも無理はなかった。
だがまだ試験は残っている。
しかも城での試験は本試験ではない、という話を聞いたプリシラは焦り、一日に二度も孤児院や病院を訪れ、熱心に慈善活動を続けていた。
「本試験ではないからといって、点数が認められないというわけではないでしょ。」
ムーア伯爵夫人の言葉に、慈善活動に出かけようとしていたプリシラの足が止まった。
だが彼女が何か行動を起こす前に、彼女の弟マイケルが口を挟んだ。
「知り合いから聞いたんだけど、バンス家の若様と王子様、もうかなり親しい関係らしいよ。」
「まあ、クレイグの娘じゃなくて?」
ムーア伯爵夫人の脳裏に、茶色の髪をしたアイリスが浮かんだ。
その顔立ちは美しいというわけではなかったが、はっきりとした印象ではあった。
「王太子様がバンス家の行事にはすべて出席なさっていると聞きましたわ。」
「バンス家で舞踏会を開いたことがあったかしら?」
「以前、お葬式があったじゃないですか。最後の日に訪問されて、夕食も召し上がったって話を聞いたことがあります。」
ムーア伯爵夫人の視線がプリシラに向けられた。
ほら、そんな話をしたでしょう、という目線に、プリシラはたじろぎながら言った。
「お葬式ですもの。当然お越しになったでしょう。我が家でも葬儀があれば、きっと来られたと思います。」
「ギャラリーにも出席されたそうよ。」
くだらない話を――。
「──そんな話、いつ聞いたの?」
「昨日。バンス家の人たちと会ってきたから。」
「どうしてそんな人たちと会ったの?」
「お母様が会いたがっていたから、ぼくが間を取り持って会わせてあげたんだ。」
プリシラの目元がぴくりと動いた。
昨日、母親が外出していたのは知っていた。
けれどその相手がバンス家だったとは思ってもいなかった。
「マイケル、あなた何を勝手に……」
「勝手になんかしてないよ。お母様が頼んだから手伝っただけだよ。知ってるでしょ。」
侯爵の令嬢であり目を引く美貌を誇るロレナや、王子とすぐに親しくなったアイリスとは違って、プリシラは平凡にすぎなかった。
ムーア伯爵夫人はため息をつきながら体をそっと回した。
人は誰しも与えられた位置があるものだ。
プリシラは予言者が示したような特別な人ではない。
彼女は自分の娘が平凡であることを知っていた。
プリシラはふさわしい家門の男と結婚して、他の人々のように子をもうけ、静かに平凡に生きていくのが一番だった。
今のようにくだらない欲心で王太子妃の試験に出て行き、時間を無駄にすることなどなく。
「アイリス、何してるの?」
同じ視角で、絵を描く道具を持って二階のアトリエへ向かうリリーは、そこで長椅子に横になっているアイリスを見つけた。
まさかどこか具合が悪いの?
こんな姿のアイリスは久しぶりだったので、リリーは一瞬、姉が病気なのかと心配した。
しかし幸いにも、彼女は病気ではなかった。
ただ静かに物思いにふけっていただけだった。
「ただ、いろいろと考えていただけ。」
「ここで? 暑くない?」
そうでなくても気温が上がり、日差しも強くなってきたせいで、リリーも絵を描く場所を変えようとしていたところだった。
アイリスは首だけ動かして、自分の方へ近づいてくるリリーを見ながら、表情一つ変えずに言った。
「誰もいないところで考えたかったの。」
応接室や書斎は誰かが使っているし、彼女の寝室は侍女たちが掃除したり、服を持って出入りしたりしていて、物音が気になっていた。
結局アイリスが選んだのは、暑くても誰もいない場所だった。
「だからって、そこで横になってるの?そのまま倒れちゃうわよ。」
リリーは呆れた顔でアイリスの手を取り、起こした。
私はすでに倒れているというのに。
アイリスはそう思いながらも、素直に妹の力に引かれて立ち上がった。
「何を考えてそんなことしてるの?」
「ただ、このままで十分じゃないかって思ってるだけ。」
このままで十分じゃないかと思うその考えがどんな考えなのか、リリーにはわからなかった。
リリーは道具を取りに来たことも忘れて、アイリスの隣に座った。
「少し前に孤児院に行ってきたじゃない?」
アイリスの言葉にリリーは黙って顎を引いた。
少し前、彼女はまた貴族の令嬢たちを集めて慈善活動をしてきたのだった。
あらかじめ連絡しておいた孤児院に、何が必要かを聞いて、それを届けるというものだ。
実際、貴族の奥方の慈善活動というのは、たいていこのようなものだった。
自分のお金や家計のお金で支援が必要な団体に物資を買って届けたり、孤児や患者と話したり、絵本を読んであげたりもする。
時にはとても熱心な人たちが、カーテンやベッドシーツのようなものを洗濯してあげたりもする。
アイリスがやったことも、そんな最もありふれた活動の一つだった。
「帰る途中、ふと『こんなので本当にいいのかな』って思ったの。」
「こういうことでもいいんじゃない?」
「それが悪いってわけじゃないんだけど……」
アイリスはため息をついた。
彼女が一日に、もしくは一週間かけて届けた食料は与えたことに満足している。
もちろん、それだけでも十分立派なことだとは思う。
当座の必要は満たされるのだから。
でも、その次は? 一週間後は? 一ヶ月後は?
誰かがずっと助けてくれるならいいけど、そうでないならどうすればいい?
「リリー、もしあなたが今すぐ家も食べる物もない状況になったら、一番必要なのは何だと思う?」
アイリスの質問に、リリーの目が大きくなった。
しばらくして、彼女は特に考え込むことなく答えた。
「家と食べ物よ。」
「でも、それが一時的なものだったら?今日一日だけ泊まれて、今日一日分の食べ物しかもらえないとしたら?明日はどこで寝るか、何を食べるか誰にもわからない。じゃあ、どうするの?」
アイリスが何を考えているのか、さっぱりわからなかった。
リリーは黙って姉を見つめながら言った。
「安定して暮らせる家とお金が欲しかったんでしょ。」
「でも食べる物も家もないのに、どうやってそれを手に入れるの?」
リリーの口がつぐまれた。
彼女は一度も家がなかったことも、食べるものがなくて空腹で倒れたこともなかった。
食べ物を節約することはあっても、飢えた経験はなかった。
着飾るドレスはなくても、着るものがなくて人前に出るのがつらいこともなかった。
アイリスはリリーに答えを求めていたわけではない。
けれど、リリーの頭の中では疑問が膨らんでいった。
孤児院や病院に必要な物を届けて寄付するのは立派な行動だ。
けれど、それだけで十分なのだろうか?
城から与えられた課題が慈善活動だったからではなく、アイリスは本当に何かをしたいと思っていたのだ。
彼女はリリーよりも貧しかった頃のことを、少し思い出した。
マーフィー伯爵夫人から食べ物や服を作る布のようなものをもらったことがある。
彼女がもう使わないイヤリングやヘアピンのようなものももらった。
それはありがたいことだった。
でもアイリスは他人の好意に期待することが、ありがたい半面、不安でもあった。
今年の服はなんとかなったけど、来年は?再来年もなんとかなる?
結婚は?
社交界に出てパートナーを見つけるには、彼女に似合うドレスと装飾品が必要だった。
それはどうやって手に入れる?うちにはお金がないのに?
不安でまた不安で、アイリスは神経質になっていった。
人間は余裕がなければ視野が狭くなることを、アイリスはその経験で学んだ。
アシュリーがますます憎らしく思えるほどに。
「私もこの前の集まりに行って、ちょっと考えるようになったの。」
しばらく考えていたリリーが再び口を開いた。
彼女はそこで文字通り新しい世界を見た。
画家たちの集まりは彼女が想像していたほど華やかで立派なものではなかった。
実際、それは当然のことだった。
リリーは裕福ではなかったが、貴族社会に属していて、彼女が出会う人々は皆裕福な貴族だった。
自分が関わる人へのリリーの基準が高いのは当然だった。
ケイシー伯爵夫人の家も悪くはなかった。
格式があるわけではないが、高級感があり清潔で整っていて、時折高価な美術品も見かけた。
しかしそこに招かれていた画家たちは違った。
服装が粗末な人もいれば、洒落た人もいたが、少なくとも貴族の目には彼らは貴族というより下層の者に近かった。
言葉遣いや振る舞いもそうだった。
もちろん、リリーはそうしたことで人を判断するような人ではなかったが努力していた。
彼女が驚いたのは、そんなことよりも絵の道具の値段や家賃が高いという会話のせいだった。
絵の道具が高いというのはなんとなく知っていた。
ダニエルが画材を用意してくれるまでは、彼女も紙に鉛筆で絵を描いていたから。
でも家賃のことは考えたこともなかった。
リリーは生まれてから今まで、自分の家以外で暮らしたことが一度もなかったのだ。
「そこで家賃の話が出てきたんだ。」
「うん。」
アイリスはうなずきながらクッキーをかじった。
彼女も他人の家を借りて住んだことがあるのを知っている。
リリーは膝を抱えて座った。
絵の道具があまりに高くて、お金を借りて買ったという人もいた。
彼女はぼんやりと口を開いた。
「前に私がパーティに行きたくないって言ったらお母様がそうおっしゃったの。人と出会いなさいって。」
その時は理解したつもりだった。
人と出会って、こんな人もあんな人もいるということを知るべきだという意味だと思った。
でも違っていた。
リリーが知らない、まったく異なる世界があった。
「確かに立派な人もいたわ。私が知らない技法だとか、最近どんな画風が人気なのかを把握している人もいた。」
でも彼らも同じような不安を抱えていた。
絵を描くのは楽しい。でも、お金の心配をしないではいられない。
リリーは、母がなぜ「絵でお金を稼げるかどうかを見てみないと」と言ったのかを、はっきりと理解した。
「でもね、そういう人たちもお金の心配をしてたの。いつまで絵を描けるかって。」
「人類がみんな消えてしまうまで続く心配じゃない?」
アイリスの言葉に、リリーはくすっと笑った。
そして言った。
「何してたの?」
その時、アシュリーがプレゼントを持って入ってきて尋ねた。
リリーがくすくす笑いながら言った。
「お金がどれだけあれば人が満足するかって話をしてたの。」
アシュリーの顔には「それは何の話?」という表情が浮かんだ。
彼女はアイリスを見つめ、ばつが悪そうに目をそらしながら小さくため息をついた。
実は、彼女は二人のお姉さんたちの会話を聞いていた。
でもとても真面目な話だったので、簡単には入り込めなかった。
わずか一歳、二歳差のお姉さんたちなのに、あんな真剣な話をしているのが、なぜかとても遠く感じられたのだ。
もともとアイリスはアシュリーよりずっと大人びていて、少し難しく感じられた。
でも、そんなアイリスとリリーが会話するのを何度も見てきたせいか、リリーもいつもより大人っぽく、遠くに感じられた。
「どれくらいお金があれば満足できるの?」
アシュリーの問いにアイリスが黙って考え込んだ。
だがリリーは迷いなく答えた。
「一生絵を描いて生きていけるくらいでいい。」
それは今でも可能じゃない?
アシュリーがそう思っている間に、アイリスが答えた。
「みんなが安定して暮らせるくらいのお金があればいいのに。」
この世界で。
リリーはあきれたように、呆然とした表情で言った。
「それってお金っていうより、奇跡に近いんじゃない?伯爵様に頼んでも無駄だと思う。」
再びアイリスとリリーの顔に笑みが浮かんだ。
アイリスは自分がとても浅はかだったと思った。
しかしアシュリーはアイリスの器がとても大きいと感じた。
「自分はこのままでいいのだろうか。」
アシュリーの表情は曇った。
王子妃になるには十分すぎるアイリスと、画家になるために侯爵の求婚さえ断ったリリー。
二人の姉は夜明けのように早足で前に進んでいくのに、自分だけがぼんやりとその場に取り残されているような気がした。