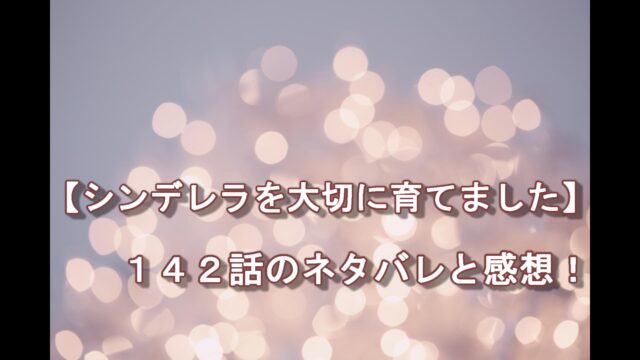こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

209話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 様々な愛
「お訪ねくださったのに、こんなことになってしまい、本当に申し訳ありません。」
二日後、ミルドレッドはリリーと約束通り、フィリップ・ケイシー卿の屋敷を訪ねた。
整えられたベッドの上で、彼は半身を起こしながら客を迎えるしかなかった。
ミルドレッドは全く気にしていなかったが、フィリップはこのような姿で客を迎えることを恥ずかしく思った。
しかし、彼女がなぜ自分を訪ねてきたのか分かっていたので、その訪問を受け入れた。
「いいえ。お怪我をされたと聞いて、当然伺わなければと思いました。」
ミルドレッドはベッドのそばに置かれた椅子に腰掛け、心配そうな表情で言った。
それは客のために召使いに運ばせた椅子だった。
彼女はその横に、客とフィリップの菓子を置けるようにと小さなテーブルも置いた。
「リリーだけでなく、奥様にもこんな姿をお見せするとは。」
「全然恥ずかしい姿ではありませんわ。ご心配なく。」
ミルドレッドの慰めにも、フィリップはなお恥ずかしそうだった。
考えは変わらなかった。
自宅の階段で足を滑らせて転ぶなんて、なんとも気恥ずかしいことだ。
あの階段は、彼が少なくとも数千回は昇り降りしたはずなのだから。
気まずそうなフィリップの様子を見たミルドレッドは、できるだけ早く用件だけを聞いて立ち去ろうと心に決めた。
だがその前に、フィリップがリリーの様子を尋ねてきた。
「リリーは元気にしていますか?」
「ええ。昨日も例の茶店に座ってスケッチをしていましたよ。」
「クロッキーですか?」
動く被写体を素早く捉えて描くスケッチのことだ。
多くの画家がカフェや競馬場、舞台裏でクロッキーを行う。
そういうことだったのか、と納得したミルドレッドは、フィリップがあっさりとリリーの行動を言い当てたことに、何とも言えない気持ちになり、ため息をついた。
そのとき、召使いがテーブルに果物を運んできた。
ミルドレッドが部屋を出て行った。
「リリーのことでいらしたのですね?」
遺産の件だろう。
フィリップは、ミルドレッドが先に切り出すのを負担に思っているだろうと察し、自分から口を開いた。
彼の問いに、彼女は感謝の表情を浮かべ、ゆっくりと言葉を選んで答えた。
「ええ、リリーのことです。ご領主様があの子に素晴らしい贈り物をなさると伺いました。」
フィリップの顔に笑みが浮かんだ。
年齢差が大きいとはいえ、フィリップは未婚だ。
結婚適齢期の娘を持つ母親が心配するのは当然だった。
フィリップもその心配を察し、すぐに言葉を続けた。
「はい、その通りです。奥様はリリーの母君ですから、私が何を考えているのか気がかりでお越しになったお気持ちも理解できます。」
「ケイシー卿、本当に素晴らしいご提案に感謝いたします。でも、リリーがそのような大層な贈り物を—」
受け取ってもいいのか分かりません。」
「もちろん受け取って構いませんよ。ええ、ぜひ。私はリリーを……」
リリーを?
フィリップが言葉を濁すと、ミルドレッドは少し困ったような表情を浮かべた。
彼はリリーの母親の前でこんなことを言っていいものかと迷っているようだった。
しかし、彼がリリーを異性として見ていると誤解されるのはもっと避けたい。
彼にとってリリーは、やっと幼さを脱したばかりの少女に過ぎなかった。
「リリーの母上の前で言うのは少々はばかられますが、私は彼女を娘のように思っています。」
もし自分に娘がいたらこんな感じなのだろう――そう思えるほど、フィリップはリリーに好感を抱いていた。
その時ふと、兄のチャールズが剣に刻まれた細工を見せてくれた時のことがよみがえった。
あの時の喜びようと同じように、彼は酒に酔って訪ねてきたあの日を思い出したのだった。
くだらないことで喜ぶと内心あきれていたが、今はわかる。
もし自分に娘がいて、その娘がリリーだったなら、酒に酔って兄を訪ね、リリーがどれほど素晴らしいか夜通し語っていたに違いない。
「過分に可愛がっていただいて、何と申し上げればよいか分かりません。」
「いえ、リリーを見ると、自分の幼い頃を思い出すんです。」
「そうですか?」
全く違わないだろうか?
ミルドレッドは笑みを浮かべた。
家庭環境も違い、性格も少し異なるはずだ。
いや、性格の一部は似ているのかもしれない。
彼女は、かつてカイルが女性だと明かした時に、フィリップが慌てて駆けつけた様子を思い出した。
リリーにも、少しそんな火花のような気質がある。二人とも芯が強いのだ。
「実は、リリーが羨ましいときもあるんです。私はリリーの—」
「自分がリリーの年頃に、もし彼女のように行動していたらどうだっただろう?」
無理なことだと分かっていながらも、フィリップはそう口にした。
もし彼が18歳で画家になると主張し続けていたなら、両親は間違いなく彼をどこかの修道院に放り込んだだろう。
だが、彼はリリーもまた、自分と状況こそ違えど同じように大変な立場にあることを理解していた。
リリーが画材を買うだけでも、画商や他の画家たちから無意味な忠告を浴びるに違いない。
社交界で噂の種にされるのは、言うまでもない。
フィリップは、そんな状況で行動するリリーの勇気、そして彼女を支えたミルドレッドの強さを羨ましく思った。
「卿とリリーでは、事情が違いますわ。」
ミルドレッドはフィリップを慰めるためにそう言った。
彼女はケイシー侯爵夫人のことを思い浮かべていた。
どれほどダグラスがリリーのために尽力してきたとしても――それでも、その家の人々はリリーを歓迎している。
その雰囲気は、フィリップが幼い頃よりもむしろ良いくらいだろう。
「ええ、状況は違います。でも、そこに私のお金が少しでも加われば、リリーの助けになるのではと思ったのです。」
「ケイシー卿、卿の存在がどれほど私とリリーの助けになっているか、ご存じないでしょう。」
ミルドレッドはため息をついて言った。これは本心だ。
彼女は絵画の価値や、その世界の事情など知らない。
絵の道具が高価だという程度の知識しか持っていない。
「ですが、その助けが経済的な部分にまで及ぶべきかは分かりません。私は卿とリリーの友情を支持しますが、卿の提案がリリーとの友情を壊すのではと心配なのです。」
もしかすると、フィリップは今のところ、リリーを理解してくれる唯一の人物なのかもしれない。
それどころか、確かに唯一無二の存在だった。
ミルドレッドは、リリーが自分と共感し、理解し合える仲間を失わないことを願っていた。
「バンス夫人、私は少し余裕のある方ですし、子どももおりません。」
フィリップは沈んだ表情でそう言い、悲しげにミルドレッドの目元を見ながら続けた。
「正直に言えば、リリーを養女に迎えたい気持ちがあります。ですが、それはリリーにも、そしてあなたにも失礼なことでしょう。」
他人が大事に育てている娘を養女にと申し出るのは、確かに無礼なことだ。
もしミルドレッドが経済的に困窮していたり、リリーを他の家に養女として出したいと考えていたなら話は別だが、今の彼女にはそんな気持ちはなかった。
フィリップは、ミルドレッドが不快に思っていないことを確かめ、ひと息ついてから、再び口を開いた。
「そうですね、私が死んだ後、私のお金がリリーの助けになるのなら嬉しいです。もちろん、そのときにリリーの助けになるほどのお金が残っているかは、その時になってみないと分かりませんが。」
フィリップの冗談めいた言葉に、ミルドレッドの顔に微笑みが浮かんだ。
しかし彼女はすぐに真剣な口調で尋ねた。
「でも卿、それを侯爵家でもお聞きになりましたか? 卿には立派なご親族がいらっしゃいますでしょう。」
「立派なご親族」と言われた瞬間、フィリップは思わず複雑な表情を浮かべた。
そういえば少し前に、ダグラスが相談を持ちかけてきたことがあった。
母がリリーを気に入るかどうか分からない、という内容だった。
もちろん、ケイシー侯爵夫人がリリーを好もうが好まなかろうが、大きな問題ではない。
だが、リリーが画家になることを両親が理解してくれるかどうかが心配だと言っていた。
彼は当然、ダグラスがその件について両親の理解を得ているものと思っていた。
あの息苦しい青年――少し打ち解けた後、フィリップは義兄夫婦に会って、ダグラスを助けると約束した。
もちろん、その後のアクシデントでダグラスを助ける話はしばらく延期となったが。
「ケイシー侯爵は裕福ですから。ダグラスは私のお金でなくても心配いらないでしょう。兄や義姉が私のお金を欲しがることもないと思います。」
「それは分からないわ。」
ミルドレッドはそう言いかけて、口をつぐんだ。
フィリップの財産は、彼が独立するときに、亡くなった先代ケイシー侯爵が与えた資金を元手に自ら築き上げたものだ。
すべてを食いつぶすような連中がいることを思えば、その財産をきちんと維持しているだけでも大したものだ。
フィリップはそれをさらに何倍にも増やしたのだからなおさら立派だが、それを他人に譲るとなれば、侯爵としてはそう簡単に許すはずがない。
どうなるかは分からないことだ。
フィリップは依然として心配そうなミルドレッドの表情を見て、杯を持ち上げながら言った。
「もし兄上ご夫妻が私の遺産を望まれるなら、三等分すればいいのです。」
「三等分ですって?」
「はい。財産を三等分してリリーとダグラスに分け、残ったお金は画家のための財団を作るつもりです。」
こんな考えをするようになったのも、ひとえにミルドレッドのおかげだ。
フィリップは彼女を見つめながら微笑んだ。
カイルがカイルラであること、そして彼女が病で一人病院で亡くなったことを、彼はミルドレッドのおかげで知ったのだ。
フィリップは、あれほど才能ある画家がそんなにもみじめな人生の末に亡くなったことに胸を痛めた。
もしミルドレッドが許さなかったなら、リリーも同じような末路をたどるかもしれない――その事実に、彼の心は冷たく締めつけられた。
「ですが、三等分まではしないつもりです。財産の半分を使って財団を設立し、リリーを代表に据えるのも悪くない方法でしょう。」
フィリップがそこまで考えているとは思わず、ミルドレッドはしばし彼を見つめ、それから口を開いた。
「リリーがケイシー卿の甥と結婚してもいいけれど、お金目当ての結婚にはなってほしくないとおっしゃっていましたよね。」
フィリップの口元にも微笑が浮かんだ。
紅茶を口にしてから再びミルドレッドを見て、こう言った。
「私がなぜ結婚を諦めたか、ご存じですか?」
「妖精の祝福のせいだと聞いていますけれど。」
「いいえ。妖精の加護があっても、相手さえ選べば結婚は可能です。貴族は家名を守るためにお金が必要なのです。」
どこにでもお金を必要とする人間はいるものだ。
没落した貴族の令嬢が富豪と結婚する話は珍しくない。
貴族社会では、それはさほど非難されることでも、珍しいことでもなかった。
「たぶん三度目の婚約だったと思います。二度の婚約破棄のあと、両親は私のために新しい花婿を選んだのです。」
フィリップはそう言って苦笑した。
彼はとても貧しい、没落貴族の娘だった。
ある富豪の二番目の妻になるか、家庭教師になるかという選択肢しかなかった令嬢が、ケイシー侯爵家の次男と婚約したのは、ほとんど奇跡に近い幸運だった。
「婚約から結婚まで、かなりとんとん拍子で進んだ記憶があります。」
最初の一か月は、過去二度の婚約破棄のようにまた解消されるのではと不安で、食事ものどを通らなかった。
しかし月日が経つにつれ、フィリップも次第に落ち着きを取り戻していった。
「結婚式を一週間後に控えた日のことでした。そのときまで婚約者は何の怪しい素振りも見せなかったので、私も安心していたのです。実は、妖精の加護がもう切れてしまったのではないかとまで思っていました。」
妖精の祝福も呪いも、そう簡単には解けない。
今思えば馬鹿げているが、当時のフィリップは本気でそう考えていたのだ。
彼は微笑み、そして深く息をついて続けた。
「婚約者と食事をしていたとき、私の友人が――いや、親しい友人ではありませんでしたが、アカデミーの同期だったのです――」
久々に会ったその友人は、フィリップに挨拶をしようとテーブルに近づいてきた。
そして友人と婚約者の視線が交わった瞬間、フィリップは二人の間に何かを感じ取った。
男女が恋に落ちる瞬間を目撃した。
「それは、言葉では説明できない光景でした。二人の世界から、お互い以外のすべてが消えてしまうのが、私の目にも見えたんです。」
いつもは静かで無表情だと思っていた婚約者の顔がぱっと明るくなった。
その瞳が輝くのを見たフィリップは、自分の友人もまったく同じ表情をしていることに気づいた。
「もちろん、友人も婚約者も私に隠れて会ったりはしていません。それは確かです。」
それがかえってフィリップを傷つけた。
むしろ隠れて会っていたのなら、まだ救いがあっただろう。
真実の愛というものは、遠慮も恥じらいも知らないのかと。
しかし、婚約者と友人はフィリップの心を読んだかのように、二人の関係を潔く清らかに保っていた。
真実の愛とはそういうものだ。
その愛が汚されることを恐れるものなのだ。
「私の人生に存在しないはずの絵を描くこと以外に、もうひとつだけ認めざるを得ないことがありました。」
婚約者は彼にとって良い伴侶になろうと努め、友人は自分と会わないようにしていた。
しかし、婚約者と友人のぎこちない様子を目にしたフィリップは、ついに両親に婚約破棄を告げることにした。
「私はリリーがダグラスと結婚してくれればと願っています。相手がダグラスでないなら、彼女が望むまま一人で絵を描きながら幸せに暮らしてほしい。その幸せをお金が邪魔することのないようにと願っています。」
その言葉の意味を悟ったミルドレッドは、ためらいがちに席を立ち、慎重にフィリップを抱き寄せた。
「あなたは本当に素晴らしい人です、ケイシー卿。」
「フィリップと呼んでください。」
リリーを直接守れないなら、せめて彼女の従兄として――。
心に留めておきたかった。
そしてフィリップは、リリーが画家になることに寛大だったミルドレッドに好感を抱いた。
それは恋愛感情ではなく、友人として。
仲の良いバンス家の人々を見ると、自分もその家族の一員になりたいと思った。
バンス家の人々にとっておじさんのような存在になるのも悪くない。
今のようにリリーが定期的に遊びに来て、絵の話をできるのなら。