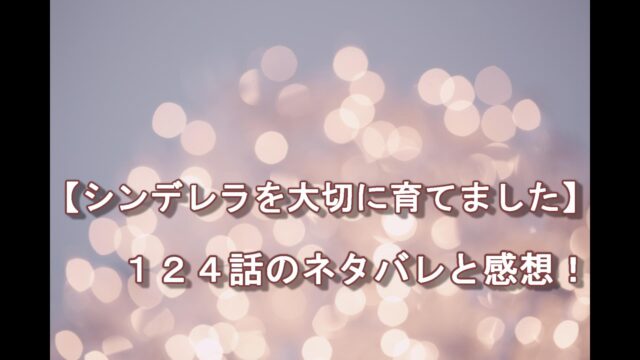こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

216話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 試験中断
「中断ですって?」
前回の試験以降、城からはアイリスを呼び出すことがなかった。
何があったのだろう。
アイリスだけでなく、ロレナも呼ばれなかったと聞き、少し安心していたのだが、今日、城から戻ったダニエルが深刻な表情で、候補者試験が一時中断されたという知らせを伝えてきた。
「まもなく召集がかかるでしょう。」
ダニエルは暗い表情でそう言い、隣に座るアイリスとリリーを振り返った。
彼はアシュリーにも視線を向けてから口を開いた。
「南部地方が伝染病の被害を受けているそうです。その被害が次第に広がっていると。」
すぐに意味が分かった。私は暗い表情で顎を引いた。
この国は以前、伝染病によって大きな被害を受けたことがある。
アイリスとリリーの父親も、アシュリーの母親も、伝染病で亡くなった。
皆が伝染病に対して恐怖心を抱いている。
「奥様。」
不安な表情を浮かべる子どもたちを抱きしめていると、ジムが応接室のドアをノックして入ってきて、私を呼んだ。
そして、今まさに話していた内容と関連する知らせを持ってきた。
「城から伝令が参りました。」
伝令が伝えた話は、先にダニエルが私たちに知らせた内容とほとんど同じだった。
国が伝染病で苦しんでいるこの状況で、王太子妃候補の試験を続けるのは適切ではないという判断から、一時的に中断することになったと聞き、私も思わず尋ねてしまった。
「では、まだ試験は残っているということですか?伝染病が収束したら再開されるんですか?」
「それは、状況が落ち着いてから改めて決定されるでしょう。」
意味は理解できた。
頭の中がひやりとした。
城が試験を中断したのは、国が混乱している今は慎重であるべきだという理由もあるだろうが、伝染病で誰が命を落とすか分からないからでもあるはずだ。
もし決まった王太子妃が婚約期間中に伝染病で命を落とすような事態になれば、それこそ城としては避けたい状況だろう。
「分かりました。」
「厨房、これからは加熱していない食べ物は置かないでください。この家に住む人は全員、必ず加熱した食べ物だけを食べるようにしなければなりません。」
私はその場で急いで台所へ駆け込んだ。
汗を流しながらジャムを作っていたコックが、きょとんとした顔で聞いてきた。
「加熱ですか?」
「牛乳、生クリーム、氷、すべて禁止です。」
「アイスクリームもですか?」
何事かと後からついてきたアシュリーが、驚きの声を上げて尋ねた。当然だ。私は彼女を一瞥してから、再びコックに言った。
「アイスクリームも禁止です。水も必ず沸騰させて使ってください。調理の際は必ず手を――」
そこまで言ったところで、ダニエルはきゅっと口を閉じた。
彼は自分の仕事に誇りを持つ優れた料理人だ。
そんな彼に、料理中に手を洗えと注意するのは失礼なことだった。
「ただの杞憂ではありません。」
私は振り返って、私の後についてきた子どもたちとダニエルに向かってそう言った。
そして、何かを察して後をついてきたジムに、他の使用人たちも呼んでくるよう頼んだ。
「伝染病が広がっているそうです。誰も病気にならないことを願います。ですから、今この瞬間から必ず守らなければならない規則を設けます。」
集まった使用人たちは、「伝染病」という言葉に表情を引き締めた。
アイリスとリリーの父、そしてアシュリーの母を奪ったあの伝染病と同じものなのか、それとも別の病気なのかは分からない。
同じ病気なら、幸運にもその時期を乗り越えたことになるが、別の病気であれば危険だ。
「みんな、外から家に入ったらすぐに石鹸で手を洗ってください。面倒だからといって大雑把に、さっと洗うのはダメです。」
そう言って、私は人々に正しい手の洗い方を実演して見せた。
指1本1本、爪の先まで、三十秒ほど丁寧にこすり洗いしなければならない。
もちろん、三十秒を計るのは難しいので、心の中で三十まで数えるようにと言ったが。
そして二日後、我が家の裏庭でなかなかの騒ぎがあった。
「魔女だという噂が広まりますよ。」
朝食を終えるとすぐ、裏庭に干してある大きな洗濯物を眺めながら、私はダニエルに挨拶代わりに言った。
散歩から帰ってきたのか、庭の奥から歩いてきた彼はにやりと笑い、私を見てから片目をすっとつぶった。
「魔女ですか?」
「大きな鍋を三つも吊るしてあるじゃないですか?」
台所では水がぐらぐらと煮立っていた。
飲み水、手洗い用の水、洗濯用の水だ。
そこまで気が回らなかったが、ジムがうまく準備してくれていた。
私は、人が一人すっぽり入れるほどの大鍋が三つも吊るされているのを、妙に感心しながら眺めていた。
「ああ、鍋を吊るしたんですね?」
ダニエルはやっと鍋の存在に気づいたような顔をした。
冗談だろう?私はあきれて言った。
「こんなに大きいのに気づかなかったなんて、まさかですよね?」
「見えませんでした。」
そう言いながら、ダニエルは私の手を取り、その甲に口づけをした。
私は彼が何を言おうとしているのか分からず、怪訝な顔をしていたが、すぐに笑ってしまった。
私を見ていて洗濯物に気づかなかったということらしい。
まったく、どうでもいい冗談をうまく気分よく言える才能があるのだから。
「石鹸のほうはどうです?」
私の質問に、ダニエルの眉間にしわが寄った。
何か事情があるような表情に、私はさらに尋ねた。
「他の大陸から石鹸を輸入するって言ってましたよね?あれはどうなったんですか?」
「ええ、今届いているところです。まだ……」
そこまで言った彼の視線は空へと向かった。
どれくらいかかるか計算しているようだ。
「1週間くらいはかかるでしょう。」
「じゃあ1週間後には輸入した石鹸が届くということですね?」
「ええ。でも全国に流通させるには少し時間がかかりますし、それにそんなに大量でもありません。」
一週間もあれば全部売れてしまうだろうという話に、私は顔をしかめた。
ビヌの木が再び育つまでにどれくらいかかるのだろう?
永遠というわけではないにせよ、今年の収穫量は例年に比べてかなり少ないと聞いていた。
そうなると、ビヌの木が育つまでの不足分をどこかで補わなければならない。
その補充を果たして私の工房でできるだろうか。
私は出勤の準備をしている工房の職人たちのことを思い浮かべた。
人を増やせば生産量をもっと上げられるだろうか。
働き手が見つかるかは分からないけれど。
「ミルドレッド。」
ぐらぐら煮立つ大鍋をぼんやり眺めながら考え込んでいると、ダニエルが私の名前を呼んだ。
顔を上げると、彼は真剣な表情で尋ねた。
「必要なものがあれば、何でも言ってください。」
「ええ、世界平和?」
ダニエルの片眉がぴくりと上がった。
彼は真剣な表情を浮かべると、しばらくして本気で考え込み始めた。
まさか、本当に世界平和をどうやって達成するか悩んでいるの?
私は驚いて、思わず彼の腕をつかみながら言った。
「冗談ですよ。」
「そうですか?」
「そんなことできるはずないじゃないですか。」
「でも、あなたが望むことなら叶えますよ。」
本気で言ってるの?
私は呆れてダニエルをじっと見つめた。
不可能なことでも、私が望めば叶えるっていうの?
ふと、彼の腕をつかんでいる自分の手が目に入った。
つい握ってしまった指先も。
指輪は依然として透き通るように輝いていた。
まあ、あれを星だなんて誰も思わないだろう。
私はため息をつきながら言った。
「世界平和なんてものは特に必要ないですよ。だから悩まなくても大丈夫です。」
「じゃあ、何をすればいいですか?」
さて――私は一瞬彼を見つめた。
私の手の中で、彼のしっかりとした腕の感触が伝わってくる。
長く引き締まった腕が私の手を握ったまま、緊張を解いているのを感じるのは、不思議な気分だった。
まるで巨大な獅子が、全身と心を私に預けているような感覚に、私は彼の腰に腕を回し、その胸に頭をあずけた。
「妖精病みたいなものにはかからないですよね?」
「分かりません。」
ダニエルはそう答えると、まるで私が何を言いたいのか察したかのように、小さく息を吐いた。
そして私を抱き寄せ、穏やかに言った。
「世界から病気をなくすことができるでしょうか?」
「願い事のようですね?」
私の言葉に、ダニエルは小さくため息をついた。
それが不可能なことは、彼も私もわかっている。
そして、私が望んでいるのはそんなことではない。
私は腕を伸ばし、彼の胸に軽くもたれて言った。
「あなたが病気にならないといいなと思って。」
ダニエルの片眉が上がった。
信じられないという表情で彼は尋ねた。
「僕のことですか?」
「この家で一番活動的なのはあなたでしょう?だから病気にかかる可能性も一番高いんです。」
私や子どもたちは限られた人としか会わないが、ダニエルは仕事や貿易の関係で他の地域の人たちとも会わざるを得ない。
もともと彼は体力があり頑丈なうえに、几帳面だからこそ――だから、彼は自分が病気になるはずがないという自信を持っているのかもしれない。
私は再びダニエルの胸に頬を寄せ、言った。
「あなたが病気にならなければいいのに。」
私の願いが意外だったのか、ダニエルの体が一瞬こわばったが、すぐにほぐれた。
彼は息を吐き、私を抱き寄せて答えた。
「分かりました。何があっても病気にはなりません。」
「そんなこと、できるんですか?」
「あなたが望むことなら、何だってしなきゃいけないでしょう。」
まったくもう。私は呆れて笑った。
ダニエルが妖精であることは知っているけれど、だからといって何でもできるわけじゃないはずだ。
それでも、私の気持ちを和らげようとする彼の行動n気分が良くなった私は、つま先立ちになって素早く彼の唇に口づけをした。
「ミルドレッド。」
当然そのままキスが続くと思っていたのに、彼は真剣な表情で私の名を呼んだ。
私は彼の腰に腕を回したまま、なぜそんな顔をするのかと見上げた。
「僕は今すぐでもあなたと結婚したい。でも、あなたは違うんでしょう?」
え?
私はダニエルの言葉を一瞬理解できず、呆然と彼を見つめた。
断ったっていうこと?
少しして、彼の言葉の意味がじわじわと頭にしみこんできた。
ダニエルは私を見つめながら口を開いた。
「だから、代わりという言い方はおかしいけれど、もしあなたがよければ、子どもたちには僕たちが婚約したと伝えたいんです。」
子どもたちに私たちが婚約したことを知らせたい、と。
「え?子どもたちは知らないの?」
私は首をかしげて尋ねた。
「子どもたち、知らないでしょうか?」
私の手には、見たことのない指輪がはめられていた。
子どもたちも気づいているんじゃないかな?と思ったけれど、ダニエルは別の考えだったらしい。
彼は微笑んで言った。
「でも、私たちがはっきりと言わない限り、それはまた別の問題です。できれば、周りの人たちにも私たちの婚約を知らせたいですね。」
周り?
頭の中にサンドラやゲリ、そして王妃まで浮かんだ。
私が一瞬考え込むと、ダニエルがすかさず続けた。
「それか、婚姻届を先に出してしまってもいいですよ。結婚式は後からでもできますし。」
婚姻届?
つまり、それって私と夫婦になりたいってこと?
私の名字がミルドレッド・ウォルフォードになるってことだ。
そして結婚を前提にしているという意味でもあった。
その瞬間、私も知らずに顔が熱くなった。
私の顔が赤く染まったのを見たダニエルは片眉を上げ、すぐに笑みを浮かべてからかうように言った。
「もちろん、奥様が望まれないなら寝室も別にしますよ。」
からかわれている。私はわざと「奥様」という言葉の意図を探ろうと彼を見上げた。
こんなことで私が恥ずかしがると思っているなら、その通りだ。
でも私はそれを隠して言った。
「婚約の報告からにしましょう。」