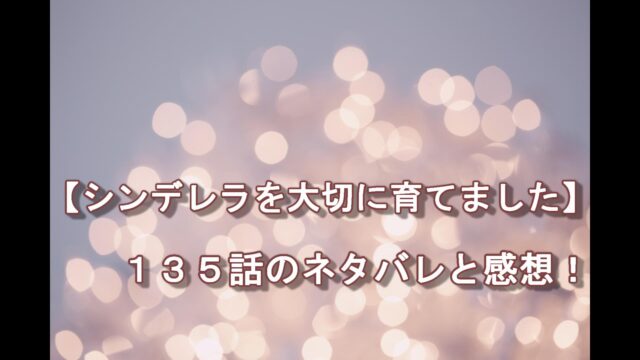こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

217話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 試験中断②
数日後、私とダニエルは人々に婚約を知らせる手紙を送った、王太妃にも。
ダニエルは自ら出向いて知らせることにし、私はサンドラとゲリを招待した。
「婚約だって?」
婚約のことを伝えると、ゲリは食べ物を口に運びかけて止まり、問い返した。
そして少し戸惑った表情でさらに聞いてきた。
「今まで婚約してなかったの?」
「ゲリ。」
すかさずサンドラの肘がゲリの脇腹に突き刺さる。
私はアシュリーとリリがその様子を見て笑いをこらえ、唇をかみしめるのを確認してから、落ち着いて答えた。
「もう何か月も前からです。そろそろみんなに知らせたほうがいいかなって話していたところなんです。」
「何か月だって?うわっ!」
今度はサンドラがゲリの足を蹴ったようだった。
ゲリは顔をしかめながら、腕をテーブルの下に下ろすのが見えた。
サンドラには取り柄が多いから、多少嫌味を言われても全く痛くもかゆくもない気がする。
「よかったじゃない、よかったわ、ミル。」
夫のことなどお構いなしに、サンドラは私の婚約を祝ってくれた。
こんな空気の読めない義姉を今まで面倒を見てくれて、むしろ感謝したいくらいだ。
アシュリーはついに我慢できず、テーブル越しに顔を近づけてじろじろ見始めた。
私はアイリスに目配せして、アシュリーを止めるよう合図し、そのあと挨拶をした。
「ありがとう。ウィルフォード男爵がいなければ、人々に知らせようなんて思わなかったと思います。」
「まあ、今は状況がちょっとあれだしね。結婚は、落ち着いたらするつもりなの?」
「分かりません。アイリスの件もありますし。」
伝染病が収束すれば、王太子妃候補の試験も再開されるはずだから、アイリスのことが先だ。
私がふと見ると、アシュリーをからかっていたアイリスが顔を赤らめて背筋を伸ばした。
サンドラは、私とアイリスを見比べて状況を察したように眉をひそめたが、ゲリはそうではなかった。
「状況が落ち着くまで待つだと?さっさとやっちまえよ。」
「ゲリ。」
「初婚でもないんだし、盛大に式を挙げる必要も……」
「ゲリ!」
ついに我慢できなくなったサンドラがゲリの腕を叩くと、ゲリの口はやっと閉じられた。
私は、子どもたちが目を丸くしてゲリを見ているのを確認し、ほっと息をついた。
ゲリは悪い人間ではない。
だが、考えが短絡的で、口にする言葉もぶっきらぼうになる欠点がある。
それをいつもサンドラがうまく補ってくれるのは、本当にありがたいことだった。
「アイリス、食べ終わったらデザートはあなたたちの部屋に持って行って食べる?」
私の言葉に、アイリスは困ったような顔でうなずいた。
リリーとアシュリーは不満げな表情でゲリーを見たが、幸い何も言わなかった。
子どもたちが席を立ったとき、ようやくゲリーは自分の失言に気づいたらしい。
顔が赤くなっている。
まるでソーセージみたいだ。
特に腹が立つわけではない。
ゲリーのそういう性格には慣れている。
でも子どもたちの前で婚約のことを持ち出すのは、少しやりすぎだ。
「悪かった、ミル。」
ゲリーは噛みしめたソーセージのような顔で謝ってきた。
私は落ち着いた表情で答えた。
「大丈夫ですよ、お兄さま。でも子どもたちの前では気をつけてください。」
ゲリの顔に「しまった」という表情が浮かんだ。
自分が恥ずかしいことをしたわけではないが、どうやら失言だったと気づいたらしい。
私は小さくため息をついた。
彼は、申し訳なさそうな表情を浮かべて口を開いた。
「気をつけるよ。二度とこんなことはしない。」
そう願いたい。
私が何も言わないでいると、サンドラが私の様子をうかがいながら場を和ませようとした。
「そうですよ。もしアイリスが王子妃になったら、あなた、本当に気をつけなきゃいけませんからね。」
「そうだな、そうだ。まったくその通りだ。アイリスが王子妃になったら、本当に注意しないとな。」
ゲリにそれができるのか。
私は少し疑わしい気持ちでゲリを見やったが、大丈夫だろう。
少なくとも彼は、どこかの誰かのように事業欲にかられて一家を食いつぶすようなことはしない。
口を滑らすことはあるが、それ以上に人の心を奪うようなこともなかった。
私は、万が一にも彼がダニエルに失言をしてしまわないかだけを心配していた。
余計な誤解を招きたくなくて、私は慌てて言った。
「ウィルフォード卿は結婚したいとおっしゃいました。婚約を知らせるだけにしたのは、私の意見です。」
ゲリーの顔に「なぜそんなことを?」という表情が浮かんだが、何も言わなかった。
私はため息をついて続けた。
「もしそうでなければ、人々に知らせようなんて思わなかったのも事実です。あの方は、結婚するか、人々に婚約を知らせたいと先におっしゃったんです。」
「おお。」
驚いたことに、サンドラの顔にも感動したような表情が浮かんだ。
なぜ?私が困惑した顔をすると、彼女は手を差し出し、私の手を握って言った。
「本当に思いやりのある人だわ。子どもたちのためにそんな提案をしてくれるなんて。本当にいい人に出会ったのね。そうでしょう、ゲリー?」
私は一瞬、サンドラが何を言っているのか分からず、ぼんやりと彼女を見つめた。
だがすぐに、彼女の言葉の意味を悟った。
サンドラの言う通りだ。
この時点で婚約を公表するのは、私のためではなく子どもたちのためでもあった。
「そうですね。」
私はため息をつき、サンドラの手を握った。
伝染病が流行しており、私の子どもたちはそれぞれ父親や母親を病で亡くしていた。
だから、私まで病に倒れるかもしれないという恐れを抱かずにいるのは難しかった。
もし私が死んでしまえば、子どもたちは完全に孤児になってしまう。
だが今、ここでダニエルと結婚するか、あるいは婚約を公表すれば、彼には私の子どもたちを守る義務が生じる。
もちろん、私もダニエルも、私が死ぬことを前提に婚約を公表するわけではない。
だが子どもたちにとっても、万が一私がいなくなったとしても、ダニエルという拠り所が残っているという安心感を与えられるだろう。
ダニエルへの愛情が胸に溢れた。
本当に素晴らしい人だ。
あの提案は純粋に私のため、そして私の子どもたちのためにしてくれたのだ。
「デザートです。」
しばし感動的な時間が流れた後、ジミーが私たちのもとにデザートとお茶を運んできた。
新しいデザートを作ってみたらしい。
作るのは簡単だが、手間はかなりかかるものだ。
「クレープケーキです。」
薄いクレープをクリームと重ねて作ったものだ。
上にまぶした砂糖のおかげで表面がきらきらと輝いている。
手間はかかるが、一枚の大きなケーキを作って切り分けて売れば、むしろ家庭で作るよりもレストランで販売する方が効率的かもしれない。
驚くことに、グレープケーキはゲリーよりもサンドラの好みに合ったようだ。
サンドラは、普通に食べてもいいが、層ごとに剥がして食べてもいいという私の説明に目を輝かせ、ケーキを食べ始めた。
「それにしても、ビヌを無料で分けてあげるって?」
あまり甘くない味が気に入らなかったのか、ゲリーは訝しげに尋ねた。
もちろんそう言いながらも、彼の手は相変わらずケーキに伸びていた。
「ええ、何人かの人たちにだけです。」
「何人か、ってほどでもないだろう。だったらもう売ればいいのに、なぜそんなことをするのか分からないな。」
「売る分はちゃんと売ってますよ。」
本当に売る分は、きちんと代金をもらっている。
むしろ、当初売るつもりだった値段よりもずっと高く売っているので、絶対に損はしていない。
しかしゲリーは、依然として納得いかない表情だった。
ケーキをもぐもぐと食べたあと、彼はこう言った。
「簡単に与えれば、その価値を分からなくなるものだ。」
「皆が苦しい状況で、必要以上に欲を出せば、いずれ代償が返ってくるものでもありますし。」
人は忘れない。
自分が困っているときに助けてくれた人を、むしろさらに善良な人として覚えている。
そして、当人が何もしていなくても、石を投げる機会があれば、ためらわずに投げるものだ。
他人に愛されるためにわざわざ努力する必要はないが、嫌われないための努力は必要だ。
「ミル、ゲリーがご主人様に口を挟んだことは確かだけど、あの人の言っていることは間違っていないわ。」
デザートを食べ終えたあと、馬車に乗り込みながらサンドラが言った。
ん?私はゲリーが何に口を挟んだのか、頭の中で思い返した。
彼はいつもご主人様に口を挟んでくる。
それは彼が私の義兄だからなのだろう。
それが私の人生に口を出す権利を与えたわけではないが、ゲリーは年上で、結婚していない貴族女性の暮らしが限られたこの国の特性上、自分にも口を出せると思っているのだろう。
慣れたことではあるし、腹が立つわけでもない。
しかし、だからといって私が拒否できないわけではない。
私は、望まない干渉を拒む権利がある。
「どういう意味ですか?」
私はサンドラの手を取りながら尋ねた。
すでに作ってあったグレープケーキを机の端に押しやっていた。
サンドラは、ゲリーが執事と話しているのを見て、私の耳元に小さな声でささやいた。
「ある階層の人たちにはビヌを高く売りながら、別の階層の人たちには無料で分けてあげているってこと、ほかの人から見たらどう映るか考えたことある?」
サンドラが何を言いたいのか、私は理解した。
貴族たちが内心面白くないと思っている、ということだ。
彼らは高価なビーヌを好きなだけ買える財力を持っているにもかかわらず。
もちろん、彼らが不満に思っているのは、自分たちがビーヌを高値で買っていることではない。
私はサンドラに倣って声を落として言った。
「特にクレイグ侯爵がそうでしょうね。」
アイリスとロレナが王太子妃候補として審査を受けていたが中断され、私が人々の支持を得ている今、クレイグ侯爵は面白くないはずだ。
サンドラは私の返事に安堵のため息をつき、安心したような表情を浮かべた。
そして私の手をしっかり握って言った。
「クレイグ侯爵がただ黙って見ているだけじゃないって話もあるわ。」
私は理解しているという表情を見せた。
しかし、彼にできることは限られている。
国王に話すだけのことだ。
それに、たとえ国王に話すとしても、一体何と言うつもりだ?
試験は中止になったが、私たちは今も慈善活動をしている、と?
慈善活動なんて、貴族の務めに近いことだ。
そんなの、どうと言うことはない。
しかし、一つだけ気がかりな点はあった。
私は立ち去ろうとするサンドラをもう一度抱き寄せ、言った。
「心配しないで、サン。私にも考えがあるんだ。」
貴族たちが弱みを握ろうとすることは分かっていた。
どこにでも、そういうことを仕掛けてくる人間はいる。
たとえそれが自分に直接的な害を与えるわけではなくても、ただ気に入らないという理由だけで、他人に対する中傷や噂を広める人もいるのだ。
「必要なことがあれば、いつでも言って。」
サンドラはそう言って、ゲリと一緒に馬車に乗って去っていった。
マーフィ伯爵夫妻のうち、少なくとも一人は信頼できる人物で本当に良かった。
私はそのまま二階の書斎に上がり、カーシ夫人のクリノリン事業を検討した。
カーシ夫人のアイデアをもとに、ダビナがデザインを担当し、クリノリン製作工房に制作を依頼したのだ。
試作品が出来上がり、私とカーシ夫人で使ってみたところ、以前のクリノリンよりはるかに使いやすかった。
「私をお探しだったんですか?」
王太后と会って戻ったダニエルは、ジムから伝言を受け取ったのか、家に着くなり書斎にやって来た。
私は席を立ち、彼を迎えながら尋ねた。
「王太后殿下はいかがでしたか?」
「いつも通りです。」
つまり穏やかだったということだ。
私はくすっと笑い、うなずいた。
「手紙をご覧になりましたか?」
私の質問に、ダニエルの顔に笑みが浮かんだ。
彼は懐に手を入れ、手形を一枚取り出した。
そして私に近づき、腰を抱き寄せながら言った。
「返事を受け取ってきました。」
かなりの金額が手形に記されていた。
これなら十分だ。
私は腕を回してダニエルを抱き寄せた。