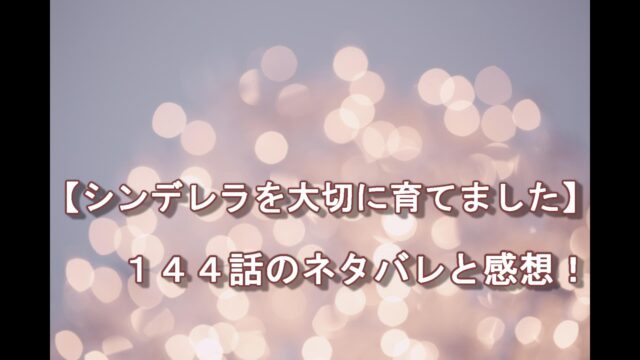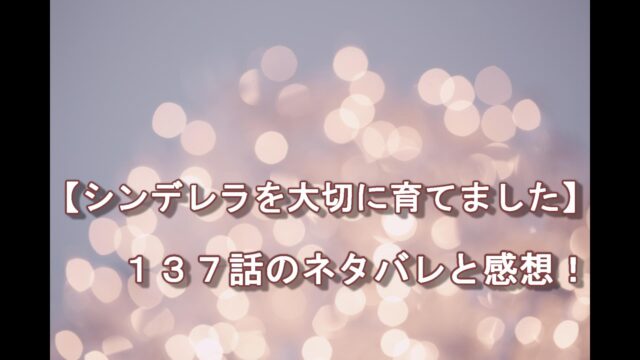こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

220話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 伝染病
恐ろしい勢いで拡散していた伝染病は、首都でも急速に広がるかと思われたが、ある瞬間から勢いが鈍り、次第に収束し始めた。
幸いなことだ。
ミルドレッドは茶碗を手に取り、ほっと息をつく。
今朝も病院に行き、患者たちの様子を見てきたが、確かに患者の数が先週に比べて減っていたのは良い兆しだ。
「それで、母上がアイリスに感謝の意を伝えたいとおっしゃっていました。」
ミルドレッドの向かい側で、リアンは嬉しそうな色を隠さずに言った。
――早すぎるのでは?
ミルドレッドがそう思った瞬間、まるで彼女の考えを読んだかのように、リアンが再び口を開いた。
「早すぎるとお考えかもしれませんが、状況はまだ完全に終息したわけではありません。ですが、全ての病院にマスクを提供するというのは、確かに良い考えだったと私たちは考えています。」
リアンの言葉に、アイリスの顔が明るくなった。
全ての病院に患者や医療関係者のためのマスクを提供してはどうか――それはアイリスの発案だ。
彼女はまずミルドレッドに自分の考えを伝えたが、ミルドレッドはバンス家にとってはあまりにも大きな金額になると説明した。
だがアイリスはそこで引き下がらなかった。
「寄付金を集めてくださったのは、王妃殿下ですよね。」
アイリスは恥ずかしそうな表情でうつむいた。
母親から「大変だ」と聞いた彼女は、王妃に手紙を書いたのだ。
彼女の母は、病は汚染された水や唾液によって感染すると話した。
だから水は必ず沸かし、手を清潔に洗わなければならない、と。
病院でも水を沸かし手を洗っていたが、患者たちは咳をし、その間に唾液が飛ぶのを防ぐ術はなかった。
それなら患者たちにもマスクを着けさせたらどうだろうか。
単純で素朴な発想だったが、患者の口を覆うマスクを提供するというのは新しい提案だった。
これまで病院では、医療関係者に危険物質が口や鼻に入るのを防ぐためにマスクを支給していたが、患者には支給していなかったからだ。
「でも、その提案をしたのはあなたじゃない。」
リアンはそう言って、アイリスを誇らしく愛おしいものを見るような表情で見つめる。
その様子を、ミルドレッドは茶杯を持ち上げた拍子に見逃してしまった。
「ロジャース嬢のおかげですわ。」
アイリスはすぐに否定した。
それはまったく彼女の考えではなかったのだ。
病院で奉仕しているエリザベスが、ふと口にしたことで知った事実である。
マスクは医療関係者に支給されるといっても、その「医療関係者」は医師だけに限られている――それがエリザベスの不満だった。
彼女のように医師ではなくても奉仕している人々や、修道女たちは別途マスクを用意しなければならない。
しかし、準備自体も難しく、少人数で患者を看護しなければならない看護師たちが、マスクを用意し毎回洗濯するのは容易なことではない。
アイリスはすぐに病院長であるエリザベスの父に会い、患者や看護師たちにマスクを支給するので、洗濯だけは責任を持ってしてほしいと頼んだ。
そして王妃に、支援をお願いする手紙を書いた。
それが伝染病の拡大を防ぐことになるだろうという言葉とともに。
「わかった。ロジャース嬢にも褒美を与えるよう話しておくよ。」
アイリスの言葉に、リアンは肩をすくめて言った。
彼はアイリスが何を望んでいるのか知っていた。
自分一人で褒美を受け取りたいわけではないのだろう。
ここへ来たのは、伝染病の拡大防止に尽力した功績として褒美を与えたいという陛下の意向を伝えるとともに、何か望みがあるかを非公式に尋ねるためだった。
もちろん、アイリスの顔を見たいという気持ちもあったが。
「ロジャース嬢が望んでいることは、私が知っているよ。」
アイリスはにっこり笑って言った。
エリザベスは今も医師になることを望んでいる。
伝染病の知らせを聞いて真っ先に病院へ駆けつけたのも、彼女だった。
「来月、改めてご連絡いたします。」
それは、来月城でミルドレッドとアイリスに賞を授与するために呼ぶ、という意味だった。
ミルドレッドは顎をかきながら言った。
「それまでに、何が欲しいか考えておくといいわ。」
かなり高価な物を望んでも構わないだろう――リアンはそう言いかけたが、結局ウォルフォード公爵が教えるだろうと思い、口を閉じた。
そしてアイリスを一瞥した後、再び口を開いた。
「それと、もう一つお伝えしたいことがあります。」
「なあに?」
アイリスの問いかけに、リアンはにっこりと笑った。
それはアイリスに関わることではなかった。
しかし、ミルドレッドには関係があった。
「ヘンリー伯爵夫人の件です。」
ヘンリー伯爵夫人は二人いる。
以前、国王の執務室でミルドレッドの証人として出てきたレジナと、彼女の養子と結婚した伯爵夫人だ。
厳密に言えば、夫が亡くなったレジナはヘンリー伯爵夫人ではない。
だが、息子がヘンリー伯爵であるため、慣例上ヘンリー伯爵夫人と呼ばれている。
リアンは、どちらのヘンリー伯爵夫人のことを言っているのかをミルドレッドの表情から素早く察した。
「レジナ・ヘンリー伯爵夫人です。」
「その方が何か?」
「その方には特に何もございません。ただ、これからは前に出ていただくことになるかもしれません。」
まさか――ミルドレッドの目が細められると、リアンはにやりと笑った。
この後、公爵が国王と会った後、国王はダニエルとリアンを呼び、命じた。
レジナ・ヘンリー子爵夫人の継子たちが、自分たちの継母に対して適切な待遇をしているかどうかを確認せよ、というのだ。
レジナは、ヘンリー子爵の正妻の座を得たものの、それは三人の息子を産んだ妻が亡くなった後のことだった。
彼女は、父の死後に爵位を継いだヘンリー子爵を育てた継母でもある。
いくら喪服の価格が高騰していたとしても、普通の家庭ならともかく、子爵家で母親に喪服を買う金を渡さないというのはあり得ない。
もしそれほどまでにヘンリー子爵家が困窮しているのなら、その理由を突き止めなければならなかった。
国王はリアンとダニエルに、ヘンリー子爵が財産を浪費したのか、それとも継母を虐げているのかを調べ、もし継母を虐げているとわかった場合には、ヘンリー子爵家と同様に後先を考えない行いをする家門が、ほかにもあるかどうかを確認するよう指示した。
「ヘンリー伯爵と同じようなことをしている家門が、もう一つあるのですよ。」
リアンの言葉に、アイリスの表情がさっと険しくなった。
母親を見捨てるようなろくでもない者たちが、またいるというのか?
同時に、ミルドレッドは深くため息をついた。
レジナは義母だったが、実母を追い出す者もいる。
妹や娘であっても、他家との関係を円滑にするために実家に送り返すことがあるのだ。
しかし、母親は実家に戻ることも生活費を稼ぐこともできず、家を出るのは惜しいのだ。
もっとも、レジナは自分名義の家を持っているので、まだ恵まれている方だ。
少なくとも、ヘンリー伯爵が家賃を払えないからといって追い出すことはなかったのだから。
「多いの?そんな家が?」
アイリスの質問に、リアンは少し言葉を詰まらせながら答えた。
「そんなに多くはないよ。ヘンリー子爵の家を含めても三軒くらいかな。そのうち一つは…うん、事情があまり良くない家だ。」
思っていたほど多くはなかった。
その程度まで冷酷な人物がいるというのは驚きだが、社交界でも珍しいことだ。
そこまで残酷に振る舞う者はほとんどいないから。
レジナや他の夫人たちの場合は、いくつかの抑止条件が働いていた。
普通なら、長子が冷酷に振る舞おうとしても、その弟や妹たちが止めるものだ。
しかし、リアンが突き止めた三軒の家は、孤立しているか、あるいは弟や妹たちも同じように冷酷な性格で、止める者がいなかった。
さらに、被害を受けた夫人たちが身近に親しい人を持たず、他人の助けを拒んでいたことも、このような事態が起こった原因であった。
「ほかの人から助けを受けられたら良かったのに。」
アイリスの残念そうな言葉に、ミルドレッドは肩をすくめた。
「アイリス、あなたも自分のことは自分でやろうとするでしょう?あの人たちも同じなのよ。」
人の助けを受けることを恥ずかしいと思う人もいる。
それはその人の性格であり、本当に困っている人なら妖精が現れて助けてくれる、というこの国の古い言い伝えのひとつでもあった。
ダニエルの言うことは正しかった。
ミルドレッドは、この国で「妖精は消えるべきだ」という彼の言葉を思い出した。
困っている人を助けるのは社会の仕組みでなければならず、妖精一人に頼ってはいけないのだ。
「人助けといえば、思い出したことがあります。」
茶碗を手にしながら、リアンが再び口を開いた。
暗くなりかけた雰囲気を和らげるためだった。
「アイリスへの称賛がすごかったですよ。」
「私?」
アイリスの頬が赤らんだ。
リアンは城で人々から聞いた話を思い出しながら続けた。
「財団の運営も上手くやっているし、慈善活動にも熱心だって、皆が褒めていました。」
「いいえ、私はただ、自分にできることをしているだけよ。」
「それが素晴らしいことなんです。」
照れくさそうにするアイリスと、そんな彼女を誇らしげに見つめるリアン。
その様子を見て、ミルドレッドはにっこり笑う。
彼女は二人の会話に加わろうとしたが、考えを変えて席を立った。
これだけ話したのだから、二人に少し二人きりの時間を与えるのも良いだろうと思ったのだ。
「ミルドレッド。」
ミルドレッドが応接室を出て階段へ向かって歩き始めたとき、ちょうどダニエルも外出から戻ってきたところだった。
彼は使用人に手洗い用の水とビヌを部屋に運ぶよう指示したあと、ミルドレッドに近づき尋ねた。
「馬車が二台停まっていましたね。」
どちらも彼が知っている馬車だ。
何事かと問うダニエルに、ミルドレッドは彼と一緒に階段を上りながら答えた。
「ケイシー卿は招待の件で来ていて、リアンは城から『褒美を授ける』という知らせを伝えに来たのです。」
「それは良いことですね。」
その階に上がったミルドレッドとダニエルは、リリーの作業室をちらりと覗いた。
疲れているとはいえ、ミルドレッドはこれまでの経験から、ダグラスがリリーに無礼を働くことはないと信じていた。
案の定、ダグラスはきちんとジャケットまで着込み椅子に腰かけており、その向かい側でリリーが絵を描いていた。
「リリーが展覧会に絵を出すそうですね?」
「ええ、聞きました。それは名誉なことなんでしょう?」
「はい。リリーのような新人にとっては。」
新人にとっては大変な栄誉だ。
ダニエルは、リリーの絵を国王が購入するかもしれないとミルドレッドに伝えようとしたが、彼女にとってそれほど大ごとではないと気づき、言葉を止めた。
代わりに、彼は知っている別の話題を口にした。
「それと、北西部の方に聖女が現れたそうですよ。」
「聖女ですって?」
「もちろん、本当に奇跡を起こすような聖女ではありません。伝染病にかかった人々を熱心に看病したそうです。それで人々が聖女だと称えているようです。」
「面白いですね。普通そういう人は妖精や妖精の長老と呼ばれるのではありませんか?」
ミルドレッドの質問に、ダニエルの顔に微笑みが浮かんだ。
彼は召使いが持ってきた水とビヌで手を洗い、タオルで水気を拭き取りながら、大したことではないというように言った。
「この国にはすでに妖精と妖精の長老がいますから。」
何のこと?
一瞬きょとんとしていたミルドレッドは、すぐにダニエルの言わんとすることを理解した。
「ああ、あなたと私のことを言っているのですね。」
「いいえ。」
きれいに手を拭ったダニエルは、ミルドレッドのもとへ戻り、彼女の手を取った。
そして、にっこり笑みながら、優しく告げた。
「あなたと、あなたの子どもたちのことを言っているんですよ。」