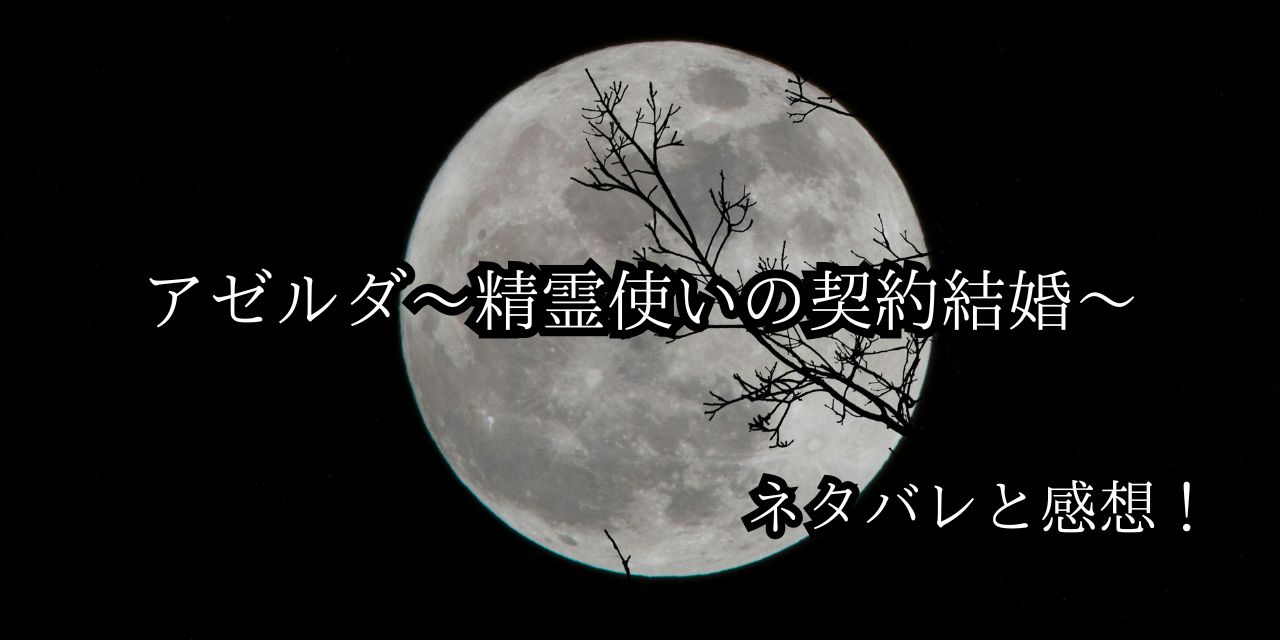こんにちは、ピッコです。
「アゼルダ~精霊使いの契約結婚~」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

36話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 無茶な要求
ベッドが置かれた部屋の小さな扉が閉まり、一行はソファが並ぶ大きな応接室からも姿を消した。
巨大な扉が閉じ、再び草花の絵が描かれた壁画が現れた。
短い独白を終えて外に出た一行は、自然とそのまま従者に続いて歩いていった。
会議を共にした大臣たちは皆、廊下で彼らを待っていた。
一行は大臣たちから少し離れた場所で立ち止まった。
遠くからアジェルダと王女を見つけて挨拶する大臣たちを見つめながら、王子がぽつりとした声で口を開いた。
「シェイド。」
シェイドは落ち着いて王子の視線を受け止め、やはり他の者には聞こえないほどの小さな声で答えた。
「どうしたのですか、トコフェン。」
「王宮では……もう黙っていてくれたらいいのに。」
その口ぶりに驚いているのは、やはりアジェルダだけのようだった。
王子はそれだけ言うと、王女に視線を移した。
おかしなことではないというように、その会話を聞いていた。
「わかった。それと、陛下の看病に役立てることがあれば、いつでも……」
王子は苛立たしげに舌打ちした。
鳥のような目に怒りが走った。
父が目の前に我が子といるのに、不快そうにシェイドの手を握っているだけでも苛立ち、部下たちが無能なのも漠然と苛立った。
治療士ジョディアクはどこかに聖霊の気配があると感じるばかりで、肝心な場所は見つけられずに精霊の住処を掘り返して回っていた。
突然、王子は声を上げて荒々しい叫びを放った。
目には怒りが浮かんでいた。
「シェイド、お前がなんの助けになるって思ってるんだ?俺が今、できる限りのことをして看病してるように見えるか?ああ?お前にできることがあるなら、俺がもうとっくにやってると思わなかったのか、ああ?」
言い終えると、トコフェン王子はシェイドの胸ぐらを強く押した。
王子よりも少し背が高いシェイドの頑丈な体は、わずかに揺れただけで、後ろに倒れることはなかった。
それが王子の気分をさらに不快にさせたようだった。
傷ついたプライドが鋭くざわめくように、王子は苛立ちを吐き出した。
「どけ!なんでまだここに立っている?偉そうにするな。この城での用が済んだら出て行け。お前のやることなんて、補助金を減らされたって文句を言うほどのことでもないだろう。」
「その補助金の件については……」
「どけって言っただろ、聞こえないのか?補助金だろうが実験だろうが、もう聞きたくないんだ。何も変わらない。そう思って、さっさと出て行け。」
王子は冷たく目をそらした。
大臣たちはこれまで自分たちが熱心に意見を出してきたことが、すべて無視され、結局は補助金問題も元の木阿弥だったということに気づかされた。
いずれにせよ、王子の機嫌を損ねたら終わりなのだ。
共に議論する代わりに、紫色の上着を着た膝の上のジャイルドの男は、かすかな笑みを隠して静かにうなずいた。
だらだらと続いていた会議の結論が出る前に、王の激しい許可が下り、全員が飛び出していった。
こんなふうに北都で急に決定されたことを報告として聞かされるのはなぜなのか?
結局、長時間にわたる会議の結論はこれだった。
不満を漏らすな、ということ。
カルロス公爵が自分の望むものを得られなかったのは彼の問題だったが、王子の一言で長い会議が消えたことは大臣たちの問題だった。
王子の威厳だった。
なぜこうなってしまったのだろうか?
生まれながらにしてすでにドラゴンの加護を授かっていたことがこの国の祝福だったが、どうしてそのような者が選ばれたのだろう?
これまでのドラゴンの加護は、名将たちにだけ授けられてきたのに。
ジャイルドの男は、冷めた表情を隠すために事がうまく進んでいないとしても、とにかく観察してみようと思った。
何にせよ、自分は宴会場の“花のような男”だった。
華やかな言動と場の雰囲気を和ませる存在として名を知られているうちに、人々が口にしそうな話題くらいは拾って帰るべきだった。
何かネタになるものはないかと耳をそばだてた。
シェイドも言葉を失った。
合理的な論理で長い時間をかけて説得してきた。
どうしてこんな結論になってしまったのだろう?
だが、トコフェンと共に育ってきた間に、こんなことは一度や二度ではなかった。
シェイドはだんだんと落ち着きを取り戻し、周囲の大臣たちの目を意識しながら、毅然とした敬語で話し始めた。
「もし私に非があるなら謝罪いたします。個人的に不満があるなら受け止めます。しかし、北部の治安は非常に重要な問題で……」
「すまないが、首都の治安の方が重要なのだ。」
いったい誰がこの国の首都を陥落させるというのだろうか。
ドラゴンの加護を受けているヴェレリア国の首都は、どんな軍事大国の首都よりも安全な場所だった。
とても信じられないような話だ。
アゼルダは二人の会話を見守っていたが、王子の口元が怒りで震えているのを見た。
ただ機嫌が悪かったのだ。
特に理由があるわけでもなく、ただ怒っていたのだ。
シェイドは、自分が合理的で必要に応じて冷静になれる人間だから、相手の非合理的で感情的な反応を理解できないようだった。
何の話かはよくわからなかったが、「支援金を削る」という話だけはしっかり耳に入ってきて離れなかった。
自分の前世よりも明らかに北部の魔物たちの動きが激しいのは明白だった。
前世と現在の違いで、自分とラウルの立場が逆になったのだろうか。
ラウルがより強くなったからだろうか?
ラウルの魔物よりも、魔物らしい振る舞いをする魔物たちを魔物が刺激したのだろうか?
いずれにせよ、今この場で支援金を減らすなんて、とんでもない話だった。
彼にとっては北部の城壁が安定してこそ、ドラゴンの巣へと近づくことができるのだ。
そのドラゴンが王家を守ろうが何しようが、彼には関係なかった。
そもそもこの王家の存在にも、興味はなかった。
木の枝にとまったカラスのように、いつでも振り払えばいいと思っていた。
ドラゴンに勝てなければ、王子だって死ぬかもしれないのだから。
ましてや北部の傭兵や騎士たちがどれほど命を懸けて戦っていることか。
そんな場所で、どうして勝手に支援金を減らせるのか?
今も戦闘が厳しい地域なのに。
彼女は、具体的な思考を巡らせる前に、衝動的に一歩前に出てしまっていた。王
子は一歩前に出た彼女を見つめた。
「何だ?」
「私がひとこと申し上げてもよろしいでしょうか?」
シェイドは王子のその表情が何を意味するかよくわかっていた。
それは「やめておけ」という合図だったので、妃の腕をそっとつかんだ。
すると、王子が笑いながら言った。
「おお、あなたはかつて私のような者とは言葉を交わすのも嫌だと顔を背けた、アゼルダ・カルロス夫人ではありませんか。いいでしょう、こうして堂々と話しかけてくださるのなら、どれ、聞いてみましょう。」
王子の皮肉混じりの口調や、不機嫌な表情を見ても、言葉を続けられる者など宮廷にはいなかった。
しかし、アゼルダはそんな彼が情けなく感じられた。
ドラゴンの加護がなければ、今すぐにでも母の喉を切ったことについて問いただしたい気持ちだけだった。
軽く息をつき、心を静めた彼女は、そばにいた男の冷ややかな口調を真似て言った。
「王子様が、北部に足を踏み入れてまだ間もない未熟な女よりも、はるかに深い見識をお持ちのうえでそのようなお言葉をおっしゃったとしても、王子様、北部の騎士たちは最善を尽くして戦っています。どうしてそのように冷たいお言葉をなさるのですか?」
彼女の切実な口調に、誰よりも驚いたのはシェイドだった。
王子は眉をひそめてじっと見つめた。
「つまり、俺よりも深い見識があるとでも?結局、教えたいわけか?夫婦揃って言いたい放題だな。」
アジェルダはそっとうつむいて、こっそり唇を噛んだ。
「そういうことではございません。もしかして私が北部公爵家の兵士たちに言った言葉でお気を悪くされたのであれば、お詫び申し上げます。本当にその話が王子様のお耳に届くとは思いませんでした。兵士たちに気を楽にさせようとした一言が、どうして王子様の耳に届いたのか……。今後は口に出すことのないようにいたします。」
王子は、自分の公爵家が内部にスパイを仕込まれていたとでも言いたげに、彼女を呆れて見つめた。
いま何をしているつもりなんだ?
膝をつき、真剣な面持ちで謝罪しているではないか。
考えを巡らせても、決して意見を変えるつもりのない様子だった。
あの階級を引きずり出して、どんな刑罰でも下せるならそうしたいと思った。
王子が無表情で口を閉じたままいると、アゼルダは再び口を開いた。
「北部が安定してこそ、ようやくこの国の隅々にまで目を配ることのできる聡明な王子様におかれても、平和なこの国に魔物がはびこることを心配なさらずに済むのではありませんか?どうかご機嫌を直して、もう一度お考え直しくださいませ。」
「は?俺がなぜ?」
「えっ?」
「俺がなぜそんなことを考えなきゃならないんだ?」
「“そんなこと”とは……。今、王子様は明らかに多くの分野を取り仕切り、国政を担っていらっしゃるではありませんか?」
普通であれば、すでに気圧されて床にひれ伏すところだった。
だが、にっこりと笑いながらもしっかりと応酬してくるこの女性は、言葉こそ丁寧でありながら、自分が下で相手が天であるかのように扱われても、態度だけは決して引かないという気迫があった。
彼はふっと、低く長いため息をつこうとした。
血圧が上がっている自分を避けることなく、王子妃と堂々と話を続ける彼女の態度が、ティルトには妙に「面白く」感じられた。
久しぶりだった。
この種の会話をするのは。
これこそが、ティルトがかつてティルトに「面白い」と語ったやり取りだった。
だが、その「面白い」と感じた瞬間に、同時に腹立たしさもこみ上げてきた。
あのアジェルダ・カルロスも、最初はどうにかして北部の情報を引き出すための道具に使って、捨ててしまえばいいと思っていた。
だが、今の様子を見れば、結婚後は完全にカルロス家の一員になってしまっていた。
父の手、剣術、そして美しくて喉が渇くほどの魅力をもった聡明な妃。
自分が欲しいと思ったことすらなかったそれらすべてが、今やシェイドの手の中にあるのだと思うと、どれほど悔しく、苛立たしいか。
そのすべてが――シェイドのせいだった。
その死んだような黒い瞳は、アゼルダの短い袖口と、その下から伸びるしなやかでしっかりとした腕をまるで舐めるように見つめた。
王子は、彼が時折冷淡なことを口にするときに見せる、歪んだ笑みを口元に浮かべた。
「俺の望むことを聞いてくれるなら、俺もお前の望むことを聞いてやろう。アゼルダ・カルロス。」
彼が他の誰にも応えられないような条件を突きつけてくるだろうことは、誰の目にも明らかだった。
しかしアゼルダは笑みを浮かべて答えた。
「それが何か、ぜひ聞かせてください。」
王子の頭は、こういうときだけはよく回る。
彼はすばやく頭を巡らせ、屈辱的なことを思いついた。
公爵夫人が絶対に受け入れられないようなこと。
彼女がどう出るのか見てみたかったのだ。
その死んだ魚のような黒い瞳に、かすかな興味が浮かんだ。
「そうだな、ちょうど明日の夕方、チアンドで客人を迎える予定がある。可愛い妹の誕生日を祝う宴なのに、立派なお客様までいらっしゃるというのに、その場を華やかにする見どころが足りないじゃないか。だからお前たち、盛り上げてくれよ?そういうのあるだろう。踊って、酒を注いでさ。」
とんでもない話だった。
王子の言葉なら、彼の靴にすら口づけしそうな家臣たちもあまりのことに青ざめ、公爵と公爵夫人の顔色をうかがうほどだった。
王子はくすくすと笑った。
「なんでそんなに場の雰囲気が悪いんだ?俺の目が楽しいとか、体が楽しいとか、何か楽しいことがあってこそ、俺があんたらの願いを聞いてやろうって気になるんじゃないか?違うか?俺が得るものもなく損だけしろって?それがあんたらの言う“忠誠”か?違うだろ。上に立つ者には“見返り”が必要なんだよ。」
冷えきった空気の中で上機嫌な王子は、自分の酒杯を振ってみせた。
いったい何を言い出すのか、誰か口を開く勇気ある者がその場にいなかっただけで、王子の暴言は今回は誰にも止められなかった。
死者を迎える席に、女性に目の保養として同席しろだなんて?
もし相手が王子でなければ、シェイドが手袋を投げつけて決闘を申し込んでもおかしくなかった。
本気でそうしろと言っているわけではない。
ただ機嫌を損ねたいだけの言葉であり、どうせこの件についてこれ以上話す気もないから、これ以上侮辱されたくなければ黙っていろ、という意味だった。
シェイドはこれ以上、王子と話す必要はないと感じた。
特に実のないこの会話がこれ以上続くのは、誰にとってもよくないと判断した。
当惑するアゼルダと目が合った瞬間、シェイドは彼女の腕をとって、軽く引いて見せた。
これ以上この件に関わる必要はないし、得られるものがないのであれば、王子の機嫌をこれ以上うかがう意味もない、という意思だった。
公爵夫人の金色の髪がふわりと揺れた。
…そして、彼は彼女が自分の表情の意味を理解したのだと思った。
だが、彼は忘れていた。
この公爵夫人は、結婚初夜に契約条件を突きつけてきた女性だ。
彼の言うことにいちいち従うような人物ではなかった。
彼女はむしろ、アジェルダの腕を握っていた彼の手に優しく触れた。
彼女の目は、まるで「私に任せて」という騎士のそれのようだった。
なに?
以前にも見たことのあるような視線だった。
堂々としていて、卑屈ではなく、自分の欲しいものをその手でつかみ取れるような目。
明らかに困難な状況にも屈しない。
シェイドが一瞬ためらっている間に、王子は皆の困惑した顔を楽しんでいるかのように、長い舌を伸ばして言葉を口にし、笑った。
「もしやるって言うなら、支援金も維持するし、支援兵も送ってやる。夫か?武器も送ってやる。何が必要なんだ?」
アジェルダは微笑みながら、軽く唇の端を上げた。
アゼルダは、アスコが交渉していたときの姿を思い出していた。
彼は決して条件が確定する前には交渉を終えなかった。
印を押す前に、自分が相手に物を渡す前に、そのすべての条件が定められていなければならなかった。
その後で交渉するのでは遅すぎる。
すでに物を渡してしまった相手に何を求めても、顔色をうかがって頼んだところで思い通りにはならない。
「どれだけ良いものをくださるのか伺ってから判断しても、よろしいでしょうか?」
王子はその言葉に呆れたように笑みをこぼした。
その傲慢な態度に緊張感がさらに高まった。
「面白いな、これは。」
彼女はちょうどそばに立っていた紫の服の貴族から、差し出された報告書を丁寧に受け取った。
公爵の整った筆致で書かれたその報告書はかなり分厚かった。
彼女が記していたリストをひとつひとつ指で示しながら、追加支援が可能かどうかを夫婦に問いかけた王子は、ふっと笑いながら顎を引いた。
アジェルダも一度振り返って確認してから、ゆっくりと頭を下げた。
「それでは、よろしいです。」
「こ、公爵夫人?」
ひそひそと彼女を呼んだのは、コチータ王女だった。
いま何について「よろしい」と言ったのか?
その場にいた従者やシェイドも、事態の行方がまったく読めず、アジェルダの顔を見つめた。
「はっきりと、あなたの口で『よろしい』と言ったのだ。あとで泣きながら私を責めてもどうにもならないからな?」
「承知いたしました。」
「ははは、は、は。はは、はははは。」
狂ったように笑い出した王子が、急に真顔になって言葉を失ったまま立ち尽くしているシェイドの顔を見つめ、そしてアジェルダの手を取り、手の甲に口づけした。
「また明日。」
乱雑に髪をかき上げた王子が、そのまま背を向けた。
顔をそむけると、騎士ティルトが凍りついたような表情で彼の後に従った。
北都に漂っていた緊張感がすっと消えていった。
その場に残った者たちの頭の中には、「どうしてこんなことになったのか」という困惑と不安だけが残っていた。
部屋に戻った後、シェイドは黙って窓の外を見つめたまましばらく立ち尽くしていた。
青と白の混ざった制服を脱ぐこともなく、席に着く余裕すらないようだった。
「旦那様。」
無視されるかと思っていたが、シェイドはその呼びかけにすぐに振り返った。
表情を読み取るのは難しかった。
「なぜ“お呼び”になったのですか?」
「大丈夫です。」
「なぜ“お呼び”になったのかと聞いたのです。」
「私は大丈夫です。」
「いや、いったい……」
言いかけた彼の顔は、どこか見慣れない表情を浮かべていた。
いや、このしかめた眉と噛みしめた口元はどこかで見たことがあるような気がした。
いつだったか?
そう、王宮の宴会場で自分が倒れたとき、目を開けた瞬間に見たあのときだ。
彼は、公爵夫人がそんな場に出たことが北部公爵家の名誉を傷つけるのではないかと心配しているのだろうか?
「ご心配なく。私の独断だと思われるでしょう。上公(※上位の貴族や王族)が私にこんなことを命じたとは、誰も思わないでしょうから。」
「何を言っているのですか?」
「たとえ失敗したとしても、誰も上公を非難したりはしないという意味です。」
「……そういうことじゃない。」
「えっ?」
「そういうことではないのではありませんか?」
「では……?」
シェイドは、この女(アジェルダ)の言葉が最初から最後までまったく気に入らなかった。
今、この瞬間も、目を大きく見開いて自分を見ることもなかった。
突き放すような態度の問題ではないか?
「心配しているんです。」
「私を?なぜですか?」
「王子は、口にしたことを実行しないような人ではありません。彼がそうすると言えば、本当にそうするでしょう。」
「知っています。噂ではたくさん聞きましたから。そして私も本気でそうするつもりです。」
シェイドは、彼女の保護者のような青い瞳を見つめた。
「……どうしてそこまでなさるのですか?」
「何をおっしゃっているんですか?公爵様も北部の安寧のために長い報告書を書かれ、あの王子様と顔を突き合わせて長時間の会議をなさいませんでしたか?難しいことだと最初から分かっていたはずなのに、今さら不満を言うんですか。」
公爵は言葉を失った。
――この女が今、何を言っているのだ?
そうだ、ずっとあの女を本当に北部の公爵夫人らしいと思っていた。
だからこそ、まさに立派な公爵夫人ということだ。
公爵夫人があんなふうに振る舞うなら、貴族たちの誇りとなるだろう。
だが彼女は、いったいなぜ?
よく知らない土地に無理やり嫁いできたのではなかったか?
王子は、彼女を徹底的に、そして無惨な目に遭わせるつもりだった。
そうしてこそ、彼女だけでなく、彼女を嫁に出した公爵自身までもが辱めを受けるだろうから。
しかし、自身の公的な評判などは、すでに落ちるところまで落ちていた。
なんとか体裁を整えようとするのも、アスコと公爵夫人の言葉のせいだった。
だから、今さらどんな噂が立とうが関係なかったはずなのに、彼女は違っていたのではないか?
公爵夫人ともあろう者が、他人の目を楽しませるために踊り、酒を注ぐだなんて、一体どれほどの侮辱なのか想像もつかなかった。
それでも彼女はあっさりと受け入れた。自分から進み出て「わかりました」と言った。
「北部のために、なぜそこまでするの?」
アゼルダは言葉を失い、自分を見つめている彼をしばらく見返してから、彼が今、自分に対して申し訳なさを感じていることに気づいた。
「大丈夫です、本当に。私は。」
「……でも、夫人。」
「上公様は剣で北部をお守りくださっているのですから、微力ながら私もお力になれればと思います。多くはできないかもしれませんが、その部分についてはできる限り尽力します。私も今では北部の人間ですから。」
彼女が笑いながら「先に失礼します」と言って部屋に入っていくと、シェイドはその場で動けなくなった。
あの女性は、そこまでして自分を犠牲にしている。
それなのに、自分は彼女を信じてやることすらできない?
そんな自分が情けなかった。
戻ったらすぐにアスコと話をしなければ。
平素と同じように同じ服を着て、同じ寝台に入った。
朝の仕度をする侍女たちが出入りするのだから、彼女の言う通り、同じ寝台にいるほうがよいということには同意した。
だが、背を向けて横になっている彼女の背中が、なぜか今日に限ってやけに華奢に見えて、視線をそらさずにはいられなかった。
心が重く、視線がついそちらに向いてしまうのは、まるで罪悪感を感じているかのようだった。
彼は何度も寝返りを打ったが、結局眠りにつくことはできなかった。