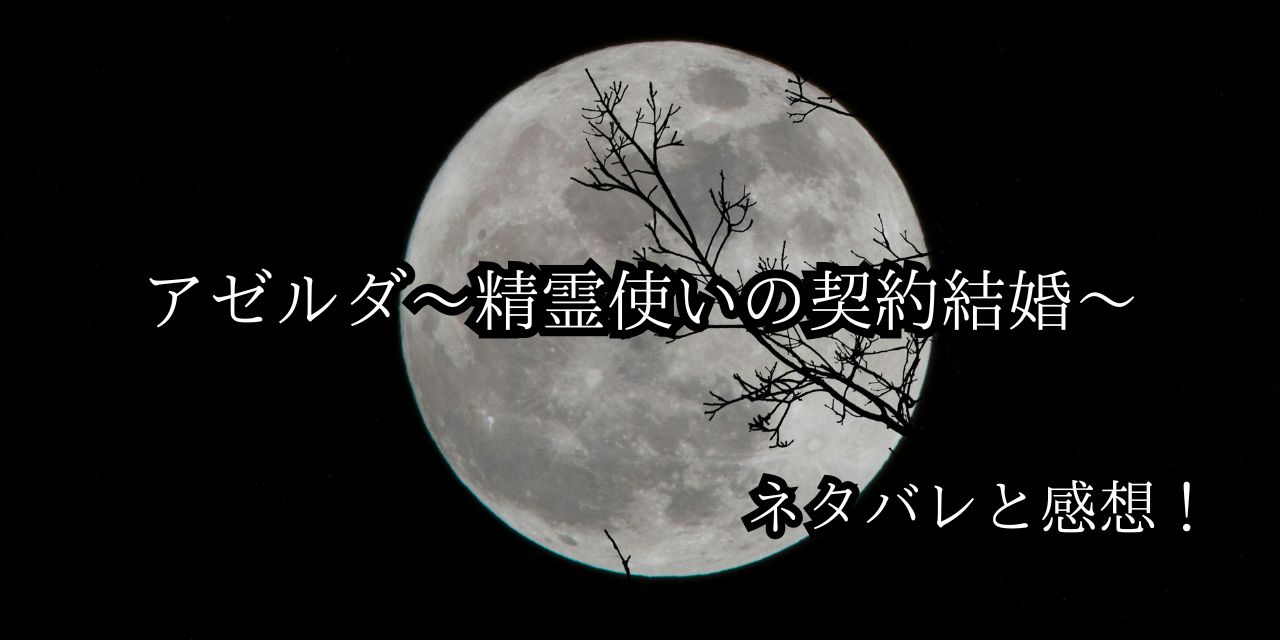こんにちは、ピッコです。
「アゼルダ~精霊使いの契約結婚~」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

37話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 予期せぬ贈り物
シェイドの言葉は正しかった。
王子は、一度言い出したら引かない性格だった。
アジェルダは、朝から窓の外から聞こえる騒がしい音に目を覚ました。
何かを打ち砕くような音だった。
「これ、一体何の音なの?」
彼女が体を起こすと、衣がはらりと落ちて、長くしなやかな脚がそのまま現れた。
ローブ型の寝巻きは、寝起きで立ち上がるとどうしてもだらしない格好になるのが常だった。
彼女が窓の外を見ようとスリッパを履く間に、シェイドは突然立ち上がり、さっと立ち去ってしまった。
王城の前庭には、大きな二つの庭園とその間に長く伸びた池があった。
王子は池の隣の広い広場に、小さな舞台を設けていたようだった。
これは、貴賓をもてなす際や有名な作家による戯曲、または音楽詩の公演を行うときに設置される特設舞台だった。
「うわぁ……噂では、舞台を設けることもあるって聞いてたけど、実際に見ることになるとは。王城まで来て、本当に盛大だわ。」
アゼルダはそうして独り言をつぶやいていたが、ようやく現実感が戻ってきた。
まさか、あれ……私が上がらなきゃいけない舞台じゃないよね?
頭が一気に冷えた。
どうやら、王子がとんでもないことを言ったらしい。
頭に血が上って、まともに考えもせず彼の言葉を受け入れてしまった。
そしてそれがそんなに大問題とも思わなかった。
どうしてだろう。
正直、自尊心が少し傷つく程度で、北部の支援金によってあれほど多くの武器が手に入るなら、ものすごい利益じゃないか?
手のない人間でもあるまいし、女性が酒を注げば食事が美味しくなるなんて馬鹿げた話も、気に入らなかったが、女だからというよりも単に侍女の真似事だと考えれば、それも耐えられる気がした。
なのに、あなたはこう出るわけですか?
恥をかかされるなら、いっそ堂々とやってみろってこと?
「……頭にくる。」
素直な気持ちが、思わず口から漏れ出た。
自分が学んできた踊りなんて、相手がいてこそ成り立つものばかりだった。
それ以外で踊るなら、それはロイナ流の教わった剣舞はあったが、その剣舞は見せるためのものではなく、剣術の一環として習ったものなので、舞台で披露しても問題ないとは思えなかった。
とはいえ、やはり剣舞を披露することになるのか?
剣舞で使う剣は、普段自分が使ってきた剣とはまったく違うだろう。
どうすればいいのか分からなかった。
困惑した気持ちで窓の外を見下ろしていると、きちんと服を整えたシェイドが彼女の隣にやってきた。
彼もまた、窓の外に設置されつつある舞台を見て、表情をしかめた。
「トコフェン、本当に……気が狂ったな。」
「……ははは、これは大事になってきましたね。」
「今、笑っておられるんですか?」
「じゃあどうすればいいんです?泣くんですか?」
本当に肝が据わっているとでも言うべきか。
シェイドが少しでも彼女の助けになる方法を考えながら頭を下げたそのとき、ノックの音が響いた。
「はい。」
侍女が出入口で腰を深く折って挨拶し、アジェルダに向かって言った。
「王女様がお呼びです。」
「王女様が?」
「はい、衣装をお貸しくださるそうです。」
「ああ……」
アジェルダはようやく、自分が持ってきた服をすでにすべて着てしまっていたことに気づいた。
しかもどれも華やかではない衣装ばかりで、“見世物”の目的にはふさわしくない可能性もあった。
王女様が貸してくださるなら、その申し出を断るのは難しい状況だった。
シェイドは少し驚いた目で彼女を見つめた。
「王女様とはいつの間にそんなに親しくなられたのですか?」
「ああ……ははは。私が?」
「昨日、一緒にお食事されたと伺いましたが。」
「まぁ、なんというか……ははは。事情がこうなった以上、行ってまいります、上公。」
「承知しました。もしも私にお手伝いできることがあれば、おっしゃってください。」
形式ばったきっちりとした言葉だったが、その一言に思わず胸が熱くなった。
アゼルダは明るく微笑みながら、頭を下げる侍女についていった。
シェイドは、どうしてこうなってしまったのかと頭を抱えた。
そして自分の部屋に置かれていた報告書を見返し、また深いため息をついた。
北部の仕事を妻にあまりにも大きな負担として背負わせてしまったようで、胸が痛んだ。
彼女がそこまでしなければならなかったのは、自分が事態をうまく処理できなかったせいだという思いが込み上げてきた。
自分は彼女を信じてもいなかったというのに。
なのに今、自分はこの結果を見ている。
彼女の肩に、どれほど多くを託しているか、今この状況を見てみろと。
メディスン家の不可解な死を調査する過程で、調査官が死亡した時点で、すでに疑念は半ば解けていた。
さらに、初めから演会(宴席)を強く嫌っていた様子を見せていた最後まで使い切られるまで、きっちりと自分のすべきことを果たしていたのだろうか。
信じがたいことに、彼女に渡した金をすべて救済院の兵士たちのために使ったという話まで側近から聞かされた。
すると、彼女の思慮深さや品格を理解できる人物は、ますます彼女を高く評価せざるを得なかった。
ここまでの女性であれば、疑ったり警戒したりするべき相手ではなく、公爵夫人として迎え入れ、感謝してでも迎えるべき存在だ。
ただ名目だけの妻としてではなく、自分と対等に肩を並べ、同じ目標を見据えることのできる人物だった。
北部の安寧のためには、自尊心など気にしない人物なのだ。
今からでも謝罪や感謝の気持ちを伝えたいと思ったが、どこからどうやって、何を切り出すべきか見当もつかなかった。
報告書を手にしたまま、ぼんやりと考えに耽っていたその時、彼の隣に側近が近づき、軽く礼を取った。
「何ですか?」
「侍従が参りました。」
「どういう用件で?」
「急ぎの会議があるそうです。王子様からのお呼びです。」
王子が?
昨日あんな顔で別れたのに、もう会いたくないだろうと思っていたトコフェンが自分を呼ぶとは——嫌な予感がした。
アゼルダが複雑な思いをなんとか整理しながら、公女様の部屋の方へ向かっているところだった。
ラウルが口を尖らせながら後ろからついてきた。
「ラウル、よく眠れた?」
[よく寝たけどさ、その公爵とかいう人、ちょっと離れて歩かせたらダメなの?]
「ごめんね。」
クスッ。
ラウルはアゼルダの後ろをとことことついていきながら、彼女の隣までぴたりと寄って一息ついた。
何かおかしな匂いがするような気がして、彼女は自分の袖の匂いも嗅いでみた。
何か香りがするような、しないような感じだった。
【ねえ、人間、どこ行ってきたの?】
「何の匂いがしますか?」
【嫌な匂い。】
「何の匂いですか?私はよくわかりませんけど。」
【その服着てどこ行ったの?】
「……あ、昨日。王女様とご飯を食べて。」
【その時は私が隣にいたからそれじゃない。】
「それから……陛下に会いに行ってきました。」
【王に会ったってこと?】
「はい。」
彼女は北廊を歩きながら、列をなして並ぶ装飾の中から、先王の代理席のレリーフを見つけ、それを指差して見せた。
「この方です。」
[王がこんな匂いのする場所に住んでるって?人間の中では良い地位なんじゃないの?何か草っぽい匂いだな。何の草かは分からないけど。]
「陛下のご体調があまりよくないんです。あの部屋からする匂いは、多分薬草か何かの匂いじゃないでしょうか?」
ラウルは、彼女が差し出した手からもれる微かな香りにも鼻をひくつかせて、鼻をくんくんと鳴らした。
[いろんな匂いが混じってる。一つじゃないよ。]
「何か分かるの?」
[人間たちは植物だの動物だの、あらゆるものを混ぜて使うから、何千年単位でやって来る俺に分かるわけないでしょ。今度薬屋か何かに行く機会があれば、匂いを嗅いでおかないと。]
「じゃあ北部に戻ったときに、ちょっと調べてみますね。でなければ、また黄金の通りにも行けるし。」
[うん、何でもいいけど、その人間とはちょっと距離をとってよ。じゃなきゃ、いっそ精霊士のところで暮らしなよ。だったら私がそばにいても関係ないじゃん。】
ある程度大きくなってからは、行動が犬のように変わってきて、主人なしでは動けない子犬のようなところが少し可愛らしく思えた。
しかし、ラウルにそんなことを言えば、どこかの名門の精霊がその程度の忠誠心しかないと侮辱されたかのように怒って暴れそうなので、アジェルダは揺れるラウルの尻尾を見ながら、その言葉を飲み込んだ。
王女の部屋につながる応接室に到着した彼女は、そっとソファに腰掛けた。
扉を開けてくれた侍女が下がると、別の侍女がやってきて、花の形をした器に香り高く美味しいお茶を入れて持ってきた。
彼女は王女を待ちながら、応接室の中をぐるりと見渡した。
これといって華美な装飾もなく、壁にも特別な飾りはなかった。
天井も装飾画で覆われているわけではなく、王宮の文様が控えめに施された、素朴な単色の仕上がりだった。
城内の重苦しい雰囲気とは違い、なぜか心が温まるような空間だと感じた。
「アゼルダ!」
扉が勢いよく開く音とともに、コチータ姫が駆け込んできた。
今日は両側に髪を結って後ろにまとめた髪型をしており、可愛らしい顔立ちがより強調されて見えた。
姫はティーカップを置くと立ち上がり、アゼルダをぎゅっと抱きしめた。
「お姫様!」
「一体どうしてあんなことしたの!?」
「それが……気づいたらそうなってたんです。」
コチータ姫はアゼルダを抱きしめたまま、心配いっぱいの表情で大きくため息をついた。
「ここでは他人行儀にしないで。名前で呼んで。」
「うん。」
姫はアゼルダがにっこり笑うのを見て堪らなくなったのか、両肩をぎゅっと掴んで激しく揺さぶった。
「あなた、どうしてそんなに平然とした顔をしていられるの?」
「別に平然としてるわけじゃないよ。心配してる。」
「ほんとに、兄上もどうしてあんなことを言えるのかしら!」
「私、すごく……腹が立ったみたい。」
コチータ王女は涙ぐみながらアジェルダを引き寄せて座らせた。
「あなたは何も悪くないのよ!ああ、ほんとに、なんてこと!兄上はほんと……怒ると一度ガッとくるから。昨日見た?笑ってたでしょ?私、あの音がダメで……前にあんなふうに笑いながら、侍女の腕を切り落とせって言ったの。中がヒリヒリして、全然眠れなかった。」
「今日はどうにか無事に乗り切らないとね。うまくいくよ。だって今日は使節が来る場でしょ? 何か起こるわけないじゃない。」
「使節が来る場だからこそ問題なのよ!あなた、そんなこともわからないの?」
アゼルダは、コチータ姫が自分のことを心配する一方で、この国の威信も案じていることに気づいた。
この人は「気が弱い」という噂に反して、実は立派な指導者としての資質を備えているのではないか?
「ふぅ……こうなった以上、本当にあなたの言う通り心配ばかりしてもいられないし、何か見つけてみよう。」
彼女はため息をつきながら、そっと掛けていたショールを整えたところで、侍女が三人入ってきた。
アゼルダの向かい側のソファに座ったコチータ姫は、急に自分の立場を自覚したのか、やや低い声でこう言った。
「公爵夫人が本日の使節団との面会に同席されるとおっしゃっているので、王家の一族として彼女の務めを助けないわけにはいかないでしょう。私の服は多くはありませんが、体格も似ていると思うので、あなたに合うものがあればご自由にお選びください。」
これほどの厚意をどう受け止めたらよいのか、戸惑わずにはいられなかった。
侍女たちはその言葉にアジェルダのサイズを測ると言い、手際よく衣装箱を運んでくると、王女はそれを見て密かに満足そうに笑みを浮かべた。
「すばらしいですね。」
さすがは王女の衣装。慎ましい北部の公爵夫人の衣装に比べると、華やかさが段違いだった。
王子と比べて地位は劣るとはいえ、それでも王女はやはり王女だった。
刺繍の糸からして違い、使われている宝石の価値もまったく違っていた。
最初、彼女はその中から比較的控えめなものを選ぼうとしたが、王女はあっさりと最も華やかなものを選んで渡した。
「どうなるか分からないけど、最大限に相手の威圧感を跳ね返せるようなカリスマのある衣装を選ぶべきだと思うの。私は、公爵夫人が圧倒されて見えるような結末なんて見たくないから。」
仮に辱めを受けるとしても、堂々と踊るその場にカリスマがなければ困るのでは?
しかし、王女の言葉にも一理あった。
自分が堂々としていれば、どんな状況であっても堂々と立ち向かえるはずだ。
結局、姫が彼女に選んでくれた衣装は、彼女の金髪と同じような金糸が織り込まれた服だった。
片方の腕は肩から袖口まで大胆に開かれ、もう片方は空色の薄布で大きな袖を作り、袖口で布が集まるようなデザインだった。
上着にはヴェレリア王宮を象徴する金色の華やかな刺繍が施されていて、体にぴったりと合っていた。
ヴェレリアの伝統舞踊衣装はスカートだったが、アゼルダはズボンを選んだ。
彼女が授かった剣舞はスカートでは踊れないほどに激しいものだった。
ズボンでも大丈夫かと心配しながら服を差し出した姫は、アゼルダの姿に感嘆の声を漏らした。
体にぴたりと合った白いズボンは、アゼルダにとてもよく似合っており、引き締まって洗練された印象を与えた。
「体型がいいから、こういうスタイルもよく似合うわね。」
姫は、自分が選んだ装いが気に入ったようだった。
王女はくるりと回って衣装の様子を見せながら、何度も回ってみせた。
アジェルダは動くには不便がないどころか、むしろ着心地が良いと感じたが、肌に吸い付くように柔らかくなじむこの衣装が、恐らく非常に高価なものなのだろうと思った。
「これはちょっと派手すぎませんか?」
「片方の袖がないから圧迫感がないでしょ?うん、いいわね。ちょうどいい感じ。ダイヤのネックレスでも一つ下げたらどう?」
「い、いえ、それは……」
「つけなさい。」
「はい、王女さま。」
「こういう時は、自分が王女で良かったって思うのよ、ふふふ。」
王女があまりに屈託なく笑うものだから、アジェルダも着たり脱いだりで疲れていたはずが、思わず吹き出して一緒に笑ってしまった。
一目見て高価そうな装身具までそろえてくれた王女のおかげで、彼女は王女が望んでいた「圧倒的なカリスマ」をまとうことができた。
「本当に気に入ったわ。」
姫はうっすらと微笑んだ。
その時、侍女の一人がそっと近づいてきて、姫の耳元に何かをささやいた。
姫は侍女が差し出した青い布に包まれた物を受け取り、そっとアゼルダの顔色をうかがいながら彼女を見つめ、首をかしげた。
表情が正直に出る方なので、視線を外そうとしながらも、時折ちらりと目を向けるのがどこか可愛らしく見えた。
姫は侍女たちを下がらせた。
二人きりになると、アゼルダは視線で問いかけた。
姫はもう一度首をかしげ、ためらいながら話を切り出した。
「その……北部で何かあったの? そろそろ戻らないといけない予定だったのに、こんなことになってしまって……。」
話を聞く前からアゼルダは、この話がどう転がるかを察して内心動揺した。
――まあ、いい。仕方ない。そういうこともある。
どうせ彼とは契約関係にあるわけでもないし、正式な夫人として認められようとも思っていない。
いずれは自分の方が先にそっと去らなければならない。
だからいい、こんな関係でも。
「ううん、大丈夫。」
王女は口をすぼめたまま、アジェルダの寂しげな笑みを見て目を大きく見開いた。
「なにが?」
「え?」
「あなた、どうして大丈夫なの?」
「うーん……上公様が、北部で急用ができたから今すぐ帰るっておっしゃったじゃない?だから今日の宴には出席しないって。もともと宴では質問攻めにするお方だから、それも理解できるし……。」
王女は淡い茶色の瞳をぎゅっと閉じ、またふいに開くと、何事もなかったかのように微笑んだ。
「何言ってるの、アジェルダ。私がいつそんなこと言った?」
「え?」
「北部で用事ができて、宴が終わったらすぐアジェルダを連れて帰らなきゃいけないなんて、私そんなこと一言も――だから、高価な衣装は貸してやらないって?なによそれ!いや、その前に私を一体なんだと思ってるの? ねえ? 私がこの程度の宝石も貸してあげられないように見える?そうなの?」
コチータ姫は彼女の首にかかったアクセサリーをもう一度しっかり結び直しながら怒りをあらわにしたが、アゼルダはその剣幕に合わせて怒ることができなかった。
腹が立つというより、彼女の言葉を理解した瞬間、かつてない彼女の庇護に唇がわずかに震えた。
「なんなのあの男は!急用があるにしてもやりすぎよ!はぁ、ほんとに。私が腹立たしい。しかも、私が侍従たちに舞を舞う時に使う剣を探して来てって頼んだの、まったく伝わってなかったのね。」
「……これ。」
アゼルダは姫が差し出した青い包みを手に取った瞬間、それが剣であることを察した。
そっとそれを開くと、中に入っていたのは細身の剣だった。
美しく銀色に輝くその剣は青い宝石がはめ込まれたそれは、最近毎日公爵が腰に差していた儀礼用の剣だった。
実戦には向かないが、宮廷内でも着用できるように作られていた。
彼女がぼんやりと剣を見つめると、コチータ姫は息が詰まったのか、またもや大きくため息をつき、低い声で小さく毒づいた。
「なにこれ、また何よ?うん?今アクセサリーを持たせるって言って、この地味な剣は何?別にきれいなわけでもないし、これ本当に騎士たちが使うあの剣じゃない?私が言ってるのはもっとシャラシャラ音がして装飾がついてる、そんな剣なのに……。ほんと、カルロス公爵ってば、いつも怖いし、無口だし、こんな噂だけ聞いてどんな人か興味なかったけど、あなたがいい人だって言うから信用したのに、どうしてこんなに無神経なの……いま笑ってるの?」
コチータ姫は怒るのをこらえ、アジェルダの目の前に顔を近づけて、にこっと笑ったまま、それ以上何も言わず、彼女の手に握られた滑らかで丁寧に作られた、地味だけれど上質な剣をじっと見つめた。
「……今、その無骨な剣をもらって喜んでるの?」
「私、喜んでるように見える?」
アゼルダは自分がそんなふうに笑っていることに自分でも驚いて口元を触ってみた。
「でも、これ、なかなか形が整ってて綺麗じゃない?」
「綺麗って? ごつごつしてるじゃない! 舞ってのは優雅であるべきでしょ。」
けれど、この剣を渡すというのは大きな意味のあることだ。
前世の彼女なら今の姫と同じように喜んだかもしれないが、自分はこれがどれほど大きな信頼の象徴であり応援の証かを理解していた。
彼がこれを誰かに渡すというのは、簡単には想像できないことだった。
しかも一緒に戻ろうと待っているなんて。
正室を相手にする当然のことにこれほど感動するとはおかしなことだが、心に何かしっかりとしたものを感じた。
そして薄い鉄片でできた華奢な剣よりも、こちらの方がずっと手になじんだ。
公女は彼女の笑顔をひとしきり見つめたあと、ため息をついた。
「はぁ、あなた本当に彼のことが好きなのね。結婚してうまくやっているみたい。やっぱり噂なんて信じるものじゃないわ。」
「……私が好きって?」
「じゃあ、好きでもない人からこんなものをもらって喜ぶの?」
好き…?
アジェルダはその言葉自体があまりにも場違いに思えた。
彼の剣術の腕前を尊敬していたし、彼の考え方を信じていた。
それがすべてだった。
そして自分がそれをもらって喜んでいるのは、そういった種類の剣に慣れ親しんでいるからにすぎない。
かつて傲慢や一度の強引さで大きな痛手を負ったことがあった。
だからこそ、自己主張せずに求めるものを与えることで、北部の支援金をしっかり確保できるなら、それで安く済むと思っていた。
だが、そんな予期せぬ贈り物を手にした今、ここまで応援されている以上、美しく見せなければと考えた。
ちゃんと見せられないにしても、ちゃんと披露できるようにはしたいものだ。
アゼルダはそれを再び布に丁寧に包み、大切そうに胸に抱いて立ち上がった。
「少し練習できる場所、あるかな?」
「いくらでも!」
急に北部に戻らなければならない理由は後で聞けばいい。
今は目の前のこの危機をどう乗り越えるかが先だ。