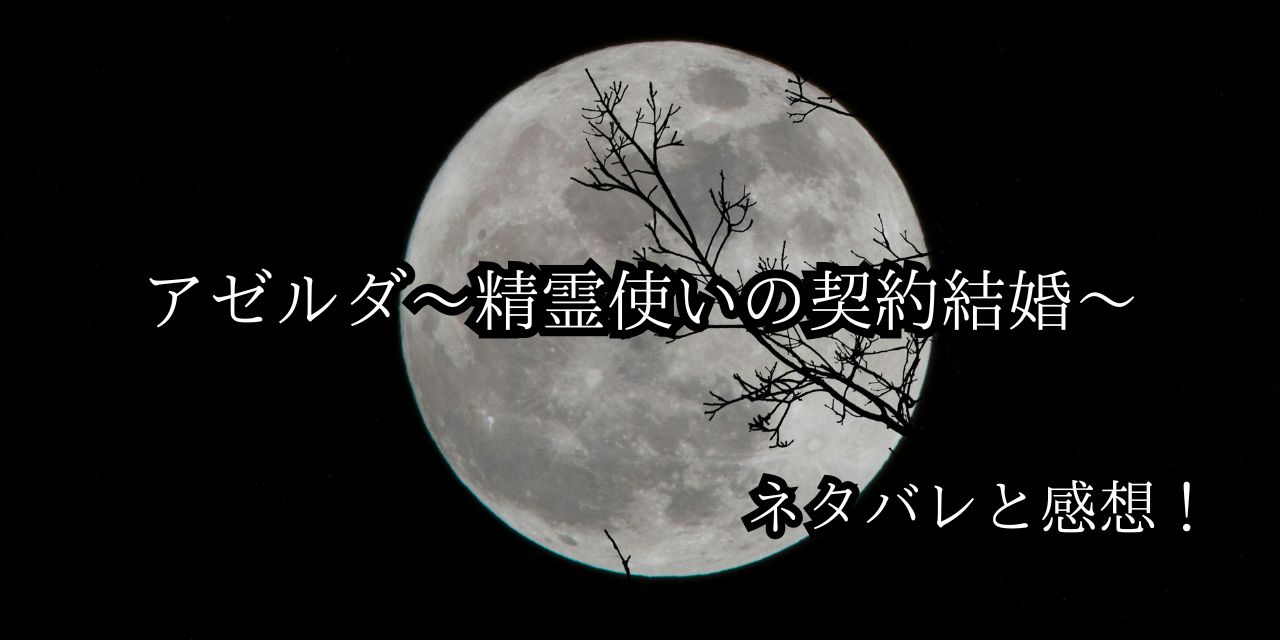こんにちは、ピッコです。
「アゼルダ~精霊使いの契約結婚~」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

38話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 舞姫
チアンドの使臣が出席した宴会は、盛大な音楽とともに始まった。
宴会場で行われていた以前の宴とは異なり、庭園を自由に楽しめるように屋外にテーブルと料理が用意され、その間を召使いたちが忙しく行き来していた。
いくら使臣をもてなす宴とはいえ、配膳を持ち歩く召使いがいるからといって、和やかな雰囲気ではなかった。
出席しているのも高位の貴族たちばかりで、男爵や下級貴族には足を踏み入れるのも難しいほどの雰囲気だった。
接待が静かに進む中、次のコースが次々と提供された。
海とすぐ隣接していないチアンドではなかなか味わえない貴重な海産物料理や、庭園の一角で焼かれた上質な肉料理が食卓に並べられた。
重い知らせを携えて来たとはいえ、チアンドの使節たちは貴賓だった。
彼らは宗教や文化が異なり、自国では味わうのが難しい贅沢な料理と音楽を楽しんでいるようだった。
チャラララン!
侍従がグラスを打ち鳴らす音が、音響装置を通じて庭園に響き渡った。
舞台を中心に半円形に配置された白いテーブルに座る高官たちは一斉に舞台に視線を集中させた。
弦楽器と管楽器を演奏する者たちは座席を占めていたが、中央は空いていた。
先ほどから人々はこの魅力的な初遊の場面がどのように展開されるのか、心配半分・期待半分で見守っていた。
公爵夫人が舞台に上がる。
この衝撃的な事件についてはすでに噂が広まっていた。
紙がパラリとめくられた後、舞台にゆっくりと上がってきたのは王子だった。
王子は声を張り上げるためのマイクの前に立ち、整った角度で前髪を上げ、顎を引いた。
「こんにちは、皆さん、この演会を楽しんでおられますか?」
礼儀正しい拍手の音が響いた。
「今日はチアンド国から直接このように訪問してくださいました。司祭様たちは地位に高低はないとおっしゃいますが、神に仕える声の方々がこうして直接訪ねてくださったことには、深い意味があると私は思います。チアンドとヴァレリアに栄光あれ。」
「栄光あれ!」
カン、カン!
グラスがぶつかる音があちこちから聞こえた。
王子は話を続けた。
「私は王位継承者に任命された後、いくつもの国をこのように巡ってみました。貴賓のために、その国の貴重な公演を披露してくださることが多いのですね。演劇や歌、特に美しい舞のようなものです。」
優雅な姿勢で話す王子を、舞台裏から見守っていた王宮の宴会担当内官の胸中はざわついた。
通常このような雰囲気が和らいで、宴の進行役や司会者が出てきて少し話すときには、舞台裏にはダンサーや派手な演劇用の衣装を着た出演者たちが出番を待機していなければならない。
そういう段取りだった。
──なのに、この舞台裏がどうしてこんなに空っぽなのか?
王子の話がうまく進むほど、人々の反応が良いほど、内心はさらに焦った。
これは非常事態だ。
自分はこの舞台を特別に任された人を呼んだことがない。
なのに昨日突然、王子が自分を探し、この舞台を埋めるのにふさわしい「彼女」を呼んだのだった──。
したがって、翌日に使えるように舞台を設置するよう命じ、仮設舞台を立てはしたが――
その適任者がカルロス家の公爵の側近だと聞いたときから、すべてがおかしくなっていると気づいていた。
そんな人物が本当に舞台に上がるのだろうか?
今日の演会ではチアンドの使節たちが長く滞在できないということで、さまざまな余興を企画することもできなかった。
万一に備えて、国内で有名な音楽詩人を急いで呼ぼうとしたが、この場にふさわしい人材を見つけることはできなかった。
耳が肥えている高位の人々ではないか?
下手な人選では自分だけが非難される羽目になる。
やはり舞台の裏は空っぽで、舞台に上がる者は見当たらなかった。
もし舞台が埋まらなければ、自分が責任を問われることになるかもしれない。
いっそ誰でも呼んで立たせたほうがよかったのではないか?
余興担当の内官はそっと唇を噛んだ。
その間に王子の話は終わりに近づいていた。
「紹介」や「踊り」といった単語がちらほら聞こえ始めた。
危機が差し迫っていた。
もうダメだ。
すべて台無しだ。
そう確信した瞬間、後ろからはっきりとした足音が近づくのが聞こえた。
「ここで待機すればいいですか?」
慌てて振り向いた彼は思わず息を呑んだ。
この人が公爵夫人だって?
澄んだ青い瞳と色白の肌、金色に輝く豊かな髪、そしてぴったりとした上着と白いズボン。
首と手首にはぴたりとくっついたブレスレットのようなバングルが光っていた。
腹部を見せる短い上着に、空色の透けるロングスカートを着た他の舞姫たちとは比べものにならないほど落ち着いた装い。
しかも彼女がズボンを履いていることに驚き、思わず口がぽかんと開いた。
内官は彼女の腕と首で輝くバングルをまじまじと見つめた。
まさか、あれはダイヤモンドじゃないよな?
あんなの、自分の退職金全部でも買えないだろう…。
特に理由もないのに、なぜあれがダイヤモンドに見えるのだろう?
馬鹿げた考えを抱いた自分を叱咤しながら、彼はぴしゃりと気を引き締めた。
自分と同じように顔色が真っ青になって待機していた侍従たちが、舞台のほうからさっと駆け降りてくるのが見えた。
「ぶ、舞台に今出られますか?」
「はい。」
女性はかすかに答えながら、両手でしっかりと握っていた儀式用の剣を力を込めてしっかりと握り直した。
その手で剣をすっと軽く回す動作は、女官のそれとは思えなかった。
普通の武官たちは剣をあのように持つのか?
あれでは武官ではなく、まるで市中の剣士や傭兵のように見えた。
そんな思いも束の間、内官は駆け寄ってきた侍従たちに彼女の引率を任せた。
侍従たちは王子の紹介に従い、彼女を連れて退出した。
「たとえその内容が機密であっても、それをあらかじめ我々の未来を見越して備えることができるようにしてくださった貴賓の皆さまをお迎えするこの場において、我々もまた、特別な舞台をご用意いたしました。他では決して見ることのできない舞台。バレリア北部を守護するカルロス公爵の命を受けて、直接舞台に上がってくださるアジェルダ・カルロス様を、ここにお迎えいたします!」
再び拍手とグラスを打ち鳴らす音がワーッと湧き上がった。
彼女は舞台の見えない場所に立っていたが、一歩前へと出た。
まるで約束されていたかのように、タイミングよく拍手が幾重にも重なって響いた。
舞台の正面を見つめながら立っている彼女の姿勢は凛としており、その瞳には人間とは思えないほどの荘厳な気配が漂っていた。
その威厳に誰もが目を離すことができなかった。
彼女の美しさに魅了されたのは、舞台下にいた貴賓や貴族たちだけではなかった。
王子さえも、自分の台詞を言い終えて退こうとしたその足を止め、その場に立ち尽くしてしまった。
まるで魚のように死んだ瞳が、彼女の凛とした眼差しに射抜かれていた。
王子はしばらく隣に立っていたアジェルダを見つめた後、彼女の手を取り、その手の甲に口づけした。
「……こんなふうに現れるとは思わなかった。本当に面白い、まったく。」
もし問題がなかったとしても、今持っている儀式用の剣でその首を切り落としたいと思いながら、アジェルダは彼を睨みつけた。
おかげで緊張感も少し和らいだ。
多くの問題が絡み合い、まるでクモの巣に縛られたように自分の思うようには動けなかったが、いっそあの王子の首を絞めてやりたい。
命を軽んじたその代償を命で払わせてやりたい。
彼女が王子のそばを通り過ぎて舞台の中央へと進み、そこに立つと、合図を待っていた管弦楽団が演奏を始めた。
ちょうどその音楽は、公女が選んでくれたゆったりとした協奏曲だった。
音楽の幅が狭い器に完全に任せきりだったが、単調な旋律のどこか陰りあるその曲は、彼女の年若い表情によく調和していた。
両手で剣の刃と柄を頭の上に掲げて立った彼女は、ゆっくりと目を閉じ、深く息を吸い込んだ。
前世で見た数々の光景が脳裏をよぎった。
舞姫がやってきて披露する公演は何度か見たことがあった。
それが自分が習った剣舞とはまったく異なることを、彼女はわかっていた。
ロイナはこの剣舞を教えるときに、「相手の急所を攻める術を知り、剣術と儀式を結びつける稽古の一環として剣舞を学ぶべきだ」と言っていた。
ただ美しく、優雅な剣舞ではない。
しかし、アジェルダはロイナに教わった剣舞を恥ずかしいとは思いたくなかった。
アジェルダは慎重に腕と脚を動かし始めた。
観客席は息を呑んだ。
「公爵夫人が踊るとは、一体どんな公演になるのだろう?」と考えていた一部の者や、「またあの王子が変なことをしようとしてるな」と思っていた者たちも、皆、彼女のゆったりとした美しい剣舞に目を奪われていた。
チマ(巻きスカート)ではなく、力強い表情が隠せないのではと思っていたが、引き締まった筋肉の動きはむしろさらに美しく見えた。
彼女は蝶が舞うように軽やかに足を上げては下ろし、重心を移動させるたびにすぐに均衡を取り戻した。
足をほとんど動かさずに移動していたが、それがぎこちなくは見えなかった。
自分の体を自在に操れる身のこなしだった。
チャランと金の鈴が空中で音を鳴らし、ゆるやかな円を描いた。
剣舞ではひらひらと回しやすい細く美しい剣を使うのが普通だが、彼女は儀式用の長い剣をまるで手に馴染んだかのように操った。
重さのある剣をピタリと止めては、滑らかに回転させる動作に観客から感嘆の声が漏れるほど見事だった。
タッ。
両手で剣を床に突き刺すように置くことで、一曲の舞いの締めくくりとなった。
パチパチパチ!
弦楽器の音色だけが満ちた中で、静まり返っていた庭園に、拍手の音が一斉に響き渡った。
「ブラボー!」
「さすがはバレリアの王宮、見るものが多い!」
使節たちさえも感嘆する声を上げるのを聞きながら、シェイドは自分もまた見入っていたことに気づき、はっとした。
「わあ、本当に剣をかなり使いこなしていらっしゃるんですね? まさにお見事です!」
ブユは救済院に行った後、シェイドの前でアジェルダを呼ぶとき「奥様」と呼ぶようになった。
シェイドはブユの態度が変わった理由を理解できた。
自分自身もこの女性には頭が上がらないほど感服しているのだから。
「何を言ってるんだ。それより戻って片付けは?」
「奥様さえご準備くだされば結構です。」
「わかった。」
シェイドは拍手が鳴り止まないその中で、長く思いにふけっていた。
続けて腕を空中に優雅に上げてから下ろし、挨拶するアジェルダを見つめた。
剣をかなり扱ってきた人だな。
本当にそうだ。
そしてその動きの様子は、どこか見覚えがあるように感じられた。
シェイドはロイナの顔を思い浮かべた。
ロイナの剣術と、あの女性が剣を扱う方法は確かに似ていた。
ロイナから直接習った剣術であれば、見覚えがあるのも当然だ。
どこかで見たように感じたのはそのためだろう。
彼は王子が再び舞台に上がっていくのを見て、うっすらと目を細めた。
節度を知らぬ王子だった。
乱れた金髪と今にも滴り落ちそうな汗をぬぐっていたアジェルダは、トコペン王子が舞台に上がってくるのを見ると、わずかに身を引いた。
しかしトコペンは笑いながら彼女のすぐ隣に歩み寄り、舞台の下にいる人々に聞こえるような大きな声で言った。
「皆さん、アジェルダ・カルロス公爵夫人の舞でございました!上手く見られましたか?はは、私が言わなければ惜しくも見逃すところでした。」
アジェルダは何の気もなく、盛大な拍手を送り歓声まで上げている観客たちに向かって、ぎこちなく口角を上げ、もう一度腕を掲げて胸に手を当てて挨拶した。
「綺麗だ。上手くて、堂々としていて。」
王子は必要以上に近づいてきた。
目が合ったのに体が動かせなかった。
アジェルダが一歩下がると、王子も同じだけ一歩近づいてきた。
ブユは拍手をしていたが、舞台の雰囲気が何かおかしく見えて手を止め、シェイドを見つめた。
その光景を見ていたシェイドも座っていた席から立ち上がった。
王子がシェイド自身の手に握られているすべてを惜しまず差し出すつもりでいることはわかっていたが、これは一体何の儀式なのか?
アジェルダはその称賛の言葉を口にしながら、自分の露わな肌をまじまじと見つめる王子に、居心地の悪さと恥ずかしさを感じた。
そしてすぐ歩き去ろうとしたとき、全身の毛が逆立つような感覚が走った。
彼女は慌てて舞台の下へ降りようとしたが、王子の手が彼女の腰に回された。
平手打ちを一発食らわせたい衝動を、歯を食いしばって耐えた。
いや、いっそその首をはねてしまいたいという衝動すらも必死に抑えた。
しかし、彼の手が自分の体を触れていることにはこれ以上我慢できなかった。
その腕を振り払って、無理やり突き放した。
「なんてこと……!」
観客席に座っていた他の高官たちや使節たちも、この事態に驚いたのか、みな一様にどうすればいいか分からず舞台を見上げていた。
王子が度を越す言動をすることはあったが、これは明らかに一線を越えていた。
他人の妻を公の場で追い回すとは!
王子は払いのけられた手首をぼんやりと見下ろし、明るい金髪の下にある冷たい目元が彼女をじっと見つめた。
明らかに機嫌を損ねた様子だった。
トコペン王子はこれではいけないと、後方の貴族席では冷静に見ている者もいた。
自分でも、こんなふうに行動している自分が不思議だった。
これまで女性たちは、ただ誘惑の対象だった。
こんなにも衝動的に、他人の視線を気にせずに行動したことは一度もなかった。
「なぜこんなことをされるのですか?」
「こんなに多くの人の前で、私に気を引かせるおつもりですか?」
それなら、あなたはこんなにも多くの人の前で、私という女性を追いかけるつもりだということですか!
言葉では何とか取り繕ったものの、目からはそのときの戸惑いを隠すことはできなかった。
王子は拒絶に慣れていなかったし、戸惑いにもさらに慣れていなかった。
彼の手が彼女の肩を動かした。
もはや貴賓がどうとか、そんなことは関係のない眼差しだった。
最前列で冷静にその一部始終を見守っていたコチータ姫は、顔が真っ青になった。
彼女が侍従たちに凍ったようなカーテンを下ろすよう合図すると、侍従たちは舞台前方を覆っていたカーテンの束を一斉に解いた。
シェイドが舞台の上に飛び上がるや否や、カーテンが一斉に下ろされて舞台を覆った。
チアンドの使節たちは、この騒動が一体何なのか分からず、互いに困惑した表情で見合わせていた。
ヴァレリアの貴族たちは、王子が見せた振る舞いのせいで顔色が青ざめていた。
シェイドが舞台に上がったのは、王子が自分に対して欲望を抱いていた上に、観客全体の前で品のないこの女に恥をかかせようとしたのだと感じたからに過ぎなかった。
「トコペン!」
アジェルダは復讐のためなら何でもやってのけると思っていたが、この王子の下品で無礼な行為はあまりにも常軌を逸していて、考える間もなく彼を打とうとした。
しかし、アジェルダがその手を振り上げる前に、シェイドが二人の間に割って入って押しのけた。
シェイドとトコペン王子の視線が交錯した。
トコペンはシェイドを見上げながら、無理に笑みを浮かべた。
「まだ約束したことはすべて終わっていないと、わかっているはずだが。」
シェイドは眉をひそめて王子をにらみつけた。
「トコフェン。」
「なんだ?俺の言うことが間違ってるか?」
「私の夫人を侮辱するな。」
王子は舞台の床に足を組んで、前髪をかきあげた。
シェイドがアジェルダの前に立ちはだかっているのが気に食わない様子だった。
「昔からお前は器用ではなかったが、女に対して不器用なやつでもなかった。だが、どうやら夫人がかなり気に入ったようだな。女ができると、もともとそんなふうに突然惹かれるものなのか?俺がかなり良い縁を繋いでやったんじゃなかったか?」
シェイドはこれ以上口論を交わすつもりはなかった。
ただ黙ってアジェルダを舞台の外へ連れ出そうとするだけだった。
しかし王子はまるで彼を行かせまいとするかのように、立ちはだかった。
普段であればこの程度で王子があきらめるはずだったのに――。
以前のシェイドは「王子」という身分にひれ伏していた。
これ以上自分の誠実さを疑われるのは損だとわかっていたから、我慢していたのだ。
しかし今は何かが違っていた。
シェイドは人を睨みつけるような目で王子の視線を真正面から受け止めた。
彼には絶対に見せたことのない眼差しだった。
「それでもお前にはナリムの臣下としての面目があると思っていたし、その点だけは尊重してきた。これ以上、はしたない真似はするな。」
「……こ、こいつは正気か!」
王子は怒りに顔を真っ赤にして叫び声を上げたが、シェイドは動じることなくアジェルダを護衛して彼の前をすっと通り過ぎた。
王子は踏みとどまりながらも道をふさごうとした。
だが、無言でその言葉を聞いていたいつものシェイドとはあまりにも違う姿に、彼は思わず動揺した。
まるで自分の名を呼びかける猫に威嚇された子ネズミのように、ただうろたえるだけでその場に立ち尽くしていた。
淡い空色の衣をまとった女性とその夫が舞台から完全に姿を消すまで、トコフェンはあまりの気迫に圧倒され、身動きできなかった。
庭園の端の控室まで退いて他人の視線を避けたあと、シェイドはアジェルダの肩を確認した。
うっすらと赤みが残っていた。
王子が手で掴んだ部分だ。
親指でそっと触れてみていた彼は、自分を見つめるアジェルダの淡い瞳に気づき、ゆっくりと手を引いた。
「大丈夫ですか?」
「何ともありません。」
「見た目には問題なくても、気分は悪いでしょう。あんな奴じゃなかったのに、どうしてあんな無礼な真似を……」
王子にこれほどまでに厳しい表現を使うシェイドを見るのは初めてだった。
相手が耳を貸さないことをわかっていても、たとえ自分が侍従であっても、王子を呼ぶときはいつも礼儀を守っていた彼なのに。
どういうわけか、その姿に胸が締めつけられるような気持ちになった。
心配そうなまなざしでじっと人を見つめるあの澄んだ青い目の前で嘘をつける人が、果たしてどれほどいるだろうか?
「もう大丈夫です」という言葉は、もはや意味を持たない気がした。
大丈夫ではなかったからだ。
しかし、この辛い気持ちを理解してくれるというだけでも慰めになった。
アジェルダはただ気まずそうに微笑みながら、彼の目が落ち着くのを待ち、それから儀式用の剣を再び納めた。
「ありがとうございました。」
「感謝します。」
アジェルダは小さく微笑みながら、深くお辞儀をした。
やはり感謝の言葉をもらうのは、嬉しいことだった。
「戻りましょう、奥様。」
「はい。」
「テレポートゲートに移動するつもりですが、今行っても大丈夫でしょうか?」
「……はい、大丈夫です。」
シェイドは上着の小さなポケットからハンカチを取り出し、彼女の額ににじんだ汗を優しく拭ってやった。
かつて王城に初めて来た時の、まるで場違いなところに迷い込んだ人のように、彼女は蒼白くこわばっていたと思っていたが、今は顔色もすっかり戻っていた。
「戻るぞ、ブユ。」
「はい!」
庭園の入口までは徒歩で向かわなければならなかったが、その先からは馬で移動できた。
シェイドはアジェルダに急ぎの用があるので一緒に馬に乗ってくれるよう頼み、アジェルダは隣の鞍にどう座ればいいのかわからず、ズボンを履いていることを幸いに思った。
滑らかに馬に乗ろうとする彼女を少し異なる視線で見ていた彼は、彼女の後ろに乗って手綱を掴んだ。
都心を移動中、防衛軍の兵士たちが慌ただしく走っているのが見えた。
何か事件が起きたのかと一瞬脳裏をよぎったが、首都ではそう大きなことにはならないだろうという思いに駆られ、その考えをすぐに追い払った。
王の騎士団と侍従一行はすでに近くに集結しており、彼らとともにテレポートゲートの前まで素早く移動することができた。