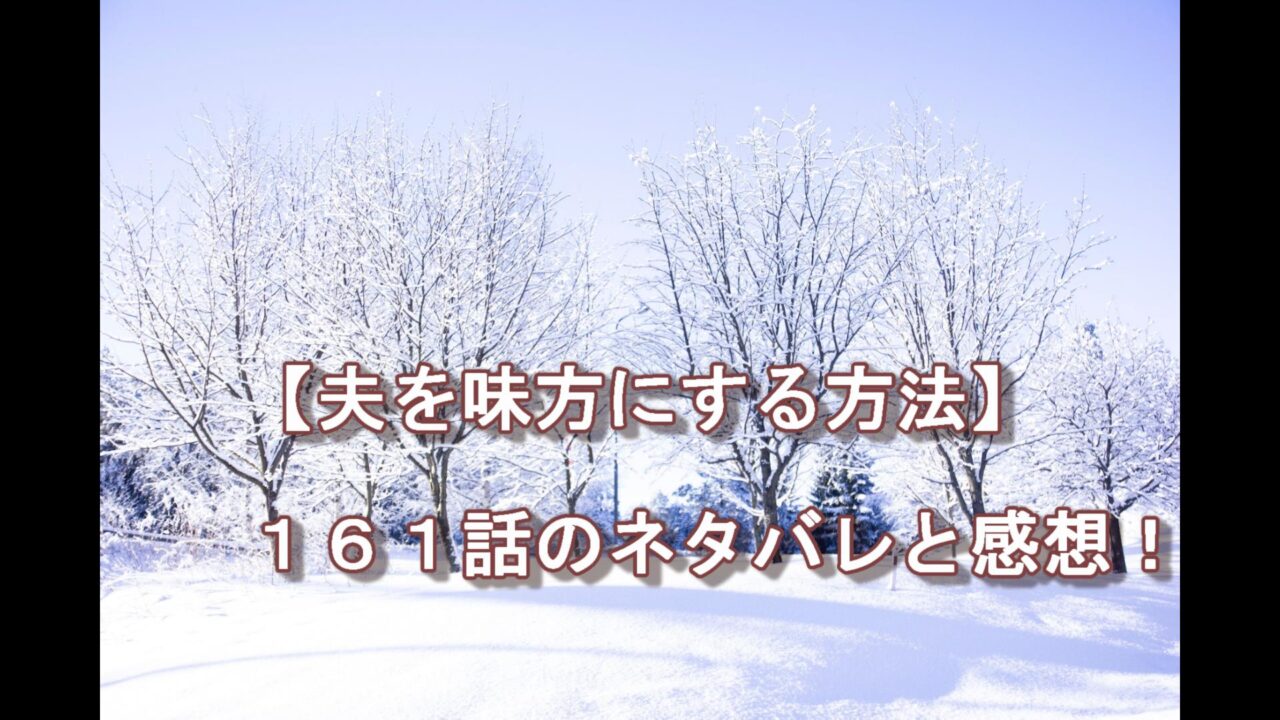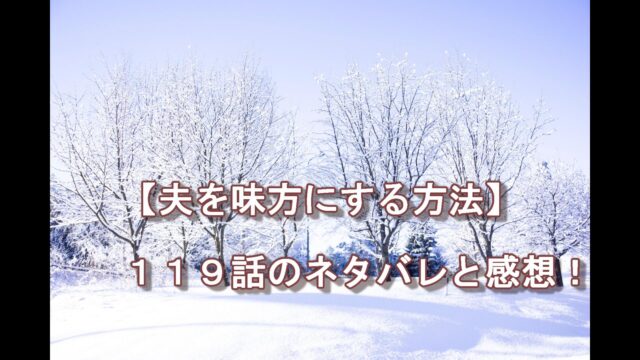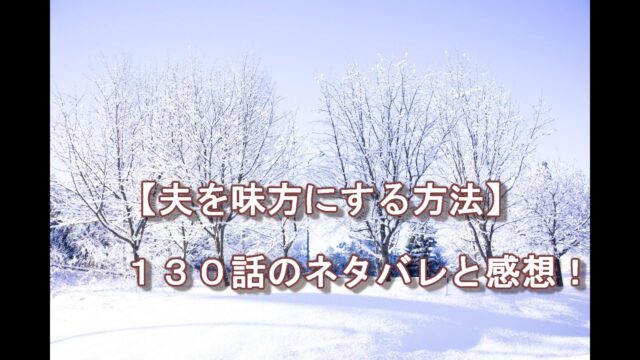こんにちは、ピッコです。
「夫を味方にする方法」を紹介させていただきます。
今回は161話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

死ぬ前に読んでいた本の中の悪女ルードべキアに憑依してしまう。
前世では養子となった家族から虐待を受けていたけど、ルードべキアも同じような境遇だった…。
しかも父によって政略結婚させられた北部最高の冷血な騎士イースケは原作で自分を殺すことになる夫だった!
小説の内容をすでに知っているルードべキアは、生き延びるために夫を愛する演技をするが…
ルードベキア:ルードベキア・デ・ボルヒア。本作の主人公。愛称はルビ。
イースケ:イースケ・バン・オメルタ。ルビの結婚相手。愛称はイース。
エレニア:エレニア・バン・オメルア。イースケの妹。愛称はエレン。
フレイヤ:フレイヤ・バン・ピュリアーナ。イースケの幼馴染。
ボルヒア:教皇。ルビの父親。
チェシアレ:チェシアレ・デ・ボルヒア。長男
エンツォ:エンツォ・デ・ボルヒア。次男。
ローニャ:ルビの専属メイド

161話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 馬鹿みたいな表情
私は手を上げて、イースケの不器用な鎧の胸板に当ててため息をつくふりをする。
「遊びで忙しいようですね。北部の社交界を制覇するつもりなのか、あらゆる集まりごとに出席して興に乗るのに忙しいらしいです。事故を起こさないでほしいですが」
「ふむ、夜が更ける頃には、一人でこっそり抜け出して、赤い灯りのついた街に行くという噂が聞こえてきたよ」
「誰がそんなことを言ったんですか?」
「うちの護衛の一人が見たんだって」
「・・・それであなたは何と言ったんですか?」
「君は一体どうしてそこにいたのかと聞いた。本当に気になって聞いてみただけなのに、急に気まずくなってね」
分かる気がして、笑いが出た。
黒い板金の鎧のあちこちをいじっている間、彼の視線が私をじっと見つめた。
どうして急に真剣になった雰囲気で、私もそっと視線を向ける刹那。
「確かに種類が違うようだね」
ひんやりと沈んだ声は、私に言う言葉というより呟きに近かった。
そうしては、じっと見上げる私の視線を避けるように、首をさっと回してしまう。
「イース?」
「・・・」
「イース、どうしたんですか・・・?」
しばらくの間、何の返事も聞こえてこなかった。
彼の表情を見るために少し体をばたつかせようとしているところに、ようやく彼が再び口を開く。
「何でもできると勘違いしていた」
「え?」
「だけど、いざ一番切実な瞬間には・・・、ちっ、偉い家門の名前も名声も何も何の役にも立たないな。相手が法王の長男だからといって」
「・・・」
「頭の中では数百回も裂いて殺したが、現実では何もできない。・・・私がこんなに無力な奴だったとは」
自嘲的ではなく、惨愴たるつぶやきに心臓がドキッとする感じが起きた。
ああ・・・、イースケはチェシアレの問題をただの一度も隅に押し込んだことがないようだ。
あの祭りの間に起きて明らかになった全てのことをいつも思い出して苦しんでいたのだ。
あなたが自責することではないという話はすでに何度もしている。
にもかかわらず、彼は依然としてつらい自責の念に苛まれていたのだ。
自責の念と私には計り知れない怒りに襲われ、イースケは身震いしていた。
私は少し体を動かし、彼にぴったりと寄り添う。
手を上げて広い肩を優しく撫でると、彼が頭を少し上げた。
「イース・・・、やめてって言ったじゃないですか。私があなたに会うずっと前から始まったことでもあるし、あなたがあの人を思い出して苦しむのは・・・」
「あの時、あいつを殺すべきだった」
「それならあなたは?私は?お父さんじゃなかったら、私が止めたんですよ。もちろん、私もあの人間が倒れて死んでしまえばいいのですが、むやみに殺したからといって終わりではないでしょう」
慎重に付け加えると、赤い瞳がこの上ない奇妙な光で揺れ動く。
「たった一度も権力が惜しかったり欲しがったことがなかったのに・・・」
うん?
「オメルタの名前だけでも十分だと思っていたが、もうそれだけでは足りないということがはっきり分かった。これを機にいっそ・・・」
彼の目にちらつく意外な光の正体は何だったのだろうか。
野望?権力欲?
いや、そういうものよりは一層高次元的な何かだった。
龍が噴き出す熱気によって空気が暑かったにもかかわらず、首筋が涼しくなる。
今、イースケは一体何を考えているの?
しかし私がまた口を開く前に、イースケは眼を何度か激しく瞬きし、あっという間にその表情を消して、私に向かってくすくす笑った。
「夫が少し震えたからといって、そんな表情をする必要はないじゃないか」
「・・・私がどんな表情をしているんですか?」
「馬鹿みたいな表情」
「バカって・・・あなたが先に馬鹿なことを言ったからじゃないですか!」
「そうかな?ごめん、運命にもないことに悩まされているうちに、哀れな思いが込み上げてきて。ちょっと抱きしめて慰めてくれるんじゃないかと思ったんだ」
肩をすくめていちゃつく夫は、少し前の奇妙な違和感は跡形もなかった。
本当に大丈夫かな?
それとも、ただ私を心配させないようにしているだけ?
とにかく、さっきの話題をまた続けたい気持ちもその気配もなかったので、私は彼を睨みつけるふりをして、鎧の上をぎゅっぎゅっと押した。
殴るふりをすると、私の手のひらがもっと痛くなりそうだったからだ。
「なんでそんなに掃くの?手のひらが汚れるじゃないか」
「不思議だからですよ、不思議だから」
「また、何がそんなに不思議なんだろう」
「まずは色から行きましょう。聖騎士の鎧なら、たいてい明るい色で作るじゃないですか。白とか銀色とか、パッと見た時に神聖で正義感のあるイメージでですね。その円卓?騎士団の方々も銀色でしたよ」
「私たちがちょっとあれだね。創立の時から二股をかけた立場なので、真っ黒なことが表に出せていないからやきもきする。だから気に入らないのかな?」
「アハハ、いいえ。むしろパラディンらしくない鎧だから、もっとかっこいいんだけど。私たちが本当に夫婦になったその日、あなたが宴会で着ていたほどではないですが」
過去のことを思い出しながら、感傷に浸るために私が今何の音を吐いたのか認知するのに少し時間がかかる。
遅い悟りにびっくりした時、夫はすでにとても見識のある顔をしていた。
「あれが気に入ったの・・・?」
「き、気に入ったというよりは悪くなかったというか・・・」
「今、この鎧よりかっこいいと言ったじゃないか。ああいうスタイルが好みだったのかな?」
好みだなんて!
そんないやらしい趣向なんてないよ!
顔に血がばっと集まる。
私は一体何に取りつかれてうわごとを全部言ったんだ?
「そんなことないですよ」
「願ったらまた着てあげられるのに。これから宴会の度に着替えてこないとね。みんな私が一生懸命働いてきたと思うだろう」
「それはダメです!」
大声で叫ぶと、イースケはぎょっとして真っ赤な目を見開いた。
私がおかしくなったよ、本当に!
「ああ、びっくりした。なんで?好みなんだろ?」
「好みなんて・・・!いや、他の人たちがしきりにあなたを・・・、まあもともといつもそうだけど、あれを着たら特に目を通すじゃないですか!一体何の服があの形なんですか!本当に仕事の時に着るものではありますか?」
「あんな模様って・・・それなりに重要な制服なんだけど。二股をかけたロンギヌス騎士団が国王の密命を奉る時に任務を遂行するために備える・・・」
「何の任務ですか?」
「え・・・?それは国家機密なんだけと・・・」
「はあ!?一体どんなに秘密の任務で、あんなデザインが必須不可欠なんですか!」
「それは・・・当然鎧よりはるかに軽いから動きも速く面積が小さいから体臭が少ないから気配がばれる恐れも減り、雨や雪が降っても濡れて傷が付いたらすぐに分かるし・・・他地方出身のやつらがよく知らないやつらは、ただある道に迷った外国人だと思うから油断させることも容易だと」
「絶対に北部で着るような服ではないですよね?それでも普段はだめです!私と一緒にいる時だけ着るなら!」
文句を言いながら付け加えると、しばらく沈黙が流れた。
あの服のインパクトは大きいですよね!
一応、便利性重視だったようです。




https://recommended.tsubasa-cham.com/matome/