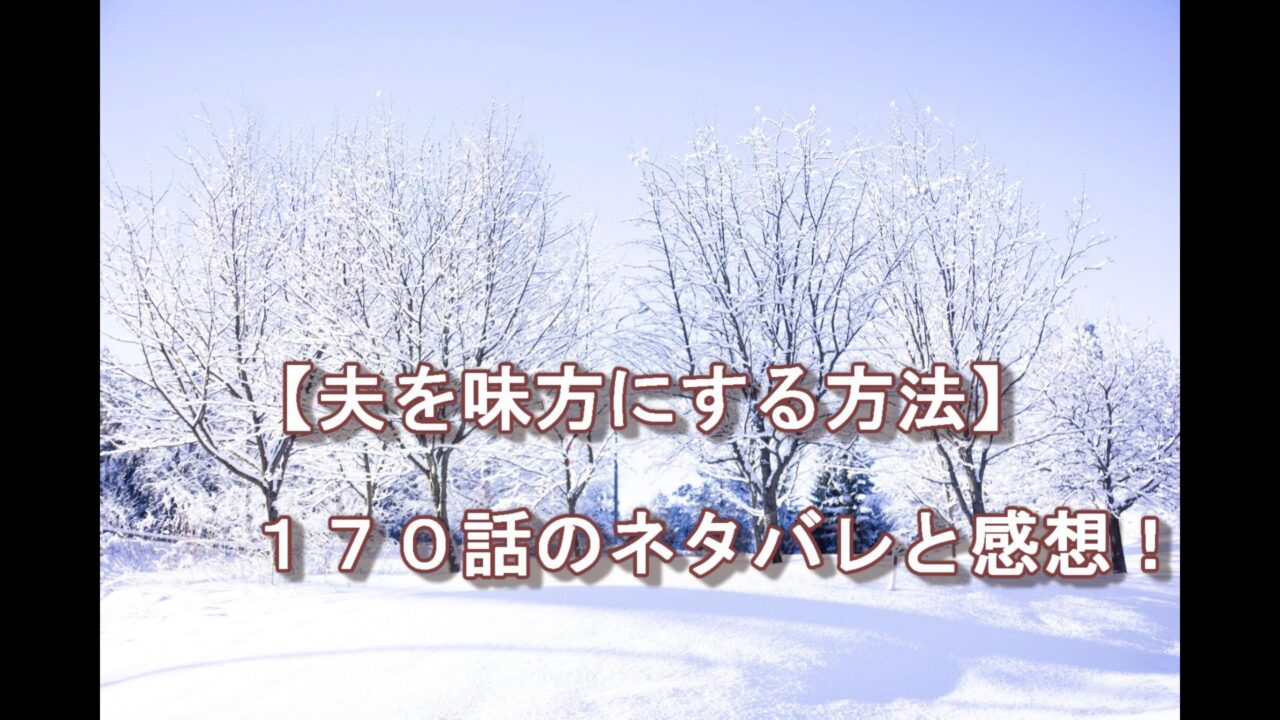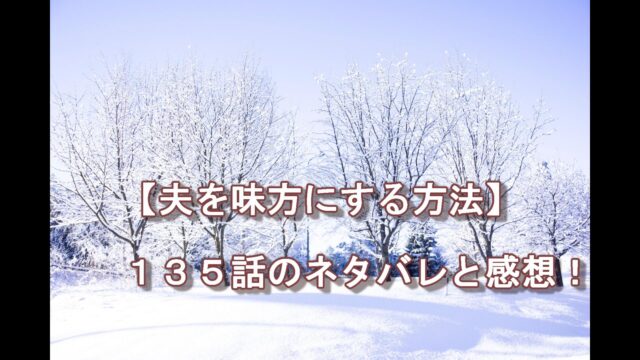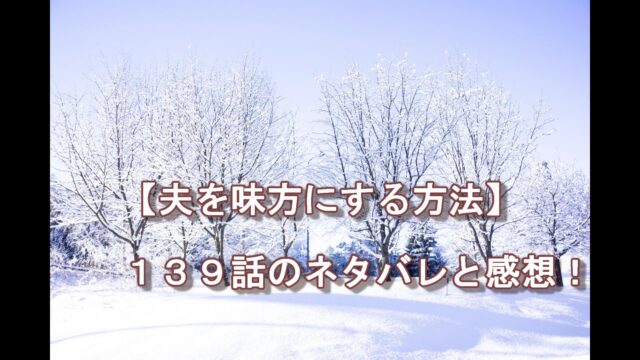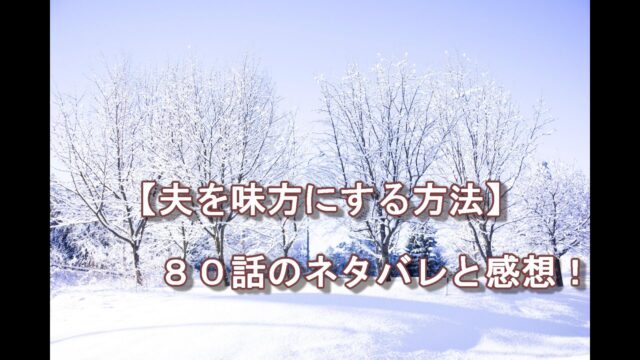こんにちは、ピッコです。
「夫を味方にする方法」を紹介させていただきます。
今回は170話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

死ぬ前に読んでいた本の中の悪女ルードべキアに憑依してしまう。
前世では養子となった家族から虐待を受けていたけど、ルードべキアも同じような境遇だった…。
しかも父によって政略結婚させられた北部最高の冷血な騎士イースケは原作で自分を殺すことになる夫だった!
小説の内容をすでに知っているルードべキアは、生き延びるために夫を愛する演技をするが…
ルードベキア:ルードベキア・デ・ボルヒア。本作の主人公。愛称はルビ。
イースケ:イースケ・バン・オメルタ。ルビの結婚相手。愛称はイース。
エレニア:エレニア・バン・オメルア。イースケの妹。愛称はエレン。
フレイヤ:フレイヤ・バン・ピュリアーナ。イースケの幼馴染。
ボルヒア:教皇。ルビの父親。
チェシアレ:チェシアレ・デ・ボルヒア。長男
エンツォ:エンツォ・デ・ボルヒア。次男。
ローニャ:ルビの専属メイド

170話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 王妃の過ち
ブリタニアのロンギヌス騎士団。
一様に優れたパラディンで構成された彼らは、建国以来現代に至るまで神殿の守護者であると同時に、王室に忠誠する騎士としてずっと二股をかけている妙な立場を固守してきた。
したがって、ロンギヌスの指導者、つまり騎士団長は他のどの騎士団長よりも特別に昇進した引っ張る能力に並々ならぬ美徳を備えていなければならない。
両者に忠実だが、決定的な瞬間には片方の頭を自ら崩すこともできる。
それが歴代のロンギヌス騎士団長たちの諺であり律法だった。
そして現在、惨愴で何と説明することも何かの事件が相次いで起きているこの決定的な時局で、現騎士団長のバロンズ卿がどちらを選んだかは非常に自明だった。
そうでなければ、目の前で大切にしている部下が王権に挑戦する途中で粉々にしようとする姿を放っておかなかったはずだから。
そして、それはバロンズ卿だけではなかった。
ただ、時ならぬ偶像崇拝で神殿が脅かされたという、神殿の守護者としての名分のためだけではなかった。
「イースケ卿!」
「止めてください!今すぐ止まってください!」
驚愕に満ちた必死の叫び声は、すべて1本の脚しかない近衛兵たちのものだ。
しかし、彼らだとしても、目が回るところに戻った北部最高のパラディンを遮るにはカ不足だった。
「・・・ああっ!」
けたたましい破裂音が鋭い悲鳴と同時に響き渡った。
防ごうとする近衛兵たちをあっという間に振り切って駆け付けたイースケが、そのまま王妃を捕まえて立たせ、床に投げ捨てたために起きたことだ。
正確には投げ出された王妃が鏡の壁にぶつかったために。
「妃殿下!」
「バロンズ卿、どうか・・・!」
「なんでみんな見てるんですか!?」
近衛隊長の血を吐くような恨みにも関わらず、バロンズ卿はただ苦々しい表情で応対するだけだった。
そのそばにずらりと並んだ少数の精鋭も、ひたすら苦々しい目つきだけを交換している。
向かい側に立っているオメルタ家の人物たちの方を言えば、こちらもまたそれほど違いがなかった。
公爵はいつものように何を考えているのか分からない顔で見守るだけで、公女もいつものように限りなく無表情だった。
すなわち、あの聖剣を抜いて宮殿に乱入して暴れる傍若無人パラディンを止められる唯一の者たちが一様に手を放した状態なのだ。
仕事が回っている内幕を詳しくは知らないが、大体は聞いた近衛兵たちはもう泣きたくなった。
彼らもまた、信仰者であり北部人として王妃の蛮行を容認する心は全くなかったが、それでも王家の守護を誓った近衛兵として現在の事態を放置することはできないではないか。
「イースケ卿!」
したがって、殺気が燃えるベロア宮についに国王の声が響き渡った時、近衛兵たちはむしろ安堵してしまった。
あまりにも早い安堵だったが。
「すぐ止めろ!」
自分の前に立ちはだかっている叔父をしばらくじっと見つめるイースケは、不思議なほど何の表情もなかった。
半分ほと解けたようだった目つきもまた、きょとんとしている。
同じように鈍い声で彼は吐き出した。
「どいてください」
「イースケ卿、これは一体どういうこと・・・」
「「退け」と言ったのですが。どうしてみんな一度で分からないんですか」
「・・・卿。王妃を切ろうとするつもりか?」
「外さなければ私も仕方がありません、纂奪者でもいいから。親族殺害こそすべての王家の美徳だそうです」
息がまともにできないほど圧倒的な殺気が空気を押しつぶしていた。
王の満面から血の気が引く。
ちょうどその時、誰も予想できなかった人物がこのきわどい現場に乱入した。
みんな気づくのに少しかかったくらい小さな人物、わずか6歳になった幼い王女が人々の間を通り抜けて矢のように走っていく。
どれだけ速い速度だったのか、近衛兵が捕まる前に王女はすでに王家を屠殺する勢いをしている従兄弟の足にぶら下がってわあわあと泣いていた。
「助けてください、お兄さん。お母様を、どうか殺さないでください」
辛うじて身を落ち羞かせていた王妃も、そのような王妃を遮っていた王も、一斉に驚愕の色になってしまったのは当然のことだろう。
彼らだけでなく、今まで手放しで見守っていた人々もぎょっとした。
「ア、アーリエン・・・」
「助けてください。どうか助けてください・・・私が悪かったです、全部、全部私のせいです。私のせいなのに、あまりにも怖くて、あの時あまりにも怖くて助けてあげることもできなかったのに・・・」
無表情な顔で王を見つめていたイースケが、ゆっくりと下を振り返る。
ぼんやりとしたルビ一色の目にいらいらが広がった。
「フアアアン、私のせいで、私のせいで、孔子妃が、孔子妃が、ああ、ごめんなさい、どうか、助けてください・・・。お母様を殺さないでください。私が代わりに死にますから・・・」
青黒い剣刃が光り、王は思わず動き出そうとした。
一瞬、イースケがそのままアーリエンを切り捨ててしまいそうだったからだ。
しかし、次の瞬間、イースケがした行動は、ただゆっくりと口を開くことだけだった。
「いらいらするほど邪魔なことも本当に多いね。私がどうして君を殺すのか。あなたまで殺せば悲しむ人が別にいるのに」
「ウフフ・・・フアアアン・・・」
その隙を狙って慌てて近衛兵がアーリエンをつかんで引き離す。
誰かがため息をついた。
「イースケ卿、お姫様は・・・」
「二人です、叔父さん」
「・・・」
「私の妻と彼女の兄。ペアで送ってしまいましたね、叔母さんが。アイバン、ゴンパロニエレがどうやって亡くなったと言ったっけ?」
珍しく冷たい目で見守っていたアイバンがゆっくりと前に出る。
彼とエレニアの視線は激しく絡み合って落ちた。
「惨愴でどうしても言いたくないのですが、目と鼻、口と耳から全身の血が抜けてお亡くなりになりました。それは公子妃の個人庭園でです。その場にいた私、公女、ちょうどその場にいた王女と私の妹もまたその場面をはっきりと目撃しました」
あちこちでため息が鳴る。
その部分について知らなかった人たちが嘆く声だった。
王妃の顔が真っ青になる。
フェアノール王も同様だった。
「アーリエンが・・・」
「さらに、ピュリアーナ侯爵家の令嬢もいらっしゃったのですから、塞ぎが悪かったのです。かわいそうな令嬢が血まみれになってしまいました。お嬢さんも私の妹も、まあ私はあまりにも見ごたえのある騎士ですが。これは公子妃から始まり、他人の家の貴重なレディーたちを相次いでテロしたのではないですか?ああ、元々いつも自分のものだけが大事だと思っていた方々でしたね」
らしくないように悪ロ一つも言わず、辛らつに皮肉を言うアイバンの行動にしばらく静寂が流れる。
バロンズ卿と低い苦笑いを交わした公爵が、ついに口を開いたのはその時だった。
「陛下がご存じだとは思いません」
「公爵・・・」
「今度王妃が犯したことは、王女が告げなければ誰も見当たらなかったでしょう。ただ、殿下、所信の嫁の身辺がかかった問題である以上、私は息子を防ぐ名分がありません。それだけでなく、私の家でゴンパロニエレが惨愴たる苦痛を経験して亡くなったうえに、娘がその姿を生々しく体験しなけれはなりませんでした。いくら忠臣だと言ってもこんなに堂々と触れたらどうしようというのか全く知る術がないんですよ」
「・・・」
王はしばらく何も言わなかった。
ただ惨愴たる顔だった。
確かに王の立場からも、乾いた空の雷級の災いではあるだろう。
じっと外宿の様子を見ていたイースケがふと首をかしげる。
何だかよく理解できないような様子だ。
「今何をよくやったとそんな表情をされますか?」
「何・・・?」
「叔父が最初からきちんとしていたら、こんなことは起きませんでした。似た者同士で遊ぶって、あの女も同じだし。子供の未来がそんなに.心配だったなら、最初からきちんと責任を負うべきだった。異邦人扱いされるという言い訳で、しっかり隠れてやりたいことだけを選んで、一つのテーマで支えてほしかったのか?」
「おい、イース・・・」
「残念ながら、私はそのような人類愛的な情緒はありません。気分としては、そのまま道を捨てたいですが、一刻を争うんでね。そちらが愚かなことをした代価として犠牲になった私の妻、髪の毛一本さえまともであることを祈るべきです。彼女が間違っていたら、その時は私が大人で、子供で、隠すことができるか分からないから」
そう言って剣を荒々しく鞘に戻した騎士が、激しい足取りで振り向いた。
その周りを静かに見守っていた彼らがそっと追いかけていく。
今まで一言も言わずに黙々と傍観していたバロンズ卿が最初に話を切り出したのもその時だった。
「卿、今度はどんな計画でも、私にちょっと教えてから行いなさい。進軍まではとても難しいことになるはずなのに一体何を企んでいるのか?」
「それなりに薄っぺらな計画があります。さっき報告したあれです」
「・・・調子は大丈夫かな?」
「いい感じに作ればいいんです。ムチが薬だそうです」
バロンズ卿の満面に実に満足そうな笑みが広がる。
しかし、公爵がそれとなく見つめると、素早く笑みを消し、再び謹厳な表情で戻る。
「公爵は何を企んでいるんだい?」
「あれこれ同盟を結ばなければならない」
「ああ、昔から同盟が本当にお好きなんですね」
「北部一部勢力の陰謀だけで終わるわけにはいかない。とにかく、誰かが騎士のイメージを台無しにする無知な刃物師ではないかと思って、戦って勝つことしか知らないんでね」
「お父さん、さっきおっしゃったのは何ですか。教皇庁がどうしたんですか」
「ああ、それか。とりあえず私は行って一番先に早くレンブラントに連絡を取らなければならないね」
つかつかと宮を出てきたイースケの足取りが止まる。
そのせいで、みんな自然についていくようになった。
公爵はただ悠々自適な顔をしていた。
「レンブラントですか?」
「あいつさ」
「信じられるでしょうか?」
「世の中に女房の身辺を信じて任せられる他の奴は、あいつだけだよ、息子よ」
アーリエンが出て来なかったら、イースケは王妃を斬っていたでしょう。
公爵は何か秘策があるのでしょうか?




https://recommended.tsubasa-cham.com/matome/