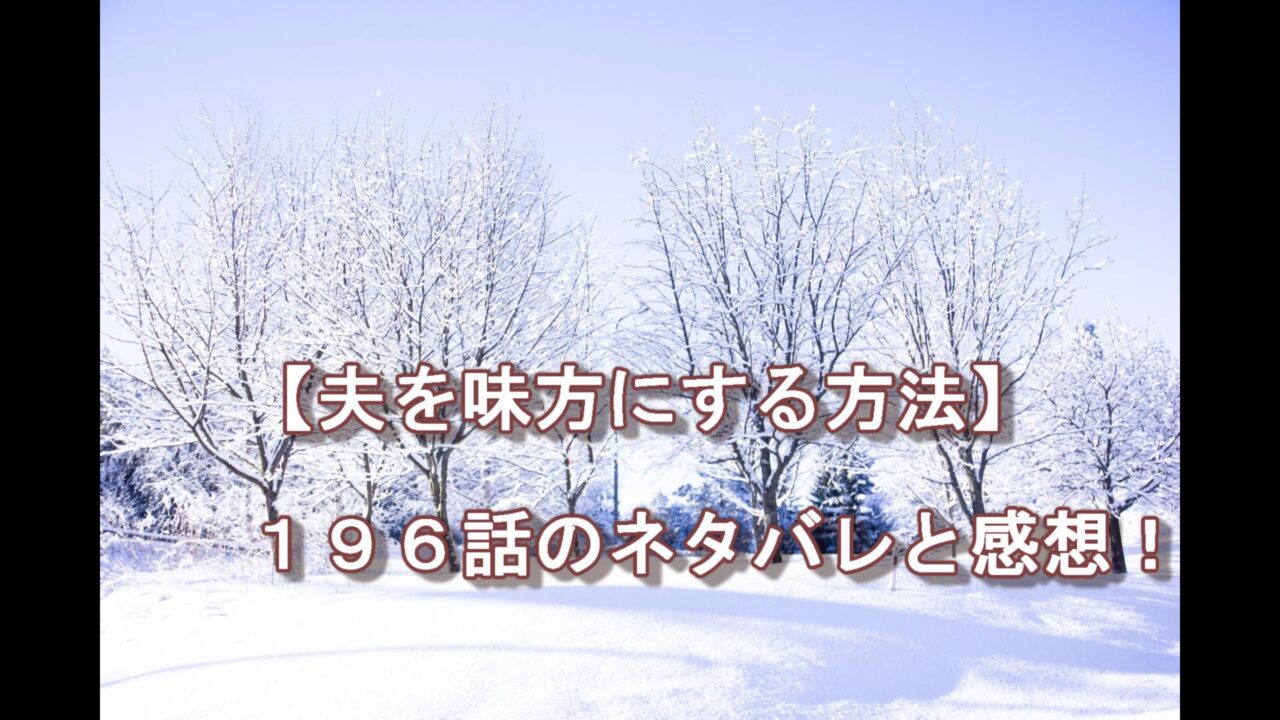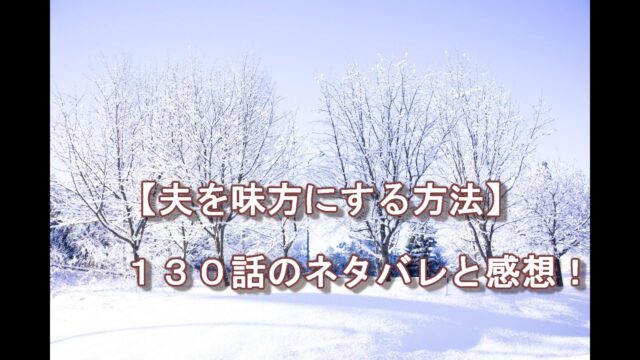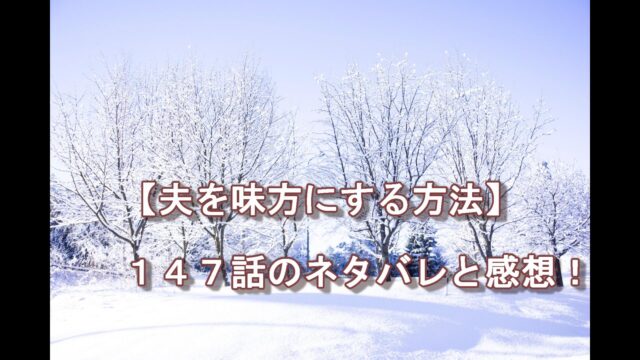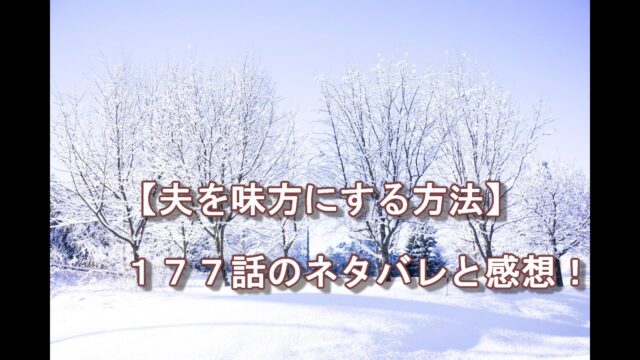こんにちは、ピッコです。
「夫を味方にする方法」を紹介させていただきます。
今回は196話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

死ぬ前に読んでいた本の中の悪女ルードべキアに憑依してしまう。
前世では養子となった家族から虐待を受けていたけど、ルードべキアも同じような境遇だった…。
しかも父によって政略結婚させられた北部最高の冷血な騎士イースケは原作で自分を殺すことになる夫だった!
小説の内容をすでに知っているルードべキアは、生き延びるために夫を愛する演技をするが…
ルードベキア:ルードベキア・デ・ボルヒア。本作の主人公。愛称はルビ。
イースケ:イースケ・バン・オメルタ。ルビの結婚相手。愛称はイース。
エレニア:エレニア・バン・オメルア。イースケの妹。愛称はエレン。
フレイヤ:フレイヤ・バン・ピュリアーナ。イースケの幼馴染。
ボルヒア:教皇。ルビの父親。
チェシアレ:チェシアレ・デ・ボルヒア。長男
エンツォ:エンツォ・デ・ボルヒア。次男。
ローニャ:ルビの専属メイド

196話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ちび王子様の夏⑤
私は正直、ダニルがその院長先生の顔や記憶をどのように覚えているのかは分からなかった。
とにかく私たちはなぜか静かになり、おとなしく彼の言うことに従うことにした。
「王子様、大丈夫ですか?」
私は近衛兵のおじさんに、「大丈夫です。私たちと一緒にかくれんぼをしませんか?」と冗談を言った。
おじさんは頭をかきながら、「今急ぎの用事ができた」と言って急いで立ち去っていく。
しばらくして、私たち三人は秘密の通路に繋がる扉を開け、階段を降りていった。
私は地下通路がきっととても暗く、気味が悪い場所だろうと想像していた。
まるでコウモリがたくさん飛び交い、黄金の幽霊のようなものが突然現れるような場所。
それくらい秘密の通路に相応しい場所でなければいけないはずだ。
だが、実際に目にするとその想像とはまったく違った。
地下通路はまったく暗くなく、むしろ明るかった。
壁に取り付けられたランプのおかげだ。
通路自体も広く、清潔で、まるで冒険をしているという雰囲気がまるで感じられなかった。
雰囲気が悪い場所だとは思えなかった。
何せお父様がお母様とデートする場所が、どこか不快で嫌な感じの場所であるはずがない。
だってお父様は何でもないふりをしていて、ものすごく格好いい感じを装う人だから。
「でも、この方向で合ってるの?」
「地図通りに進んでるんだから合ってるはず。」
「じゃあ、あっちに行けば何かあるかな?」
「ただの空き地なんじゃない?何も書かれてなかったじゃん。」
見たところ、ユリとダニルも私と同じくらい期待外れな感じがした。
私は地図を持ったまま前を歩いていたが、突然良いアイデアが浮かんで立ち止まる。
どうせ今のうちに、私たちがいなくなったことを誰も気づかず、ここまで探しに来ることもないだろうから、早くここから抜け出すのが得策だろう。
「後ろに誰か来てる!」
「やばい、急いで逃げろ!」
声を上げて走り出すと、ユリとダニルも興奮した様子で後を追いかけてきた。
そしてここでも、私たちが発する声がものすごく大きく響き渡った。
その秘密の倉庫よりもさらに大きく響いているようだ。
「うわあああああ!」
「わあああああ!」
私たちは叫び声を上げながら、楽しげに走ったり歩いたりを繰り返していた。
どれくらいそれが続いたのかはわからないが、とにかく気が付くと、とうとう通路の終わりに何か巨大な部屋のようなものが現れた。
「うわあ、あれ何?」
ダニルが驚いたように声を上げた。
階段を見るのは初めてだろうか?
もちろん、こんなに大きな階段を見るのは私も生まれて初めてだった。
宮殿にある星の塔ほどではないが、とにかくとても高かった。
私たちの目の前から始まり、上のほうの天井近くまで、ずっとくねくねと続いている。
首が痛くなるほど上を見上げていたユリが、急に顔をしかめた。
「絶対に蛇みたいだ!」
「違うよ、ただの装飾用の石だよ。」
「蛇だって!」
「装飾用の石だって!」
「おバカさんたち、ただの階段だよ!」
ユリとダニルが大声を張り上げて言い争うのを見て、私は少し大笑いしてしまった。
やがて二人ともばからしいと気づいて争いをやめる。
それから私たちは前を向いて階段を駆け上がり始めた。
一気に登り切ろうとしたけど、思った以上にきつくて途中で少し休むことにした。
汗をかき喉が渇いたので、私が持ってきた飴を一つずつ分けて食べた。
次に冒険に行くときは、必ず水筒のようなものも持っていかなければいけないと決心した。
なぜなら、水がないといけない場面に必ず遭遇するだろうから。
・・・でも、この地下道を流れる水を飲んでも大丈夫なのかな?
「うわっ!」
階段の上の大きな段差に躓いた途端、私たちは足元が滑り、床に倒れ込んでしまった。
しばらくの間、私たちはぼう然として座り込んでいた。
疲れ果てたが、冒険というのはもともと危険で過酷なものだと自分に言い聞かせる。
「見てよ! 私たち、こんなにたくさん登ってきたんだ!」
一時的な達成感に浸り、ふと下を見下ろしてみた。
でも、こうして見ると、あまり大したことがないようにも思える。
ところがその時、ダニルが突然、「下に落ちてしまうかもしれない」と言い始め、愚痴をこぼし始めた。
そして「もう家に帰りたい」と言いながら文句ばかり言い続けた。
私が何か言おうとする前に、ユリが立ち上がり、ダニルの襟首を掴んだ。
ユリは本当に頭のてっぺんまで怒っているように見えた。
「だったら一人で帰れ! この裏切り者め! 次からお前とは絶対に冒険しないからな!」
「はぁ、でもアレオサが絶交しないと思うけど・・・。」
「それはお前が、私たちの冒険を台無しにする前の話だ!」
「言っとくけど! これから君とは遊ばないからね! 授業も一緒に受けないし、知り合いってフリもしないよ! 君の味方にも絶対ならないから! それに君の弟や妹もいじめちゃうかもしれないよ!」
私は空が崩れるほどの怒りがこみ上げてきたけど、ダニルのつまらない弟妹と遊びたいという気持ちは全くなかった。
それはユリも同じだったはずだ。
あの子たちは、一つの話題に固執するばかりで、大人びたふりをするくせに、思わず一発殴りたくなるような生意気さを持っていた。
しかも、兄よりもさらにひどいわがままっ子だ。
でも、大人たちはほとんど全員、あの子を気に入っていた。
大人たちはバカだ。
何にせよ、ダニルはもう家に帰りたいとは言わなかった。
私はまだ不満げなユリの肩を軽く叩いた。
「見て。」
目の前の壁には、大きな丸い扉が取り付けられていた。
その後、みんなは口を閉ざして黙々とその扉の前に近づいていった。
扉の外では何が待ち構えているのだろうか?
胸が再びドキドキと高鳴り始めた。
私はダニルを振り返った。
「お前が開けろ。」
「え、僕が?」
「そうだよ。これでまた裏切らないって証明できるでしょ。」
ユリが言葉に賛同して頷いた。
ダニルは扉の取っ手に手を伸ばし、ぎゅっと目を閉じた。
すると、何度か大きく深呼吸をした後に思い切って押し開けた。
「うわぁ・・・!」
冷たい風が顔に吹きつけた。
私たちは一瞬、目をしばたたきながら周りを見回した。
目の前には巨大な木がそびえ立っていた。
その木は天まで届くほどの高さで、空さえほとんど見えない壮大な景色だった。
目の前には、初めて見る花々と、実がたわわに実った木々、小さな小道が広がっていた。
私たちは息を潜めるようにしながら、互いを見つめ合う。
まさか、これがあの「アジト」なのか?
「ねえ、あそこに何があるのか見てみようよ・・・?」
木々の間に続く小道を登る間、誰も一言も発しなかった。
もしこれが冒険の終わりだとしたら、本当にがっかりするだろう。
これを見るためだけで、あの長い階段を登ってきたなんて、信じられる?
名も知らぬ草花に囲まれた景色は、何一つ特別なものではなく、むしろ自分の宮殿の庭園のほうが遥かに美しいとさえ思えた。
「なんだか美味しそうな匂いがする!」
がっかりしないように必死で心を保とうとしていると、ユリが急にどこからかサンドイッチの匂いがする、と言い出した。
そして腹が空いたとお腹をさすりながら文句を言い始めた。
叱ろうとした矢先、なんだか笑いが込み上げてきてしまった。
確かに本当の匂いのようだった。
「ここに美味しそうな匂いを漂わせる果実でもあるんじゃない?」
「違うよ、これは明らかにチルメンチョーのサンドイッチの匂いだ。それに焼きリンゴの匂いも混じってる気がする。」
ユリは、もうサンドイッチと焼きリンゴだけでなく、チョコレートや、自分のお父さんが飲む謎の飲み物の匂いまで漂っていると言い出した。
そんな匂いにつられて、私たちは皆お腹が空いてきた。
特にダニルは、さっきからぐうぐうとお腹を鳴らし始めている。
すると、ユリが「お前のせいだ!」と言わんばかりに、ダニルに「自分が空腹になったのはダニルのせいだ」と文句を言い出した。
ダニルは困惑しつつ、自分はそんなこと言った覚えがないと反論した。
ユリは耳を引っ張りながら、さらにおかしな冗談を言っていると非難した。
ダニルはその後、ユリに向かって勢いよく突っかかりながら叫んだ。
「すぐに取り消せ!」
「笑うな!」
「やめて、このおバカたち・・・!うわぁ!」
二人を止めようとしていた私は、そのまま巻き込まれて一緒に地面に倒れ込んでしまった。
私たちは転げ回りながら、互いに文句を言ったり大声をあげたりしていた。
そのうち、何かにぶつかって斜面を転がり落ちる羽目になった。
「うわああああ!」
痛くはなかったが、恐怖で頭が混乱して吐きそうだった。
ようやく転げ落ちるのが止まると、ユリがまるで死にそうな勢いで咳き込みながら、自分の母親を呼び始める。
その様子を見て、私もお母さまが無性に恋しくなった。
ダニルは自分の服が破れたことに気づいて、「どうすればいいんだ!」と泣き叫んだ。
「どうするって?弟に全部押し付けるんだ、この泣き虫野郎!」
「・・・え、王子様?」
私が勢いよく振り返ったとき、どこかから妙な声が聞こえてきた。
私たちはみんな驚いて固まり、息を呑んだ。
そして、その場で動けなくなった。
というのも、目の前には大きな靴を履いた足が見えたからだ。
長い椅子に寄りかかりながらサンドイッチを食べていた男性たちも、まるで私たちと同じように固まったように見えた。
本当にサンドイッチがあったなんて。
昼食を食べてからそれほど時間が経っていなかったにもかかわらず、お腹が急に鳴り出してしまった。でも、それが問題ではなかった。
なんといっても、大人たちだ!
しかも彼らはすべて知っている顔だったのだ。
最悪なことに、私たちをじっと見つめている男性の中の一人は、明らかに私たちの父親たちの親友であることがわかった。
そのため、逃れるすべはなかった。
サンドイッチを床に落とし、立ち上がった男性がゆっくりとこちらに近づいてきた。
ダニルは震え上がっているのがはっきりと分かった。