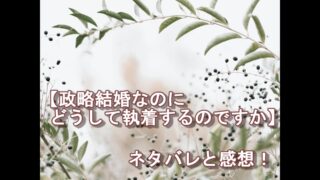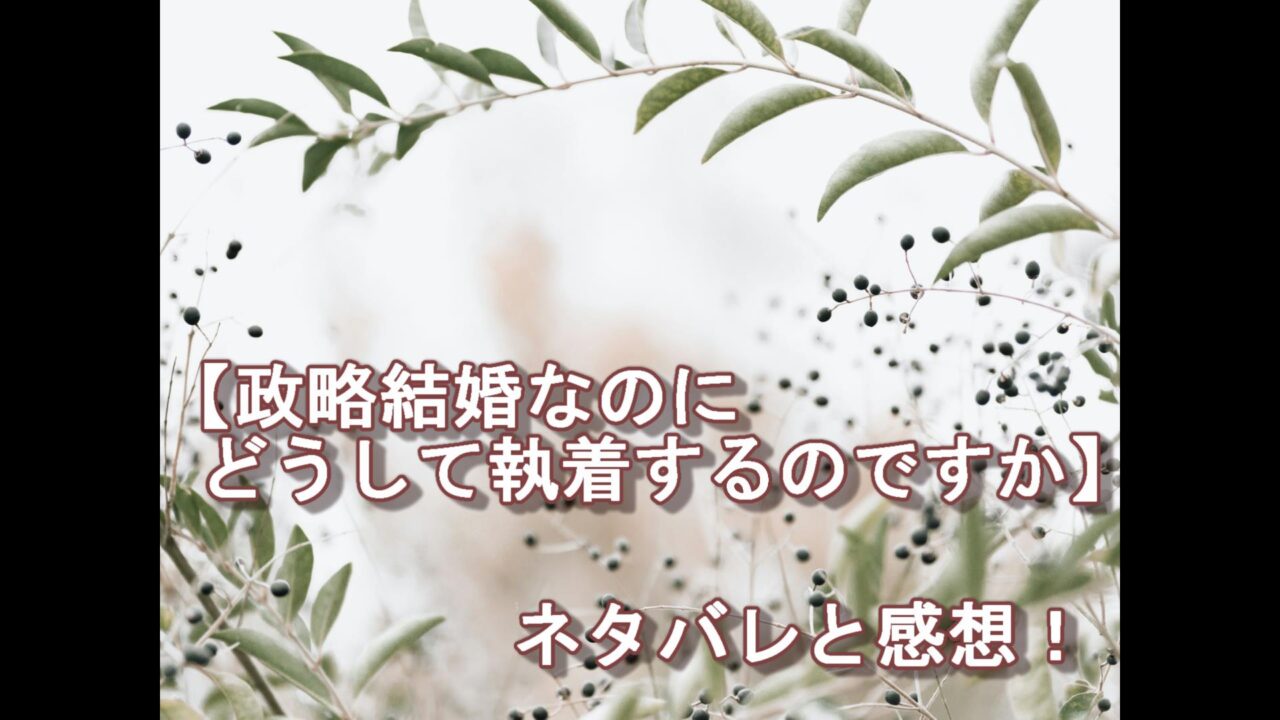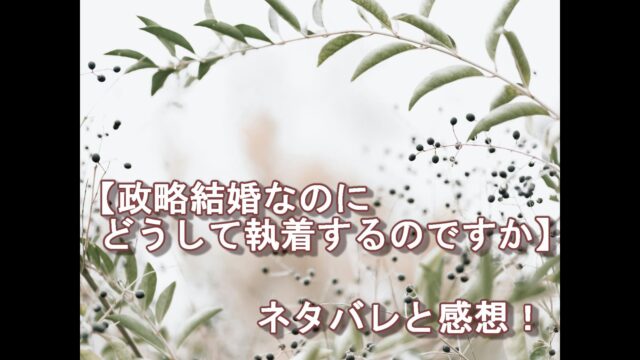こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

102話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 罠③
ロデイルが包囲されたという知らせは、最も近くにいたナディアにまず伝えられた。
それが他でもないジスカールが危機に瀕しているという知らせだったため、ナディアは椅子を叩いて立ち上がるほど驚いて叫んだ。
「ジスカール卿が助けを求めただって?どういうことなの?」
「詳しい事情はこちらをご覧ください。」
伝令が差し出したのは、ジスカールが書いた書状だった。
内容を要約するとこうだ。
敵軍が突然現れ、城門を包囲した。外に出て戦う代わりに交渉しながら時間を稼いでいる。
水路を通じて水を補給しようとしているが、敵が川の上流に軍船を浮かべて監視している。
大部分の兵力が抜けたロデイルの力だけでは長く持ちこたえられそうにないので、援軍と食糧を送ってほしい。
ナディアが落ち着いて尋ねた。
「敵軍の指揮官が誰かは分かっているのか?」
「バラジット公爵の騎士であるアルパード卿とのことです。」
「そう? それなら、あの人じゃないってことね。」
「え?」
ナディアの言葉を理解できなかった伝令が目を丸くする。彼女は手をひらひら振って答えた。
「独り言よ。気にしないで。」
「は、はい。」
ナディアの視線がテーブルの上に広げられた地図に向かう。
ジスカールが滞在しているロデイル城は、決して重要な場所ではなかった。
なぜここへ向かったのか──大軍を移動させたのではと疑うほどだ。
南部軍がこの場所を狙う可能性は低いと判断していたが、その点を逆に利用されたようだ。
『むしろよかった。公爵家の兵力をここに縛りつけておこう。』
ナディアがアドリアン卿を呼んで尋ねた。
「卿はどうお考えですか?」
「ロデイル城は川に面していますから……補給を受けて長く持ちこたえることが目的であれば、水路を利用するのがよいでしょう。陸路よりも包囲を突破しやすいですから。うーん、それならば奇襲をかけるのがいいかもしれませんが……」
彼らの境界が緩んだ隙を突いて、最短距離で迅速に移動しなければならない。
アドリアンの目が地図を見つめた。
あまり人目につかない場所にありながらも、軍船が停泊できる港のある村……
アドリアンの指が川の一端を指さした。
「ここが良さそうですね。」
「いいわ。あなたの言う通り、ここから出発しましょう。他ならぬジスカール卿が危機に陥っているのだから、必ず成功しなければなりません。」
アドリアンは、彼女が出そうとしていた命令の代わりに、そう口にした。
ナディアは家臣たちに細かい計画を伝えた後、自分の幕舎に戻った。
彼女は高鳴る胸を落ち着けようと考えた。
「まさか私が動くことになるとは思わなかった。」
自分の任務は後方を守り、必要な物資を適切なときに送ることだと思っていた。
緊張していないと言えば嘘になるが、他でもないジスカール卿が危機に陥ったというのに無視できるはずがない。
「できる。」
彼女の目的は、城壁を取り囲む敵軍を攻撃することではなかった。
物資と兵力を積んだ船が無事に出発するのを確認することだけ。
その後の指揮はアドリアン卿が行うことになる。
それだけなのに、なぜこんなにも緊張しているのか自分でもわからなかった。
ナディアがベッドに腰掛けたまま深く息をついたその時、少女アイディンが近づいてきた。
伝令に会って戻ってきたマダムが、やや緊張した面持ちを見せたのを見て、心配していたのだろう。
「奥様、大丈夫ですか?」
「うん?」
「前哨兵から伝えられた知らせ、あまり良くなかったのでは?もしかして…敗戦とか……。」
「いや、そんなことないわ。」
ナディアは不安そうな侍女に手を振ってみせた。
「でも、ちょっと行ってこなければならない場所があるの。あなたを連れてはいけないと思うから、ここで待っていて。」
「え?奥様はずっと後方を守るんじゃなかったんですか?一体どこへ……」
「それは秘密よ。」
緊張感を忘れるため、彼女はむしろふざけたような笑みを浮かべなければならなかった。
その後、ナディアは支援軍と共に陣地を離れた。
グレンの書簡が届いたのは、彼女が出発して間もなくのこと。
・
・
・
暗闇に紛れて人々が物資を船の中へ運んでいた。
どこか間違っている点はないかと、ナディアは息を潜めたまま、その姿を最初から最後までじっと観察しなければならなかった。
しばらくして、兵士の一人が近づいて彼女にそっと耳打ちした。
「侯爵夫人、準備がすべて整いました。」
「ご苦労。」
空を見上げると、月はいつの間にか高い位置に昇っていた。
その時、アドリアンが近づいて話しかけた。
「奥様、私は月が頭上に昇ったら出発しようと思っています。夜も更けてきたので、ここらでお戻りください。ここから先は私が責任を持ちます。」
「閣下が出発するのを確認したら戻ります。それだけはこの目で確かめないと、安心できない気がします。」
「まあ、それなら……私が止めるわけにはいきませんね。」
時間が経つにつれ、緊張が高まっていった。
ドキドキする胸を落ち着かせるため、ナディアは深く深呼吸をしなければならなかった。
どうか、ジスカール閣下を救い出せますように。
時間は果てしなくゆっくりと流れているようで、時には氷のように冷たく流れているようにも感じられた。
気づけば、出発の時刻が近づいてきていた。
「侯爵夫人、アドリアン閣下がまもなく出発されます。」
船出くらいは見送ろうと思い、彼女は外套を羽織って港へ向かった。
夜の港は暗闇に包まれていた。
移動のための最小限の灯火だけが道を照らしているだけだった。
ナディアはすべての準備を終えたアドリアンに約束を求めながら言った。
「うまくやれると信じてます、アドリアン卿。」
「必ずや奥様の期待に応えてみせます。」
しかし、二人がまさに手を取り合い、約束を交わそうとしたその瞬間だった。
ピィッ!
背後から風を切る音がして、光る何かが横をかすめていった。
『あれは……?』
ナディアが目を大きく見開いて、その正体を見極めようとした。
それはまるで鬼火のように空中をブンブン飛び回っている炎だった。
空を飛ぶ炎は、ナディアが乗り込もうとしていた船に衝突した。
その瞬間、彼女はそれが火炎弾であることに気づいた。
「……!」
鋭い感覚が後頭部をかすめていく。
同時に、背後から大きな音が響き渡った。
「うわあああああ!」
「襲撃だ!敵の襲撃だ!」
タンタンタンタン!
敵軍の叫びと共に鐘が狂ったように鳴り始めた。
アドリアンがナディアの腕をつかんで言った。
「奥様!避けてください!」
「わかりました。」
状況が正確にどうなっているかはわからなかったが、一つ明確なのは計画が敵に察知されたということだった。
ナディアはすぐに足音を辿って馬小屋へと向かった。
馬に乗って逃げるためだった。
しかし少し後、どこからか現れた一団の敵軍が細い路地をふさいだ。
「しまった。」
アドリアンが彼女の腕を放しながら言った。
「戻る道は分かりますか?」
「はい、覚えています。」
「それならよかった。先に行ってください。ここは私が食い止めます。」
「……」
ナディアの瞳孔が大きく揺れた。
しかしここで一人で行くことはできないという理由で躊躇うことに意味はなかった。
むしろアドリアンが稼いでくれた時間を無駄にする行為だった。
「……後で会いましょう。必ず。」
彼が返事の代わりに手綱を握りしめる姿を最後に、ナディアは足を踏み出した。
幸いだったのは、村の裏路地がクモの巣のように広く細かく広がっているということだった。
彼女が向かう道は、まだ敵軍に占領されていなかった。
チャイン、チャイン!
遠くから火の粉が飛び散る音、悲鳴が聞こえてくる。
彼女は嘔吐感を堪えながら岩の間を駆け抜けた。
「はぁっ……はっ!」
村に火をつけたかのように、納屋から鋭い煙が漏れていた。
汗が熱気でじっとりとして、呼吸すらままならなかった。
「ゴホッ、ゴホッ!」
ナディアはむせながら、必死に脚を動かした。
ようやく目的地が視界に入る。
幸いにも、彼女の馬は岩の間にしっかりと繋がれていた。
しかし、その瞬間だった。
「きゃあっ!」
誰かが髪をつかむような感覚に、ナディアはよろめきながら地面に倒れ込まずにはいられなかった。
彼女はとっさに短剣を持ち上げ、自分をつかんだ相手の正体を確認した。
それは敵軍の服を着た兵士だった。
「死ね!」
興奮して正気ではなさそうな敵兵が、ナディアに向かって槍を突き出した
いや、突き刺そうとしていた。
胸の間から火花のように短剣を突き出したが──たとえナディアがそこにいなかったとしても、槍に貫かれていただろう。
「ごほっ。」
敵兵の口から飛び出た血が彼女の頬にも飛び散った。
やがてその体は地面に崩れ落ちた。
ナディアはそのまま後ずさりしながら考えた。
体が震えていた。
『た、助かった……。』
しかし、何かがおかしかった。
敵兵の背に突き刺さった矢は、ア軍のものではなかった。
黒い矢羽。
それは南部軍の印だった。
「……!」
ナディアが息を呑み、もう一度短剣を振り上げた。
燃え上がる村を背景に、黒い軍馬がどっしりと立っていた。
黒いマントと兜まで備え、まるで地獄から現れた死神のような姿だった。
チャキン。
その黒い軍馬が血の水たまりを踏みしめながら近づいてくる。
やがて馬から騎士が降りてくる。
弓を放った者が頭巾を脱ぎながら言った。
「間に合ってよかったです。若い女性は殺すなと言われたのに、命令を無視する奴らがいるんですね。」
「……」
顔を上げたその人物は、やはりナディアが見覚えのある人物だった。
彼女が見上げると、その顔が青ざめていく。
そんな彼女に、タクミは驚かせまいとするように柔らかく微笑み、そっと手を差し伸べた。
「ご安心ください。これからは私があなたをお守りします。」