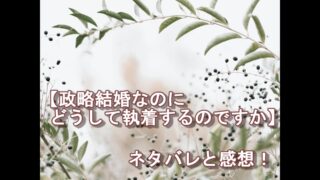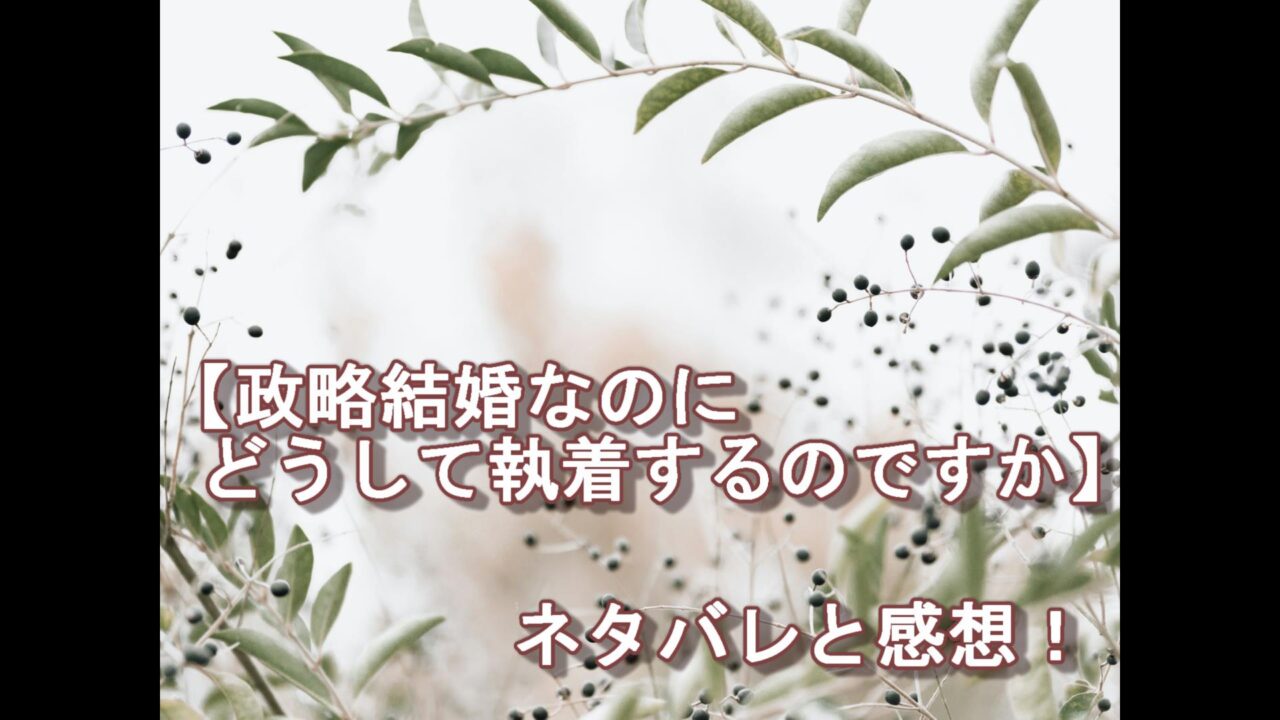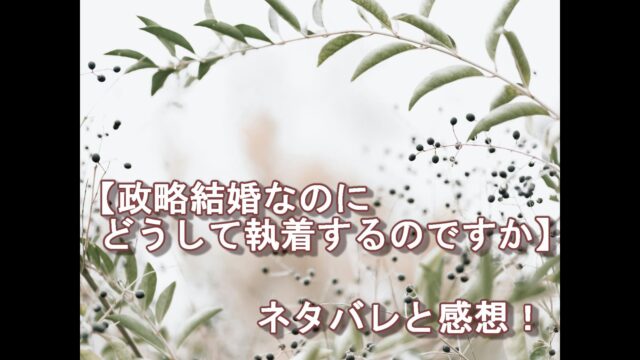こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

107話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 脱出③
ノアが徐々に高度を下げ始めたのは、うっそうとした森の近くに近づいたころだった。
白々と生い茂る木々が次第にまばらになり、空いた空き地が目に入ってきた。
その上には一団の人々が立っていた。
ウィンターフェル家の紋章がなくても、特有の赤いマントがなくても、ナディアは彼らをひと目で見分けることができた。
そしてノアが彼女を地上に降ろした。
彼女は肩が外れたことも忘れて飛ぶように駆け出した。
「ナディア!」
グレンが倒れそうになりながらも必死に駆け寄ってくる彼女を受け止めた。
そのおかげでナディアは彼にしがみつく形になってしまった。
『あったかい。』
全身を包むような温もりに触れただけなのに、なぜか安全に守られている気がした。
ナディアはようやく心の底から安堵することができた。
グレンは彼女の肩を優しく抱きしめながら尋ねた。
「体は大丈夫か?どこかケガは?」
「大丈夫です。それより……あなたの体、すごく温かくて気持ちいいですね……」
「えっ?」
何を言ってるんだというように目を大きく見開いたクレン。
彼はすぐに、彼女の体がまるで氷のように冷たくなっていることに気づいた。
空中で強い風にずっとさらされていたせいだろう。
「体がすごく冷たい。」
「そうですね。春なのに、どうしてこんなに寒いんでしょう……」
体が震えるほどだった。
緊張がすっかり解けたせいか、これまで感じなかった寒さが一気に押し寄せてきたのだ。
「全く、まずはこれでも着て。」
グレンは自分のマントを脱いで彼女の肩にかけてくれた。
優しい感触が体全体を包んだ。
人々が周囲にざわざわと集まり始めたのはその頃だった。
「お嬢様、ご無事だったのですね。」
「ご無事にお戻りになられて、何よりです。」
「待っている間、寿命が10年は縮まった気がしますよ……。」
見慣れた顔の騎士たちだった。
なぜだか涙がこぼれそうになる気分だった。
ナディアは涙をこらえながら答えた。
「皆さん、お久しぶりですね。また会えて、本当に、本当にうれしいです。」
「お嬢様がフォロに連れていかれたという知らせを聞いて、私たちがどれだけ驚いたかご存じですか?心臓が止まるかと思いました!」
「まあ、私たちが驚いたといっても、領主様ほどではないでしょうけど。ご主人様もそのお顔を見なければならなかったのに……」
「ご心配おかけしてすみません。」
ちょうど騎士たちとの再会の感動を分かち合っていたそのときだった。
「邪魔して悪いが、今はそんなことをしている場合ではない。」
「……?」
背後からとても聞き慣れない声が聞こえてきた。
初めて聞く声だ。
騎士たちの中に、この声を聞き逃した者がいたのか?
ナディアは不審に思いながら後ろを振り返った。
「人間を乗せて来たから高度が取れなかった。私が向かった方向を見ただろう?追ってくるはず。早く移動しなければ。」
「……」
そして、気づいた。
ゆったりと話している龍の姿に……。
「ノ、ノア?」
「うん?」
「……」
いつの間にか小さな姿に戻ったヨンが、泰然とした声で応える。
彼女は冷や汗をかきながら思った。
『そ、そういえば、話せるって言ってたっけ……』
そんな話を聞くのと、実際に見るのとでは違う。
それにしてもこんなに雄弁だとは思わなかった。
グレンが冷や汗をかいているナディアを抱きながら言った。
「その通りだ。面倒なことが起こる前に早くこの場を離れたほうがいいな。」
「ちょ、ちょっと待って。グレン、私を下ろして。」
「じっとしてろ。どうせ俺と同じ馬に乗るんだから。」
そう言って、彼はナディアを自分の馬の上に乗せた。
そしてそのまま後ろにひょいと飛び乗った。
その勢いで彼女はグレンのマントに包まれた状態で、彼の胸に抱かれる格好になった。
独特の体臭がふわっと香る。
なぜか安心感を覚えた。
「少し不便かもしれないが我慢して。今はとにかく早くここから脱出することが重要だから。」
「はい。」
間もなく二人を乗せた馬が、ひづめの音を立てて動き始めた。
再び目を開けたとき、ナディアが最初に気づいたのは、見慣れた天井だった。
確かにグレンと一緒に馬に乗って移動していたはずなのに、なぜ見慣れた寝室に横たわっているのか分からなかった。
『移動中に眠ってしまったのかな……?』
まさか、馬の上で眠ってしまうなんて。
グレンがどれだけ呆れただろうと想像すると、顔がカーッと熱くなる気がした。
「うぅぅぅ……」
筋肉痛に耐えながら体を起こしたナディアが、周囲を見回した。
確かに初めて見る寝室だ。
どうにか寝室の端まで歩いて行こうとしたが、うまくいかず、彼女はベッドの横の手すりをつかまざるを得なかった。
そこへ、見覚えのない顔の一人がドアを開けて入ってきた。
「侯爵夫人、お目覚めになられたのですね。」
「ここはどこ?」
「ノイバン領主城です。」
ノイバンであれば、父の分家の一つ。
どうやら北部軍に占領された後、拠点として使用されているようだ。
「よろしければ侯爵様をお呼びしてもよろしいですか? あの方が、奥様が目を覚ましたらすぐ知らせてくれと言っておられました。」
「うん。」
まるで彼と話したくてたまらなかったようだった。
彼女が寝室を出てまもなく、グレンのものと思われる足音が響き始めた。
すぐに、バン!という音とともに扉が開いた。
「ナディア。」
急いで駆けつけてきたようなグレンは、少し息を整えていた。
彼女が尋ねた。
「私、何日ぶりに目覚めたんですか?」
「俺の馬の上にいた時間も合わせると、ほぼ丸二日眠ってたよ。」
ナディアは少し驚いた。
アラウンドで彼らを徹夜で見張ったあとでも、翌日には目覚めていたはずでは?
『体は楽だったけど、精神的にはかなりの負担があったみたいね。』
しかし、あの男の前でまるで皆が許されたかのようにくすくすと笑うのは、並大抵のことではなかった。
それに、ドラゴンの脚にぶら下がったまま長距離を移動したのだから、なおさらだ。
ナディアが筋肉痛でわずかにうめくと、グレンが表情を変えて尋ねた。
「具合が悪いのか?医者は外傷はないって言ってたけど……」
「ただの筋肉痛です。ドラゴンの脚にぶら下がって飛ぶのって、そんなに楽なことじゃないですね。」
「奴らが君に害を加えたりはしなかったか?」
「監禁されたのがちょっと不快だっただけで、むしろうまく応対しましたよ。「公爵令嬢」という地位をしっかり利用しました。」
すると、グレンの顔に安堵の色が浮かんだ。
「それはよかった。きっと上手く対処できるだろうとは思っていたけど……」
「もちろん、この脱出で私はもう完全に裏切り者になってしまいましたが、おそらくまた捕まった日には本当に殺されるでしょう?」
「……そんなことは絶対にさせない。」
そう言うグレンの顔には、罪悪感と自分自身への怒りが滲んでいた。
敵の策略に嵌められたのがナディア本人だったとはいえ。
『色白で冷たそうに見えるけど、意外と情に厚いな。』
彼女がふっと笑いながら、彼に手招きした。
「なんでそんなに離れて立ってるんですか、私たちの仲で?もうちょっと近くに来てください。」
「こう?」
「もう少し。」
グレンはナディアが手を伸ばせば届くくらい近くまで寄ってこなければならなかった。
実際、彼女は腕を伸ばしてグレンの頬に手を触れた。
「……!」
予期せぬスキンシップに、彼は驚いた表情を浮かべた。
ナディアは笑いながら尋ねた。
「そんなに驚くこと?」
「驚くのは当然だろう。突然顔を触るなんて……」
「じっとしてて。ゆっくり見ていたいから。」
そう言って、彼女は彼の頬骨やあごのラインをゆっくり撫でた。
指先が触れる場所の形を、まるで記憶に刻みつけるかのように。
指先が触れるたび、その部分がかっと熱くなって、むず痒くなる。
彼はその不思議な感覚に耐えきれなかった。
「……僕の顔に何か問題でもあるのか?」
「もう二度と見られないかと思って。だからこの機会にいっぱい見ておきたくて。ずっと会いたかったんです。」
「……」
「ん?急にすごく赤くなってますよ。」
「からかわないで。」
どうしてそんなことを言われて赤くならずにいられるだろうか?
彼の顔が赤くなるのに、3秒とかからなかった。
グレンは不利な話題をそらすために別の話を持ち出さなければならなかった。
「ひとつ聞いてみたいことがあるんだけど。」
「言ってください。」
「以前、私に送ってくれた……あのネックレスと手紙のことなんだけど……」
彼は勇気を出してナディアと目を合わせた。
「その意味を……聞いてもいいかな?」
「表情を見る限り、もう分かってるみたいですけど?」
「……!」
ほんのり赤くなっていたグレンの顔が、完全に真っ赤になった。
「ビシュが好きだって言ったとき、それってつまり私のことが好きだって意味だったんですよね?」
「そ、そうだ。」
「じゃあ、そのビシュがあなたの気持ちに応えるっていうのは、どういう意味ですか?」
「私の告白を……受け入れてくれるってこと……?」
「ほんとに、これ全部いちいち説明しなきゃわからないんですか?でも、あんまり手慣れてるよりは、こっちの方がずっと可愛いかも……。ところで、そのネックレスはどこにありますか?」
「ここにあるよ。」
グレンは机の引き出しを開けてネックレスを取り出した。
そして、喜びと恥じらいが混ざった表情で言った。
「もう一度つけてあげてもいいかな?」
「ええ、もちろん。」
彼が慎重にネックレスを手に取る。
その次の瞬間に起きたことは、ナディアにとっても予想外のことだった。
グレンが彼女の額にそっとキスをしたのだ。
彼女の目を優しく見つめながら。
『わぁ。』
それは、無言の求愛だった。
唇にキスしてもいいかと尋ねるような問いかけ。
ナディアは声もなく感嘆した。
『うわあ……「そっけない」なんて言葉、撤回。』
恋愛経験がないのは確かだが、もしかすると生まれつきそうなのかもしれないと思った。
彼女が感動している間にも、彼の手先は確かに動いていた。
垂れ下がった髪をかき分け、慎重に首にかけてやる。
留め具をつけた後、彼が口を開いた。
「僕の気持ちを受け入れてくれたこと、絶対に後悔させない。僕の名誉をかけて……いや、僕のすべてをかけて誓うよ。」
「本当ですか?すべてをかけて?」
「そうだ、すべてを賭けて君を選んでくれて、どれほど感謝してるか分からない。」
「感謝なんて……誰かに強制されたわけでもないし、私もあなたが好きだから受け取ったんです。」
「……!」
彼女がそうはっきり言うと、一度引いていた彼の顔が再び赤くなった。
赤くなった顔を見せたくないのか、彼は左手のひらでそっと顔を覆った。
『こうやって見ると、また純粋な一面もあるのよね。』
ナディアの口から、可愛いとでも言いたげな笑い声がもれた。
「グレン。」
「う、うん?」
「許します。してもいいですよ。」
「……」
すると彼の喉仏が上下するのが目に映った。
ひどく緊張しているような、私の“そっけない夫”のために、ナディアはそっと目を閉じた。
短い静寂が流れた後、そっと肩を抱きしめる手の感触が伝わってくる。
唇に柔らかいものが触れ、開いた口に飛び込んできたのは、その次の瞬間だった。
「んん……」
彼女は腕を伸ばし、グレンの首筋に腕を回した。
最初のキスは、かなり長く続いた。
目の前でナディアを見失った直後、タクミはすぐに追撃隊を出動させた。
近くにウィンターフェル侯爵家の兵力が潜んでいると確信していたからだ。
「森の中で大規模な人員が通った痕跡があります。すでに我々の領域を離れたようです。」
「これ以上の追跡は不可能……だと思われます。」
「……」
しかし迅速な対応にもかかわらず、結果は芳しくなかった。
報告を伝える部下たちの言葉に、タクミの表情が曇った。
「つまり、逃したということか?」
「ええ……そうみたいですね。」
「はっ!」
彼の口から苦笑がこぼれた。
実のところ、彼女が突然従順に屈したときから、何か裏があるのではと予想はしていた。
それでも彼女の要求を受け入れたのは、逃れる手立てがないと判断したからだった。
まさかあの場面で龍が現れるとは……想像もしていなかった。
表情を引き締めたタクミに向かって、彼の部下が口を開いた。
「も、もちろん予想外のことが起きはしましたが、タクミ様の厳重な警備が無駄だったわけではありませんよね?」
「はい。逃したのはたった一人の女だけです。」
「その女の身元がウィンターフェル侯爵の妻であり、バラジート公爵の令嬢であれば話は変わります。」
「そ、それは……」
目の前で逃してしまった。
自分の手の中にあったのに、一瞬で翼を広げて消えてしまった。
まるで「お前ごときが一生かかっても私を手に入れることはできない」と言っているかのように。
「………」
あの瞬間が網膜に焼き付いたかのように生々しく思い出された。
一生忘れられないだろう。
「ええ……どうなさいますか?もう少し捜索を……」
「もういい。今ごろは無事に到着しているはずだ。」
「はっ、了解しました!」
内心では腸が煮えくり返るように腹立たしくても、ここでさらに時間を浪費するのは無意味なことだった。
「まずは元の予定どおりに移動する。」
タクミはそう命じると、体を翻した。
まずは移動した後でナディアを探し出す方法を考えなければならなかった。
戦はまだ終わっておらず、機会は残っている。
しかし、彼の計画は最初から困難に直面することになる。
本来の目的地である城に到着した直後、先に到着していたエイデンが彼を迎えながらこう言った。
「話はすでに聞いている。私の従姉を逃がしたそうだな。」
「申し訳ありません。私の不手際です。」
「過ちを犯したのだから、それに対する処罰があってこそ他の者も納得するだろう。しばらくの間、警備指揮権を剥奪する。」
「……え?」
タクミが信じられないというような低い声を出した。
たった一人を逃したとはいえ、彼が長い間の勝利を手にしたという功績が消えるわけではない。
それでも指揮権を剥奪するとは?
「……従妹をあんなに情深く思っていたなんて、気づきませんでした。」
「そんなはずが。」
エイデンがくすっと笑って後に言葉を続けた。
「そいつが死のうが生きようが、我が家門を裏切ったことには変わりない。いや、私は自分の目を信じている。あの娘一人が何をできるというのか?」
「じゃあ……?」
「しかし、我々の秘密を知っている人間が敵側に渡ったとなると、話は別だ。」
彼が疑っているタクミホの耳元に声を低くして囁いた。
「ナディアが侯爵を慕っているのを知っている。」
「……!」
「この事実がウィンターフェル侯爵とその参謀たちの耳に入るのは時間の問題だ。彼らがこの貴重な情報を見逃すわけがない。」
北部貴族たちが馬鹿の集まりではない以上、公爵の健康問題を簡単に隠して秘密にしたのではないか?
だが、タクミにも言い返す言葉はあった。
「それより前に、どうしてその事実がナディア嬢の耳に入ったのですか?少なくとも私は秘密を口外したことはありませんが……。」
「………」
バラジート公爵の健康問題を知っている者は多くない。
せいぜい十数人程度だ。
そしてその十数人の中でナディアと接触したのは、たった三人だった。
自分とラファエット子爵、そして目の前にいるエイデン。
「私が不注意だったことは認めます。しかし処罰よりも秘密が漏れた経路を把握することが先だと思います。」
「それは私が調査しよう。卿が気にすることではなさそうだ。」
その瞬間、タクミは罵声を上げないように歯を食いしばらなければならなかった。
『やはり勘違いじゃなかった。』
悪魔戦争以降、彼が露骨に自分を警戒していると感じていたのだ。
意図せずとはいえ、ナディアに秘密を漏らしたのはまさにエイデン自身だった。
自分の過ちを他人に転嫁してうやむやにしようとしているのだ。
「君に悪感情があるわけじゃない。だが、これくらいの措置も取らなければ、みんな不満を持つだろう。一時的な措置だから、どうか私の立場も考慮してほしい。」
「………」
エイデンはそう言うとすぐに背を向けてその場を離れた。
タクミはその場に立ったまま、徐々に遠ざかる彼の背中を見つめるしかなかった。
何か言いたいことはあったが、エイデンは公爵の代理であり後継者だ。
彼に対して真っ向から対立したところで得るものはなかった。
『あの食えないやつめ……。』
内部分裂を引き起こすわけにはいかない。
一時的な措置と言ったのだから、信じてみるしかない。
タクミもまた、ため息とともに席を立った。
ナディアは後方に戻る代わりに、グレンのそばに留まることにした。
「私のそばが一番安全だ」という彼の強い主張に押されたおかげだった。
そして予想外にもグレンと同行することになったナディアの今の気持ちは――
「はぁああ……。」
退屈で体をくねらせている最中だった。
「ううぅん……」
「どこか不快な点でもございますか、奥様?」
「なんだか……変なの。」
「え?」
「何もすることがない!何日もただ遊んでるだけ!この感じが変なのよ!」
「………」
そうじゃなくて、本当に気まずかった。
帰還後ずっと軽く息切れしていた彼女だった。
グレンにすべての責任を押しつけた後、狭いベッドの上でうろうろしているのだから、落ち着かないのも無理はない。
そのとき、すばやくナディアの膝の上に乗ってきたノアが体をすり寄せてきた。
「キーリク!」
まるで退屈なら一緒に遊ぼうとでも言っているかのようだった。
ナディアは思った。
『いや、この子は一体……。いつまで喋れないふりをするつもりなの?もちろんその方が可愛いけど……。』
それでも、あまりに可愛いので頭を撫でながらナディアが熱心に黒いブラシを上に置いていた時だった。
「奥様、ジスカール卿がお越しになりました。」
「そう?すぐに通すように言って。」
来客の登場を告げる声にナディアは席からぱっと立ち上がった。
ちょうど退屈していたところだ。
何の用かと思いきや、ジスカールの使者は彼女に届けられた連絡を伝えに来たのだった。
彼は手紙を差し出しながら言った。
「こちらはアドリアンの手紙です。怪我は順調に回復しているそうです。マダムに安否を伝えたかったようです。」
「手紙が書けるくらいに回復したようですね。よかったです。」
彼が生きているという知らせを受けたとき、どれほど安堵したことか。
負傷した状態で川に飛び込み逃げたという。
暗い夜だったため、敵軍の目を逃れられたのはまさに幸運だった。
敵陣に囚われている間、彼の生死を知らずどれほど心配したことか……。
『あれ?』
その時の記憶を思い出したナディアの体がぴたりと止まった。
脱出に全神経を集中していたあの時、忘れていた記憶が蘇ったのだ。
「そうだ!忘れてて言わなかったことがあるんです。」
「重要なことですか?」
「はい、テニア城で捕まっていたときに聞いた内容なんですが……。」
ナディアは声を低めて話した。
「父の、つまりバラジット公爵の健康が良くないようです。軽く流せる病気ではないことは明らかです。」
「そ、それは本当ですか?」
「はい、エイデンの口から出た言葉なので確かです。」
「やっぱり……」
ジスカールが真剣な顔で顎に手を当てた。
反応が妙だった。
彼女が驚いて尋ねた。
「まさか、知ってたんですか?」
「それは違います。ただ、内戦の途中でも彼があまりにも最前線から外れている感じがしたんです。だから何か問題があるのではないかと思ったのですが、まさか健康問題だったとは……。こんな時に重病を患うとは、運が悪いですね。」
「これまでの悪行がすべて返ってくる感じですね。」
「教えてくださってありがとうございます、マダム。おかげで少し大胆な作戦も試してみることができそうです。」
「なんですって。」
手を打っていたナディアが「あっ」と感嘆の声を上げた。
「ところで最近グレンは何をしているんですか?」
「領主様ですか?彼はいつも通りのようですが……」
「ふうむ……」
夫の近況を伝え聞いたナディアの目がうっすらと潤んだ。
普段と変わりがないのに私を探しに来ないってこと?
「でも、それがなぜ気になるのですか?」
「そういうことがあるんです。ちょっと探しに行ってみなきゃ。」