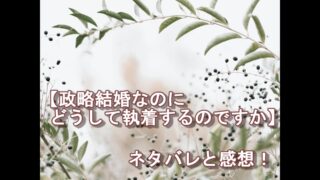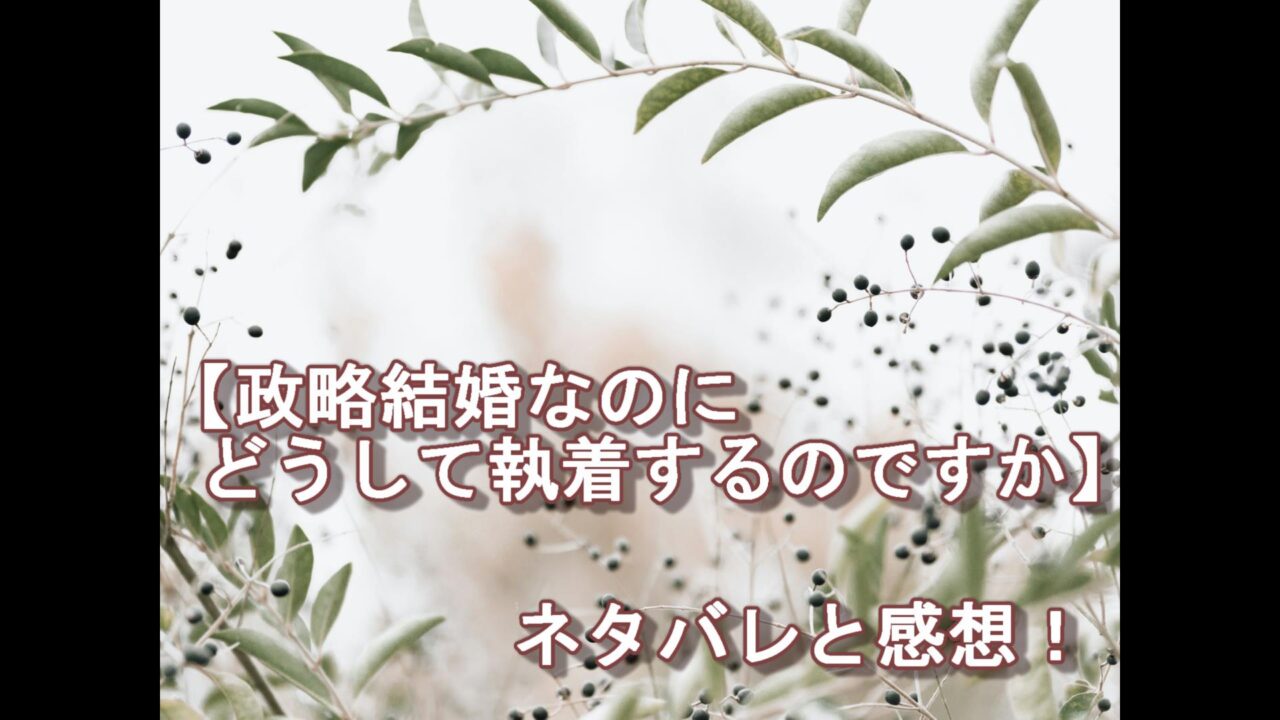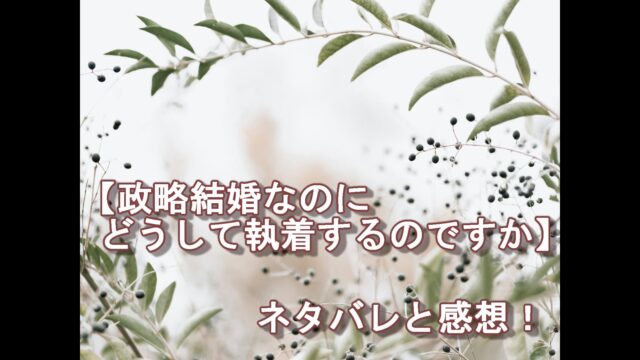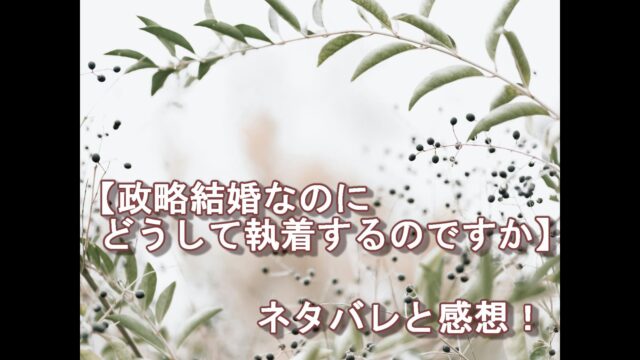こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

110話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 終結
森での戦闘により、バラジット軍の攻撃は精鋭兵の大半を失う結果となった。
残ったのは、領地に撤退したごく一部の兵力のみだった。
南部の領地は肥沃な平野が広がっており、一見すると防壁のようなものには見えなかった。
だが、実際にはそれが逆に防御線としての役割を果たしていた。
莫大な生産力で南部を豊かにしていた平野も、戦時下では少しの余裕もなかった。
そのおかげで、ウィンターフェルや一部の北部領主たちはためらうことなくバリスタの製造能力まで強化することができた。
ただし、バリスタを積み重ねて築いた城壁を超えるほどの効果は得られなかった。
目に見える成果が乏しいため、グレンは接近戦の方法を少し変えることに。
「無理に正攻法をとる必要はない。降伏した者たちには命と財産の保障を条件に提示しろ。きっと裏切り者が出てくるはずだ。」
戦局が傾いたことは、物事をわきまえている者なら誰でも知っていた。
命がけででもそれを手に入れようとする小人たちは、必ず現れるに違いない。
内通者を待つ作戦を選んだ以上、残されたのは知らせが来るのを待つことだけだった。
それからあまり時間が経たないうちに、予想通りに投降の意思を示す者が現れた。
「私の主人はナタニエル・ラファイエット子爵様です。ご家族の安全とわずかな財産の保障さえあれば、城門を開けて北部軍を迎え入れる所存でございます。」
しかし、名乗られたその名前は予想通りだった。
主人の名を聞いたナディアは、静かに薄ら笑いを浮かべていることを知ってか知らずか、黒衣をまとった従者はグレンに書信を差し出した。
「こちら、ラファエット子爵様からの書信です。」
「ふむ。」
書信をすべて読み終えたグレンは、それを別の者に渡しながら言った。
「興味深いな。お前の主君が真っ先にバラジットを裏切るとは思わなかったぞ。彼は侯爵の最も近しい家臣の一人じゃなかったか?」
疑念を含んだ声だった。
その気配をいち早く察した伝令が言葉を続けた。
「はい、あの方はバラジット公爵様に忠誠を尽くしておられました。いえ、今となっては“前(元)”公爵様とお呼びすべきでしょうけど。」
「……何ですって?」
「前バラジット公爵様は、先週末に戦死なさいました。その空席をエイデン様が埋めていますが、明らかに力不足です。私の主君が投降を決めたのも、それが理由の一つです。」
「……」
その言葉を額面通りに信じてよいのかどうか。
簡単に判断できることではなかった。
予想していたよりも、はるかに大きな魚が投降の意思を示していたのだ。
結局、司令部はラファエット子爵の伝令を送り返した後、再び会議を開かざるを得なかった。
「罠である可能性も否定できません。慎重に行動すべきです。」
「それならば、分裂策を使った理由は何ですか? 裏切り者が出てくるのを待つと言いながら、正確に投降の意志を示した者に接触したのに、疑っているとは!」
「ハピルであれば、彼は侯爵の側近の一人だったので、信頼できないのではありませんか!」
会議室はさまざまな意見で割れるのに時間はかからなかった。
それぞれにそれなりの根拠があるため、なおさら結論は出なかった。
ナディアが口を開いたのは、まさにその時だった。
「いえ、私の考えは違います。ラファイエット子爵は“人”に忠誠を誓う方です。」
「“人”に忠誠を?」
「はい。忠誠を捧げていた者が命を落とした以上、これ以上義理を守る理由はないと考えたのでしょう。私は彼の裏切りが本心である可能性が高いと見ています。」
「もし、公爵が死んだという話自体が嘘だったとしたら?」
「回復の見込みがないというのは、確かな事実です。それなのに姿を現さないというのは──もうすべてを物語っているのではないでしょうか?」
「ふぅ……」
ウィンターフェル内部で彼女の発言が持つ影響力は絶対的だった。
他の家門から来た者たちが反発しようと口を開きかけたが、正統のグレンが支持を表明したのだから、反論できるはずもなかった。
結局その日の会議は、ラファエット子爵の投降を受け入れることで結論づけられた。
内戦勃発から171日目。
北部軍と内通したラファイエット子爵が城門を開いた。
城門が開かれた状況でも、南部軍の抵抗は激しかった。
しかし暗い夜の帳を突いて、敵軍が開かれた門からなだれ込んでくる状況だった。
勝敗が明らかになった戦いに違いなかった。
城内で激しい戦闘が繰り広げられている間、ナディアは安全な軍営の一角で知らせを待たねばならなかった。
平凡な貴婦人である彼女にとっては、仕方のない選択だった。
一睡もせずに夜を明かし、目の周りのくまも気にせず、周囲の権力を断ち切った彼女は、朝が明けるや否やこう尋ねた。
「状況はどうなっているのか分かりますか?」
質問というよりは確認に近かった。
遠くから聞こえていた騒音が徐々に静かになってきていたのだ。
戦闘が終わりつつある証拠だった。
「ほとんど整理されましたが、一部の抵抗が残っています。」
「では、まだ城内に入るのは難しいでしょうか?」
「うーん、それは……護衛と同行という条件なら問題ないと思います。」
それはすなわち、事実上すべてが片付いたという意味に他ならなかった。
「ですが、軍がそこまでされる必要があるでしょうか。戦いが完全に終わってからでも……」
「グレンに会いたいんです。怪我をしてないか心配で。」
「領主様が負傷されたという知らせは届いておりませんが……。いずれにしても分かりました。ただし、危険な場所には足を踏み入れないでください。我々の判断に従っていただきますよう。」
「わかりました。」
こうしてナディアはバラジット公爵城の中へと入っていった。
外城はすでに整理された状況だったため、障害はなかった。
ただし、内城に近づくにつれて、剣と槍がぶつかる音と共に叫び声が混じって聞こえてきて、小規模な戦闘が少しずつ続いているようだった。
「その道は通れません。城壁の上に登ってください、マダム。領主様もそこにいらっしゃいます。」
「わかりました。」
誰かがナディアの足音を呼び止めながら、そう言った。
軍が止める場所まで足を踏み入れてまで迷惑をかけるつもりはなかったので、彼女は周囲の指示に従っておとなしく城壁の上に登った。
高い場所に登ると、内側の様子がはっきりと見えた。
本館の建物を中心に、残った兵士たちが最後の抵抗をしていた。
無意味な抵抗だとわかっているのだろうか?
下を見下ろしていた彼女に、ウィンターフェルの騎士の一人が近づいてきて言った。
「ご婦人のいとこ、エイデン・エルンストの遺体が発見されました。ご確認されますか?」
「……」
その瞬間、ナディアが思い浮かべたのは、生死を共にしたエイデンだった。
特に親しかったわけではないが、関係が悪かったわけでもなかった従兄だった。
彼女は短く考え込んだ末、口を開いた。
「いいえ。ただ、遺体は粗末にせず、きちんと葬ってあげてください。ああ、それと、彼の家族は見つかりましたか?」
「まだです。」
「もし生きていたら、決して殺さないでください。エイデンの子どもはまだ2歳です。そんな幼い子まで手をかけたら、こちらの立場が悪くなります。」
「はい。」
残酷だという悪名を避けなければならないという名目だったが、その本当の意図はナディアも知っていたし、話を聞いていた者たちもわかっていた。
何も知らない子どもであっても命を奪わないことが、彼女にできる最大限の慈悲だった。
言葉を告げた騎士が去った後も、彼女はしばらくの間、下を見下ろしていた。
ほとんどの場所はすでに整理されていたが、いまだに抵抗が続いている場所があった。
彼女が知っている人物を見つけたのは、その無意味な抵抗を痛ましげな目で見つめているときだった。
見慣れた黒髪が視界に入ってくる。
喉元がかすかに見えるほどの距離だったが、ナディアには一目で誰か分かった。
タクミだった。
「……!」
彼女は声もなく驚き、心の中でこう思った。
『あの人、まだ生きていたのね。』
むしろ自分の見えない場所で死んでいたら、ここまで気を取られることはなかっただろうに。
唇を固く結んでいた彼女のそばに、いつの間にか近づいていたグレンが声をかけた。
「ナディア。」
「わっ!びっくりした。」
他のことに気を取られていたナディアは、驚いて肩を跳ね上げた。
「えっ、いつ来たの?」
「さっき。君がここに来るって聞いてね。」
「私がわがままを言って送ってもらったの。部下たちを煩わせるつもりはなかったから。」
「いや。君の行く手を阻める者はウィンターフェルにはいないさ。」
グレンは肩をすくめながら、再び軽く矢を引いた。
「これ、何ですか?」
「前に言ったでしょ。本人が片づけるべき縁だって。」
「………」
グレンは苦笑いを浮かべながら、言葉を続けた。
「どんな縁があったのかを聞こうってわけじゃない。僕には君の結婚前のことに口出しする権利なんてないから。」
「………」
「ただ、君が自分で整理したいって言ったから……望むなら機会を与えることはできる。どちらにしても、君の意思を尊重するよ。望むなら、そのままやればいい。」
「……」
ナディアはゆっくりと彼が差し出した弓を受け取った。
運動用の剣を習ったグレンから、弓まで教わったのがこんなふうに使われるとは。
ナディアが再び城壁の内側に視線を向けたとき、タクミは彼女が立っている場所をじっと見つめていた。
「……!」
離れている距離にもかかわらず、目が合ったような気がした。
かすかに見えるその首筋が、どういうわけか笑っているようだった。
言葉では言い表せない感情が頭の中で渦巻いていた。
まるで彼が死ぬと考えた瞬間、気分がひどくなった。
『彼は……バラジット公爵の血筋だ。死は避けられない。』
ナディアはゆっくりと腕を上げて矢をつがえた。
そして、彼が死ななければならない理由を思い浮かべてみた。
『自分の欲望のために私を捨てたのは明らかだ。それに、「一瞬の過ちだった」なんて言い訳までして……。』
矢を放とうとする手が震えていた。
矢が完全につがえられたと分かっていても、彼は逃げようとも防ごうとも、一切の動きを見せなかった。
『私を裏切って、私の死を黙って見ていた人よ。今さら来て、言い訳する理由なんてないわ。』
しかしどれほど心を鬼にしようとしても、彼女は弓を手放すことができなかった。
彼を自分の手で殺したくはなかった。
ついにその事実に気づいた彼女は、ゆっくり……とてもゆっくり腕を下ろした。
そしてグレンに弓を返しながら言った。
「撃たないほうがいいと思います。もし万が一あの軍に当たったらどうしますか? 正確に的に当てる自信がないんです。」
「そうか。」
「私はこれで失礼します。会わなければならない人がいるので。では、また後で。」
そう言い残して、彼女はゆっくりと城壁を降りていった。
階段を下っていた途中だった。
背後から、突然、轟くような歓声が沸き起こった。
「………」
ナディアの足取りがふと止まった。
無意識のうちに、拳がぎゅっと握られていた。
それを不審に思った護衛兵が尋ねた。
「どうなさったのですか、奥様?」
「………」
彼女はしばらく沈黙した後、ようやく口を開いた。
「何でもありません。それよりも、私に捜してほしいと言っていた人がどこにいるか分かりましたか?私の異母妹カレインのことです。」
「はい。私がご案内いたします。」
そわそわと先を行く従者の後をついていきながら、ナディアは素早く涙を拭った。
カレインが幽閉されている場所は、尖塔の最上部の小さな部屋だった。
階段を上るだけで息が切れるほどの高さに、彼女はひとり閉じ込められていた。
ギイィッ。
扉が軋む音を立てて開かれ、狭い部屋の中の様子が現れた。
小さな窓と簡素なベッド、机が一つと椅子が一脚あるだけの、やっと一人が入れるほどの部屋だった。
ナディアの異母妹、カレインは椅子にもたれかかるように座っていた。
ナディアがゆっくりと口を開き、挨拶をした。
「久しぶりね、カレイン。」
「………」
その間に多くの苦労があったのか、彼女の顔にはかなり傷が残っていた。
かつて誇っていた金色の髪は、もはや手入れの行き届かない状態だった。
それでもなお、揺るがずに静かに燃えるような瞳の光は健在だった。
気の強い性格だと思っていたが、それよりも誇り高い様子だった。
侯爵令嬢としての品位を守ろうとする姿勢は、想像以上だとでも言うべきだろうか?
「ここに来た理由は何?」
「最後のあいさつをしに来たの。」
「……」
最後の挨拶。
その言葉に、机の上に置かれたカレインの手が反射的に拳を握った。
姉の言葉が自分の死を意味するかは分からなかった。
だが、死の恐怖にも勝るほど、気になっていたことがあった。
この場所に閉じ込められて以来、ずっと抱いていた疑問。
カレインは全身を震わせながら尋ねた。
「ねえ……一体どうしてそんなことをしたの?」
「何のこと?」
「どうしてお父様を裏切ったの?!なんで北部の奴らの味方をしたのよ!お父様があなたに何か悪いことをした?あなたみたいな混血児を拾って育ててくださったのに!恩をこんなふうに返すの? 天罰を受けるわよ!」
狭い部屋の中がビリビリと震えるほどの大声だった。
ナディアはまるで気が狂ったように悪態をつくカレインを静かに見つめてから、口を開いた。
「どうしてあなたがあんなことをしたの?」
「は?」
「もしあなたが……」
何かを言おうとしたナディアは、すぐに後悔とともに口を閉じた。
意味のない質問だった。
どうせカレインはその出来事すら覚えていないはずだから。
「黙ってないで返事しなよ!どうしてお父様を裏切ったの!?お父様はあんなにもあなたを大切にしてくださったのに……!あなたのしつけまで気にかけてくださったのに!」
「それは私を大切にしたんじゃなくて、チェスの駒として使いやすかったからでしょ。あなたは楽観的すぎるのよ、カレイン。」
「黙れ、この裏切り者!ウィンターフェル侯爵家の後継者の立場を捨てて、一族を裏切った張本人のくせに……!」
カレインは、絶望に近い叫びをぶつけた。
「今はあなたに優しくしてるかもしれない。でも見てなさい。あなたに利用価値がなくなったとき、今まで与えられてきた厚遇はまるで蜃気楼のように消えてしまうわ。」
あまりにも続く聞き苦しい声に疲れて、ナディアは質問に質問で返した。
「あなた、お父様が亡くなったの知ってる?」
「………」
結論から言えば、非常に効果的な選択だった。
罵倒していたカレインの口がぴたりと閉じたからだ。
「エイデンおじさまが戦死したという話は?」
「う……」
するとカレインは卓の上に崩れるように倒れ込んだ。
カレインは泣き始めた。
すすり泣く声がかすかに漏れてくる。
両腕で顔を覆っていたので、表情は見えなかった。
実のところ、ナディアはそれほど見たいとも思わなかった。
ナディアは席から立ち上がり、袖の中から小さなガラス瓶を取り出してテーブルの上に置いた。
「これは、苦しまずに死ねる薬よ。私の最後の情けと思って、置いていくわ。」
「……」
返事はなかった。
それでもナディアは、カレインの最後の言葉を待たずに、静かに部屋を後にした。
ドアを閉めて出ると、ファビアンが近づいて尋ねた。
「何事もありませんでしたか?」
「叫び声がうるさくて少し耳が痛いけれど、それ以外は何もなかったわ。もう降りましょう。ああ、またあの階段を降りなきゃならないなんて。」
ナディアはため息をつきながら、らせん階段を一段ずつ下り始めた。
事が起こったのは、彼女が塔を出て別の場所へ移動しようとした時だった。
ドン!
背後で何かがぶつかるような大きな音が響き、ナディアは反射的に足を止めた。
彼女は体を向けて尋ねた。
「今の音、何だったの?」
「ええっと……レディ・カレインが塔の上から身を投げたようです。あまり見るに堪えない姿かと思われますので、今は席を外された方がよろしいかと。」
「そうですか。」
ナディアは軽くうなずきながら、妹のことを思い返した。
野心家で、愛情に飢え、飽くことなく自分を追い詰め、そしてついには、自ら命を絶つことを選んだ異母妹のことを。
ただぼんやりしているだけかと思ったら、苦しまずに死ぬ薬という言葉を信じるほど無能ではなかったようだ。
ナディアは体を向け直し、命令を下した。
「遺体は丁重に葬ってあげてください。」
「はい、マダム。」
彼女はもうカレインのことを忘れることにした。