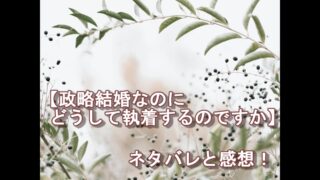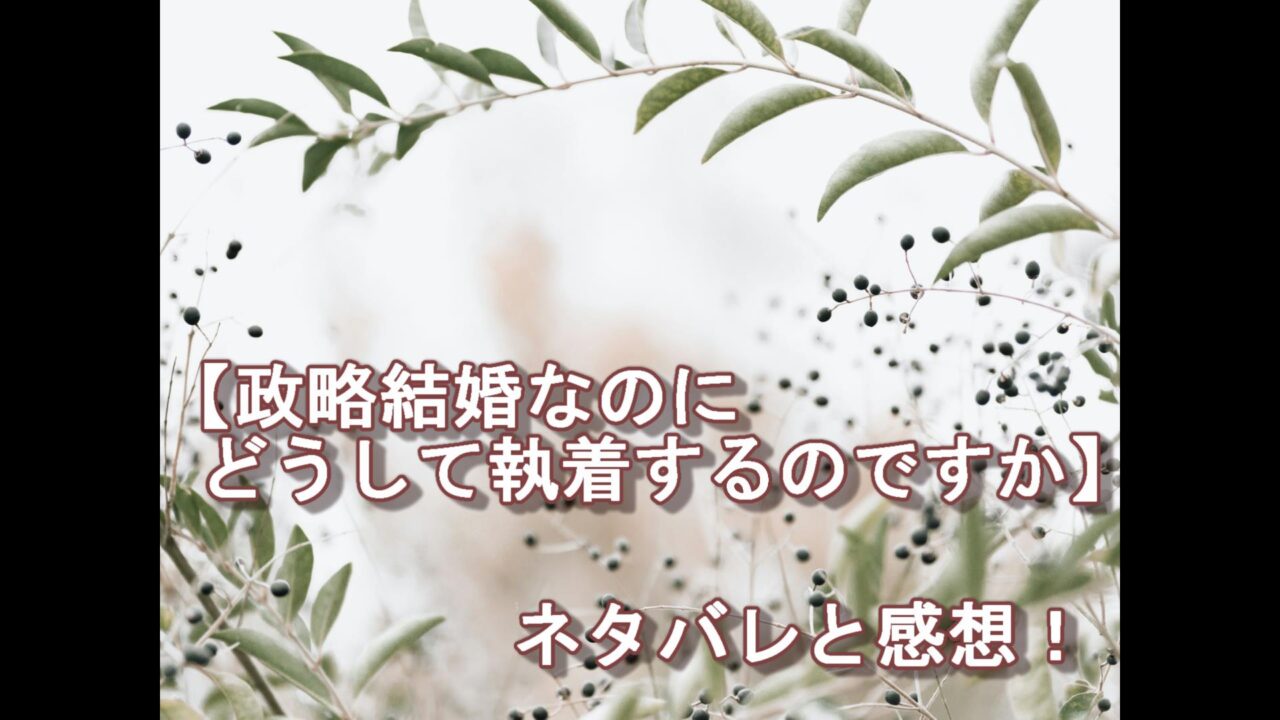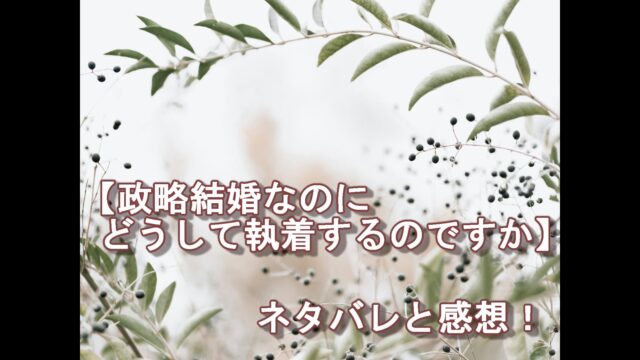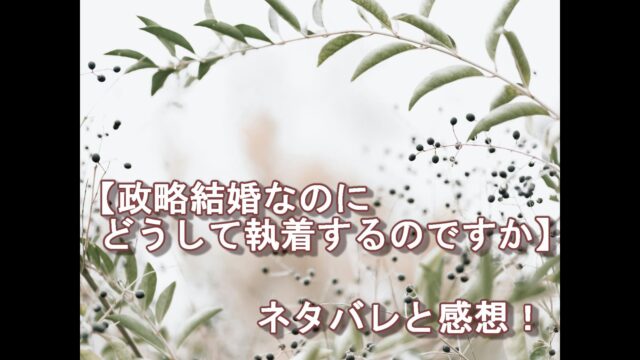こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

113話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 期待に応えて
グレンは混乱する公爵領の状況を整理しているところだった。
首都から伝えられた知らせは、日に日に死に瀕していた人々にとって一筋の恵みの雨となった。
「オルデル伯爵が首都から脱出したそうです。」
「よかったな。」
簡潔な感想を述べたのは、感動がなかったわけではなく、強く反応する気力がなかったからだった。
疲れたように眉間を押さえるグレンに、ジスカールが近づき追加の報告を続けた。
「各地で抵抗が続いているようですが、もうすぐ収束するでしょう。士気が高まっており、投降する者たちも続出しています。」
「降伏した者たちは生かし、最後まで抗った者は──ところで、今マダムはどこへ行かれたのですか?そういえば今朝からお見かけしていないような……」
彼が知るナディアは、無断で長時間姿を消すような人ではなかった。
不審に思うガシンのために、グレンが答えた。
「少し考えを整理したいと言って、城の外に出た。」
「え?」
そのとき、ジスカールの目が見開かれた。
その意味を誤解したグレンが、慌てて言葉を続けた。
「この近辺と後方まで制圧されたので、大きな問題はない。」
「それよりも奥様がご心配されておられますが、どうして領主様がここにいらっしゃるのですか?」
「……さっきまでは死者の手でも借りたいと言っていなかったか?」
「何が重要か、優先順位が分からないのですか?」
すぐにこの人物がウィンターフェルの主か、ナディアか判断がつかないような状況だった。
さらに問題は、あまりにも堂々とした表情で話すので──
「まさか?」という考えさえよぎるようになっていた。
さらには、他の人たちまで同調し始めた。
「幼少期を共に過ごした親しい仲だったのに壊れてしまったのではありませんか? まさかウィンターフェル家の人間になろうと決心されたのでは……と考えるのも無理はありませんよ。」
「侯爵様、今はそんなことをしている場合ではありません。すぐに奥様をお探しください。」
周囲の反応がそうであるだけに、ナディアが自分たちの家門を敵視していると知るグレンは、どうしても罪悪感を抱かざるを得なかった。
彼は沈痛な顔で凍りついた。
「私があまりにも無神経だったんだ……。」
「今からでも気づかれて幸いです。さあ、行きましょう。」
こうしてグレンは業務地獄から解放され、城壁の外へと出ることになった。
要塞の東門を出て、少し馬車を走らせれば川辺にたどり着くことができる。
暑さが増してくる時期とはいえ、武装したまま日差しの下に立っているのはなかなか骨の折れることだった。
川辺の桟橋の上、ウィンターフェル家の紋章を刻んだ騎士たちが三々五々集まり、小さな桟橋を囲んでいた。
「今、何時間経った?少なくとも3時間は経ったと思うけど……」
「とりあえず、うっすらお腹が空いてきたってことは、正午は過ぎてるのは確かだな。」
「奥様は……足、もう痛くないのか?」
桟橋の周囲にいた騎士たちの視線が自然と川辺に向かう。
そこには喪服のような濃い色のドレスを身にまとったナディアが、川を見つめながら立っていた。
「簡易椅子でもお持ちしましょうか?」
「いいえ、結構です。気が重いでしょうに、一人でいさせてください。」
夫人を見つめる騎士たちの目には、哀れみが浮かんでいた。
いくら夫であるグレンを愛していたとしても、義理の死刑を見守るのは異常なことに違いない。
ましてや血縁の家族まで無残に殺される状況なのでは?
夫人が朝から川辺で物思いにふけっているのは、百回、いや千回でも理解できることだった。
『哀れな夫人……。』
「私たちがもっとよくしてあげなきゃ。」
一方、川風に吹かれながら立っていたナディアは、こんなことを考えていた。
「はぁ……バラジット公爵はもう少し苦しんでから死ぬべきだったのに……」
最初から実の父親でない可能性が高かった上に、自分を道具のように利用して捨てた人に、家族としての情などあるはずがなかった。
自分が一生をかけて築き上げた業績が砂の城のように崩れる様を見ながら、肉体的にも精神的にも長い苦しみを受けて死を迎えるべきだった。
それなのに、身内や親戚たちに見守られながらベッドの上で安らかに息を引き取ったなんて!
『まさかこの時期に死に至るような重い病を患っていたとは思わなかった。私にも隠していたなんて……いや。考えてみれば、彼が私に知らせる理由などないか。』
当時の自分は、政略結婚の駒にすぎなかったのだから。
せめて慰めになるのは、彼の息がまだあったときにも、すでに後継者が決まっていたという点だった。
自分が死んだあと、一族が滅びるかもしれないという恐怖。
せめて彼が心の痛みの中で死を迎えたことを願うばかりだ。
カレインの死についても語ることはなかった。
彼女が自分のことを妹だと思ったことなど一瞬たりともなかったのだから。
ただ——
「……」
寂しげな視線が木の箱へと向かった。
城を出るときにはいつも薬草が入っていたその木箱は、いつの間にか空っぽになっていた。
ナディアは、それがどこかへ流されたのかと想像しながら、遥か遠くの川の流れを見つめた。
「あなた、とても遠い国から来たって言ってましたよね。」
誰に向けたのかわからない独り言だった。
タクミが家族のように自分を裏切った人を思いながら——
変わらない事実ではあったが……それでも納得できず、どこかしっくりこない気がしていた。
「どうか、あそこまで無事にたどり着けますように。」
カチッ。
彼女は空の箱の蓋を閉めた。
そして、それを川の水の中へと投げ込んだ。
自分の名前を呼ぶ声が聞こえてきたのは、その時だった。
「ナディア。」
「……?」
ナディアはそのとき初めて、自分のすぐそばに誰かが近づいてきているのに気づいた。
いつの間にここまで近づいてきたのか、グレンはすぐそばに立っていた。
「……ああ、あなただったのね。少し余裕ができたみたいね?忙しいのに私だけでのんびりしていてごめんね。」
「いや、今までうちの家門のために尽くしてくれただけで十分さ。気分もよくないだろうし、しばらくは何も気にせずゆっくり休んで。」
その言葉に、ナディアは一瞬どきりとした。
「……私の気分が悪いの、そんなに分かりやすかったですか?」
彼がさらに誤解する前に、ナディアが何とか弁明しようとした瞬間だった。
「むしろ、私があまりに無神経だったことについて謝らないとね。いくら関係が良くなかったとしても、あの親しみ深い眼差しがあなたにとって無意味だったはずがない……」
「え?」
彼女の目が丸くなった。
その間もグレンは真剣な表情で言葉を続けていた。
何か誤解されていると感じているようだった。
「僕が君の新しい家族になってあげる。」
「……」
「決して、家族の不在を感じさせないようにするよ。これからは君が一人で寂しい時間を過ごすようなことは、僕が絶対にさせないよ。」
そう言う彼の顔は、任命式で騎士の誓いを捧げたときのメンセラのように、真剣そのものだった。
あまりに真剣な顔なので、からかいたくなる気持ちが湧いてきた。
しばらく沈んでいたナディアの気分も、少しずつ和らいできた。
「は、ははっ!」
「……なんで笑ってるんだ?」
「だって、くすぐったくて。」
飼っていた子犬が「これからは僕がご主人様を守ってあげる!」と言わんばかりに、勇ましく前に出てくる姿を見ているような気分だった。
さらには状況を断定的に誤解しているほどだった。
ナディアは短く笑った後、彼の胸に身を預けた。
すると、グレンの体が震えているのが肌を通して感じられた。
「新しい家族が恋しいわけではないんです……。ただ少し、気が抜けただけです。」
「復讐を果たしたあとの虚しさ、みたいなものか?」
「似たようなものだと思います。だから、変な考えが浮かばないようにしてくれませんか?」
その意味深な提案に、グレンの表情がわずかに揺れた。
「俺が?」
「はい、さっき私の家族になってくれるって言ったじゃないですか。だからこれくらいのお願いは快く聞いてくれないと。」
「……」
すると彼は本当に困ったような表情を浮かべた。
慰めてほしいわけでもなく、特別な考えが浮かんだわけでもないようにしてほしいだなんて、だなんて。
本当にどうしていいか分からないといった彼の表情に、ナディアは少しヒントを与えることにした。
『あまりに要領が良すぎるよりは、少し鈍いほうがかわいいかもね。』
そう言って彼女は飾りボタンをトントンと叩いた。
「私の頭の中が複雑になれば、他のことは考えられなくなると思うんです。」
「頭の中が……複雑に?」
「できることがあるじゃないですか。夫として。」
「……あ。」
最後の言葉まで聞いてようやく、彼はかすかに笑みを浮かべた表情を見せた。
「できることだと思いますよね?」
「……もちろん。」
左手が上がって彼女の肩をそっと抱いた。
その同時に、ナディアはつま先立ちになって彼が簡単にキスができるように手助けしてくれた。
唇と唇が触れ合った瞬間、川辺に山風が吹き込んだ。
ナディアの茶色の髪とまつ毛が宙に舞う。
彼女は腕を伸ばしてグレンの肩を抱いた。
薄い夏服越しに温もりが伝わってくる。
谷間の陽だまりの下にいたにもかかわらず、不思議と体がもっと温かくなる気がした。
『もう私の家族はこの人なのね。』
ここがまさに彼女が落ち着くべき場所だった。
父と弟に関することはすべて忘れて、これからはこの人を家族として思わなければならない人。
私はこの人とずっと幸せに生きていくつもりだ。
彼の肩を抱きしめているナディアの腕に力がこもった。
ナディアとグレンが再び城に戻ってきたのは、ちょうど夕日が沈みかけていた頃だった。
城内に足を踏み入れて数歩も進まないうちに、二人は非常に目を引く場面を目撃する。
まさに大きな酒瓶を抱えたまま通り過ぎる使用人の姿だった。
いや、正確に言えば使用人“たち”の姿だった。
ナディアが思わず尋ねた。
「ねえ……誰が見ても酒でしょ?」
「ここまで匂いが漂ってくるほどなら、見るまでもないわね。」
「どうしてあんなにたくさん……」
あれは誰が見ても派手なパーティーの準備をしている様子だ。
ぞろぞろ歩いていく使用人たちを見ながら、グレンが密かに眉をひそめた。
まだ内情は完全には終わっていないのに、誰が──
「領主の許可も得ずに葬儀を計画したというのか?」
犯人を突き止めるのはそれほど難しくなかった。
「私たちが指示しました。」
自らの口で自白したおかげだった。
ただ問題があるとすれば、単独犯ではなかったということだ。
「もちろん一部の地域ではまだ抵抗が続いているのは事実ですが、実質的に内戦は終わったと見るのが正しいのではありませんか?」
「同感です。工業都市を制圧した後も、目を離す暇もなく忙しかったのです。これから少しずつ整理していって、一日でも早く呼吸を整えるように……」
「……。」
使用人たちが一斉に集まって同じことを言っているので、グレンとしても彼らを処罰することができなかった。
グレンが動揺していることに気づいたヌチチェン一行が、控えめな声でささやいた。
「それに、公爵夫人の気持ちを慰めてあげてください。もともと心が空虚な時には、思いきりはしゃいで遊ぶことほど癒されるものはありません。」
「ふむ。」
奥様を喜ばせることほど効果的な方法は他にない、というわけだ。
そして、ひと気がなかった公爵城で、久しぶりにパーティーが開かれることになった。
場所は公爵城のグレイトホール。
主人が変わってから長らく閉鎖されていた場所だったが、宴のために再び扉を開いたのだった。
グレイトホールへと向かう回廊を歩きながら、ナディアは久しぶりに幼い頃の記憶を思い出すことができた。
「ここを使うのは、ほぼ15年ぶりですね。」
「そういえば、幼い頃は公爵城に住んでいたと言ってたね。」
「はい、この回廊でよく走り回って遊んでいた記憶があります。」
乳母に厳しく叱られたという話も聞いたが、それはもう過ぎたことだ。
使用人が開けてくれた扉を通り過ぎると、すでにグレイツホールの中には人々がぎっしりと詰まっていた。
使用人たちが立ち上がり、彼らを出迎えた。
「奥様、いらっしゃいませ!ようこそお越しくださいました。」
「……私の姿は見えていないのか?」
「もちろん、公爵様も歓迎いたします。」
一時ざわめきはあったものの、しばらくして二人は上座に着席した。
席に着くやいなや、酒杯がすぐに満たされた。
「これが倉庫の中で最も奥深いところに隠されていた酒だそうです。」
こんな日に他人の好意を無視できるだろうか。
勧められるままに食べ物と酒を受け取るナディアは、どこか気まずそうに微笑みながら思った。
『なんだか、みんな普段より親切な気がする……。』
皆が勝利の喜びに包まれ、残る人に対してもより親切になったのだろうか?
彼女は周囲を見渡した。
宴会を楽しむ人々の顔には、不安や懸念を見つけることができなかった。
思い思いに微笑むその光景は、まるで幸福そのもののようだった。
「早く故郷に帰らなければ……」
「……妻が無事に出産を……」
「……もう何ヶ月も経ってしまった……」
あちこちから酒に酔ってへべれけになった人々の声が聞こえてくる。
広いホールの中はざわざわと騒がしかったが、ナディアの口元には微笑みが浮かんでいた。
親しい人々と一緒に食事をしながら過ごすうちに、なんとなく虚しかった心が満たされる気がした。
隣の席で酒杯をゆっくりと傾けていたグレンが、彼女を見つめながらつぶやいた。
「気分がだいぶ晴れたようですね。」
「はい、とても。」
「よかったです。」
彼の口元にもほのかな笑みが浮かんでいた。
召使いたちが彼の許可もなく勝手に宴会を開いたことは少しばかり気にかかるが、今のナディアの表情を見ると、良い判断だったようだ。
そうして時間が流れ、月が頭上高くに昇る頃になった。
グレイトホールの雰囲気はなかなか冷めずに盛り上がっていたが、ナディアには次第に限界が近づいていた。
差し出される酒もほとんど受け取らなくなっていた。
グレンがやや疲れた顔で宴席を見渡しているナディアに尋ねた。
「疲れたなら、そろそろ帰ろうか?」
「うーん……そうですね、それがいいかもしれません。」
そう言いながらも、彼女は目を開けたままうとうとしていた。
グレンに手を引かれて席を立つ。
ナディアの動きを察した侍女たちが尋ねる。
「えっ、もうお帰りになりますか?」
「お酒に弱くて……皆さんはゆっくり楽しんでください。あ、くれぐれも事故だけは起こさないようにね。」
ナディアが挨拶を交わした後、歩き出した。
自分の体を支えてくれている誰かがいることに気づいたのは、ホールの外に完全に出た後だった。
大きな手が腰をしっかりと支えてくれていた。
彼女はぼんやりした頭で考えた。
『どうしてこんなにふらつくのに、まっすぐ歩けてるのかしら……』
支えてくれていた手の主は当然ながらグレンだった。
「こんなふうに抜け出してもいいの?」
「酔った人に一人で歩けとは言えないでしょ。使用人たちに任せればいいんです。もともと、ああいう場では余所者は早めに抜けるのが一番なんだよ。」
「……そうですね。」
酔いが回ったのか、たわいない会話にも笑みがこぼれる。
ナディアはずっと絶え間なく笑いながら、よろよろと歩き続けていた。
夜の涼しい風に当たりながら歩いているうちに、寝室に着く頃には多少意識が戻ってきた。
ベッドに腰かけた彼女の周りを、グレンがうろうろと歩き始めた。
「着替えないといけないのに……メイドたちを呼んでこよう。」
「呼ばなくても大丈夫ですよ。そのまま上着を脱いで寝ればいいんです。どうせ夏ですし。」
それに加え、気候が温暖な南部の土地で、夜でも暑さを感じるほどだった。
そういう意味ではナディアの発言にも特に問題はなかった。
ただ……場所と状況のせいで、少し妙に聞こえただけ。
「………」
「………」
暗い寝室、ほどよく回ってきた酔い。
そして、この寝室の中には二人きりだった。
「……あ……そ、そうか。むしろ寝巻きを着た方が楽かもしれないね。」
グレンは戸惑って言葉をどもったが、それが彼女にとって不快に感じるはずもなかった。
彼はそそくさと身を翻して寝室を出ていった。
「じゃあ、僕はこれで失礼するよ。良い夜を……」
「グレン。」
いや、出て行こうとした。
彼の服の裾を掴む手の感触がなかったならば。
振りほどこうと思えばいくらでも振り払える力があるのに、どうしても引き離すことができなかった。
脚がぐらついたのだ。
動かないまま立ち尽くしていた。
ナディアが彼の服の裾を掴んで言った。
「まさか、そのまま行くつもりじゃないですよね?」
「………」
「いや、返事がないのを見ると、本当に行くつもりだったんですか?」
彼女は少し慌てた。
酔いが一気に冷めるほどだった。
ナディアは彼の背中に向かって言葉を続けた。
「私の家族になってくれるって、言ってくれたじゃないですか?その言葉を聞いてから、まだ一日も経っていないと思うんですけど。」
「それは……それは当然のことだよ。君はもう僕の家族だ。僕の羽の中の人ってことさ。」
「じゃあ行かないで。宴会場に戻らずに、ここにいてください。」
「……」
グレンはゆっくりと振り返った。ためらう音がするほどぎこちない動作だった。
そして……完全に体を回したとき、彼はそれを見つけた。
窓から差し込む月の光を浴びて、ほのかに笑っているナディアの姿を。
ごくり。わずかに喉仏が動いた。
「私がこんなにしがみついてるのに……まさかこのまま行っちゃうつもりじゃないですよね?」
「………」
彼は無意識のうちに手を伸ばし、肩にかかった髪の毛をそっと撫でた。
手に触れる感触は絹のように柔らかい。
感嘆を飲み込んだグレンは、ゆっくりと口を開いて答えた。
「それなら、その期待に応えないとね。」