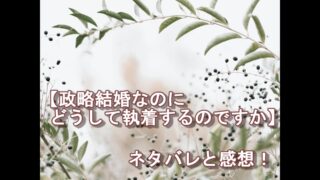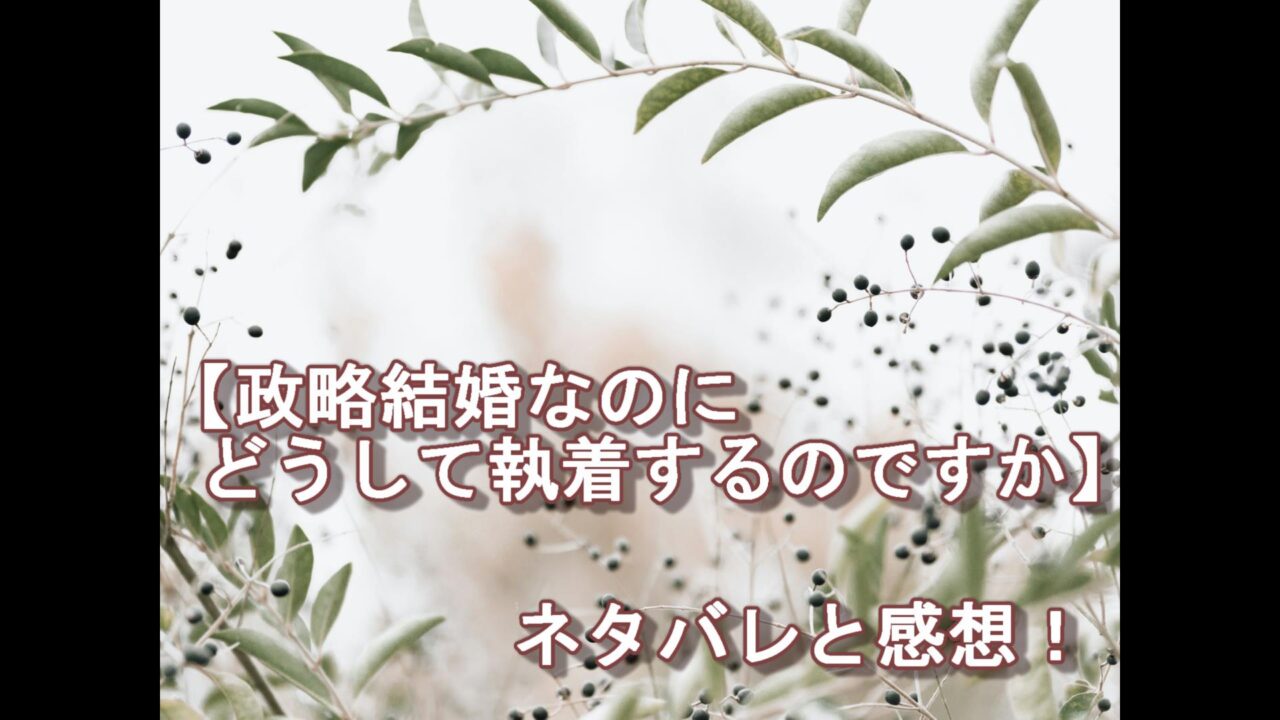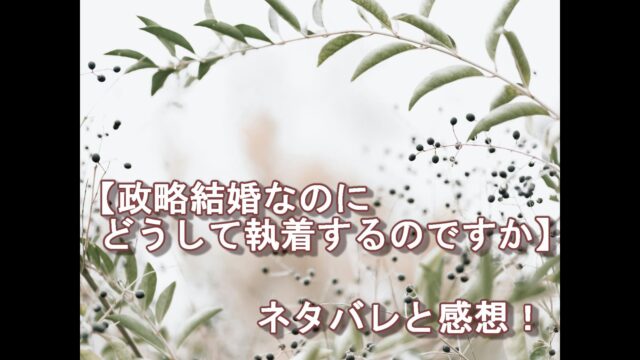こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

115話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- サプライズプレゼント
首都の城壁は遠くから見ても酷く傷んでいた。
まず南門が丸ごと吹き飛ばされたというところからして、そうだ。
青ざめた顔の侯爵夫妻に、王宮から出てきた使用人が急いで弁明を述べた。
「本来は城門周辺の城壁まですべて使えない状態になっておりました。まずは城壁から修理を……」
「事情はわかりました。」
衝撃的だった最初の印象とは異なり、首都での歓迎は華やかなものだった。
王宮に入るやいなや駆け寄ってきた顔がフレイであったことで特にそう感じられた。
「侯爵夫人!」
ナディアを見つけるなり顔を輝かせて駆け寄ってくるフレイに、オーデル伯爵が険しい表情で叫んだ。
「殿下、走らないでください!」
まさにナディアが言いたかった言葉だった。
その叫び声に驚いたのか、フレイがすぐに速度を緩めた。
彼は足早に近づいて、落ち着いた声で言った。
「護衛たちを出迎えに行こうと思ったせいか、今朝から何か手につかないんですよ。」
ナディアは考えた。
『もう麻酔と酩酊の違いをお分かりになったのね。』
短期間で全てが完璧になったわけではないが、どうであれ進歩があったということだ。
彼女は笑いながら答えた。
「私も首都に入城した宮殿を見ると思うと、出発のときから胸が高鳴っていました。」
「あなたは言葉で人の心を温める才能があるんだね。」
フレイは喜びの表情で彼女をそっと抱きしめようとした。
ナディアもまた、新たな王となる人物の後援を気持ちよく受け入れた……いや、それは息子になると言われていた。
「えっ?」
誰かが私の肩を後ろから掴んだわけではなかった。
ナディアの肩を掴んだのは、他でもないクレンだった。
戸惑っている彼女を背後に置いた彼が、急いで話題を変えた。
「殿下、それよりひとつお伺いしたいことがあります。」
「え…… 重要なことか?」
挨拶はまず済ませてから話すべきだった。
フレイは呆れた顔で頬を掻いた。
「はい、首都に向かう途中で第二王子リアムの紋章を何度も見かけました。まだ彼の行方はつかめていないのですか?」
「確かに……。しかし、隠れて命を繋いでいるのが全てだろう。彼が新たな反乱の火種になる可能性は低いと思いますが。」
「私もその意見には同意しますが……それでもすべてのことは確実に進めるのが良いでしょう。予想を外して北部へ逃亡したかもしれませんから、そちら方面にも捜索網を広げた方がいいでしょう。私たちも協力します。」
「そう言ってくれるなら、私たちとしては大歓迎です。」
はじめから真剣な話題が出たため、挨拶は自然に後回しになってしまった。
ましてや遠方から来たことがわかっている状況では、長く引き止めるわけにもいかない。
やむを得ず、フレイは随行員を送り出すように命じた。
「遠くから来られたので、今日はゆっくりお休みください。」
「歓迎していただきありがとうございます。」
後続が向かったのは、より正確に言えば、新たな忠誠の誓約を交わすために集められた貴族たちが集まっている、王宮の一角に存在する別宮だった。
案内してくれる侍従の後に続きながら、ナディアはグレンに軽く抗議するようにつぶやいた。
「グレン、さっきなんであんなことをしたの?」
「さっきって?」
グレンはとりあえず知らないふりをしてみせた。
「私が皇太子殿下と挨拶していたとき、後ろに引っ張ったじゃないですか!あれのせいで会話が中途半端になっちゃいましたよ。」
「挨拶?それが挨拶だって?王子があなたを抱きしめた!しかも夫が見ている前で!?」
「それが挨拶なんです!軽い抱擁は挨拶に含まれるって!」
その頃には、二人の声はすでに私語の範囲を越えていた。
つまり、周囲にいる人々の耳には十分に聞こえるほどの声量だったということだ。
「でも……私の立場からすれば見逃せない話だ。」
「あなたの立場ですって?」
「それを君が言うべきじゃないの?」
「いや、言わなきゃどうしてわかるの? 私、テレパシーが使えるわけでもないのに。」
ナディアが目をしばたたきながら見上げて睨むと、グレンは観念したように唇をぎゅっと引き結んだ。
悩んだ末、彼はそっと横を向いて話すことにした。
「鏡を見て。その中に答えがある。」
「鏡ですか?」
わからないというように、ナディアの目がまんまるになる。
他のときは気配を読むのがやたらと早いのに、なぜこういうときだけは一向に気づかないのか分からなかった。
『でも……前からちょっと鈍感だったわよね。』
どうしようもないというように目を閉じてまた開けたグレンが、ため息とともに口を開いた。
「はあ……他のやつらの目に入ると安心できないってことだ。」
「まぁ。」
ナディアはぷっと吹き出して笑いをこらえた。
あんなに可愛い声を出されたら、怒っていても気分を変えざるを得ないのでは?
少し恥ずかしそうに視線をそらしている様子がさらに可愛く見えた。
からかいたくなる気分だった。
ナディアが彼の腕に腕を絡ませたまま、肩に頭をもたれかけて尋ねた。
「今、嫉妬してるんですか?」
「……否定しても俺だけ恥ずかしくなるだけだろ。」
「正直で、もっと可愛いです。」
そんな時だった。
「うぐっ。」
背後から誰かがうめく声に、二人は反射的に後ろを振り返らざるを得なかった。
後ろからついてきていたファビアンが唇を暗い色でぎゅっと閉じている。
ナディアが尋ねた。
「ファビアン卿?どうされたんですか?お腹の具合が悪いんですか?」
「はい……。長時間馬に乗っていたので、そうなったのかもしれません。」
「……長時間馬に乗って、お腹の具合が悪くなったんですか?」
騎士が馬に乗っていて気分が悪くなるとは、何とも意味不明な話である。
とんでもない話だと思いつつも、ぐったりと疲れ切った人を問い詰めるわけにもいかない。
『昨夜こっそりお酒でも飲んだのでは?』
何か事情があるのだろうが、ナディアはあえて目をつむってあげることにした。
可愛らしいことをしてくれる夫のおかげで、機嫌もかなり良くなっていたので。
「今日は私の護衛を任せずに、少し休むのがいいですね。パビアン卿の代わりを務める人、どこ……え?」
一時的な護衛を選ぼうとしたナディアの目がぐらついた。
後ろについてきた侍女たちの表情があまり良くなかったのだ。
「……皆さん、昨夜私とグレンが知らぬ間に飲み会でも開いたんですか? 二日酔い中なんです? 今?」
「おお、久しぶりの旅程のせいで、みんなコンディションが良くないようで……」
「いや、体力が落ちたら倒れる人がどうしてこんなに多いのか……」
心から疑っているマダムの顔の前で、使用人たちは肩を落とした。
その表情から察するに、自分が過度な行動をしたという自覚すらなさそうだった。
グレンが口を開いた。
「長旅で疲れがたまったのだろう。今日は皆、それぞれの部屋で十分に休むことにしよう。」
こちらも、自覚がないのは同じようだった。
絶望した侍女たちは、それぞれの持ち場にバラバラに散っていった。
滅亡した名家の領地を再分配する問題、王室と北部が新たに忠誠の誓約を交わした件などにより、王宮の会議室では一日中話し声が止まらなかった。
主導権は勝利を収めた奉臣たちに渡っており、フレイはそうした状況で王室の権利を主張するだけの余裕はなかった。
その結果、王室と一部の家臣が参加した会議は、一週間という時間を経て、ようやく結論が出された。
グレンからその結果を聞いたナディアは少し驚いた。
想像していた以上のものを手に入れたのだ。
そして驚くべきことは、それだけではなかった。
「公爵家の財産のうち……半分が私のものですって?」
「残りの半分は国に帰属するそうだ。ウィンターフェルとは関係のない、あなたの個人資産だ。」
「よかったです。そんなに期待はしていなかったのに……」
ナディアは罪人となったバラジット公爵との関係を断つため、自ら絶縁を宣言した。
そのため、バラジット家の存命の血縁者であっても、公爵家の財産について所有権を主張することはできなかった。
いずれにせよ、彼女にとっては得になるどころか損にしかならない内容だった。
『お金は多ければ多いほどいいけれど。』
ウィンターフェルの金庫の鍵を握っているとはいえ、それとは別に個人の財産があるというのは、心の支えになるものだ。
そして、グレンはもうひとつの驚くべき知らせを伝えた。
「それと、フレイ殿下の婚姻の話ですが、できるだけ早く結婚するつもりだそうです。」
「そりゃそうでしょう。王妃の座を空けておくわけにはいきませんから。」
「私たちが発つ前に、婚約式までは済ませる予定のようです。当然、出席しないといけませんね。」
「それはもちろんです。」
首都近くに滞在している以上、次期国王の婚約式に出席しないという選択肢はありえなかった。
「ところで、一つ聞きたいことがあるんですが。」
「ん?」
「王子様が婚約されるっていうのに、あなた嬉しそうですね?」
グレンは2秒間目を動かしてから答えた。
「まぁ結婚すれば人って少しは成長するでしょ。そういう意味で嬉しいよ。」
「……本当ですか?」
「本当さ。」
ナディアは心の中で思った。
『このヤキモチ焼きめ。』
なぜひとりで架空の敵を作って戦っているのかは分からなかったが、彼女は知らないふりをすることにした。
「それにしても、婚約式が楽しみですね。」
「そう?こういう式は面倒くさがるタイプかと思ってたけど。」
「新しい国王の婚約式なんだから、きっと華やかでしょう?いい見ものじゃないですか?私の婚約式と結婚式は、まったく地味に済ませたので。」
「……」
彼女が何気なく言ったその言葉に、グレンの表情が崩れ始めた。
もちろんナディアはそれに気づいていなかった。
彼は様子を伺いながら、慎重に問いかけた。
「……他の貴族たちの婚約式や結婚式も参加したことないの?」
「ええ、そうなんです……私、庶女だったので貴族社会では少し浮いてたんですよ。だから、代わりにカレイン様が代表としてよく出席されてました。」
「………」
「でも、それがどうかしたんですか?」
「………」
「返事しないんですか?」
不審に思ったナディアが何度か尋ねたが、返ってくる答えはなかった。
ただ、いたずらで放った言葉に戸惑ったのか、冷や汗が一筋流れるだけだった。
フレイが無事に婚約式と結婚式を執り行ったのを確認した侯爵一行は、すぐに北部への帰還を選んだ。
増えた領地の処理すべき仕事が山のように積まれていたからだ。
そして平和が戻ってきたという事実がかえって目立たなかったとはいえ、ナディアはしばらくの間、休む暇もなく忙しい日々を送らなければならなかった。
どれほど仕事に埋もれて生活していたのだろうか?
秋が深まりきった頃、彼女はようやくゆっくりと眠れる自由を手に入れることができた。
初秋の穏やかな午前、主人の寝室の中で——
カリカリ、カリカリ。
果物をかじる音が静かに響いていた。
肘掛け椅子にもたれかかって果物をかじっているナディアから出ていた音だった。
ぐっすり寝た後、美しく整えられた秋の庭園を眺めながら果物を食べるなんて……まさに天国そのものだった。
ナディアは肘掛け椅子の上で猫を撫でながらくつろいでいた。
「はあ……やっぱり故郷が一番ね。いくら首都の王宮が素敵でも、故郷だけは別格。この風景が恋しかったのよ。」
「えっと…… 失礼ですが、奥様の故郷は南部ではないのですか?」
疑問を我慢できなかった侍女の一人が尋ねたが、奥様の反応はあっさりしていた。
「もともと心が落ち着く場所が新しい故郷になるものよ。」
「なるほど、奥様のおっしゃること、確かにそうかもしれません。」
「でしょう?」
二人のとりとめもない会話に、そばで聞いていた他の侍女たちも小さく笑みを浮かべた。
寝室の中は、和やかな笑い声で満たされていた。
その時、外からノックの音が聞こえた。
「入って。」
ナディアはドアを見もしないまま返事をした。
きっと執事か行政官のどちらかだろう。
「うん?」
しかし彼女の予想に反して、ドアを開けて目の前に現れたのは数人の侍女たちだった。
しかも皆、それぞれ手に小さな帽子の箱を持っていた。
『私、侍女たちを呼んだ覚えないけど?』
ナディアは慌てながら尋ねた。
「みんな…… ここでは何の用事?奥の部屋で働いている顔ぶれではないようだけど。」
「領主様のご命令です。あの方が奥様のためにサプライズプレゼントを用意されたとのことです。」
「サプライズプレゼント?クレンが?」
「はい、私がしばらく奥様の目を覆ってもよろしいですか?」
「まあ。」
ナディアの口元に、驚きつつも嬉しそうな微笑みが浮かんだ。
気が滅入っていたのは確かだった。
こういうイベントは必要だ。
彼女は笑いながら許可を出した。
「いいわ、許すわ。」
「では、失礼します。」
侍女長がそう言って、慎重にナディアの目元にアイマスクを当てた。
しかし、そこでは終わらなかった。
まるで、わざわざ侍女たちを呼んだのではないと言わんばかりに、残りの侍女たちがナディアに群がってきたのだった。
「?!」
薄手の室内着が脱がされ、少しごわついた衣服が彼女の体を包んだ。
まるで仕立て服のような物が体に引っかかっていた。
『サプライズプレゼントを受け取るのに、こんなことまで必要なの……?』
一体どんなプレゼントを用意したら、着替えまでしなければならないのか、わからない話だった。
好奇心を抑えられなかったナディアが口を開いた。
「ずいぶん豪華なプレゼントを用意したみたいね。どんな種類なのか、ヒントだけでももらえないかしら?」
「申し訳ありません、奥様。領主様のご命令ですから……。それにサプライズプレゼントは、何も知らない状態で受け取った方がもっと嬉しいものです。」
「……そう。」
いったいまたどんな可愛いことを準備したのだろう?
ナディアはどきどきする気持ちを抑えながら、侍女たちと一緒に寝室の外へと向かった。
しかし、進む道が思ったよりも長かった。
奥まった場所を通り抜けると、彼女を馬車に乗せた。
「……?」
まさか馬車に乗ってどこかへ行くなんて?
少なくとも宮廷の内部ではないのは明らかだった。
案の定、馬車が宮廷を出たのか、外の音がにわかに騒がしくなってきた。
『いったいどこまで連れて行くつもりなの?』
ナディアは疑いながらも、好奇心を抑えることはできなかった。
とりあえず馬車の中には聞ける相手が誰もいなかったからだ。
しばらくして、完全に城内を離れたのか、外の音が止んだ。
時折聞こえる蹄の音と馬車の揺れる音だけが響いてくる。