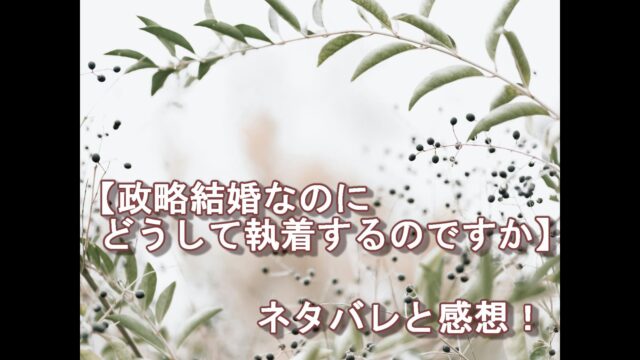こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
今回は61話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

61話 ネタバレ
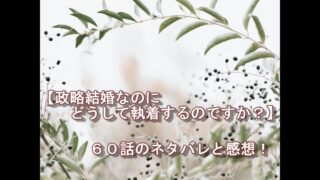
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 釣り糸の先②
城内に広がる噂は当然ながらフレイの耳にも届くことに。
最初はとても信じられないでたらめな話だと思い、笑い飛ばした。
そんなはずがない、と。
だが、事態の深刻さに気づいたのは少し時間が経ってからだった。
それが簡単には済まないことだと察知したのだ。
「古代から原因不明の自然災害を鎮めるために用いられてきた方法でした」
講義中に聞いた歴史学の先生の言葉が、ようやく頭をよぎったのはどうしてだろう。
歴史の勉強を熱心にしたことはなかったが、それでも王族らしく最低限の知識は頭に入っていた。
長期間の干ばつ、洪水、その他の天災が起こった際、昔の人々はその原因を突き止め、解決しようとしたのだ。
大部分の場合、祭祀を行い神をなだめる程度で終わらせたが・・・王族の誰か一人に全ての責任を押し付ける場合もままあった。
その存在を最も邪魔に感じる人だからこそ・・・。
いくら歴史の勉強を適当にしてきたフレイでも、この程度の推測はできなかったわけではない。
現時点で王位の変動が生じた場合、次の王位を受け継ぐのは異母兄弟のリアムである。
そこまで推測したフレイが最初に抱いたのは「なぜ?」という疑問だった。
「特に仲の良い兄弟ではなかったが、互いを害するほど険悪な関係ではないと思っていた」
「・・・」
「私が先に譲れば歴史の悲劇は起こらないだろうと思っていた。私は王位に就きたいという気持ちがないんだ・・・だからただ穏やかに過ごせると思っていた。」
「・・・」
「でも、それは私の思い違いだったみたいだ」
裏切られたような表情でそう語る王子の声は完全に静まり返っていた。
今にも涙を流しそうな様子だったのか、それは定かではない。
弟の裏切りに歯を食いしばるフレイに向かって。
なんとも気の毒な話だが・・・ナディアは心の底から幸運だと思った。
(幸運だ。自分を攻撃している相手が誰なのかも分からないほど愚かではないから・・・)
そっと頭を傾けて隣を確認すると、グレンもまた動じない表情をしている。
継母のせいで育ちが貧弱な面はあるが、生まれつき萎縮しているわけではないようだ。
二人が動じない混乱の中でも王子は引き続き話し始めた。
「どうして兄弟同士で血を流して戦わなければならないんだ?僕は本当に何もしていないんだ。侯爵夫人、僕が間違って考えているのだろうか?」
「全体的に誤りがあるとすれば、それはあなたがあまりにも寛大であったということです。責任を自分に押し付けないでください」
「理解できない。僕はリアムを脅かすつもりなんて微塵もなかった。彼が平和に王位を継げるよう望んでいただけなんだ。それなのに、どうして僕がこんな目に遭わなければならないんだ!」
ナディアは冷や汗をかきながら考えた。
(申し訳ありません、殿下。私が少し余計なことをしてしまいました・・・)
しかし、長子が王位を継ぐのが法である以上、父王はいつかフレイの王位継承権を取り上げようとするだろう。
その過程で彼が無事でいられるという保証はなかった。
この純粋な王子を騙しているということに少し罪悪感を感じたが、ナディアはお互いに利益になることだと考えることにした。
いつか受ける痛みを予め経験するつもりなのか?敵を見極めるのは一日でも早いほうが良い。
彼女は憐れみを含んだ表情を浮かべながら言った。
「彼らの本心が私たちにどう映るかは分かりませんが・・・おそらく邪魔になるものは全て排除しようとするのが本音でしょう。それより殿下、このまま黙ってやられるおつもりですか?」
「それは・・・それは嫌だ。このままやられてしまうのは避けたい」
フレイは唇を強く噛み締め、しっかりと返答した。
その青い瞳に決意が宿り始めている。
王宮の召使たちが大切にしていた壺を割っても笑って許されるほどの彼の温厚な性格を考えると、弟の態度がこれほどまでに衝撃的だったとは思えない。
彼は怒りを押し殺した声で言った。
「でも今さらどうすればいいのか分からない」
もしリアムが本気で貴族たちと手を組み、自分を攻撃しようとしているのだとしたら、その時はどうすればいいのか?
(僕の味方になってくれる人なんて・・・父上?いや、違う。父上でさえリアムのほうが賢いと思っているに違いない。では外戚部?属部はもう長い間自分に連絡を寄越していないが・・・)
どれだけ頭を働かせても、それに相当する人物が思い浮かばない。
当然のことだった。
これまで彼は自分の勢力を築こうなどと全く考えたことがなかったのだから。
長子という正当性も、自らに権力欲があるときに初めて有効に使えるものだ。
遅れて慌てて動いても、準備万端の弟との違いを埋めることはできないだろう。
現実に気付いた瞬間、誰かが首筋を押しつけてくるような圧迫感を感じた。
(私はあまりに無防備だったんだな・・・)
なぜ本当に気づけなかったのだろうか?なぜ世の中には一方的に恩を与えたとしても、その恩が報われない関係があることに気づけなかったのだろう?
いや、一度はプレイにその事実を伝えようとした者たちが存在していた。
(忠告をしてくれた人々はいたんだ。ただ、自分が聞かなかっただけだ)
かつて誠実な進言をしてくれた人々は、自分の態度に嫌気がさし、次々と離れていった。
外戚部が再び首都の政争に干渉しないと見て、永遠に戻ってこなくなったかのように。
一瞬失望を浮かべた彼の顔を見上げると、フレイの表情がわずかに揺れたように見えた。
(遅すぎた・・・)
すでに彼のそばには誰一人残っていなかった。
現実に気づいたフレイが絶望の中へ沈み込もうとしていたその瞬間、厳しい状況の中でも彼に手を差し伸べる存在が一つあった。
ガシッ!
誰かが自分の手を掴む感触に、フレイは驚いて顔を上げる。
彼の目に映ったのは___。
「殿下、それでは私たちの話を聞いてみていただけますか?」
「・・・?」
自分の手を掴んだまま、目を輝かせているウィンターフェル侯爵夫人の姿だった。
城壁の塔に登ると、首都近郊の青い川と広がる農地が一目で見渡せる。
余裕がある日には、そこに登って首都の全景を眺めるのがリアムのささやかな趣味の一つだった。
その豊かな景色を見るたびに浮かぶ考えがあった。
いつかこの全ての土地の主人になるだろう。
民の立場からしても、愚鈍な兄より自分が王になるほうが百倍も優れた選択だ。
そのためには兄が消える必要がある。
無邪気に笑う兄の顔を思い浮かべると、彼は少し顔をしかめて視線をそらした。
少し鈍感ではあったが悪い人間ではなかったのに、このような状況まで追い詰められることがどうにも腑に落ちなかったのだ。
「それでおとなしく過ごしていれば良かったものを。軍の権限を拒否して罰を受けるなんて」
「それは、もしかしてフレイ殿下の話ですか?」
リアムは声が聞こえた方向に目を向ける。
バラジット公爵の甥、エイデン・エルネストがこちらに向かって歩いてきていた。
「それでも、その件についてお伝えすることがあります。ウィンターフェル侯爵が宮廷に入り、第1王子を訪ねたそうです」
「どのくらい前のことだ?」
「かなり長い間、独りでいらっしゃったようです」
「なんと慎重な方だな、私の兄上は」
リアムは抑えきれないため息を深く吐き出す。
本当に王位に就きたいのならば、行動に移さなくてはならないのだ。
どう見えるだろうか。
今さら自分の勢力を作ろうとバタバタしてみても、すでに大勢は決している。
(遠くにいる北方領主たちと手を組んでみたところで、彼らの助けがどれほどになるというのだ・・・)
さらに、異邦人の騎士タクミが立てた計画が成功した場合、フレイは完全に失脚することになる。
この首都の中で彼を擁護してくれる勢力は皆無なのだから。
黒髪の異邦人騎士を思い浮かべたリアムの眉間に少し皺が寄った。
「ともかく、今回の計画を立てた者の話だ」
「タクミ卿のことをおっしゃっているのですか?」
「そうだ、あの黒髪の異邦人だ。本当に彼の言葉を信じてもいいのか?本当に何か異変が起こるとでも?」
「伯父様は確信されているようでした。聞いたところによると、数年前にもタクミ卿が月の動きを予測したことがあるそうです。長期間の記録を調べてみると、一定の規則があることがわかる、と言っておられました」
「占星術の人間だと言っていたか?そういえば、東大陸では占星術が発達していると聞いたことがある」
「占星術とは少し異なる学問のようですが、とにかく重要なのは彼がどうやって予測したかではなく、それがどのような結果をもたらすかです」
「あなたたちが少し手を煩わせる必要がありそうだ」
「当然、私たちがすべきことです。事が起きた後は、殿下はただ沈黙を守っていただければ結構です。天の意を受け、第1王子の廃位を主張するのは私たち貴族の役目ですから」
どこにも隙がない計画だ。
まともな支持者もいないフレイが、今回の騒動を乗り越えられるわけがなかった。
そう、これだけ結果が明確に見えていることなのに・・・。
「ただ一つ、気になる点がある」
なぜ心の片隅で引っかかるものが拭えないのだろうか。
「兄上とウィンターフェル侯爵夫人はどんな会話をしたのだろう?」
「その件については具体的な情報はありませんが・・・・おそらくあちら側でも他に手段はないでしょう。もしかすると、予言そのものを信じていない可能性もあります」
「ふむ、そうか」
それでもバラジット公爵の確信がなければ、異邦人の騎士の言葉を信じることはなかっただろう。
もしかすると兄上は、そんなことが起こるはずがないと心のどこかで安心しているのかもしれない。
そう考えると、原因不明の不安感が少しずつ大きくなってきたようだった。
しかし、予期しないことは油断したときに起こるものである。
「王子様、確認しなければならないことがございます」
リアムがその知らせを初めて聞いたのは、気楽な気持ちで王宮に戻る途中のことだった。
ちょうど入宮しようとした矢先、補佐官の一人が小声で耳打ちをしてきたのだ。リアムは思わず立ち止まる。
「何事だ?」
「それが、その・・・市場で広がっている噂が・・・」
リアムは話を最後まで聞く前に手を振り払った。
「つまらない噂話まで俺が知る必要があるのか?もういい」
「は、しかし・・・」
「聞きたくない」
どうせ大した価値のない噂だろう。
そう思って足を踏み出そうとしたその瞬間だった。
もしもの可能性が頭をよぎったのだ。
「待て」
市場で広がっているという噂だと?
以前、兄上を中傷する噂を流したことがあった。
このタイミングで同じようなことが起こるとは。
バラジット公爵が仕組んだものか、それともフレイが仕掛けたものか。
どちらであっても耳を傾ける価値がある。
「気が変わった。話してみろ」
「以前、異変が起こるという噂が広まったことがありました」
「そうか、それならそうだ」
他でもない、自分自身が流した噂なのだから間違えるはずがなかった。
「ところが、異変はこれから起こる災いの一部に過ぎないという噂が急速に広まっています。洪水や地震などが次々に起こるだろうと」
「ふむ?」
リアムの声色が少し硬くなる。
このような話はバラジット公爵からは一度も聞いたことがなかったのだが?
しかし、侍従の話はそこで終わらなかった。
「ところで、災いを防ぐには・・・供え物の儀式を行わなければならないそうです。そして、その儀式を執り行う役割は、王子様であるあなたが担うことになるようです」
本来、儀式を行う役目は通常、王の後継者が務めるもの。
しかし、フレイはそうしたことに興味を持たないだろう。
それがない以上、その重要な役割がリアムの手に委ねられたのだった。
リアムはしばらく考え込んだ末に、小さく感嘆の声を漏らした。
「儀式だね」
「何を・・・おっしゃるのですか?」
「兄上のことだ。今回は儀式を利用するつもりなんだな」
これでは、リアムがどんな行動をとろうとも問題が生じることになる。
もし儀式を行わなかった場合、災いが起こったらどうなる?それは彼が重要な予言を無視したことになってしまうのだ。
儀式を行ったのに災いが起きた場合? それはそのまま私の責任になるということだ。
あの無害そうに見える兄上にも、こんな策略があったとは。
(いや、そばで助言している者がいるのではないか?)
どちらにせよ、かなり興味深い展開だ。
感心していたリアムは、宮内の補佐官が伝えた内容に、何かおかしな部分があると気づき始めた。
「でも災いが連続して起きる? それはまたどういうことだ?」
「最初に起きるのは洪水で、その次が月食、最後が地震だそうです」
「・・・?」
彼の表情が険しくなった。
「この状況で何の洪水だ?」
「私もそれが疑問なのですが・・・」
「・・・」
リアムは再び考え込んだ。
とりあえず、新たに広まった噂が兄上の仕業であることは分かったが、「災いは連続する」という論調を持ち出した理由は何だろうか?
しばらく考え込んだリアムはやがて首を左右に振った。
どうせそんなことが起きるわけもないのだから、気にする必要はない。
「今の状況で大雨が降るはずがない。我々がやるべきことは、君が伝えた話が全て嘘だという立場を貫くことだ」
冷静に決断を下すようなリアムに向かって、側近が心配そうに言った。
「でも、異常気象というものがあるかもしれません・・・」
「予測できないから異常気象だ!それを誰が事前に察知できるというのか?」
「タクミ卿が天体現象を予測したように、もしかしたら別の大陸では天気を予測する学問があるのかもしれません」
「・・・」
言葉を失う瞬間だった。
その言葉にはそれだけの説得力があったのだ。
月の動きを予測する学問があるのなら、天気を予測する学問がないはずがあるだろうか?
自分が知らない知識が存在する可能性を完全に否定することはできなかったが、リアムはひとまず側近の意見を受け入れることにした。
「では、彼に直接尋ねてみよう。未来の異常気象を予測できるというのが本当に可能なことなのかを」
自分の現状を理解したフレイ王子。
ナディアはどんな助言を与えたのでしょうか?