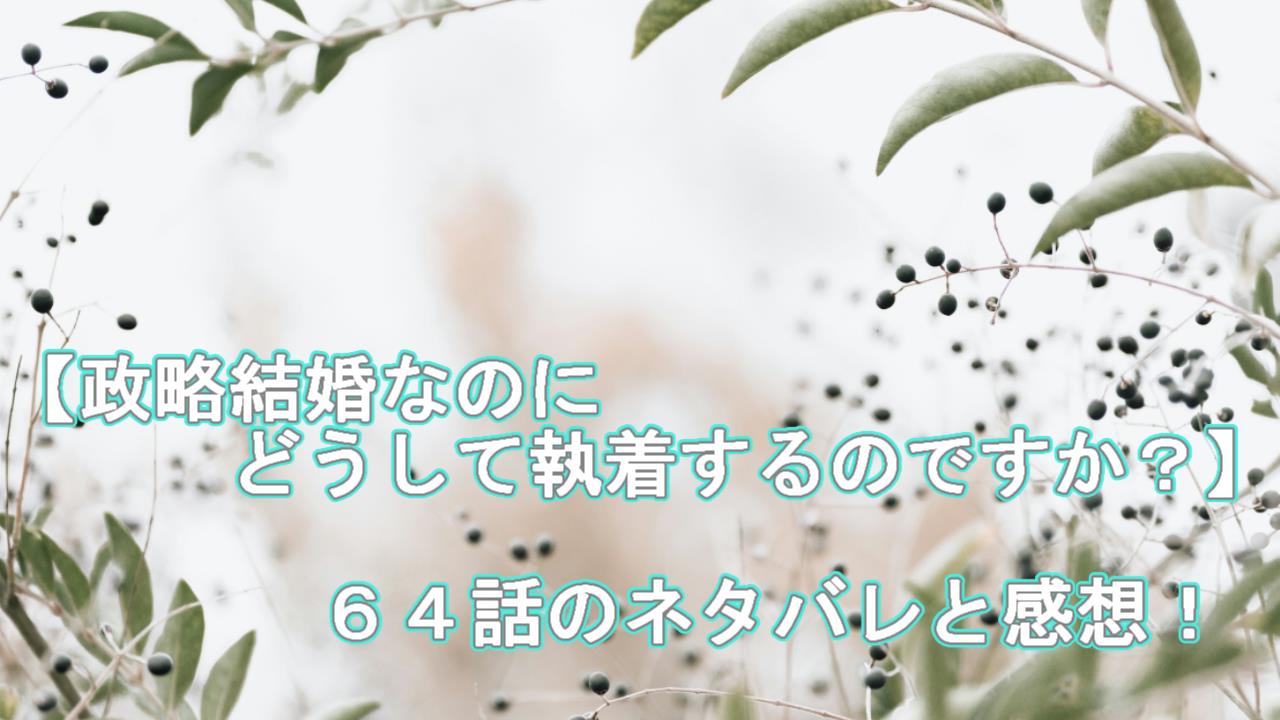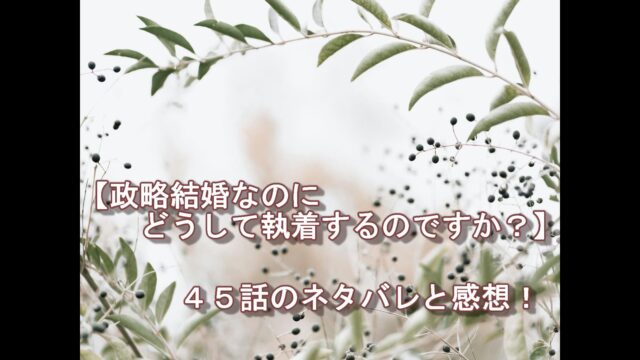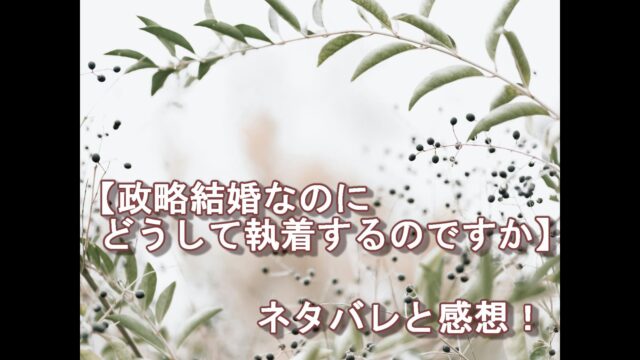こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
今回は64話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

64話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 災害対応
災害の直撃を受けたカンギスム村は、その名の通り完全に廃墟と化していた。
半ば崩壊した家々の残骸は吹き溜まりのように散乱している。
高い場所からその光景を眺めると、その惨状がひと目で分かる。
「もし事前に避難していれば、少なくとも半分は・・・」
「大勢が亡くなったんだな。」
静かに言葉を紡ぐグレンの声に、ナディアが軽くうなずいた。
「みんな助けることができたら良かったのですが・・・。」
「仕方がない。君は最善を尽くしたんだ。」
下では村人たちと王室の兵士たちが協力し、瓦礫を片付けている最中だ。
ナディアがそろそろ降りようかと提案しようとしたその時、誰かが彼らに近づいてきた。
「ここにいたんですね。」
「殿下。」
丘の上にやって来たのは、他でもない王太子フレイだった。
普段は質素な服を身につけている彼が、今日は軍服を身につけ、その上に真新しい塵がついていた。
(こんな場所で豪華な服を着てこないだけ、少しは空気を読んでいると言えるわね・・・)
ナディアは本心からそう思い、安心する。
グレンが尋ねた。
「ここで何の用ですか?」
「じっとしていられなかったのさ。正直言って、君たちの話を半信半疑で聞いていただけなんだけどね。」
そう言うフレイの瞳は、驚きと感動が入り混じった輝きを放っていた。
ナディアは、その視線の重さを無視しながら言わなければならないことを伝えた。
「殿下、お気持ちは分かりますが、まだ安心してはいけません。私が申し上げたことをしっかりと実行できるかどうか、お分かりになりますか?」
「もちろんだ。そういうことなら、すでに父王に直接、祭祀を執り行いたいと申し出たと伝えたよ。」
自信満々に答えるフレイは、さらに何か言いたそうにナディアの表情を伺い始めた。
(何を言おうとしているのか、何となく分かる気がするけど・・・)
「侯爵夫人、今さらこんなことを聞くのは少しばかり滑稽かもしれませんが・・・それでも気になることがありまして。」
「お答えできることなら、お答えします。」
「一体どうして豪雨が降ることを知っていたのか?」
なぜこの質問が出てこなかったのか、と感じた。
ナディアは一瞬戸惑ったふりをして答えた。
「それは・・・申し訳ありませんが、秘密です。」
「私にも教えられない秘密なのか?」
「魔術師のトリックのようなものです。信じていただくしかありません。」
「そうか、それなら仕方ないが・・・。」
フレイは残念そうにしながらも、口をつぐんだ。「では、別の質問をさせてもらおう。」
「それもお答えできる範囲でお答えします。」
「あなたが私を助けた理由は何だ?」
「・・・。」
「いや、質問を少し変えよう。ウィンターフェル家が私を助けた理由は何だ?北部で平穏に暮らすこともできる彼らが、首都の出来事に関わるのは得策ではないはずだ。それに、侯爵夫人の父親はバラジット公爵ではないのか?」
「それは・・・」
あなたの父が思ったより早く亡くなったからだ___と、言うわけにはいかない。
幸運なことに、この純真な王子を納得させるのに、長々と説明する必要はなかった。
ナディアは決然とした表情を浮かべて答える。
「殿下がおっしゃる通り、私の父はバラジット公爵です。」
「そうだ。バラジット家はずっと昔からリアムを支えている。」
「そのために私は幼い頃から彼を見てきました。リアム殿下の性格を把握するには十分な時間でした。」
今こそ少し演技力を発揮する時だ。
ナディアは控えめに口元を軽く引き締める。
「長い間熟考した末に私は結論を出しました。第二王子殿下は王位に適した方ではないと。」
「リアムが?では、夫人から見て私の方が適任だということか?いや、なぜ?」
「なぜ?」という問いが続くのを見ると、自分自身をある程度客観視する能力がある様子だった。
悪い性質ではない。
自分を客観的に見る力を持つ人は、能力外のことに手を出して事故を招くことが少ないものだ。
ナディアはさらに演技に磨きをかけた。
「あの方は聡明で才気あふれる方ですが、少し性格に欠ける部分があります。」
「そうだな・・・。確かにそういう面は否定できないな。」
「以前、ミスを犯した公爵家の使用人に手を切り落とす罰を与えたことがあるんです。あの子は幼い頃から私に仕える幼なじみのような存在でした。でも、手を切られた後、自宅から追い出されました。手のない使用人を雇う理由はない、というわけです。」
最後に添えられた話は作り話だったが、リアムの性格を示すものとして全く根拠のない話ではなかった。
使用人たちが失敗しても笑いながら寛大に許すフレイとは異なり、彼の弟は必要以上に厳しく罰を与える性格だった。
「もしリアム殿下が人の命を重んじる方だったなら、災害が起こるかもしれないという噂を聞いたとき、何らかの措置を講じたでしょう。たとえ一つでも事故が起きれば、多くの人が命を落とすことになりますから。」
「でも、そうはしなかった。なぜなのか気になるな。」
「それは、たかが噂話に振り回されて自分の体面が損なわれることを恐れたからです。いくら聡明で才知に富んでいるとしても、そんな人は王になるべきではありません。王位を継ぐ者は、仁義と慈悲を理解していなければなりません。」
「・・・」
フレイは何も答えず、ただナディアを見つめていた。
彼の瞳には理解し難い感情が揺れていた。
このような言葉を耳にしたのは初めてのことだったからだ。
皆が彼を弟よりも劣った兄だと批判するばかりだった。
おおよそ乱雑な性格すら、王位継承者にとって慈悲は美徳ではないという言葉で切り捨てられていた。
「王になるならば、弱さを断ち切らなければならない」という言葉だけが、彼を縛りつけていた。
今のままでも大丈夫だと言ってくれたのは、彼女が初めてだった。
もし過去に誰かが・・・弟と比較することなく、自分の価値を認めてくれていたなら、彼は一時的な感情で諦めることはなかったかもしれない。
王位は最初から自分のものではないと体感しなかっただろう。
何かを言いたいのに、喉が詰まったように声が出なかった。
しばらくの間、口ごもっていたフレイは、ついに声を発した。
「侯爵夫人が私をそんなふうに評価してくださるとは、嬉しい反面、恐縮だ。あなたとウィンターフェル家には大きな恩がある。どうやってその恩を返せばいいのか・・・」
「では、勉強してください。それで十分です。」
「え?」
フレイの首が少し傾いた。
普段なら、このような時は臣下としてのありきたりな賛辞しか返ってこないのでは・・・?
彼が長く疑問を抱く暇もなく、ナディアが知っている限りの言葉を続けた。
「第二王子殿下が近くにいらっしゃるので、今が絶好の機会です。変わった姿をお見せしなければなりません。これまで何も変わらない姿を見せてきたのは、偶然であり外部の脅威を避けるためだったのだ、という印象を与えるのが良いと思います。」
「ちょっと待って、もう少しゆっくり・・・。」
「他の地域はもちろん、首都内でも私の父の行動を快く思わない人がいるのは確かです。でも彼らが声を上げない理由は何だと思いますか?それは、父に対抗できる力の中心を持たないからです!嵐の中で無防備に飛び出してくるようなものです。」
冷静だった声が徐々に激しくなる。
その姿はまるで厳しい教師に叱られているかのようだ、とフレイは感じた。
「このチャンスを絶対に逃してはいけません。私の言っていること、分かりますよね?」
「ふっ、十分分かった。が、頑張ってみるさ。」
自分が本当にやり遂げられるのか確信はなかったが、できないと断言することはできなかった。
自分の異母弟はすでに自分を敵と見なしている。
このような状況で一人で優位に立っても、無駄であることは彼も分かっていただろう。
「この事実にもう少し早く気づいていたらよかったのに・・・」
そうであれば、今のように考えなしに過ごすことはなかっただろう。
フレイはグレンに視線を向けながら言った。
「君は本当に幸せな男だね。こんなに聡明な協力者がいるなんて、羨ましい限りだ。」
「・・・殿下には王室に忠実な奉仕者がいます。」
そう答えるグレンの目つきが少し鋭くなった。
先ほどから気になっていた点がさらに明確になり始めた。
それは、ナディアの手をしっかりと握っているフレイの手だった。
(既婚女性の手をあまりに長時間握りしめているのではないか?)
彼女に感謝の気持ちを抱くのは理解できるが、スキンシップが長すぎるのは見過ごせなかった。
第一王子がまだ未婚だという事実、一匹狼を貫いて結婚を避けてきたが、この状況をさらに苛立たせた。
グレンはナディアをそっと自分の側に引き寄せ、話題を切り替えた。
「それよりも復興費用の話ですが、私たちウィンターフェルでも費用の一部を支援させてもらいます」
「これはありがたいな。副王陛下が北部を支援してくださるとは、大変感謝する。」
「ウィンターフェルが復興に支援した事実だけが広まれば、それで十分です。」
「そうか、それなら心配しないよ。ああそうだ、彼らから多くの助けを受けた私としても、何か一つ手助けをしたいと思うんだが。」
「・・・?」
再び自分を見つめるフレイの視線に、ナディアは首をかしげた。
「侯爵夫人、リアムのせいで手首を失ったという彼女の話だけど、名前を知っているかい?」
「・・・え?」
知っているはずがなかった。
その場で作り上げられた架空の人物なのだから。
ナディアの首筋に冷や汗が伝っているのを見たのか、フレイは明るい顔でさらに話を続けた。
「幼い頃から夫人の唯一の遊び相手だったんだね。その彼女が少しでも助けになるなら手を貸したい。王族の推薦状があれば、身体に不自由があっても楽な職場に就けるはずだ。僕がその彼女に推薦状を・・・。」
「まあ、お気遣いありがとうございます・・・!」
「ん?」
「その子は田舎の故郷に戻って家族と仲良く暮らしているそうです。わざわざ首都に呼び寄せる必要はないかと思います。」
「そうか? まあ、故郷で元気に暮らしているならそれでいいだろう。」
フレイは肩をすくめる。
特にナディアの言葉を疑っている様子はないようだ。
「もし首都で働きたいと言ってきたら、いつでも教えてくれ。いい仕事を紹介してやれると思うから。」
「そのお気持ちだけで十分です。」
ナディアの言葉を疑わない誠実な性格には、本当に感謝しかない。
彼女はこっそりと首元に浮かんだ冷や汗を拭き取った。