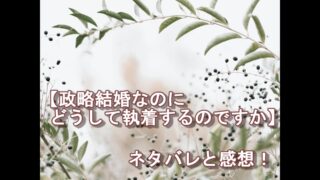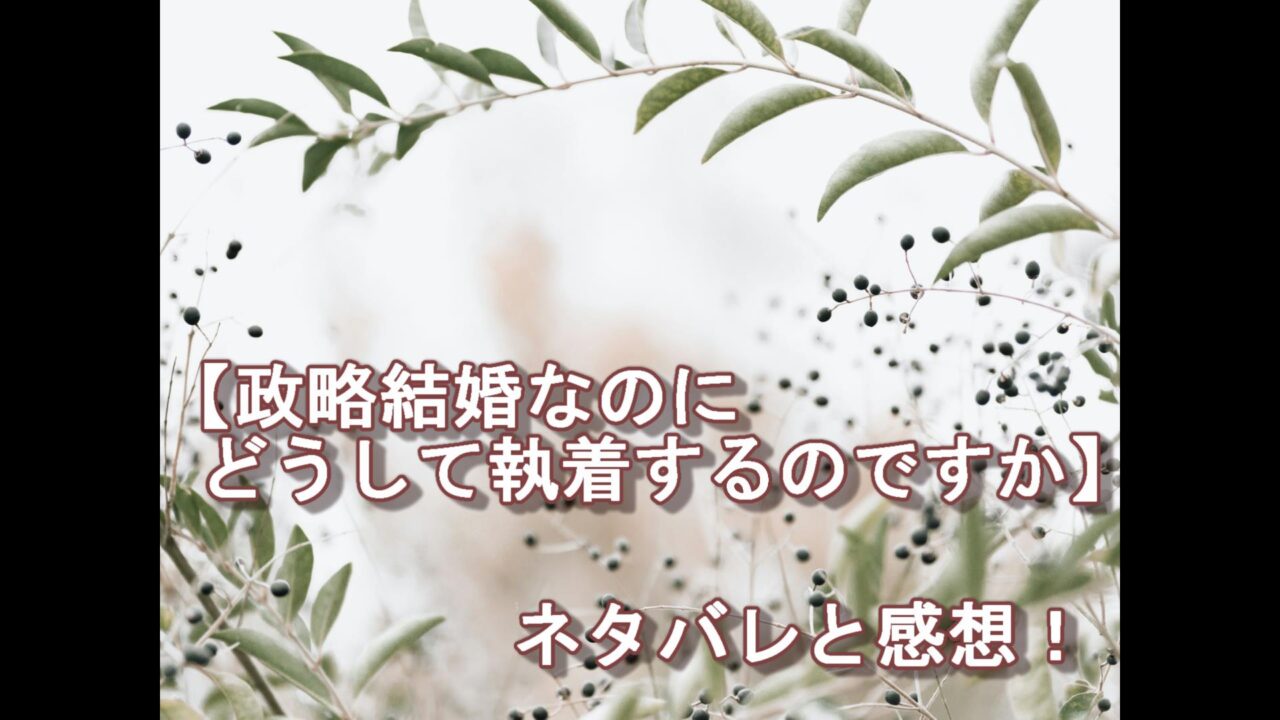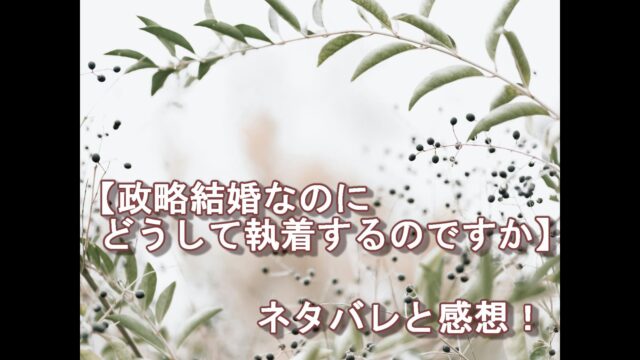こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

75話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 気恥ずかしい光景③
「どうやら『例の件』みたいだな。」
「・・・『例の件』とは?」
グレンは彼女の問いに答える代わりに、ノバートに視線を移した。
「申し訳ないが、急ぎの用件ができてしまった。この場を離れてもいいだろうか?」
「ああ、もちろんです。詳しい内容は後ほど事務手続きを通じて確認するべきでしょう。急を要する件であれば、まずそれを処理されるのが当然です。」
「理解してくれて感謝する。」
実際には理解できないというよりも、説明するのが難しい状況でもあった。
あの若い領主の表情を見ればわかるだろう。
どんな場合でも、カタリナという商人に飛びつきたがっているようには見えない。
しかし、ノバートが上手く対応できなかったために、笑うこともできず、無視するわけにもいかず、席を外すしかないという表情だった。
「一体何が起きたら、あそこまでなるんだ・・・?」
正直に言えば、その「用件」というものが何なのか興味が湧いてくる。
この広大な領地を治める若い主が、顔色を変えながら急ぎ席を外さなければならないほどの理由とは・・・。
彼はウーロへ向かうという一行について行く形で席を外した。
案内される部屋すらまだ分からない状態で、一行は彼らについて行く以外に方法がなかった。
彼らがついに到着したのは、本邸の応接室だった。
応接室の中央には赤い髪をした中年の女性が立っており、ノバートは一目で彼女がリーム商会のカタリナだと気づいた。
「お久しぶりです、侯爵様。そして侯爵夫人も、この間お元気でいらっしゃいましたか?」
「注文した品物は?」
「はは、それにしても性急ですね。私が誰だと思っていらっしゃるのですか?どんな気難しいご婦人でも失望させたことはありません、私。」
中年の女性、カタリナはその細い指で小さな箱を差し出した。
ノバートの喉がごくりと鳴った。
『あれは、なんだろう?』
一見すると宝石箱のように見えた。
だが、侯爵がその物を受け取る行為を「急を要する用件」と表現するとは思えなかった。
明らかにそこには隠された真実があるに違いない・・・。
「こちらはおっしゃっていたビーチの首飾りです。最高級品でございます。これ以上の品質は他にないと自負しております。」
・・・本当に宝石箱だった。
カタリナの手で開かれた箱の中に入っていたのは、エメラルドグリーンの宝石で装飾された首飾りだった。
何度目を見開いても、その美しさに変わりはなかった。
ナディアが驚いた顔で口を開く。
「まさか・・・以前に私がエメラルドが好きだと言ったからですか?」
「贈り物をすると言っただろう?どうだい、気に入らないのか?」
「いえ、それとは違います・・・ただ、クレタ商会に頼んだ用件があると聞いて驚いただけです。何か特別なことがあったのかと・・・。」
「君を驚かせたかったんだ。それで驚きすぎたなら謝るよ。」
夫婦の会話を聞いていたノバートの表情が少し緩んだ。
「サプライズプレゼントか・・・まあ、急な用事というのも納得だ。」
時間が経てば、カタリナなのか何者なのか、この商人がこの首飾りを持参した理由がナディアに伝わるのではないか?
そう考えるのは理にかなっているようだった。
急いでここまで駆け付けたグレンの事情が本当に、心から理解できた。うん、理解できた。
しかし、侯爵夫妻の愛情たっぷりな仕草はそこで止まらなかった。
「ここで試しにつけてみるかい?いや、私が直接かけてあげよう。」
「ここでですか?まあ・・・いいですよ。あなたのご意向があるのなら。」
ナディアが椅子に座ると、彼女の背後でグレンが長い髪をかき分け、ネックレスをそっとかけた。
彼の指先が首元に軽く触れる。
その微かな感触にナディアは身震いした。
まだ本格的な冬が訪れる前で、彼女は襟元が開いた服を着ていた。
そのため、白い肌と緑色の宝石が対比され、とても見事な絵のような印象を与えたのだ。
カタリナはさすが一流の商人らしく、その光景に感嘆した。
「まあ!私の目に狂いはありませんね。これはまさに侯爵夫人のために作られた逸品です。」
「カタリナ・・・恥ずかしいから、そのようなことは控えて。」
「私の口からは真実しか出ませんよ。それに、恥ずかしがることなんてありません。」
彼女が背筋を伸ばして答えると、その堂々とした態度に周囲から笑い声が漏れた。
グレンがカタリナを宥め始めたのは、まさにその時だった。
「侯爵夫人が私の言葉を信じないようなので、何よりも直接その目で確かめてもらうのが良いでしょう。コートを持ってきなさい。」
「はい、こちらにございます。」
カタリナが冷たいコートを丁寧に差し出した。
そのとき、ナディアは自分の首にかかったネックレスの姿を確認することができた。
「直接身につけるともっと素敵ですね。」
それは、細かい細工が施されたアイテムだった。
カタリナが迅速に最高品質の素材を取り寄せた後、領地の熟練工たちにさらなる手間を加えさせて完成させたものである。
「最近ミアトがあまり姿を見せないと思ったら・・・そういう事情があったのですね。」
ナディアは、彼が意図的に自分を避けていたのではないか——顔を合わせればすぐに仕事を頼むから——その可能性を一瞬疑ってしまい、反省するべきだと思った。
その時、グレンが静かに尋ねた。
「どうだい?気に入らなければ他のものを用意しよう。」
「気に入らないなんてことはありません。」
ドワーフたちの労働力を尽くして作られた工芸品が、気に入らないわけがない。
バラジット公爵の元にいた頃には、夢にも手に入れられなかったものだった。
それが嬉しくないわけがない。
嘘偽りのない本音だ。
ナディアはそれを大切に抱え、少し照れたように微笑んだ。
「本当にありがとうございます。私が持っているものの中で、きっと一番大切なものになると思います。」
「・・・」
サルトのように接近してくるその眼差しは、どこか愛おしさに満ちていた。
一瞬、言葉を失うほどだった。
彼は少しの間、何を言うべきか考え、ようやく口を開けた。
「君が喜ぶ姿を見ると、やっぱり嬉しいよ。」
「まあ、普段からそんな風に特別なことを言うなんて・・・」
「部下たちがどうして求婚相手に宝石を贈るのか、なんとなくわかる気がする。」
「・・・え?」
誰が聞いても作為的なコメントだった。
しかし、それを聞いていたノバートの後ろ首には冷や汗がじわりと浮かび始めた。
「あ、あの・・・公爵閣下。」
『私はまだここにいますよ。お客様が隣にいらっしゃるのです。』
突然の軽口にノバートだけでなく、公爵夫人も驚いて目を丸くしていた。
「えっ、今の何ですか・・・?」
「私があなたを笑わせられるという事実が、単純に嬉しいという意味ですよ。」
もうこれ以上は聞いていられない。
耐えきれなくなったノバートの喉から荒い咳払いが漏れ始めた。
「ゴホッ、ゴホゴホ!」
すると、応接室の中にいた全員の視線が彼に向けられた。
グレンの表情がまるで気まずそうに変わるのが見えた。
「・・・君、いつからそこにいたんだ?」
「最初から・・・いました。」
「疲れているだろうに、なぜ休まずに・・・。まさか使用人たちが客室へ案内しなかったのか?」
「はい・・・」
誰も自分に気を配ってくれなかった、とノバートは言いたかったが、その言葉をぐっと飲み込んだ。
「それは失礼だったな。コートン、早くマイヤー子爵を客室に案内しろ。滞在中に不便がないように。」
「はい、領主様。」
その後、侍女たちがやってきて、彼を部屋の外に案内した。
ノバートはようやく緊張から解放され、大きく息をつくことができた。
『侯爵夫人がただの飾り物の主人だという噂は全部嘘だったのか。』
一体誰がバラジット公爵の娘がウィンターフェルでは立場がないなどという根拠のない噂を広めたのか?
事実無根の噂を鵜呑みにして、侯爵夫人を見下すようなことをしたら、大きな代償を払うことになるだろう。
今日見聞きしたことを周囲の人々に必ず伝えなければならないという思いで、ノバートは足を進めた。