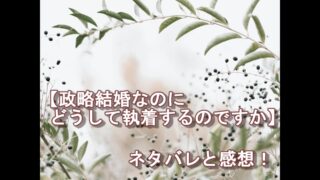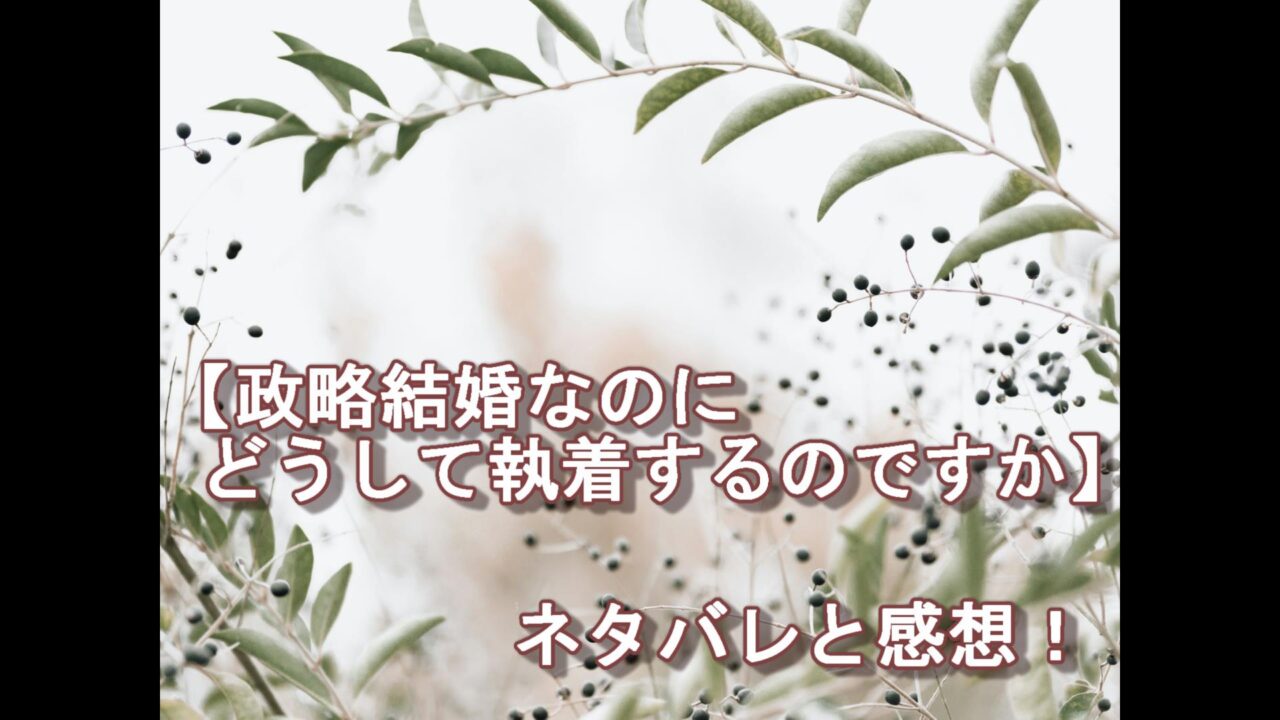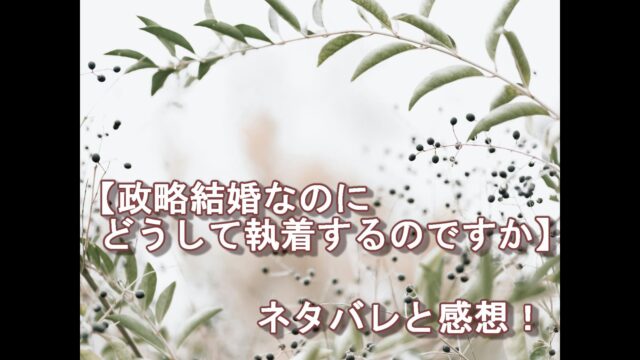こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
今回は69話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

69話 ネタバレ
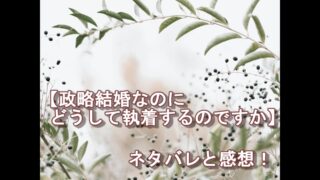
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 不愉快な記憶③
しばらく考え込んでいたナディアが演技を始めた。
世の中には、それでも堅実な人物が存在し得ることを示すように、毅然とした表情で。
「それはなんと無礼な者たちでしょう!いかに親族といえども、彼は王に忠誠を誓った臣下にすぎません。どんな神が感嘆して王のもとに送り出した者でしょうか。その素性を論じるなんて、どういうことですか?」
「そ、そうかな?」
「誰かの素性をあれこれ詮索するなんて、不適切です!」
彼女が積極的に自分の味方をしてくれると、フレイは少し戸惑った表情を浮かべた。
しかしその一方で、彼の目には徐々に自信が蘇りつつあるのがわかった。
(あれを単純だと言うべきか、それとも味方がいない王宮で育ったから仕方がないと思うべきか。)
ナディアは目をキラキラ輝かせながら王子に向かって言葉を続けた。
「私には、その無礼な人の鼻をへし折る方法があります。」
「そんな方法があるのか?それは一体何なんだ?」
「自分の判断が間違っていたと自覚させることです。」
「・・・?」
少し理解しきれない表情を見せる彼を見て、ナディアはさらに詳しい説明が必要だと感じた。
「オーデル伯爵のもとを訪ね、過去の助言を無視した件についてまず謝罪してください。」
「何?」
「陛下にはそれだけの過ちがあったと、態度で示す必要があります。それを感じさせるのです。彼が無礼な言動を日常的にしているのは、陛下が王位を継ぐ資格がないと判断したからではありませんか?そうであれば、その判断が間違っていたことを示してください。困難を乗り越えた後に変わったことを理解させるのです。」
「ああ、いや、そうは言っても・・・果たしてそれだけで外戚の態度を変えられるだろうか?私は懐疑的だ。」
「失望とは、期待を抱いた時に起こるものです。彼が陛下に辛辣なことを言ったのは、愛情があったからなのです。」
「・・・」
「ですから、臣下に先に逃げ腰を見せることは避けてください。それは陛下の権威を失う行動ではなく、むしろ高める行動なのです。少し態度を変えるだけでも、オーデル伯爵はすぐに手を差し伸べてくるはずです。」
フレイは返事をせず、黙って聞いていた。
しかし、反論の言葉が返ってこない以上、すでに説得されたも同然である。
ナディアはさらに穏やかに続けた。
「彼が最終的に陛下を認める姿を見たいとは思いませんか?」
「うーん・・・」
「それは単に侮辱に対する謝罪を受け入れるよりも、はるかに堂々とした勝利です。」
王子の瞳がかすかに揺れていた。
外戚を疎んじる気持ちよりも、彼に認められたいという欲求が勝っていたのだ。
そして何よりも——。
(ここで最後まで意地を張れば、公爵夫人までもが自分に失望するだろう。)
それは嫌だった。
想像するだけでも心が痛む。
人は誰しも他人に認められたいと思うものだ。
初めて自分の価値を認めてくれた人を失望させたくはなかった。
結局、フレイはナディアの提案を受け入れるしかなかった。
「では、伯爵を訪ねて話をしてみる。ただし、彼が私に会ってくれるかどうかは別だ。」
「結局、大した問題にはならないでしょう。そんな人物であれば、初めから戴冠式が終わった直後に領地に戻っていたはずです。それがまだ宮廷に留まっているというのは、その証拠です。私の言っていること、お分かりになりますよね?」
「・・・」
相変わらず険しい表情ではあるが、次第に説得されていく様子が見える。
まるで言うことを聞かない小さな子犬を宥めるような気分だった。
「きっと上手くいきます。必ずやり遂げられますよ。」
国王の誕生日の宴が終わった後、約1か月が過ぎた。
本来の予定通りなら、既に領地に戻っているはずだった。
首都を離れようとしていたオーデル伯爵の足を引き留めたのは、全く予想外の出来事だった。
それは甥のフレイが奇妙な事件に巻き込まれたからである。
初めは無視しようとした。それは単なる噂話だと思っていたからだ。
しかし、噂の真偽を確かめた結果、甥を陥れようとする企みがあることが明らかになった。
そのため、彼はその事件が一段落した後も、簡単には首都を離れることができなかった。
異母兄弟の実態を明らかにしたフレイが、自分の考えを改めるのではないかと期待していたからである。
「でも、来ないんだな・・・」
親族が首都に留まっていることを知りながらも、だ。
窓の外を眺めていたオーデル伯爵は深いため息をついた。
そして彼は執事を呼び、命令した。
「領地へ戻る準備をしろ。」
「いつ頃ご出発のご予定でしょうか?」
「準備が整い次第出発するつもりだ。できるだけ早く。この先、しばらく首都に戻ってくることもないだろうな。」
そう言いながら、深いため息をついた。
その表情からしても、彼がひどく傷ついているわけではなく、ただ気持ちが沈んでいるだけだというのは明らかだ。
あるいは、何か突発的な事態が起きるのを恐れているのだろうか。
執事は慎重に口を開いた。
「二日以内に出発できるよう手配を終わらせます。」
「そうか。」
執事が部屋を去った後も、オーデル伯爵、アレクサンドの表情は緩むことはなかった。
彼はただ静かに背中を丸めたまま、窓の外を見つめていた。
窓の外には忙しそうに家を移動させている召使いたちが見える。
このまま領地に戻るのであれば、しばらくの間、首都に戻ってくることはないだろう。
(カトリン、僕はもう何をすればいいのか分からない。)
彼にはただ一人の姉、カトリンが残した息子がいた。
王位継承権や何やらといった問題を放っておいて、ただ一人の甥を無視するわけにはいかない。
彼は以前からプレイに何度も忠告していた。
リアムとうまくやっていくのは不可能だ。
王妃もまた、見せかけの振る舞いをしているに過ぎない。
彼らを信じてはいけないのだ・・・と。
しかし、プレイはいつも「自分が王位を放棄すればいいだけだ」と考え、その忠告をただ耳障りな小言としか思っていなかった。
(そうだ、何度譲ったとしても王位を手放したくはないさ。)
それならば、弟が王になった後も自分を支える器量を保たなければならないのではないか?
力のない者が唱える平和は、平和と同じくらい無意味なものでしかない。
せめて公平な評価を得るためにも、信頼を自分の味方につけなければならない。
継母の陰謀のせいで、プレイは人々にとって遊び好きな放蕩者として認識されていた。
王となったリアムが兄を害したり殺したりするという者たちは、誰一人としてプレイを庇おうとはしないだろう。
それがいわば一族の残酷さだった。
それでも今回の件で少しは目を覚ますかと思ったが、これはどうだ。
まだ全く見当違いの振る舞いをしている。
(このように状況を把握できない者を王位継承者として支援することはできない。下手をすればオーデルまでも危険にさらしてしまう。)
彼はプレイの外戚であると同時にオーデル家の一員であった。
叔父の立場よりも家門の利益を優先する必要があった。
「はあ・・・。」
それでもなお、不満と苛立ちの感情が胸を満たしていった。
甥が唯一その足で危うい道を歩んでいるのに、どうして気が楽になるだろうか?
しかし、どうしようもないことだ。
彼は揺るがないために何度も心を固めなければならなかった。
ところがその時だった。
コンコン。
「伯爵様、王子様がお見えになりました。」
「何?」
アレクサンダーの顧問が驚いて振り返った。
(王子殿下?)
あまりに唐突な来訪を聞いたものだから、驚いた彼は扉へと飛び込むように駆け出した。
使用人が扉を開けてくれるのを待つ余裕などなかった。
自分の手で勢いよく扉を開けた瞬間、聞いたことが幻聴ではないことを彼は確信した。
開かれた扉の隙間から甥の顔が見えたのだ。
姉にそっくりな顔が、恐れとときめきを半分ずつ抱えた表情で自分を見つめていた。
「・・・!」
続いて、フレイがぎこちない微笑を浮かべながら挨拶した。
「お久しぶりです・・・叔父さん。」