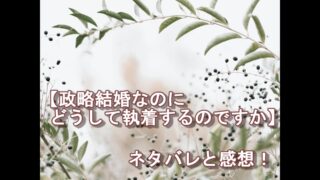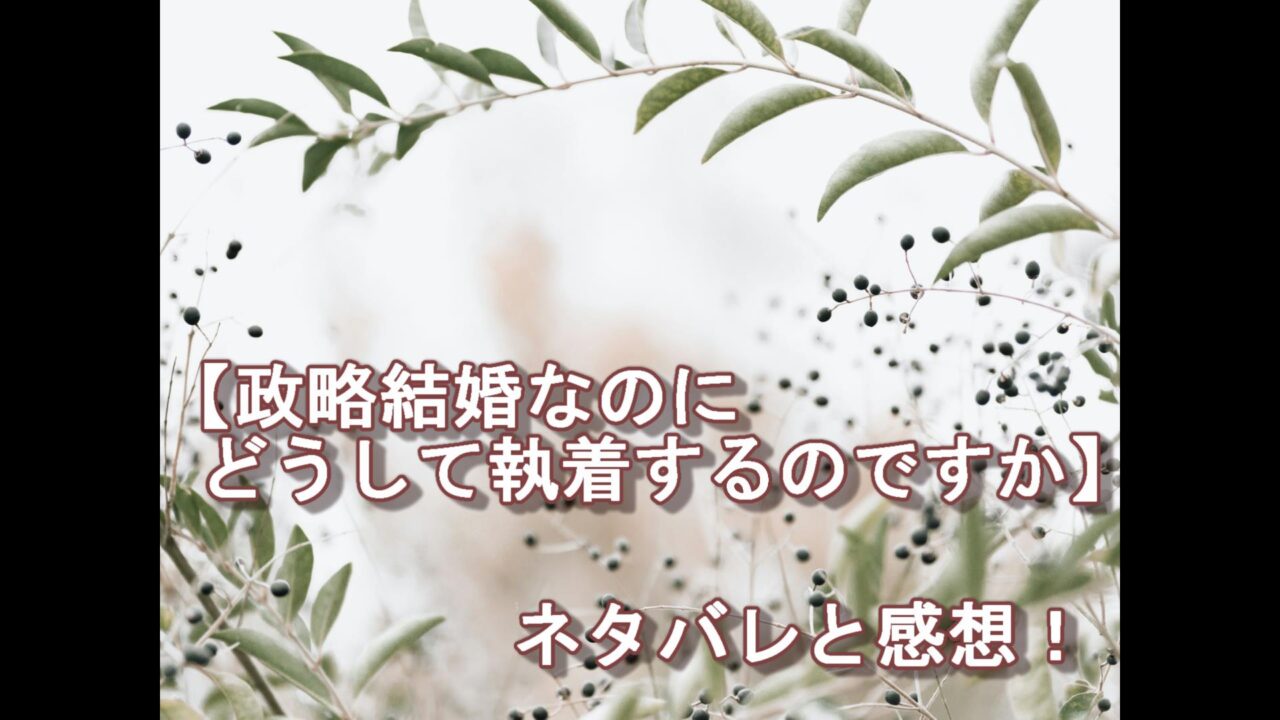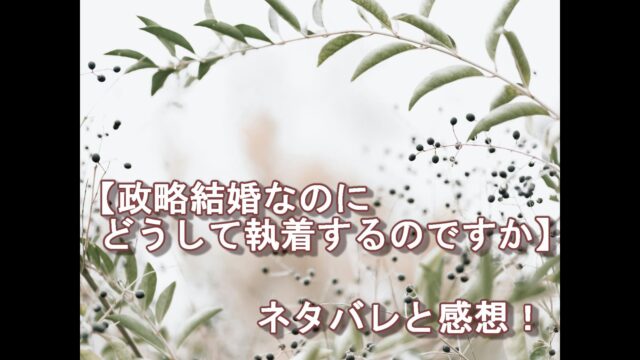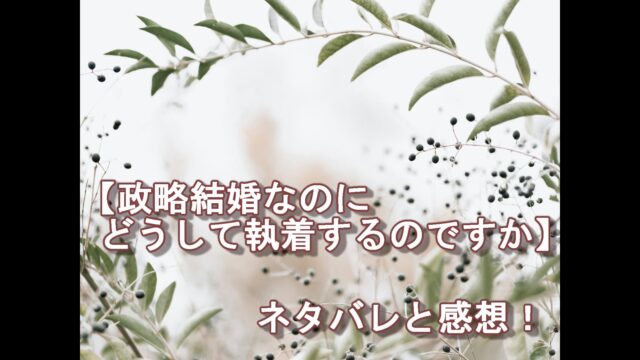こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

105話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 脱出
脱出方法を考えているうちに眠ってしまったようだ。
目を開けると、朝の日差しがカーテンの下から差し込んでいた。
『……最悪。』
ナディアは心の中で罵りながらカーテンを勢いよく閉めた。
窓の外には警備兵たちがあちこちに配置されているのが見えた。
どう考えても、非力な自分があの警備兵の包囲網を突破するのは不可能だ。
『警備を突破するのは二の次で、まずは侍女たちを巻かないと。』
この部屋を出るだけで、どこへ行こうと侍女たちがぞろぞろついてくるのだ。
ナディアは静かに唇を噛みしめ、焦りを抑えた。
すると、そう時間も経たないうちに、侍女の一人がドアの隙間からトレーを差し出してきた。
「お目覚めですか、お嬢様?」
「城主様にお会いしたいのですが、今執務室に伺ってもいいですか?」
「え?でも今はまだ早い時間ですし……。まず朝食をとられてから行かれてはいかがでしょうか?」
「そうね、そうするわ。」
ナディアはなんとなくスプーンを握った。
昨晩は夕食を食べたような食べなかったような感じだったので、お腹が空いていた。
侍女が朝食の準備をしに出ていった間、ひとり残ったナディアは考えを整理した。
『自力での脱出は不可能。使えるものは最大限利用するしかない。』
今のところ、彼女が得た最大の利点は、まさに感情的な優位だった。
タクミが自分に対して強い罪悪感を抱いているということ。
朝食を終えた後、執務室へ向かう途中で、ナディアはとても見覚えのある顔を目にした。
それはまさしく、父の配下の一人であるラファエット子爵だった。
「……っ!」
目が合ったのに見なかったふりはできなかった。
彼女は彼に近づいて挨拶をした。
「子爵様、お久しぶりですね。またお会いできて嬉しいです。」
「やはりお噂通りですね、レディ・ナディア。公爵令嬢から戻ってこられたという話は聞いていましたが、こうしてまたお会いすると感慨深いです。」
捕らえられて戻ってきたのではなく、自ら戻ってきた、か……。
どうやらタクミが近くに控えていたようだった。
『でも、どうやら満足には扱われていないようだな。』
ラファエット子爵の目には、ナディアに対する警戒心と敵意がはっきりと浮かんでいた。
父親から「ナディアが裏切り者だ」という話を聞かされていたからだ。
「お父様はお元気ですか?」
「今は首都を守っておられるはずです。公爵令嬢が戻られたという知らせを聞けば、きっと喜ばれるでしょう。公爵様にお会いになりに行かれるのですか?」
「状況が落ち着いたら、首都に戻らなければなりません。ちょうどその件で領主……つまりタクミ卿と話をするところでした。」
「おや、私ったら気づかずにずいぶんお引き止めしてしまったようですね。どうぞお先にお進みください。」
そう言うラファエット子爵の目からは、警戒の色が消えてはいなかった。
これにより推測するに、公爵令嬢を信用してはいけない、というのが使用人たちの間で暗黙の了解のようになっていた。
ナディアは歩を進めながら考えにふけった。
『タクミ卿、一体どんな手段で私を保護しているというの……?』
監禁しながら護衛とは名ばかりで、貴賓室で優雅に過ごしているなんて。
タクミの発言権はそれほど強大だということか?
そんな疑念を抱きながら歩いているうちに、いつの間にか執務室の前にたどり着いていた。
ナディアはノックと同時にドアを開けた。
「タクミ卿、入ってもいいですか?」
中から何かがドサドサと音を立てた。
ドアをバッと開けると、慌てて机の上を片付けているタクミの姿が見えた。
しかし彼女は何も言わず、そのまま堂々と歩み寄った。
「どういうことですか、ここは……」
「ちょっと聞きたいことがあって来ました。さっきラファエット子爵に会ったのですが……あれ?これは何ですか?」
書類の下に見えたのは、乱雑に積み重ねられた封筒の山だった。
そしてその隙間に見覚えのある紋章が目に入った。
ウィンターフェルのものである。
ナディアが無意識のうちに手を伸ばした。
しかし彼女の手が手紙に触れる前に、誰かがそれを素早く奪い取った。
「……!」
手紙を奪ったのは当然ながらタクミだった。
彼女が声を上げて言った。
「グレンが送った手紙でしょう?見せてよ!」
「ダメです。」
手を引いてもう一度奪い取ろうとしたが、無理だった。
力で取り返すのは絶対に不可能だとナディアは悟った。
ナディアは声を震わせながら懇願した。
「なぜ見せてくれないんですか?私のことについての手紙なんでしょう?読ませてください。ね?」
「……」
涙ぐんだ表情に、彼は一瞬たじろいだ。
しかしそれもつかの間、すぐに冷静な答えが返ってきた。
「ナディア嬢に関する内容ではありません。申し訳ありませんが、お見せできません。」
「嘘よ!そんなはずないわ。グレンが交渉しようと言ったの?」
「グレン?その人のことを名前で呼ぶのか?」
「今それが重要なことじゃないでしょ!」
ナディアがつま先でぴょんぴょん跳ねながら手紙を奪おうとしたが、無駄な努力だった。
子どもとの身長差が大きすぎた。
「なぜ見せてくれないのよ……あっ!」
彼の手から放たれた手紙が壁の中へと吸い込まれた。
紙のような感触が炎に包まれ、灰へと変わるまでのことは一瞬だった。
「……あ……」
ナディアができることは、茫然と壁際の窓を見つめることだけだった。
何かを言う暇もなく、タクミが彼女を引っ張って椅子に座らせた。
「とにかく、よく来てくれました。やっていただきたいことがあります。」
「……何ですって?」
グレンの手紙を燃やしておいて、頼み事があるって?
困惑するナディアの前に、彼は便箋と筆記具を差し出した。
「ウィンターフェル侯爵宛てに、自筆の手紙を一通書いてください。」
「今、何をしているんですか?」
「道中でラファエット子爵にお会いになったとか。話しやすかったでしょう。彼があなたにどんな態度を見せましたか?」
「……表面上は笑っていても、心からは快く思っていないようでした。」
「他の人々も同じです。侯爵様からして、ナディア嬢を裏切り者と見なしているんです。私が弁護できるのも、長くはないでしょう。」
「それで、一体何をどうしろというんですか?」
「ウィンターフェル侯爵の前で、南部に留まるという手紙を書いてください。」
「え?」
「疑いの目からあなたを守るためには、これくらいの証拠は必要です。侯爵家に戻るつもりがないこと、そして親族の元に留まるつもりだという意思を明確にしてください。だからあちら側の助けは必要ないと……」
「……」
ナディアは歯を食いしばりながら彼を睨んだ。
「嫌です。」
「はあ……」
ため息をついたが、そういう返事が返ってくることは予想していたようだった。
「それでは、ナディア嬢を弁護する私の立場が難しくなります。侯爵様や他の家臣たちが結託して訴追を主張すれば、本当に監獄に入ることになるかもしれません。それでもよろしいのですか?」
「その方がマシです。あなたが私の父をどれだけ嫌っているか知っていながら、そんなことを言うんですか?」
「そうでなくても、そうすべきです。そうしなければ、あなたの安全を保証できないということです。目を閉じてでも、うそでも構いません。あの方々に対してだけでもそうしてください。」
「そんなに私の安全がご心配なら、侯爵邸に送り返してください。あなたが焼いたあの手紙、グレンが私を訪ねる理由だったんじゃないんですか?」
「いいえ。」
彼はきっぱりと言い切った。
「子どもがいなければ完全な夫婦ではないって、ご存知でしょう? それにナディア嬢は彼が大切に思っているバラジット公爵の娘です。なぜウィンターフェル侯爵があなたを探すと思われるのですか?」
「……」
その言葉にしばし沈黙した彼女は、ゆっくりと口を開いた。一文字ずつ搾り出すように。
「グレンが……私を探さないってことですか?」
「ええ、ナディア嬢について言及された内容はありませんでした。」
「……それには理由があるのではありませんか?」
平然と嘘をつく彼の表情は、あまりにも自然だった。
ナディアはその飄々とした顔を、怒りに満ちた目で睨んでみたが、意味のない努力だった。
彼がとった行動は、ただ紙と筆記具をナディアの前に差し出すことだった。
「あなたの安全のためです。どうかご理解ください。」
「……」
「本当に仕方ないのです。ナディア嬢も裏切り者として死にたくはないでしょう?」
「そんなに私の身の安全が心配なら、いっそ送り返してくれませんか?」
「申し訳ありません。それはできません。」
「どうして?あなた、私のことが好きなんでしょう?」
「……はい、そうです。」
彼女はまたもや失望した。
タクミという人間は、時を超えて来た後も変わらなかった。
口では「愛している」と言いながら、自分の意思はまるで考慮しようとしない。
バラジット公爵との取り引きを受け入れたように、愛する人の意見よりも自分の判断を優先するだけだ。
彼は冷静に自分を睨んでくるナディアの手に筆記具を握らせながら言った。
「まずは生き残らなければなりません。それが最優先ではありませんか?」
その後しばらくして、タクミはナディアに、もう少し奥にある城へ移動するのがよいのではないかと提案した。
言葉では提案だったが、実際は通告に近かった。
ナディアは「なぜ?」と尋ねる代わりに、静かにその提案に込められた意味を読み取った。
『前線が後退したってことか。』
つまり、遠く離れた場所にいるグレンが無事にやってくれているという意味だ。
もし自分が捕まったことで動揺していないかと心配していたが、それが杞憂に終わったのは幸いだった。
ちょうどその頃、彼女は自分の手紙に対する彼の反応がどうだったかを、慎重に尋ねてみた。
当然のことながら、まともな返答はなかったが。
「今後はこうした複雑な件に関心を持たないでください。私はただ、あなたがこれから無事に過ごして、幸せな思いだけをしてくれればいいと考えています。」
「……」
彼の表情はとても落ち着いていた。
まるでこの土地に根を下ろして親しんでいるかのような。
『結局その話をするために私に……』
言いたい言葉が喉元までこみ上げてきたが、我慢するしかなかった。
そしてしばらく時間が流れ、テニア城を出発しなければならない日が目前に迫った。
出発の二日前、城内がどこか落ち着かない気配に気づき、外へ出た彼女は、どこか見覚えのある顔に出会う。
「エイデンお兄様?」
それはまさに、従兄弟のエイデンだった。
久しぶりに再会した彼の姿はずいぶん変わっていた。
目元を覆っている眼帯からしてそうだった。
「なんてこと……目が……!」
「全部お前の旦那のおかげさ。あいつが放った矢が目に当たったのさ。」
「………」
「もちろんお前を責めるつもりじゃないから、そんなにびくびくするなよ。」
エイデンは肩をすくめながらそう言った。
けれど、その軽口とは裏腹に、彼の顔には深刻さが浮かんでいた。
温室の中にいた坊ちゃんだった彼を直接見た最後の記憶の印象とは比べものにならないほどだ。
ナディアは慌てて話題を変えようとした。
「テニアにはどんなご用でいらしたのですか?」
「タクミ卿と一緒に合流して移動することになっててね。ちょっと立ち寄っただけだよ。君と一緒に出発するんだ。」
「……ああ……」
「それにしてもナディア、本当に久しぶりだね。この間、元気にしていたかい?」
空言でも「元気だった」とは言えなかった。
ナディアは淡々と答えた。
「まあ色々ありましたけど、生きてますし。ここでお兄様に会えて嬉しいです。」
「私も嬉しいよ。」
そう言いながらも、彼の表情はどこか暗かった。彼は険しい顔で言葉を続けた。
「最近、良くない知らせばかりで気分が沈んでいたんだ……。でも君が小さな喜びをくれたよ。私の従姉妹が裏切り者じゃなかったのは幸運だ。」
「私こそ幸運ですよ。お兄様が私を信じてくださったんです。父は私を疑っていらっしゃいますから。それを知ったとき、どれだけ驚いたか分からないです。」
「そう?」
「ええ、今はタクミ卿が間に入って誤解をうまく解いてくれたみたいなので大丈夫ですが……」
「でもね、あの方はまだ君のことを完全には信じていないと思うよ。一度抱いた疑いは簡単には解かない方だって、君もよく知ってるだろう?」
「……」
どういうわけか、何かがおかしいと感じた。
心の中に抱いていた疑問の一つが解けたような気がした。
「それでも君の存在を容認したのは、タクミが君を熱心にかばってくれたおかげだ。機会があればぜひ感謝を伝えてくれ。」
だが、頭の中のすべての疑問に対する明確な答えが見つかったわけではなかった。
『私をまだ疑っているのに、彼の立場を見て私の存在を許したって?もちろん悪魔族との戦争以後、彼の影響力が大きくなったのは事実だけど、それほどではないはずなのに……』
従姉妹が疑っていることに気づいたかのように、エイデンはふっと短く笑った。
「嘘がつけない顔だな。」
「どうしても……そうですね。」
「仮に君が裏切り者だとしても、大きなことは起こさない。君をしっかり監視するという条件を出したらしい。それで今、君が命をつないでいられるんだ。」
「でもタクミ卿は側近の中の一人に過ぎませんよ。その名に重みがあるのは分かりますけど……まさか父が彼の言葉にそこまで重きを置いているとは思いませんでした。」
「伯父様はとても体調が悪いんだ。」
「えっ?」
ナディアの目が大きく見開かれた。
心配というより驚きだった。
これまでまったく知らなかった情報だったからだ。
娘のナディアさえ知らなかったのを見ると、側近の一部しか知らない事実のようだった。
では今になってそれを自分に教えようというその意図は何なのか?
彼女の目にはわずかに警戒の色が浮かんだ。
「タクミ卿の頼みを聞き入れたのは、後継者を任せなければならない家臣たちの心をなだめるためだったんだろう。死を覚悟しなければならないほど、体調が良くないということさ。」
「………」
「だからナディア、子である者として、体の調子が良くない父に心配をかけるようなことはするな。カレインだって追放された庭に、お前までそうなってはいけない。」
エイデンはそう言って、ナディアの肩に手を上げた。
そしてその手に重みを感じたように、強く驚いた。
「私の言ったこと、わかった?」
「……はい。」
「それはよかった。」
唯一見える彼の目が新月のように細まった。
しかし瞳孔だけは冷ややかさを失っていなかった。
それは、タクミの顔を見て命は救ってやるが、軽率な行動は取るなという警告だった。
『この人も私を疑っているのね。』
――まあ、父が後継者として目を付けた人物だから。
ナディアは穏やかな笑みを浮かべて答えた。
「絶対にご心労をおかけしません。」
「よく考えたな。ところで、出発の準備はできてるか?」
「もちろんです。実は持っていくものも特に……」
「明日すぐに出発するから、今夜は早めに休むように。しばらくは野営になるからな。」
「明日?出発が明日なんですか?」
彼女の声が少し上ずった。
「出発はしばらく先じゃなかったですか?タクミ卿はそう言っていたような……」
「正確に言えば、私が到着した翌日に一緒に出発する予定だった。でも、私が予定より1日早く着いたじゃない?だから、君のスケジュールも1日ずれたんだ。」
「…ああ……。」
ナディアは表情を崩さないために少し力を込めなければならなかった。
「そういうことなんですね。私はまた状況がもっと悪化して、撤退が起きたんじゃないかと心配していました。」
「そんなに心配しなくていい。みんな私の身を守るのに必死だから、君のようなか弱いお嬢様まで気を遣う必要はないよ。」
「……はい……。」
エイデンは幼い従姉妹の肩を軽く叩いて席を離れた。
一人残されたナディアは考えた。
『あの人たちが私を生かしておいたのは、血縁への情なんかじゃない。』
それは情けではなく、打算だった。
ナディアのように力のない若い女性一人くらい生かしておいても、何もできはしないという判断。
徹底的に監視し、行動を制限すれば、いくらでも抑えられるという傲慢さ。
むしろ彼女を殺すことでタクミの反感を買うよりは、生かしておいたほうが得策だと判断したのだ。
遠ざかる従兄の背中を見つめながら、ナディアは固く決意した。
—それが誤解だったと、思い知らせてやる。