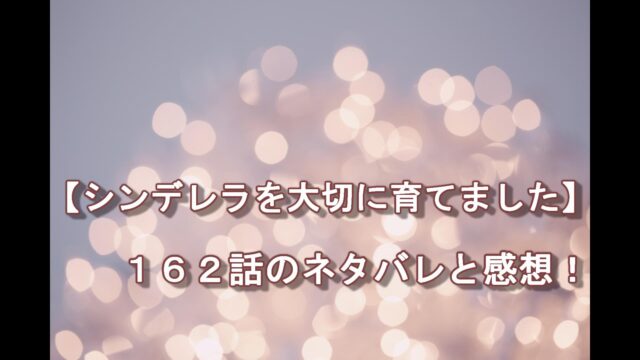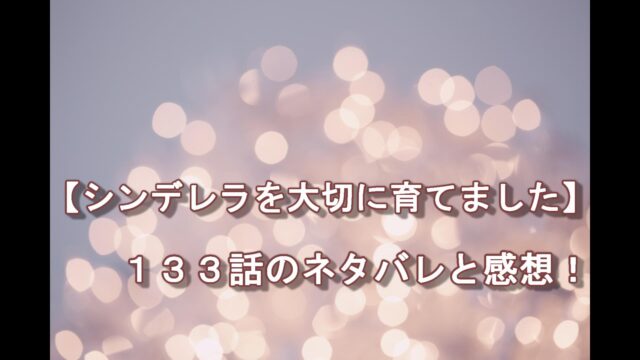こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

202話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 助けの申し出
「来てくれてありがとう。」
私のあいさつにカーシー夫人は緊張した表情でカップを握った。
私はまず彼女の緊張をほぐすためにお茶をすすめた。
今日添えられたデザートは生クリームを使わないカステラで、アイリスが持って行くことになっていたため、たくさん焼いた。
もちろん私が焼いたのではなく、家政婦が焼いたのだけれど。
「前に私に見せてくれた下着のことでお話したいとおっしゃってましたよね?」
私はカーシー夫人がカステラを半分ほど食べたところで言った。
それまで天気の話や最近社交界で流行している話などをしていたが、本題に入った。
当然のことながら、先日彼女が持ってきた下着の話をすると、彼女の動きが緊張でこわばるのが見えた。
「ウィルフォード男爵と話をしてみました。」
私が口を開いた途端、カーシー夫人の顔に驚きの表情が浮かんだ。
私は彼女を安心させるためにすぐに続けた。
「心配しないでください。何かを話したわけではありません。ただ、あなたが斬新な女性用衣類を考案されたので、それを売るにはどうしたらいいか相談しただけです。」
ようやく彼女の顔に安心の色が浮かんだ。
彼女は小さくため息をつくと、私に少し安心したように言った。
「ウィルフォード男爵であれば、事業についてよくご存知でしょう。」
そうだろう、それで彼に聞いてみたのだから。
もちろんダビナのこともふと思い出した。
少し軽めのクリノリン(パニエ)が人気になりそうだとも思った。
「少し話がしたい」と言った私の言葉に、すぐさま我が家に駆けつけてきたダビナを思い出して、くすりと笑った。
アイリスのドレス事件のあと、ダビナは人と会う時にとても慎重になっていた。
彼女にとっては衝撃的だったのだろう。
自分の店のスタッフが、客のオーダードレス情報を別のところに売っていたなんて。
クレイグ侯爵令嬢やムーア伯爵令嬢のドレスに大きな宝石が付いていたという話を聞いて、ダビナは驚いて私のもとを訪ねてきた。
胸元に宝石を付けようとしていた私の冗談を覚えていたのだ。
スタッフが情報を売ってしまった状況に困惑していたダビナに、私は「今回は一度だけ見逃す」と言った。
誰でも一度は過ちを犯すものだ。
ダビナの店は今ようやく軌道に乗り始めたところなのだから。
事業を始めたばかりで、彼女は人を使った経験がなく、失敗もあるかもしれない。
「従業員はすぐに解雇します。」
「あなたのお店で、あなたの従業員なのだから、お好きにどうぞ。」
従業員を解雇するという言葉に、私はダビナに「好きにしなさい」と言った。
彼女の店であって、私の店ではないから。
私が解雇しろと言うのは主人のすることだ。
しかし、信頼できない従業員を雇い続けることは店の評価にも大きく影響する。
今回は私は何も言わないが、クレイグ侯爵やムーア伯爵はどう思うか分からない。
ダビナはすぐにその従業員を解雇し、信頼できる新しい従業員を見つけるまで一人でかなり苦労して仕事をこなした。
「ウォルフォード男爵は、夫人の服を使って独占販売権を得ようとしているようですね。」
私は紅茶を一口飲みながら、ダニエルの提案についてカーシー夫人に話した。
私のビーヌも独占販売権を得ようとしている。
彼は、カーシー夫人の新しい服飾道具がそれほど革新的なものであれば、独占販売権を取得するのも悪くないと考えていた。
もちろん、販売は他の人に委託するという条件で。
「独占販売権ですか?」
「簡単に言えば、一定期間は夫人だけがそれを販売して利益を得られるということです。」
それを「独占契約」と呼ぶ。
私が住んでいた場所では一般的なことだった。
ただし、問題はそれが法律で年数まで決まっているわけではなく、結局は国王の判断によって左右されるという点だ。
国王に多くのお金を払えば、独占期間も長くなるのではないか。
私はそんなことを考えながら苦々しく笑った。
「一定期間、私だけが売るということですか? それはいい話ですが……」
ですが?私の説明を聞いたカージ夫人の表情は曇った。
彼女は明らかにいい知らせにもかかわらず、それを喜んでいない様子だった。
なぜだろうと私は表情を浮かべたが、彼女は声を落として言った。
「それほど大げさな話じゃないんです。独占販売権だなんて。話が大きくなりすぎた気がして……」
何それ? 私はあきれて顔をしかめた。
それほど大げさな話?
クリノリンは女性たちがほぼ毎日身につける下着だ。
それが大げさな話じゃないなら、一体何が大げさなの?
私は体を乗り出して攻撃的に言った。
「カーシー夫人、今スカートの下に何を履いています?」
「スカートの下ですか?下着のことでしょう?」
「クリノリンを履いてるんじゃないですか?」
「え、そ、それはそうですけど……」
「クリノリンを履かないときっていつなんですか?」
カーシー夫人の顔に不思議そうな表情が浮かんだ。
彼女は私をじっと見つめながら、小さな声で答えた。
「寝るときですね。それに、実は家では時々脱いでいることもあります。」
不便ですもの。私もそうだ。
私は大きく頷いてから再び尋ねた。
「じゃあ、一日の半分はクリノリンを履いて生活しているってことですね。」
「そ、そうですね。」
「でもそれなら、別に大げさなことではないんじゃないですか?すべての女性が一日の半分以上はそれを着ていないんですから。」
ある日突然、すべての人がクリノリンを履かなくてもいいとなるかもしれない。
でも、少なくともこの国では、この世界で生きていくにはクリノリンを履かなくてはならない。
つまり、年に何度か新しいクリノリンを買わなければならないということだ。
これは本当にとてつもない市場だ。
私の説明にカーシー夫人の顔に驚きが浮かんだ。
彼女も自分がどんな市場を開拓したのか知らなかったようで、私は苦笑した。
そういえば私も以前そうだった。
リボンで花を作るのを大したことないと思っていた。
でも、それが金になる。
ここはお金になる場所なのだ。
「独占販売権を取るのを手伝ってあげます。」
私はまだ驚いているカーシー夫人を見ながら言った。
ああ、もちろん独占販売権を私が与えられるわけではない。
宮廷に入り、国王の面談を許される人物なら話は別だが。
「正確に言えば、私じゃなくてウルフォード男爵が手伝ってくれるんです。彼に少し利益を分けなきゃいけませんけど。」
「それだけですか?」
カーシー夫人は信じられないというように尋ねた。
利益を分けるのが嫌なら手伝ってくれたのだから何か返さなければならないが、今のカーシー夫人にダニエルに与えられるものがあるはずがない。
私はため息をつき、小さな声で言った。
「利益を分けるのが気に入らないのなら、望むならウルフォード男爵に会ってもう一度話してみてください。」
「いえ、そうではありません。」
カーシー夫人の態度が急に変わった。
私は彼女がダニエルに会って話をしなければならないという事実に不快感を抱いていることに気づき、目を細めた。
なぜダニエルとの会話を不快に感じるのだろうか。
あんなにハンサムな顔を目の前でじっと見つめているのに。
「私が聞きたいのは、夫人のことです。夫人には何をして差し上げればよいですか?」
「私ですか?」
私に何をしてくれるって?
私は一瞬戸惑いながら彼女を見つめ、うーんと言って腕を組んだ。
そうだ、ここで私が何かしているわけでもないのに、何かをもらう理由があるのか?
私が戸惑っているのをカーシー夫人は違う意味で受け取ったようだった。
彼女は私を見つめ、目を大きく開いたまま口元を押さえた。
そして申し訳なさそうに言った。
「ごめんなさい。私が出すぎたことを言いました。男爵様とバンス夫人はとても親しい仲なんです。」
え?それまた何の話?
私は自分でも知らないうちに顔をしかめ、急いで表情を整えた。
「ウィルフォード男爵とは全く関係ないんです。私があの時あれこれ言ったのは、何かをもらったから何かをしたわけじゃないからです。」
「でも男爵が私の仕事を手伝ってくれたのは、バンス夫人がお願いしたからじゃないですか?」
うん、それもそうね。
カーシー夫人が「クリノリンはいいもの」と言ったとき、彼はそれが人気を得るかどうか尋ねた。
私が住んでいたところでも一時期人気だったから、ここでもそうなるかもしれない。
改めて考えてみると、ダニエルがカーシー夫人の事業アイテムに独占販売権を取ることを勧めたのは、私の頼みだけではなかった。
確実に人気が出て利益になると判断したのだろう。
私は首を横に振りながら言った。
「でも違うんです。彼は人情で動く人で、商売に投資するようなタイプじゃないんです。」
私の言葉にカーシー夫人の目が見開かれた。
彼女は私をじっと見てから、小さな声で言った。
「でも男爵様と相談できるほど親しいのは、夫人だけですよ。」
「はは、まさか。」
相談くらいなら誰でもできるだろう。
その程度の関係を築けるくらい親しいのは悪いことじゃない。
例えばフィリップ・ケイシーもいるし。
しかしカーシー夫人はそうは思っていないようだった。
彼女はため息をつきながら言った。
「それでも男爵様と親しく過ごしているなんて、本当にすごいですね。」
「そうですか?」
「男爵様は、ハンサムだけれど……。」
ハンサムだけど?
私はカーシー夫人の次の言葉を待った。
彼女はしばらく茶碗を見つめていたが、私を見てすぐに口を開いた。
「すみません。ご夫人と親しい方のことをこんなふうに話すのは、よくないですね。」
親しい?
私は、彼が今朝出かける前に私にキスをしてきたことを思い出した。
それを単に親しいというだけでは言い表せない気がする。
カーシー夫人も顔を赤らめてうつむいた。
「ただ、少し驚いただけなんです。実は、私だけじゃなかったんですよ。彼を戸惑わせた女性は他にもいたんです。でもこうしてご夫人と近しいのを見て、やっぱり人には縁があるんだなって思ったんです。」
そうかな。私は無言で微笑んだ。
彼が他の女性にはずいぶん冷たかったということは知っている。
以前リリーに対してもそうだったし、ガス嬢に対してもそうだった。
私はふとダニエルのことを思い浮かべた。
彼はいつも私には親切で優しいが、思い返してみると、他の女性たちには必要以上に無愛想だった。
もしかしたら、それが彼の示せる最大限の親切なのかもしれない。
心にもない相手に親切に接して、無駄な希望を抱かせないために。
そういう意味で、ダニエルは本当に偉大だと思った。
私は、自分に好意を持っている人に対して、あれほど冷たくはできない。
私が鈍感なせいかもしれないし、彼が妖精だからそうかもしれない。
妖精である彼は、絶望した人々、助けを求める人々を私より多く見てきたはずだ。
そして、すべての人を助けることはできないということを知っていたから、むしろ冷たくなることを選んだのかもしれない。
それに比べて、そうした経験が少ない私は、誰かが助けを求めてくると、すぐに冷たくはなれない。
私に人々を助ける力があるとしたら、その力が無限だったら、果たしてどうなるだろうか。
ミルドレッドに殺到する助けの申し出。
その渦中で、自分が巻き込まれないようにするには、ダニエルのように振る舞うしかないのかもしれない。
「次は、ウォルフォードの旦那様にも一緒に話してもらわなければなりませんね。」
そう言って私は席を整えた。
独占販売権をどう取得するか、どうやって販売するかを話すには、ダニエルとダビナを呼んで話し合うのが良いと考えたからだ。
すると、席を立とうとしたカーシー夫人が気まずそうに言った。
「何か差し上げたいんです。」
「まだ私が何かしたわけでもないんですよ。独占販売権を得られるかもわからないし、ご夫人のクリノリンが売れるかどうかもわかりませんから。」
「でも、私を助けようとしてくださったじゃないですか。何か必要なものや、私にできることがあれば、何でもおっしゃってください。」
カーシー夫人の言葉は誠実に響いた。
私は席を立ちかけたが、再びソファに腰を下ろし、彼女の顔を見つめた。
私が彼女のクリノリンを商品化するのを手伝った理由は二つあった。
一つ目は、カーシー夫人が一人で立ち上がれるように願ったからで、
二つ目は、この偽りのようなクリノリンが消えてほしいと思ったからだった。
だが、この国のすべての女性が着るクリノリンが一瞬で消えるわけがない。
たとえダニエルに頼んでなくしてもらっても、何か別のものがその場所を埋めるだろう。
彼が五歳の時に使えなかった全ての言葉が、砂のように姿を変えたように。
「私は……クリノリンがなくなればいいと思っているんです。」
私の静かな言葉に、カーシー夫人の表情がわずかに凍りついた。
彼女が作ったクリノリンを商品化しておいて、どうしてそのクリノリンをなくしたいだなんて言えるのかと。
「すべての人が使っているある物が、ある瞬間に一斉に消えてなくなるのは難しいです。時間が経つにつれて使われることが減っていき、自然と姿を消していくものですよ。」
カーシー夫人が作った新しいクリノリンは、今私が使っているものよりはるかに小さく簡素化されたバージョンだ。
「すぐには無理でしょう。もしかしたら私が生きている間にも難しいかもしれません。でも、私はとりあえず種を蒔いておいたのだから、いつか私の子どもの子ども、そのまた子どもが生まれる頃には消えているかもしれません。私がいた場所でも、クリノリンは百年前の物でしたから。」
「わかりました。私が生きている間に、せめてこれが消えるよう努力してみます。」
カーシー夫人の決意に、私はにっこり笑った。
彼女の稼ぎが何十倍にもなるのだから、消えてくれればいい。
そう決意したアイリスだったが、同時にカーシ夫人に感謝の気持ちも抱いた。
「でもカーシー夫人、あなたはそれでお金を稼がなきゃいけないじゃないですか。」
「大丈夫です。生涯これで稼ぐつもりはありませんから。あなたもいろんなものを作ってきたでしょう?生きていればまた別の良いアイデアが浮かぶものです。」
そうかもしれない。
私は立ち上がり、カーシー夫人に向かって手を差し出した。
彼女が作ったクリノリンでたくさんのお金を稼げたらいいなと思った。
そして、私と彼女が老いて死ぬ頃には、それが消えてくれていたら、なおいい。