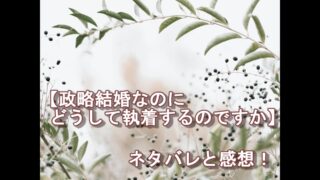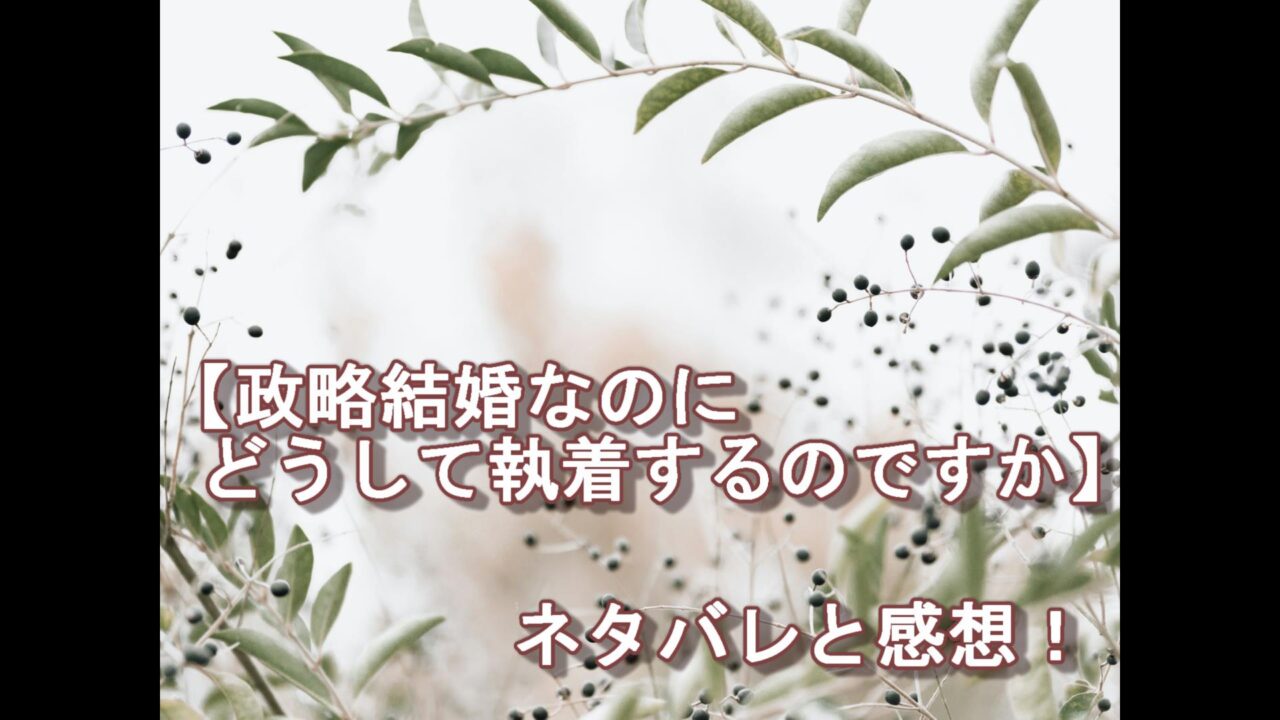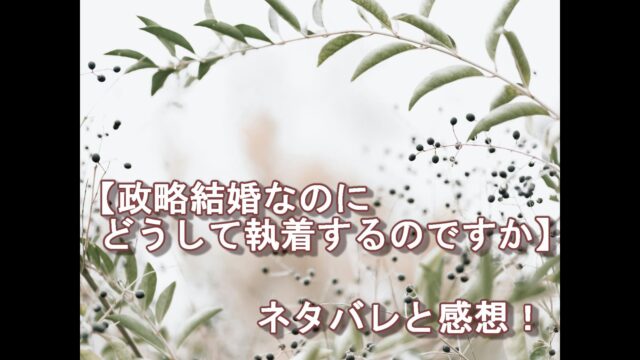こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

114話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 暖かい情景
「まあ、奥様。最近お肌の調子が良くなってきたようですね。」
「そうかしら。最近は元気がなさそうに見えて心配してたんだけど……ただの取り越し苦労だったのね。」
「そう?」
メイドたちの驚きにナディアは手を伸ばして自分の頬を触ってみた。
手のひらに触れる感触が柔らかい。
『確かにそんな気もするし……』
視線を横に移すと、秘訣を尋ねるかのように目を輝かせるメイドたちの姿が見えた。
一瞬、頭の中に思い浮かんだ考えがあったが、それをそのまま口に出すことはできなかった。
ナディアはぎこちなく笑いながら、なんとかごまかすしかなかった。
「うーん……戦争が終わったら、気持ちが楽になったからかも?」
「なるほど。これまで心労が多かったようですね。」
「何にしても、そうね。」
すべてが終わると、気持ちが晴れやかになったのは事実だった。
そういう意味では、嘘をついたわけではない。
彼女はそっと話題を変えた。
「それより荷物は全部まとめた?スケジュールが詰まってるからね。」
「はいっ、すぐに片付けます!」
しばらく気が緩んでいたメイドたちはすぐに自分の持ち場に戻った。
手際よい手つきで物をカバンに詰めていく。
公爵領を離れるための荷造りだ。
リサは手では服を畳みながら、口ではふてくされたように言った。
「もう出発するのがちょっと名残惜しいですね。南部に来るのは初めてだったんですよ。初めて見る風景が面白かったんです。」
「すぐに北部に戻るわけじゃないから、心配しないで。首都には少し立ち寄る予定なんだ。」
「えっ、本当ですか?」
ナディアの返事に、彼女の口がぱっと開いた。
「そんなにうれしい?」
「はい、一度は首都を観光してみたかったんです。」
北部の平民が遠く離れた首都まで旅するなんて、一生に一度あるかどうかの出来事だった。
主人夫妻の旅に同行し、ただで首都見物ができるのだから、喜ぶしかなかった。
ずっとくすくす笑っていたリサが、ふと思い出したように尋ねた。
「ところで、どうして首都に寄るんですか?」
「王室と新たな忠誠の誓約を交わすためだよ。」
「新たな忠誠の誓約ですか?」
「そう、私たちにとって不満な点があったじゃない。この機会にしっかり押さえておかないとね。」
「なるほど……」
実のところ、リサは王と領主の関係がどうなっているのか――忠誠の誓約の意味が何なのか正確には分からなかった。
だが——
『マダムと領主様がうまく解決してくださるだろう。』
お二人とも賢明な方々なのだから当然だ。
リサはうなずき、再びしていた作業を片付け始めた。
ナディアが席を立ったのはちょうどそのときだった。
「じゃあ、ちょっと出てくるね。」
「どこに行かれるんですか?」
「一人で散歩に。私が子供のころを過ごした場所だから。」
このまま北部に戻ってしまえば、再び南部を訪れることができるかはわからなかった。
いや、もしかすると今回が最後の訪問になるかもしれない。
もの悲しい気持ちにとらわれたナディアは、ついていくふりをして召使いたちをまいて、ひとり邸宅の裏手へと出た。
幼い頃、彼女が過ごした場所は邸宅ではなく別棟だった。
ナディアは別棟へ向かう小道を歩きながら考えにふけった。
『実のところ、あまり良い思い出がある場所ではないけど……』
公爵邸の偉そうな使用人たちが、当時彼女をまともに扱ってくれるはずがなかったのだから。
それでも名残惜しく、彼女が最後に公爵城を見て回ろうとしたのは、母と一緒に過ごした記憶が残っている場所だったからだ。
幼い頃、唯一自分の味方だった母。
ある日から徐々にやつれ、突然この世を去ってしまった母。
幼い頃にはただ、母が体が弱かったのだと思っていた。
だが、今振り返ってみると、その突然の死の裏にはバラジート公爵がいたのではないかと思わざるを得ない。
正室の公爵夫人も、やはり似たような症状を患って死んだからだ。
『本人が不治の病だということを聞きたくなくて隠していた……』
かつて彼女が父だと思っていたその男は、思った以上に卑劣な男だった。
母を思い浮かべると、公爵への怒りが胸の奥から込み上げてくるようだった。
ナディアは歩みを進めながら、嘆くように言った。
「はあ……やっぱりあの人、あっけなく死にすぎたわ。」
彼の病状が簡単に勝利へと繋がったことは知っていたが、それでも何か物足りない気持ちを拭えなかった。
今ごろ地獄に落ちているといいけれど。
彼女が静かに芝生を踏みしめながら歩いていたときだった。
カサッ。
背後で枯れ枝が折れる音がした。ナディアは反射的に振り返った。
「まあ。来ていたなら声をかけてくれればよかったのに?」
そこには戸惑った顔のグレンが立っていた。
その表情を見るに、枝を踏んだのはかなり意外だったようだった。
「私を驚かせようと思ったんですか?」
「いや、そうじゃなくて……ただ一人で芝生を踏みながら考え事をしていたら……」
「……あ。」
今回はナディアが戸惑ったような様子だった。
小さな声で言ったのに、それが届いてしまったようだ。
彼女は慌てた理由を取り繕い始めた。
「お父さん……つまり、バラジット公爵についての独り言でした。あの人は罪のわりにあっけなく死んだ気がして……そう言っただけです。」
「そうか、それならよかった。」
「え?何がですか?」
「もし家族に情が残っていたらどうしようかと心配していたんだ。最近元気がなかったから。」
「そんなはずありません!」
そんな心が痛むような言葉に、ナディアは本気で震えた。
「まるで私を憎んでいたかのように聞こえる言い方はしないでください。」
「まるで憎んでいたかのようだった?」
「この別荘は、幼い頃に私が母と一緒に過ごした場所なんです。前に言いましたよね?」
「そうか、思い出したよ。」
同じベッドを使いながら、なかなか寝つけなかった夜にナディアが幼い頃のことをぽつぽつと話していたのを。
「夫婦仲が悪かったのかもしれないな。」
「悪かったというよりは…… 母の死の背後にバラジット公爵がいた可能性が高いです。母は屋敷の中で唯一私の味方でした。」
「………」
予想以上の答えだった。グレンは言葉を失ってしまった。
だがそれも一瞬で、驚くべきことでもないと思い直した。
ナディアのように心の温かい人が親しい相手を裏切ろうと決心するには、それだけのことがあったに違いない。
複雑な眼差しで自分を見つめているグレンに、ナディアは肩をすくめながら答えた。
「そんな目で見ないでください。ともかく私は復讐に成功したんですから。バラジート公爵が生涯かけて築いたものをすべて……」
「おい、あれを見て。」
「え?」
その時、グレンが驚いた声を上げながら背中越しに指さした。
ナディアは反射的に振り返らなければならなかった。
だが、そこには何もなかった。
「なに?何を見たの……」
チュッ。
それは彼女が疑わしく思って再び顔を向けたときに起きた出来事だった。
左の頬に彼の唇が軽く触れて離れる。ナディアの口がわずかに開いた。
「いまの……何をしたんですか?」
「その、君の機嫌がちょっと、良くないように見えて……気分をよくしてあげたくて……」
「なんですって?」
彼女の口はさっきよりもさらに開いた。
グレンは堂々と奇襲攻撃を仕掛けた張本人で、恥ずかしさがじわじわ込み上げてきたのか、彼女の視線をまともに見られなかった。
胸にキスをするくらいなら、いっそさっぱりと済ませればよかったのに。
じっとしてから急に恥ずかしがる様子がとても……。
『かわいいじゃない?』
ナディアは最近、自分の男性の好みを理解し始めた。
それはまさに冷たい印象のイケメンなのに、意外にも可愛い一面の多い男性。
彼女は微笑んで口を開いた。
「自分のキスで私の気分が晴れると思うなんて……自信満々ですね。」
「それは……」
「おや、美男の自信ってこういうことなんですか?ま、これだけの美貌なら自信を持って当然ですね。」
少し驚いたせいか、顔がほんのり赤く染まる。
そういう反応を見ると、さらにからかいたくなる気持ちもわかるというものだ。
「えいっ。」
ナディアがつま先立ちになって彼の首筋に腕を回した。
そして──
チュッ。
さっきグレンがしたのと同じように、素早く彼の頬に唇を当てた。
それなら多少は避けられただろうから、「奇襲」という表現は少し合わなかったかもしれない。
「……!」
グレンは驚いたように目を大きく見開いたが、特に他の反応はなかった。
彼女はクスクス笑いながら言った。
「そんなに驚くことですか?もらった分だけ返しただけなのに。」
「本当に……。」
止められないというようにため息をついたグレンが、再びナディアの唇にキスをした。
一方、その甘くとろける時間を過ごしている二人を、遠くから見つめる視線があった。
ちょうど本館のテラスでうろうろしていた侍女たちだ。
高い階に位置していたため、別邸の庭で起きていることがはっきり見えた。
「うちの奥様と侯爵様……最近、より親しくなられたようにお見受けしますけど?」
「気のせいじゃないわ。お二人の会話を聞いていると、1週間前に食べたランチまで吐き出しそうな気分よ。周りの人のことも少しは考えてほしいわ!」
「もちろん、主君ご夫妻の仲が良くなるようお仕えしたい気持ちは本当なんだけど……」
でもこれはあまりにも突然すぎるんじゃない?
みんなの頭の中をよぎった思いだった。
静まり返ったテラスの中で、突然誰かの叫び声が響き渡った。
「ちょっと、みんな何を言ってるの?奥様の恋が実ったんじゃない!まったく祝うべきことでしょ!」
「そ、それはそうなんですが……。」
「少なくとも、これでもう奥様がウィンターフェルを去るんじゃないかって心配はしなくて済むよね。」
「それもそうね。」
侍女たちの大半がその言葉にうなずきながら笑みを浮かべた。
片思いに疲れたナディアが心を寄せるのを心配したというわけだ。
夫妻のいちゃつきぶりが少し過剰に感じる時もあるが……それも時間が経てばいずれ慣れるものだろう。
「もうすぐ侯爵様の願いが叶うかもしれませんね。」
「侯爵様の願い?」
「侯爵者の継承が安定するという意味です。」
「ああ。」
「そういえば、少し前から赤ちゃん用品を買わなきゃとか、インテリアをまたやり直さなきゃとか言ってて、そわそわしてましたよ。」
「時期的にはちょうどいいですね。内戦も終わったし、周囲の環境も安定してきたし、子どもが育つには良いでしょう。」
後継者が生まれたウィンターフェルの将来はどんな姿になるだろうか?
侍女たちはそれぞれの頭の中で、そのぼんやりと暖かい情景を思い描いた。
仲睦まじい夫婦と幼い子ども。
想像するだけで心が温まる光景だ。
侍女としても、この上なく誇らしい光景に思えた。
しかしその時、感動を破る声が響いた。
「ちょっと待って。じゃあ私たちの領主様、これからは西域第十四位になるってこと?」
「え?それって、そういうことになるの?」
彼らの顔が一瞬で真剣になった。
使用人として優秀に務めるには、家の中の序列を正確に把握していなければならないのだ。
『どう考えても……奥様から生まれた子供のほうが令夫人より序列が下になることはないよね?』
『当然のことだよ。』
わずかに令夫人の序列が一段下がることになるわけだ。
使用人たちは互いに無言で目を見合わせ、結論を出そうとしていた。
その視線が向かった先には――まさにナディアとグレンの間に割り込むように、小さな小さなひな鳥のような赤ん坊だった。
ノアがナディアと会話していたグレンの頭の上に乗せてしまった。
続いて、何か不満を訴えるようなグレンの唸り声がかすかに聞こえてきたが、遠くにいた使用人たちには赤ん坊の声までは聞き取れなかった。
その光景を見た瞬間、皆の頭の中をある考えがかすめた。誰かがその思いを口にした。
「いや、5位になるかも?」
「やめようよ。それでも私たちのご主人様だよ。」
「そうね……子どもが生まれても4位にはなるし。」
当主の権威のため、彼らは言いたいことをぐっとこらえた。
首都へと旅立つ日が近づいたある日の午後だった。